概論
テクニカル分析の世界において、ゴールデンクロスとデッドクロスほど広く知られ、多くの投資家によって信頼されている売買シグナルは他にないかもしれません。その定義はシンプルです。ゴールデンクロスは、短期の移動平均線(例えば50日線)が、長期の移動平均線(例えば200日線)を上抜いた状態を指し、一般的に強力な買いシグナルと見なされます。反対に、デッドクロスは、短期線が長期線を下抜いた状態であり、売りシグナルと解釈されます。
このシグナルの背後にあるロジックは、トレンドフォローという考え方に基づいています。短期的な市場の勢い(短期線)が、長期的なトレンド(長期線)を上回る(あるいは下回る)ことで、新たなトレンドの発生、あるいは既存のトレンドの強化を示唆するというものです。その分かりやすさから、ゴールデンクロスとデッドクロスは、投資の教科書やメディアで頻繁に取り上げられ、多くの個人投資家にとっての道標となってきました。
しかし、学術的な金融理論の世界では、長らくテクニカル分析全般に対して懐疑的な見方が支配的でした。効率的市場仮説が主張するように、もし市場価格が全ての利用可能な情報を即座に織り込んでいるのであれば、過去の価格パターンを分析して将来のリターンを予測することは、不可能だと考えられていたからです。
この学術界の常識に一石を投じたのが、ブロック、ラコニショック、ルバロンによる1992年の画期的な研究です。彼らは、100年近くにわたるダウ平均株価のデータを分析し、移動平均線を用いたシンプルな売買ルール(ゴールデンクロスやデッドクロスと非常に類似したルール)が、統計的に有意な予測力を持つことを発見しました [1]。この研究は、テクニカル分析の有効性をめぐる学術的な議論の口火を切り、その後の数多くの実証研究を促すきっかけとなったのです。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所:一部市場で確認された収益性
ゴールデンクロスやデッドクロスといった移動平均線戦略の最大の強みは、その有効性が一部の学術研究によって支持されているという点にあります。これは、数多あるテクニカル指標の中でも稀有な特徴です。
ブロックらの研究では、移動平均線が生成する買いシグナルの後のリターンは、売りシグナルの後のリターンを一貫して上回ることが示されました [1]。この肯定的な結果は、その後、欧州の16の株式市場を対象とした、より新しい時代の大規模な研究によっても支持されています。その研究によれば、移動平均線ルールは、統計的な偶然性を排除する検定を行った後でさえ、バイ・アンド・ホールド戦略を上回る利益を生む予測力を持つことが示唆されています [2]。
さらに、南アジアの株式市場を対象とした別の研究でも、移動平均線を用いたテクニカルな手法が、単純なバイ・アンド・ホールド戦略を上回る超過リターンを生み出すことが報告されています [3]。これらの研究結果は、移動平均線戦略の有効性が、特定の市場や時代に限られない可能性を示唆しています。
短所:再現性の欠如と統計的な罠
一方で、これらの肯定的な研究結果を手放しで称賛することはできません。移動平均線戦略の有効性には、数多くの深刻な限界や注意点が存在します。
第一に、その有効性は、市場によって大きく異なるという点です。例えば、米国の株式市場で観測されたような明確な優位性は、他の多くの国の株式市場では確認できない、あるいは非常に弱いという実証結果も報告されています [4]。ゴールデンクロスが、あらゆる市場で機能する普遍的な法則ではないことは明らかです。
第二に、そしてより根源的な問題として、そもそも観測された利益が、統計的な見せかけに過ぎない可能性も指摘されています。ブロックらの研究を再検証したある研究は、その見かけ上の成功が「データスヌーピングによる見せかけの結果(spurious result of data snooping)」である可能性が高いと主張しています [5]。歴史的なデータに見られるパターンは、たとえそれが非常に一貫しているように見えても、将来も継続するとは限らないのです。
ゴールデンクロスやデッドクロスは、その性質上、トレンドが発生しないレンジ相場では、頻繁に売買シグナルを発生させる「ダマシ」が多くなります。このダマシによって繰り返される不要な売買は、取引コストを積み上げ、リターンを蝕んでいきます。統計的な優位性がそもそも疑わしい上に、現実の取引コストという壁が、この戦略から継続的に利益を上げることを極めて困難にしているのです。
非対称性と摩擦の視点から
ゴールデンクロスやデッドクロスが、時に有効なシグナルとして機能する可能性の根源には、市場が持つ「非対称性」が存在します。しかし、その優位性は、常に市場の「摩擦」によって蝕まれる運命にあります。
Asymmetry:トレンドが持つ非対称な性質
ゴールデンクロスのようなトレンドフォロー戦略が機能する背景には、市場のトレンドそのものが持つ「非対称な」性質があります。株価は、一般的に、短く急激な下落と、長く緩やかな上昇という、非対称なサイクルを繰り返す傾向があります。ゴールデンクロスは、この長く続く上昇トレンドの初期段階を捉え、その波に乗ることを目指す戦略です。
ブロックらの研究[1]で、買いシグナルが売りシグナルよりも特に強いリターンを示したという結果は、この市場の非対称な性質を反映している可能性があります。歴史的に見て、株式市場には長期的な上昇バイアスが存在するため、その流れに乗るゴールデンクロスは、流れに逆らう(あるいは下降トレンドを捉える)デッドクロスよりも、有利な結果を生み出しやすいのです。この戦略の優位性は、市場に存在するリターンの非対称性を捉える能力に根差していると言えるでしょう。
Friction:優位性を蝕む「遅延」と「統計的幻想」という摩擦
移動平均線戦略が直面する最も根源的な摩擦は、その算出方法に起因する「情報の遅延」です。移動平均線は過去の価格データから計算されるため、ゴールデンクロスというシグナルが点灯する頃には、価格はすでに底値からある程度上昇してしまっています。この構造的な「遅れ」は、トレンドの最も美味しい部分を逃してしまうという、避けられない機会損失(摩擦)を生み出します。
さらに、この遅延は、明確なトレンドが存在しないレンジ相場において、「ダマシ」という形で致命的な摩擦となります。価格が短期的な上下動を繰り返す中で、ゴールデンクロスとデッドクロスが頻繁に発生し、その都度売買を繰り返すことで、取引コストだけが着実に積み重なっていきます。
そして最も深刻な摩擦は、そもそも観測されている優位性そのものが、統計的な幻想であるかもしれないという「検証の摩擦」です。移動平均線ルールの有効性を検証した研究は、データスヌーピング、すなわち無数のルールを試すうちに見つかった偶然の産物である可能性が指摘されています [5]。たとえ過去のデータで完璧に見えるルールであっても、それが未来の利益を保証しないのは、この統計的な不確実性という摩擦が存在するためです。
総括
- ゴールデンクロスとデッドクロスは、短期と長期の移動平均線の交差を利用した、最も有名なトレンドフォロー型のテクニカル指標です。
- 1992年のブロックらによる画期的な研究[1]は、米国の長期的な株式データにおいて、移動平均線ルールが統計的に有意な予測力を持つことを示しました。
- その後の研究でも、欧州[2]や南アジア[3]といった他の市場で有効性が確認された事例があります。
- 一方で、その有効性は普遍的ではなく、他の国際市場では明確な優位性が確認されない場合もあり [4]、再現性には疑問が残ります。
- 最大の弱点は、その優位性自体が「データスヌーピングによる見せかけの結果」である可能性が指摘されている点です [5]。加えて、シグナルの遅延性や取引コストといった現実の「摩擦」が、理論上の利益を大きく損なう可能性があります。
用語集
ゴールデンクロス 短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜ける現象。強気相場の始まりを示す、強力な買いシグナルとされる。
デッドクロス 短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜ける現象。弱気相場の始まりを示す、強力な売りシグナルとされる。
移動平均線 過去の一定期間の価格の平均値を線で結んだ、最も基本的なテクニカル指標。価格のトレンドや方向性を視覚的に捉えるために用いられる。
トレンドフォロー 市場に発生したトレンド(上昇または下降)に追随して、その流れに乗ることで利益を狙う投資戦略。
ダマシ (Whipsaw) テクニカル指標が売買シグナルを発したにもかかわらず、価格がその通りに動かず、すぐに反転してしまう現象。レンジ相場で発生しやすい。
効率的市場仮説 市場価格は利用可能な全ての情報を即座に織り込んでいるため、過去の価格パターンなどのテクニカル分析によって、継続的に市場を上回る利益を得ることはできないとする理論。
データスヌーピング 大量のデータを分析するうちに、本来は意味のない偶然の相関関係を、意味のある規則性であるかのように見つけ出してしまうこと。テクニカル分析の有効性検証における大きな課題。
取引コスト 金融商品を売買する際に発生する費用の総称。売買手数料、ビッド・アスク・スプレッド、マーケットインパクトなどが含まれる。
バイ・アンド・ホールド 金融商品を一度購入したら、長期にわたって保有し続ける投資戦略。移動平均線戦略のパフォーマンスを評価する際の比較対象(ベンチマーク)となることが多い。
バックテスト ある投資戦略が、過去の市場データを用いてシミュレーションした場合に、どのようなパフォーマンスを示したかを検証すること。
参考文献一覧
[1] Brock, W., Lakonishok, J., & LeBaron, B. (1992). Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. The Journal of Finance, 47(5), 1731-1764.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04681.x
[2] Metghalchi, M., Marcucci, J., & Chang, Y. H. (2012). Are moving average trading rules profitable? Evidence from the European stock markets. Applied Economics, 44(12), 1539-1559.
https://doi.org/10.1080/00036846.2010.543084
[3] Gunasekarage, A., & Power, D. M. (2001). The profitability of moving average trading rules in South Asian stock markets. Emerging Markets Review, 2(1), 17-31.
https://doi.org/10.1016/S1566-0141(00)00017-0
[4] Bessembinder, H., & Chan, K. (1998). Market efficiency and the returns to technical analysis. Financial Management, 27(2), 5-17.
https://doi.org/10.2307/3666289
[5] Ready, M. J. (2002). Profits from technical trading rules. Financial Management, 31(3), 43-61.
https://doi.org/10.2307/3666314
本サイト/本記事は、著者個人の見解、経験、学習・研究内容に基づいた情報提供を目的としています。特定の銘柄や投資手法の推奨を目的としたものではなく、また、金融商品取引法に基づく投資助言サービスではありません。
投資には元本割れを含む様々なリスクがあります。価格変動、金利変動、為替変動、発行者の信用状況などにより、損失が生じる可能性があります。
本サイト/本記事で提供される情報を利用した投資判断や取引によって生じたいかなる損害についても、筆者および運営者は一切の責任を負いません。
投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行って(あるいは行わないで)ください。
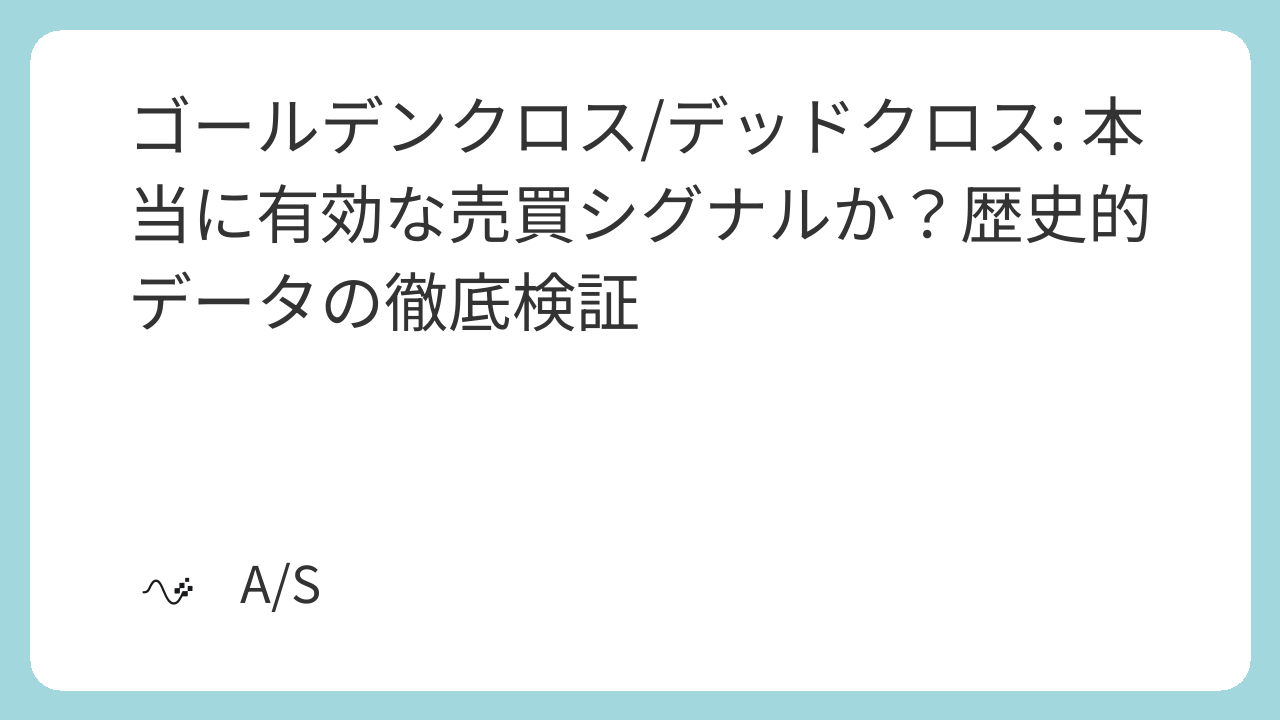
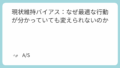
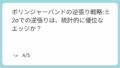
コメント