概論
新しいスマートフォンを購入した時、デフォルトで設定されている着信音や壁紙を、特に理由もなくそのまま使い続けてしまった経験はないでしょうか。あるいは、会社の退職金プランについて、よく分からないからと、とりあえずデフォルト(初期設定)の運用プランのまま何年も放置してしまってはいないでしょうか。
このように、より良い選択肢が存在する可能性があるにも関わらず、現在の状況(Status Quo)を不釣り合いなほど強く好み、変化を避けようとする心理的な傾向は、現状維持バイアス(Status Quo Bias)として知られています。
このバイアスの存在を、一連の巧みな実験と現実世界の観察を通じて学術的に確立したのが、ウィリアム・サミュエルソンとリチャード・ゼックハウザーによる1988年の論文です [1]。彼らは、ある選択肢が「現状(status quo)」として提示されるだけで、その選択肢が選ばれる確率が劇的に高まることを明らかにしました。人間は、積極的に何かを選び取るという行動よりも、「何もしない」という選択を、無意識のうちに好んでしまうのです。
では、なぜこのような不合理な慣性が働くのでしょうか。その背景には、人間のより根源的な心理が潜んでいます。
カーネマン、クネッチ、セイラーによる1991年の研究は、この現状維持バイアスが、プロスペクト理論で示された損失回避(Loss Aversion)と密接に関連していることを論じました [2]。現状から別の選択肢へと移行する行為は、必ず「何かを得る可能性」と「何かを失う可能性」を天秤にかけることになります。しかし、損失の痛みが利益の喜びを上回るため、私たちは、新しい選択肢がもたらすかもしれない利益よりも、「もし変化した結果、今より悪くなったらどうしよう」という後悔のリスク(損失)の方を、より重く受け止めてしまうのです。この損失への恐怖が、私たちを現状という「安全地帯」に縛り付ける、強力な重力として機能します。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
短所、弱み、リスクについて:何もしないことのリスク(損失事例)
現状維持バイアスは、トレーディングや長期投資において、静かに、しかし確実に資産を蝕む、最も危険なバイアスの一つです。
退職金運用における悲劇
このバイアスがもたらす影響を最も劇的に示したのが、企業年金(401kプラン)の研究です。
マドリアンとシェイによる2001年の金字塔的な研究は、ある企業が退職金プランの仕組みを「オプトイン方式(自ら参加を申し込む必要がある)」から「オプトアウト方式(自動的に参加となり、辞めたい人だけが申し出る)」に変更した際の、従業員の行動の変化を分析しました [3]。
結果は驚くべきものでした。オプトイン方式、すなわち何もしなければ「不参加」が現状であった時には、従業員の加入率は非常に低迷していました。しかし、オプトアウト方式、すなわち何もしなければ「参加」が現状となるようにデフォルト設定を変更しただけで、加入率は劇的に跳ね上がったのです。さらに、多くの従業員は、自動的に設定された掛金率や投資先の配分(多くは安全だが低リターンな金融商品)を、その後も変更することなく放置し続けました。
これは、現状維持バイアスという強力な慣性が、多くの人々の老後の資産形成という、人生で最も重要な財務判断の一つを、いかに大きく左右しているかを示す強力な証拠です。
ポートフォリオの陳腐化
この「一度決めたら変えられない」という慣性は、よりアクティブな投資家のポートフォリオ管理においても、深刻な問題を引き起こします。
カルベット、キャンベル、ソディーニによる2009年の研究は、スウェーデンの個人投資家の詳細な取引データを分析し、多くの投資家が、市場環境の変化に応じてポートフォリオをリバランス(資産配分の再調整)することを怠っている実態を明らかにしました [4]。当初は最適だったはずのポートフォリオも、何もしなければ、株価の変動によってそのリスク特性は大きく変化し、陳腐化していきます。現状維持バイアスは、投資家をこの緩やかなリスクの増大から目をそむけさせてしまうのです。
長所、強み、有用な点について:「ナッジ」による行動変容(収益事例)
現状維持バイアスは、個人の合理的な判断を妨げる強力な力ですが、その性質を逆手に取ることで、人々をより良い方向へと導くことも可能です。
「ナッジ」と自由主義的パターナリズム
この考え方を体系化したのが、リチャード・セイラーとキャス・サンスティーンによる2003年の論文(およびその後の著作「ナッジ」)で提唱された「自由主義的パターナリズム」という概念です [5]。
これは、人々の選択の自由を奪うことなく、しかし、彼らがより良い選択を自ら行えるように、選択の「初期設定(デフォルト)」を賢く設計しよう、という考え方です。人々が現状維持バイアスに強く影響されるという事実を受け入れた上で、その「現状」を、専門家が推奨する最も望ましい選択肢にあらかじめ設定しておく。この、肘で軽くつつく(nudge)ような介入が、人々の行動を劇的に改善させることが示されています。
デフォルト設定の力
この「ナッジ」がもたらす「収益」、すなわち社会的な便益は、マドリアンとシェイの研究[3]に明確に示されています。退職金プランへの加入をデフォルトに設定するという、わずかな設計の変更が、何百万人もの従業員の老後の経済的な安定を、大きく改善させたのです。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、私たちはこれほどまでに「現状」に固執し、合理的な変化を避けてしまうのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:現状と「変化」の非対称性
現状維持バイアスの根源には、「現状」と「変化」を評価する際の、心理的な天秤が、著しく非対称であるという事実が存在します。
カーネマンらの研究が示すように、私たちは「現状」を意思決定の参照点として用います [2]。そして、現状から変化するということは、必ず「現状の利点を失う可能性」と、「新しい選択肢の利点を得る可能性」を比較検討することを意味します。
ここに、プロスペクト理論の「損失回避」という、強力で非対称な心理が作用します。私たちは、失うことの痛みを、得ることの喜びよりも遥かに強く感じるため、変化に伴う潜在的なデメリット(損失)を、潜在的なメリット(利得)よりも、非対称に重く評価してしまうのです。
その結果、新しい選択肢が、現状よりも「少しだけ良い」程度では、変化を起こす動機付けとしては不十分になります。「変化に伴う損失の恐怖」という強力な引力を振り切るためには、それを遥かに上回るほどの、圧倒的な魅力(利得)が必要となるのです。この心理的な天秤の非対称性こそが、私たちを現状に縛り付ける力の源泉です。
Friction:「何もしない」ことの魅力という認知的摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、現状維持バイアスは、人間の認知プロセスそのものに深く根差した、抗いがたい「摩擦」によって引き起こされます。
思考のコストという摩擦
現状を維持することは、「何もしない」ことを意味します。それは、認知的な努力を全く必要としない、最も楽な選択肢です。
一方で、現状を変更するためには、
- 新しい選択肢を探し、
- それぞれの長所と短所を比較検討し、
- 最善のものを選択し、
- 実際に手続きを行う という、一連の思考と行動のコストを支払わなければなりません。
この「変化に伴うコスト」という摩擦が、多くの人々を、たとえ現状が最適ではないと薄々感じていたとしても、「面倒だから、今のままでいい」という思考停止へと導いてしまうのです。退職金プランの例が示すように、この摩擦の力は絶大です [3]。
後悔の回避という摩擦
もう一つの強力な摩擦が、「後悔したくない」という感情です。
もし、現状維持を選択して悪い結果になったとしても、「自分は何もしなかったのだから仕方ない」と、責任を回避することができます。しかし、もし自らの意思で積極的に現状を変更し、その結果が悪かった場合、「あの時、何もしなければよかった」という、より痛烈な「後悔の念」に苛まれることになります。
この「将来の後悔を避けたい」という心理が、不確実な変化に踏み出すことを躊躇させ、より安全に見える「何もしない」という選択へと人々を誘導する、強力な摩擦として機能するのです。
総括
・現状維持バイアスとは、より良い選択肢が存在していても、現在の状況を不合理なほど強く好み、変化を避けてしまうという認知バイアスです [1]。
・その背景には、変化に伴う潜在的な「損失」を過度に恐れる損失回避の心理が存在します [2]。
・このバイアスは、退職金プランへの不参加 [3]や、ポートフォリオのリバランスの懈怠 [4]といった、個人の資産形成において深刻な不利益をもたらします。
・一方で、このバイアスの強力さを理解することは、自動加入制度のように、人々の選択の「初期設定(デフォルト)」を賢く設計することで、より良い結果へと導く「ナッジ」というアプローチの基礎となります [5]。
用語集
現状維持バイアス (Status Quo Bias) より合理的な選択肢が存在する場合でも、現在の状況(現状)を維持することを不釣り合いに好む認知バイアス。
認知バイアス (Cognitive Bias) 人間の思考の癖や、思い込みによって、非合理的な判断を下してしまう心理的な傾向のこと。
損失回避 (Loss Aversion) 同じ金額であれば、利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛の方を精神的に2倍以上重く受け止めてしまうという人間の非対称な心理的傾向。
プロスペクト理論 (Prospect Theory) 不確実性のある状況下での人間の意思決定を、心理学的な実験に基づいてモデル化した理論。損失回避はその中核をなす。
参照点 (Reference Point) 利得と損失を判断するための基準となる点。現状維持バイアスにおいては、「現在の状況」そのものが参照点となる。
ナッジ (Nudge) 人々がより良い選択を自発的に行えるように、選択の設計を工夫することで、行動をそっと後押しするアプローチ。「肘で軽く突く」が原義。
自由主義的パターナリズム (Libertarian Paternalism) 人々の選択の自由を保証しつつも、彼らがより良い結果を得られるように、デフォルト設定などで緩やかに誘導しようとする考え方。「ナッジ」の基礎となる思想。
デフォルト (Default) 利用者が特に何も選択しなかった場合に、自動的に適用される初期設定のこと。現状維持バイアスをハックする上で極めて重要な要素。
リバランス (Rebalancing) ポートフォリオの資産配分が、当初の目標比率から乖離した場合に、資産を売買して元の比率に戻すこと。
ポートフォリオ 投資家が保有する、株式、債券、不動産などの金融資産の組み合わせ、またその一覧。
参考文献一覧
[1] Samuelson, W., & Zeckhauser, R. (1988). Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty, 1(1), 7-59.
https://doi.org/10.1007/BF00055564
[2] Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 193-206.
https://doi.org/10.1257/jep.5.1.193
[3] Madrian, B. C., & Shea, D. F. (2001). The power of suggestion: Inertia in 401(k) participation and savings behavior. The Quarterly Journal of Economics, 116(4), 1149-1187.
https://doi.org/10.1162/003355301753265543
[4] Calvet, L. E., Campbell, J. Y., & Sodini, P. (2009). Measuring the financial sophistication of households. American Economic Review, 99(2), 393-98.
https://doi.org/10.1257/aer.99.2.393
[5] Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2003). Libertarian paternalism is not an oxymoron. The University of Chicago Law Review, 70(4), 1159-1202.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.405940
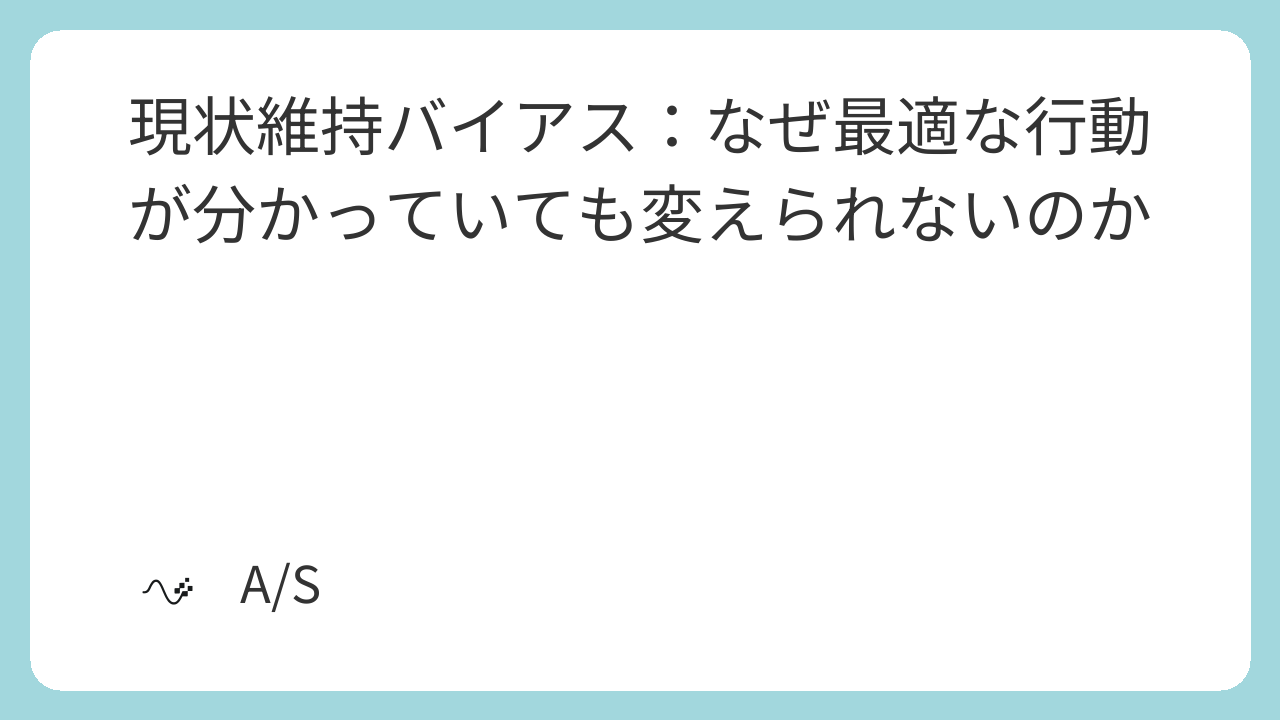
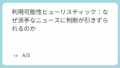
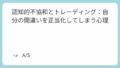
コメント