概論
あるレストランの前に行列ができていたら、「きっと美味しいに違いない」と、つい並んでしまった経験はないでしょうか。あるいは、周りの人が一斉に空を見上げたら、理由も分からず自分も空を見上げてしまう。このように、個人が自らの私的な情報や判断を無視し、周囲の他者の行動に追随してしまう傾向は、ハーディング行動(Herding Behavior)、あるいは群集行動として知られています。
金融市場において、このハーディング行動は、バブルの形成や、その後の暴落といった、市場の極端な動きを生み出す根源的なメカニズムであると考えられています。
一見すると、ハーディングは非合理的なパニックや思考停止の結果であるかのように思えます。しかし、学術研究は、ハーディングが必ずしも非合理的とは言えない、巧妙なロジックに基づいている可能性を明らかにしました。主に二つの理論が、その背景を説明しています。
- 情報カスケード(Informational Cascade): これは、他者の行動が、それ自体として「情報」の役割を果たす、という考え方です。アビジット・バナジーによる1992年の理論モデルは、このプロセスを巧みに説明しました [1]。例えば、ある銘柄について、自分は「割高だ」という情報を持っていても、信頼する二人の投資家が次々とその銘柄を買っていくのを見たとします。この時、「彼らは、私が知らない何かポジティブな情報を知っているのかもしれない」と考えるのは、ある意味で合理的です。そして、自分の「割高だ」という情報を捨て、彼らの行動に追随するという判断を下すのです。この連鎖が、情報カスケードです。
- 評判(レピュテーション)ハーディング: これは、特にファンドマネージャーのような、常に他者からの評価に晒されているプロの世界で起こりやすいハーディングです。シャーフスタインとスタインによる1990年の有名な研究は、このメカニズムを指摘しました [2]。彼らの主張によれば、ファンドマネージャーは、たとえ自分の分析が「この銘柄は買うべきではない」と示していても、他の多くのマネージャーが買っているのであれば、それに追随するインセンティブを持ちます。なぜなら、もし自分の判断が正しく、一人だけ儲けたとしても評価は少し上がるだけですが、もし自分の判断が間違って一人だけ損をすれば、「能力がない」という烙印を押され、キャリアに致命的なダメージを受けるからです。「皆で渡れば怖くない」ならぬ、「皆と同じ間違いを犯す方が、一人で正しいことをするより安全」という、歪んだ合理性がハーディングを生むのです。
長短の解説、利益例・損失例の紹介
短所、弱み、リスクについて:群集が生み出すバブルと暴落(損失事例)
ハーディング行動が市場にもたらす最大のリスクは、株価がその本質的な価値(ファンダメンタルズ)から大きく、そして長期間にわたって乖離してしまうことです。
市場の不安定化
群集が同じ方向に動くとき、その力は自己増殖的なループを生み出します。買いが買いを呼び、株価は実態とかけ離れて上昇し、バブルを形成します。そして、ひとたび何かのきっかけで群集のセンチメントが反転すると、今度は売りが売りを呼び、暴落を引き起こすのです。ハーディングは、市場のボラティリティを増幅させ、不安定化させる主要な要因と考えられています。
専門家の「群れ」
このハーディングは、個人投資家だけの問題ではありません。専門家であるはずの証券アナリストの間でも、ハーディングが起こることが実証されています。イヴォ・ウェルチによる2000年の研究は、アナリストが、自らの独自の分析よりも、先に発表された他のアナリストの業績予想に、その予想を寄せていく傾向があることを示しました [3]。
機関投資家のハーディング
さらに、プロの投資家であるミューチュアル・ファンドの間でも、ハーディングは明確に観測されています。ラッセル・ワーマーズによる1999年の大規模な実証研究は、多くのファンドが、特定の四半期に同じ銘柄を買い、同じ銘柄を売るというハーディング行動を示していることを発見しました [4]。この機関投資家によるハーディングは、株価に対して大きな影響を与え、価格の歪みを生み出す力を持っていることも、彼の研究は明らかにしています。
この現象は、米国市場だけでなく、タンらの2008年の研究が示すように、中国市場のような新興国市場においても観測されており、その普遍性が示唆されています [5]。
長所、強み、有用な点について:群集心理の逆を行く
ハーディング行動は、市場に非効率性をもたらす元凶ですが、その存在を理解し、客観的に分析できる投資家にとっては、収益機会の源泉となり得ます。
逆張り戦略の根拠
ハーディングによって株価がファンダメンタルズから大きく乖離した場合、いずれその価格は是正される、という期待が生まれます。群集が熱狂して買い上げている銘柄は、いずれ暴落する可能性を秘めた「割高」な候補であり、逆に、群集が悲観して売り叩いている銘柄は、いずれ見直される可能性を秘めた「割安」な候補となります。ハーディングの兆候を検知することは、逆張り戦略(Contrarian Strategy)の有効なシグナルとなり得るのです。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、多くの個人や、時にはプロの投資家までもが、群集の熱狂やパニックに飲み込まれてしまうのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:私的情報と公的情報の「非対称性」
ハーディング行動が生まれる根源には、自分が持つ「私的情報」と、他者の行動によって示される「公的情報」との間の、価値の非対称性が存在します。
情報カスケードの理論が示すように、投資家の意思決定のプロセスは非対称です [1]。最初の数人が行動する前は、各個人は自らが持つ私的情報(独自の分析や信念)に頼るしかありません。しかし、一度、他者の行動という公的なシグナルが観測され始めると、状況は一変します。「あれだけ多くの人が買っているのだから、何か理由があるはずだ」という推論が働き、自分の私的情報よりも、公的情報の方に、非対称に大きな重みが置かれるようになるのです。
この情報の重み付けにおける非対称性が、時に個人の合理的な判断を麻痺させ、群集全体の非合理な行動へと繋がっていきます。このアノマリーにおける収益機会とは、市場の大多数がこの公的情報に流されている中で、自らが持つ質の高い私的情報を信じ、群集から離れて独立した意思決定を下せる能力にあるのです。しかしそれは同時に、群集が正しく、自分の私的情報が間違っているリスクを負うことと表裏一体です。
Friction:「同調圧力」と「評判」という社会的摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、ハーディングという現象には、人間の心理や社会構造に根差した、より強力な「社会的摩擦」が存在します。
評判リスクという制度的摩擦
特にプロのファンドマネージャーの世界では、「評判(レピュテーション)」が、合理的な意思決定を妨げる巨大な摩擦として機能します。シャーフスタインとスタインの研究が示したように、彼らにとって最悪のシナリオは、群集と異なる独自の判断を下し、一人だけ失敗することです [2]。
たとえ群集と同じ行動を取って失敗したとしても、「市場環境が悪かった」と言い訳ができます。しかし、一人だけ違う行動を取って失敗すれば、その責任は全て自分一人が負うことになり、キャリアに傷がつきます。この「キャリアリスク」という制度的な摩擦が、多くのマネージャーに、たとえ内心では間違っていると思っていても、他の大多数と同じポジションを取るという「安全な」選択を強いるのです。この摩擦が、バブルが専門家によっても是正されずに、長期間にわたって拡大し続ける一因となります。
「孤独」への恐怖という認知的摩擦
群集と異なる行動を取ることは、心理的に大きな苦痛を伴います。自分の判断が本当に正しいのかという不安、そして、もし間違っていたら「馬鹿だと思われるのではないか」という他者からの評価への恐怖。この「孤独」への恐怖は、合理的な思考を妨げる、強力な認知的な摩擦です。
多くの人々は、この心理的な不快感を避けるため、たとえ疑問を感じていても、心地よい群集の中に留まることを選択します。ハーディング行動とは、この認知的な摩擦に屈した結果とも言えるのです。
総括
・ハーディング行動(群集行動)とは、投資家が自らの情報を無視し、他の多くの参加者の行動に追随してしまう現象です。
・その背景には、他者の行動から情報を得ようとする合理的な側面(情報カスケード)[1]や、キャリアを守ろうとするプロの投資家の防衛的な動機(評判ハーディング)[2]が存在します。
・実証研究によれば、証券アナリスト [3]やミューチュアル・ファンド [4]の間でもハーディングは明確に観測されており、市場の不安定化を助長する一因となっています。
・ハーディングは、株価を本質的価値から乖離させるため、群集の逆を行く逆張り投資家にとっては収益機会となり得ますが、そのためには強力な制度的・認知的摩擦を乗り越える必要があります。
用語集
ハーディング行動 (Herding Behavior) 個人が、周囲の他者の行動に影響され、自らの判断を捨てて同じ行動を取ってしまう現象。群集行動。
情報カスケード (Informational Cascade) 人々が、自らの私的な情報よりも、先行する他者の行動をより重要な情報源と見なし、次々と行動を模倣していく連鎖的なプロセス。
評判リスク (Reputational Risk) 他者と異なる行動を取って失敗した場合に、自らの評判やキャリアが傷つくリスク。
逆張り戦略 (Contrarian Strategy) 市場の大多数の投資家の意見や行動(コンセンサス)とは逆のポジションを取る投資戦略。
バブル (Bubble) 資産の価格が、その本質的な価値から大きくかけ離れて、熱狂的に高騰する状態。
ファンダメンタルズ (Fundamentals) 企業の収益力や財務状況、資産価値といった、その企業の本質的な価値を決定する基礎的条件。
センチメント (Sentiment) 市場参加者の総意として形成される、楽観や悲観といった市場全体の心理状態や雰囲気のこと。
市場中立 (Market Neutral) 株式市場全体の上下の動き(ベータ)に対するエクスポージャーがゼロになるように構築されたポートフォリオ。
アノマリー (Anomaly) 現代ファイナンス理論の常識では説明できないが、市場で経験的に観測されるリターンの規則性。
ボラティリティ (Volatility) 資産価格の変動の激しさを示す指標。リターンの標準偏差で測定されることが多い。
参考文献一覧
[1] Banerjee, A. V. (1992). A simple model of herd behavior. The Quarterly Journal of Economics, 107(3), 797-817.
https://doi.org/10.2307/2118364
[2] Scharfstein, D. S., & Stein, J. C. (1990). Herd behavior and investment. The American Economic Review, 80(3), 465-479.
https://www.jstor.org/stable/2006678
[3] Welch, I. (2000). Herding among security analysts. Journal of Financial Economics, 58(3), 369-396.
https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00076-3
[4] Wermers, R. (1999). Mutual fund herding and the impact on stock prices. The Journal of Finance, 54(2), 581-622.
https://www.jstor.org/stable/2697720
[5] Tan, L., Chiang, T. C., Mason, J. R., & Nelling, E. (2008). Herding behavior in Chinese stock markets: An examination of A and B shares. Pacific-Basin Finance Journal, 16(1-2), 61-77.
https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.04.004
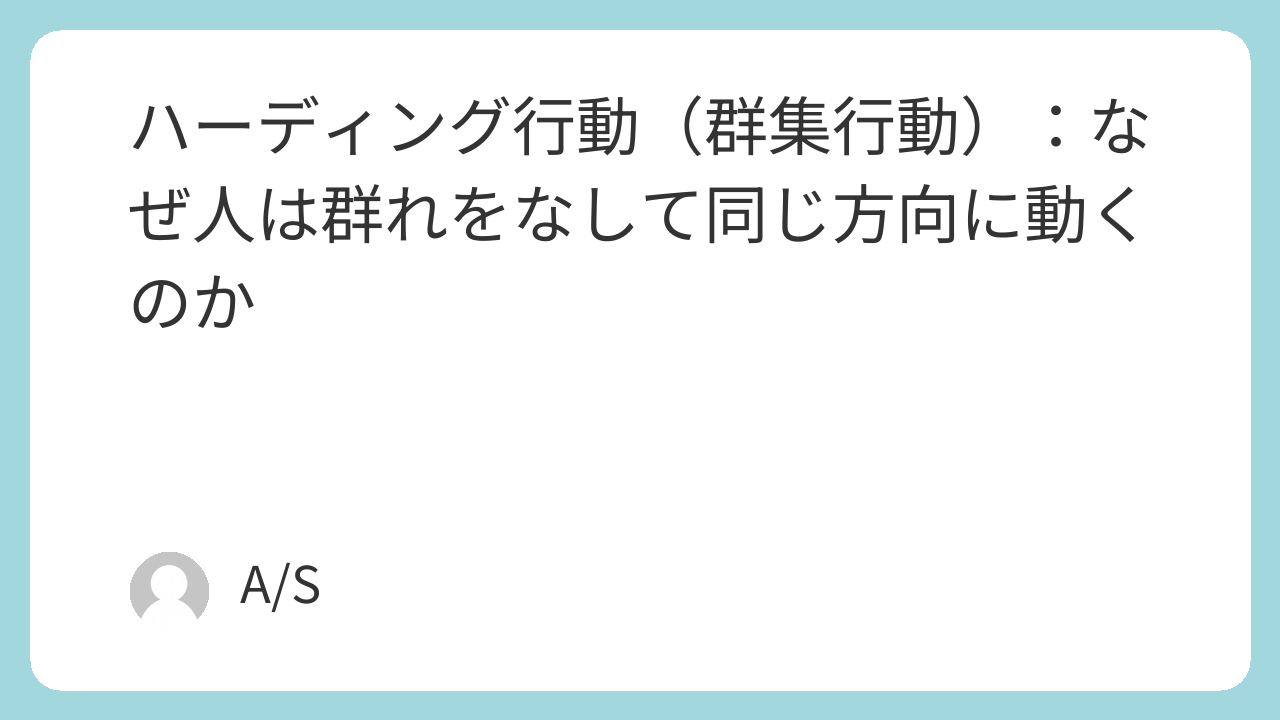
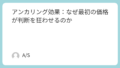
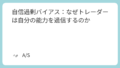
コメント