概論
ある中古車の価格交渉を想像してみてください。ディーラーが最初に「300万円」という価格を提示したとします。たとえあなたがその価格を高いと感じたとしても、その後の交渉は、無意識のうちにこの「300万円」という数字を基準に進んでいくのではないでしょうか。最終的に250万円まで値切れたとしても、「50万円も得をした」と感じてしまうかもしれません。しかし、もし最初の提示価格が250万円だったら、あなたは200万円まで値切れたかもしれません。
このように、人間が意思決定を行う際に、最初に提示された特定の情報(アンカー)に、その後の判断が不合理なほど強く影響を受けてしまうという認知バイアスが、アンカリング(係留)効果です。
このバイアスの存在を、一連の巧みな実験で世に知らしめたのが、行動経済学の父であるダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーです。彼らが1974年に発表した論文「Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases」は、この分野における金字塔的な研究です [1]。
彼らの有名な実験の一つに、次のようなものがあります。まず、被験者の前で、1から100までの数字が書かれたルーレットを回します。ただし、このルーレットには仕掛けがあり、常に「10」か「65」のどちらかしか出ないようになっています。その後、被験者に対して「国連に加盟しているアフリカ諸国の割合は、このルーレットの数字よりも高いか、低いか?」そして「具体的に何パーセントだと思うか?」という質問をします。
結果は驚くべきものでした。ルーレットで「10」が出たグループが推定した割合の中央値は25%だったのに対し、「65」が出たグループの中央値は45%でした。国連加盟国の割合という、ルーレットの出目とは全く無関係なはずの質問に対して、被験者の答えは、偶然与えられただけの無意味な数字(アンカー)に、明らかに引きずられていたのです。
このアンカリング効果は、私たちの日常生活だけでなく、金融市場における投資家の意思決定にも、強力で、そしてしばしば破壊的な影響を及ぼしています。
長短の解説、利益例・損失例の紹介
短所、弱み、リスクについて:アンカーが引き起こす投資判断の歪み
トレーダーや投資家は、日々様々な「数字(アンカー)」に晒されています。そして、それらのアンカーが、合理的な判断をいかに歪ませるかが、多くの研究によって示されています。
「取得価格」という呪縛
多くの投資家にとって、最も強力なアンカーとなるのが、自らがその株式を購入した「取得価格」です。このアンカーは、プロスペクト理論の回で解説した「ディスポジション効果」(利益が出ている株は早く売り、損失が出ている株は塩漬けにする)の温床となります。株価が取得価格を上回れば「利益が出た」と感じて早く売りたくなり、下回れば「元値に戻るまで」という不合理な期待を抱いて損切りを躊躇してしまうのです。
「52週高値」という市場のアンカー
ジョージ、ファン、リーによる2015年の研究は、決算発表に対する投資家の反応が、52週高値というアンカーに強く影響されていることを示しました [2]。彼らの発見によれば、株価が52週高値に近い時にポジティブな決算サプライズが出ても、投資家はその高値を意識するあまり、株価の上昇反応が抑制されてしまう(アンダーリアクションが起こる)傾向があるとのことです。
さらに、このアンカーは、企業のM&A(合併・買収)という、本来は極めて合理的に行われるべき意思決定にさえ影響します。ベイカー、パン、ワーグラーによる2012年の研究は、企業の取締役会が買収提案を受け入れるかどうかの判断において、提案価格が52週高値を上回っているかどうかを、重要な判断材料にしていることを示しました [3]。
長所、強み、有用な点について:他者のバイアスを利用する
アンカリングは、自らが囚われれば判断を誤らせる罠ですが、市場の他の参加者がこのバイアスに囚われていることを理解すれば、それは収益機会の源泉となり得ます。
モメンタム戦略への応用
ジョージとファンによる2004年の研究は、52週高値というアンカーが、モメンタム効果(株価のトレンドが継続する現象)の一因となっている可能性を示しました [4]。
彼らの分析によれば、株価が52週高値に近づくにつれて、投資家の注目が集まり、売買が活発になる傾向があります。そして、ひとたび株価がこの強力なアンカー(抵抗線と見なされることもある)をブレイクすると、それが強気のシグナルとなってさらに多くの買いを呼び、その後の株価上昇が継続しやすくなる、というのです。
バリュー投資への応用
逆張り戦略であるバリュー投資も、アンカリングの観点からその有効性を説明できます。ある企業の株価が、悪材料によって過去の高値から大きく下落したとします。多くの投資家は、過去の高値というアンカーに心理的に縛られ、「あの株はあんなに高かったのに」と感じ、下落した後の新しい価格水準での合理的な価値評価が困難になります。
バーバリスとセイラーによる2003年の行動ファイナンスに関するレビュー論文でも論じられているように、このような認知バイアスが、市場に「過剰反応」による価格の歪みを生み出します [5]。アンカリングに囚われないバリュー投資家は、この市場の過度な悲観を利用し、不当に安値で放置された銘柄に投資する機会を得ることができるのです。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、全く無関係なはずの数字が、私たちの判断をこれほどまでに支配するのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:アンカーからの「不十分な調整」という非対称性
アンカリング効果のメカニズムは、「アンカーの設定」と、それに続く「調整」という二つのプロセスで説明されます [1]。そして、この「調整」のプロセスに、決定的な非対称性が潜んでいます。
人間は、最初に与えられたアンカーを起点として、そこから自分の最終的な答えに近づくように、思考を「調整」していきます。しかし、この調整のプロセスは、多くの場合「不十分」なところで打ち切られてしまいます。私たちは、アンカーから少しだけ離れて、自分の心の中で「もっともらしい」と思える範囲に到達した瞬間に、思考を止めてしまうのです。
この結果、最終的な判断は、アンカーが置かれた位置に、非対称に強く引きずられます。もし最初のアンカーが高すぎれば、最終的な判断も高すぎる位置に偏ります。逆に、アンカーが低すぎれば、最終的な判断も低すぎる位置に偏ります。
この「出発点(アンカー)が、終着点(最終判断)を不当に決定づけてしまう」という思考プロセスの非対称性こそが、アンカリング効果の本質です。このアノマリーにおける収益機会とは、市場の大多数が、過去の高値やアナリストの目標株価といった、不適切かもしれないアンカーに判断を歪められている中で、それらのアンカーを完全に無視し、ゼロベースで価値を評価できる能力を持つことにあるのです。
Friction:「最初の情報」という抗いがたい認知的摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、アンカリング効果は、人間の認知プロセスそのものに深く根差した、抗いがたい「摩擦」によって引き起こされます。
第一印象の呪縛という認知的摩擦
アンカリング効果は、「第一印象」が持つ絶大な力を示しています。一度、特定の数字がアンカーとして心に植え付けられてしまうと、その後にどれだけ合理的で、より重要な情報が与えられたとしても、最初のアンカーの影響を完全に消し去ることは、極めて困難です。
この「最初に与えられた情報に固執してしまう」という性質は、合理的な情報処理を妨げる、強力な認知的な摩擦として機能します。脳は、新しい情報に基づいてゼロから判断を再構築するよりも、既存のアンカーを少しだけ修正する方が、認知的負荷が少ない(楽である)ため、無意識のうちに後者を選択してしまうのです。
一貫性を求める心理という摩擦
一度アンカーが設定されると、人々はそのアンカーと「一貫性」のある情報を、無意識のうちに探し始める傾向があります。これは確証バイアスとも関連しています。
例えば、ある株式の取得価格(アンカー)が1000円で、現在の株価が500円に下落したとします。この時、多くの投資家は、「この会社が1000円に戻るべき理由」を探し始め、それに合致する情報ばかりに目が行くようになります。この「自らのアンカーを正当化したい」という心理的な欲求が、客観的な分析を妨げる摩擦となり、合理的な損切り判断を遅らせるのです。
総括
・アンカリング効果とは、最初に提示された情報(アンカー)が、その後の意思決定に不合理なほど強い影響を与えるという、人間の根源的な認知バイアスです [1]。
・金融市場において、投資家は「取得価格」や「52週高値」といった数字に強くアンカリングされる傾向があり、それが決算発表への反応 [2]や、企業のM&Aの判断 [3]さえも歪ませることが示されています。
・このバイアスは、モメンタム効果 [4]のように、市場に予測可能なパターンを生み出す一因となる可能性があり、他者のバイアスを理解する投資家にとっては収益機会となり得ます。
・アンカリング効果は、「最初の情報に固執する」という、人間の思考における強力な「認知的摩擦」によって引き起こされており、その影響から完全に自由になることは極めて困難です。
用語集
アンカリング効果 (Anchoring Effect) 最初に提示された情報(アンカー)に、その後の判断が強く影響を受けてしまう認知バイアス。「係留効果」とも訳される。
ヒューリスティック (Heuristic) 人々が複雑な問題に対して、経験則などに基づき、直感的に素早く答えを導き出す思考のショートカットのこと。アンカリングは、その代表例の一つ。
認知バイアス (Cognitive Bias) 人間の思考の癖や、思い込みによって、非合理的な判断を下してしまう心理的な傾向のこと。
参照点 (Reference Point) 利得と損失、あるいは高いか低いかを判断するための基準となる点。アンカーは、この参照点を設定する上で強力な役割を果たす。
52週高値 (52-Week High) 過去52週間(約1年間)における、ある株式の最高値のこと。市場参加者が共通して意識する、強力なアンカーの一つ。
モメンタム効果 (Momentum Effect) 過去の価格トレンドが継続する傾向。過去に価格が上昇した銘柄は、その後も上昇しやすい。
バリュー投資 (Value Investing) 企業の本来的な価値(ファンダメンタSルズ)に比べて、株価が割安に評価されている銘柄に投資する手法。
ディスポジション効果 (Disposition Effect) 投資家が、利益の出ている資産は早く売り、損失の出ている資産は保有し続けるという体系的な行動バイアス。取得価格へのアンカリングが原因の一つとされる。
プロスペクト理論 (Prospect Theory) 不確実性のある状況下での人間の意思決定を、心理学的な実験に基づいてモデル化した理論。
効率的市場仮説 (Efficient Market Hypothesis) 市場価格は利用可能な全ての情報を即座に織り込んでいるため、継続的に市場を上回ることはできないとする理論。
参考文献一覧
[1] Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124-1131.
https://www.jstor.org/stable/1738360
[2] George, T. J., Hwang, C. Y., & Li, Y. (2015). Anchoring, the 52-week high and post earnings announcement drift. Available at SSRN 2391455.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2391455
[3] Baker, M., Pan, X., & Wurgler, J. (2012). The effect of reference point prices on mergers and acquisitions. Journal of Financial Economics, 106(1), 49-71.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.04.010
[4] George, T. J., & Hwang, C. Y. (2004). The 52-week high and momentum investing. The Journal of Finance, 59(5), 2145-2176.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00695.x
[5] Barberis, N., & Thaler, R. H. (2003). A survey of behavioral finance. In G. M. Constantinides, M. Harris, & R. M. Stulz (Eds.), Handbook of the Economics of Finance (Vol. 1, pp. 1053-1128). Elsevier.
https://doi.org/10.3386/w9222
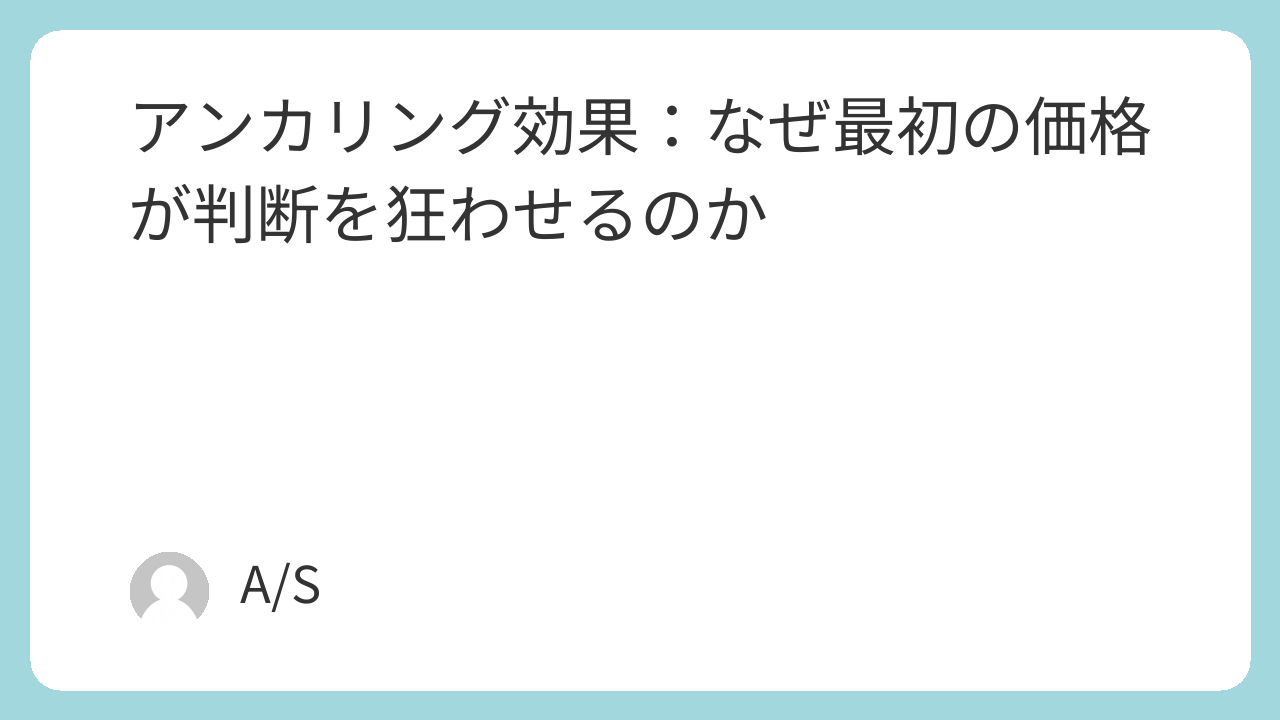
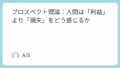
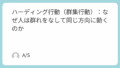
コメント