流動性という言葉は、一般的には「液体のようによどみなく流れる性質」を指しますが、金融や投資の世界では、市場の健全性や個々の資産の価値を測る上で、生命線を意味するほど重要な概念です。投資における流動性とは、ある資産を「いかに速く、いかに低コストで、価格を大きく変動させることなく」売買できるか、という度合いを示します。
例えば、日本円や米ドルのような主要通貨、あるいはトヨタ自動車のような巨大企業の株式は、世界中の無数の参加者が常に取引しており、極めて流動性が高い状態にあります。一方で、地方の土地や美術品、あるいは一部の小型株は、買い手を見つけるのに時間がかかったり、希望する価格で売るためには大幅な値引きが必要になったりします。これらは流動性が低い資産の典型例です。
この「売買のしやすさ」は、単なる利便性の問題に留まりません。資産の期待リターン、つまり将来どれだけ儲かるかの見込みにまで、直接的な影響を及ぼします。取引のしにくさ、すなわち非流動性は、投資家が負担すべきコストの一種であり、そのコストは資産価格に織り込まれるべきである、という考え方が古くから研究されてきました [1]。
この記事では、なぜ流動性が「市場の血液」とまで呼ばれるのか、その重要性とリスク、そして投資家がこの不可欠な概念をどのように自らの投資戦略に組み込んでいくべきかを、学術的な知見を基に初心者にも分かりやすく徹底解説します。
流動性の重要性:なぜ「いつでも売買できる」という前提は危険なのか
多くの投資家は、特に市場が安定しているときには、自分が保有する株式やその他の資産を「いつでも好きな時に、表示されている価格で売れる」と無意識に信じています。しかし、この前提は非常に危険です。流動性は常に存在するものではなく、時に枯渇し、投資家に深刻な損失をもたらす牙を剥きます。
流動性が価格に織り込む「隠れたコスト」
流動性を理解する上で最も基本的なコストが「ビッド・アスク・スプレッド」です。ビッド(買値)は買い手が提示する最も高い価格、アスク(売値)は売り手が提示する最も低い価格を指し、この二つの価格の差がスプレッドです。投資家が資産を買ってすぐに売ろうとすると、このスプレッドの分だけ必ず損失が出ます。これは、市場に即時性を要求するための手数料であり、流動性が低い資産ほどスプレッドは広がる傾向にあります [1]。
さらに、自分自身の取引が価格を不利な方向に動かしてしまう「価格インパクト」というコストも存在します。流動性が低い銘柄で大量の売り注文を出せば、買い注文が少ないため、株価は大きく下落してしまいます。これもまた、投資家が負担する隠れたコストなのです。
流動性リスク:売りたい時に売れない恐怖
流動性に関する最大のリスク、それが「流動性リスク」です。これは、市場環境の悪化などにより流動性が急激に枯渇し、資産を妥当な価格で売却できなくなるリスクを指します。2008年の金融危機では、多くの金融商品の流動性が一瞬にして蒸発し、売りたくても買い手が見つからないというパニック状態に陥りました。
このような市場全体の流動性が枯渇する局面では、個々の資産の価格は、そのファンダメンタルズ(本質的価値)とは無関係に暴落することがあります。そして、重要なのは、このような市場全体の流動性変動に敏感な資産は、より高いリスクを持つと見なされ、平時においても高い期待リターンを要求される、という事実が研究によって示されています [2]。
利益と損失の具体例:流動性を制する者と見過ごす者
- 損失例:流動性の罠にはまる投資家 ある投資家が、将来性を信じて時価総額の小さな新興企業の株式に多額の投資をしました。しかし、その後、予期せぬ悪材料が出て業績が悪化。投資家は損失を確定するために急いで売ろうとしますが、普段から取引が閑散としているため、買い注文が全く入りません。画面に表示されている株価は1000円でも、実際に売れるのは800円、あるいはそれ以下かもしれません。これが流動性リスクの現実です。
- 利益例:非流動性プレミアムを狙う投資家 一方、流動性の性質を熟知した長期投資家は、あえて流動性の低い資産に投資することがあります。なぜなら、市場参加者は一般的に流動性の低い資産を敬遠するため、それらの資産は本来の価値よりも割安な価格で放置されていることが多いからです。この価格の歪みは「非流動性プレミアム」と呼ばれ、長期間にわたって資産を保有できる投資家にとっては、超過リターンの源泉となり得ます [5]。彼らは、流動性リスクを許容する代わりに、その対価として高いリターンを狙うのです。
流動性を測るモノサシ:市場の深さを見抜く
流動性は目に見えませんが、いくつかの指標を通じてその度合いを客観的に測ることが可能です。これらのモノサシを使うことで、市場の「深さ」や「厚み」をある程度把握することができます。
ビッド・アスク・スプレッド:最も直接的な取引コスト
前述の通り、ビッド(買値)とアスク(売値)の差であるスプレッドは、流動性を測る最も直接的で分かりやすい指標です。スプレッドが狭い(小さい)ほど、売買のコストが低く、流動性が高いことを意味します [1].
売買代金と出来高:市場の活発度
特定の期間(通常は1日)にどれだけの金額の取引が成立したかを示す「売買代金」や、どれだけの株数が取引されたかを示す「出来高」も、流動性を測る基本的な指標です。これらの数値が大きいほど、市場参加者が多く、取引が活発であることを示しており、一般的に流動性が高いと判断できます。
カイルのラムダ:価格インパクトを測る指標
より専門的な指標として、アルバート・カイルが1985年の論文で提示したモデルに基づく「カイルのラムダ(Kyle’s Lambda)」があります [4]。これは、「ある一定の注文量(例えば1億円の買い)が、価格をどれだけ動かすか」という価格インパクトの度合いを測る指標です。このラムダの値が小さいほど、市場が大きな注文を吸収する能力(深さ)があり、流動性が高いことを示します。機関投資家などが大口の取引を行う際に、市場への影響を最小限に抑えるために重視する指標です。
市場に潜む非対称性と摩擦:流動性の視点から
流動性の世界は、全ての参加者が平等な情報を持つクリーンな場所ではありません。そこには、収益機会を生む「非対称性」と、リターンを蝕む「摩擦」が渦巻いています。
ポジティブファクター:情報の非対称性と流動性供給という機会
市場における最大の非対称性は「情報」です。企業の内部情報を持つインサイダーなど、一部の市場参加者は他の参加者が知らない情報を持っています。彼らが取引を行うと、その注文自体が新たな情報を市場に伝え、価格形成に影響を与えます [4]。この情報の非対称性が、市場の奥行きや流動性の変動を生み出す根源の一つです。
この状況は、一般投資家にとって収益機会にもなり得ます。例えば、市場がパニックに陥り、多くの人が恐怖から投げ売りしている(流動性を渇望している)状況で、冷静に買い向かう(流動性を供給する)ことは、一種の保険を売る行為に似ています。流動性が最も価値を持つ瞬間にそれを提供することで、割安な価格で資産を仕入れ、将来的に高いリターンを得る可能性があります。
ネガティブファクター:流動性リスクという根源的な摩擦
一方で、流動性はリターンを阻害する「摩擦」そのものでもあります。取引コスト(スプレッドや手数料)はもちろんのこと、より根源的な摩擦は「流動性リスク」の存在です。近年の資産価格理論の研究では、個々の資産の流動性だけでなく、その資産が「市場全体の流動性危機に対してどれだけ脆弱か」という点も、期待リターンを決定する重要な要素であることが示されています [2, 3]。
つまり、市場全体が混乱したときに、一緒に流動性が枯渇しやすい資産は、よりリスクが高いと見なされます。投資家は、この追加的なリスクを引き受ける対価として、より高いリターンを要求します。この「共通の流動性変動に対する感応度」を考慮せずにポートフォリオを組むことは、見えないリスクを抱え込むことであり、長期的なパフォーマンスを損なう要因となり得ます。
流動性の知識を投資に活かすための具体的なアクション
流動性の理論を学んだら、それを日々の投資判断に活かすことが重要です。初心者でもすぐに実践できることから、長期的に取り組むべきことまで、具体的な行動計画を紹介します。
すぐできること
- 取引前に売買代金とスプレッドを確認する: 株式などを売買する前には、必ずその銘柄の一日あたりの平均的な売買代金や、現在のビッド・アスク・スプレッドを確認する習慣をつけましょう。特に、自分の注文量が一日のでき高に比べて大きい場合は、価格インパクトが発生する可能性を念頭に置くべきです。
- 成行注文より指値注文を活用する: 「いくらでもいいから今すぐ売買したい」という成行注文は、予期せぬ高い価格で買ったり、安い価格で売ったりするリスクがあります。特に流動性が低い銘柄では、「この価格以下で買う」「この価格以上で売る」と指定する指値注文を基本とすることで、取引コストをコントロールできます。
長期的に取り組むこと
- ポートフォリオ全体の流動性を管理する: あなたの資産全体の中で、すぐに現金化できる資産(預金、流動性の高い株式や投資信託)と、そうでない資産(不動産、非公開株など)のバランスを意識しましょう。急な資金需要が発生した際に、流動性の低い資産を不利な条件で無理に売却しなくて済むように、ポートフォリオ全体の流動性を管理することが重要です。
- 非流動性プレミアムを意識した資産配分: 長期的な視点を持つことができるのであれば、非流動性プレミアムをリターンの源泉として活用することを検討しましょう。ポートフォリオの一部として、流動性は低いものの割安に放置されている資産クラスを組み入れることで、全体の期待リターン向上を目指すことができます [5]。ただし、その際は流動性リスクを十分に理解し、許容できる範囲に留めることが絶対条件です。
総括
この記事では、投資における流動性の概念について、その本質から実践的な応用までを解説しました。最後に、重要なポイントを振り返ります。
- 流動性とは、資産を「速く、安く、価格を乱さずに」売買できる度合いを示す、市場の健全性のバロメーターである。
- 流動性が低い資産には、ビッド・アスク・スプレッドや価格インパクトといった「隠れたコスト」が存在する。
- 市場全体の流動性が枯渇すると、売りたい時に売れない「流動性リスク」が発生し、価格が暴落することがある。
- 流動性リスクは体系的なリスクファクターの一つであり、投資家はそのリスクを引き受ける対価として、より高い期待リターン(非流動性プレミアム)を要求する。
- 投資家は、日々の取引で流動性を意識するとともに、長期的なポートフォリオ管理においても流動性のバランスを考慮することが重要である。
流動性は、空気のように、普段はその存在を意識しません。しかし、ひとたび失われれば、市場も投資家も窒息してしまいます。この「市場の血液」の流れを常に意識することが、賢明な投資家への第一歩となるでしょう。
用語集
- ビッド (Bid): 買い手が提示している最も高い購入価格。買値。
- アスク (Ask): 売り手が提示している最も低い売却価格。売値。
- スプレッド (Spread): ビッドとアスクの価格差。実質的な取引コストとなる。
- 出来高 (Volume): ある一定期間に売買が成立した株数や枚数。
- 板情報 (Order Book): ある銘柄に対して、どの価格にどれくらいの買い注文や売り注文が出されているかを示す一覧情報。
- マーケットメーカー (Market Maker): 常にビッドとアスクの両方を提示し、市場に流動性を供給する役割を担う業者。
- 価格インパクト (Price Impact): 自分自身の取引によって、市場価格が不利な方向に動いてしまうこと。
- 流動性リスク (Liquidity Risk): 市場の混乱などで流動性が枯渇し、保有資産を妥当な価格で売却できなくなるリスク。
- アセットプライシング (Asset Pricing): 資産の価格(期待リターン)が、どのような要因(リスク)によって決まるのかを説明する理論。
- 市場ミクロ構造論 (Market Microstructure): 個別の取引ルールや投資家行動が、どのように価格形成や流動性に影響を与えるかを分析する学問分野。
参考文献一覧
[1] Amihud, Y., & Mendelson, H. (1986). Asset Pricing and the Bid-Ask Spread. Journal of Financial Economics, 17(2), 223-249.https://doi.org/10.1016/0304-405X(86)90065-6
[2] Pástor, Ľ., & Stambaugh, R. F. (2003). Liquidity Risk and Expected Stock Returns. Journal of Political Economy, 111(3), 642-685.https://doi.org/10.3386/w8462
[3] Acharya, V. V., & Pedersen, L. H. (2005). Asset Pricing with Liquidity Risk. Journal of Financial Economics, 77(2), 375-410.https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.06.007
[4] Kyle, A. S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading. Econometrica, 53(6), 1315-1335.https://doi.org/10.2307/1913210
[5] Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56.https://doi.org/10.1016/S1386-4181(01)00024-6
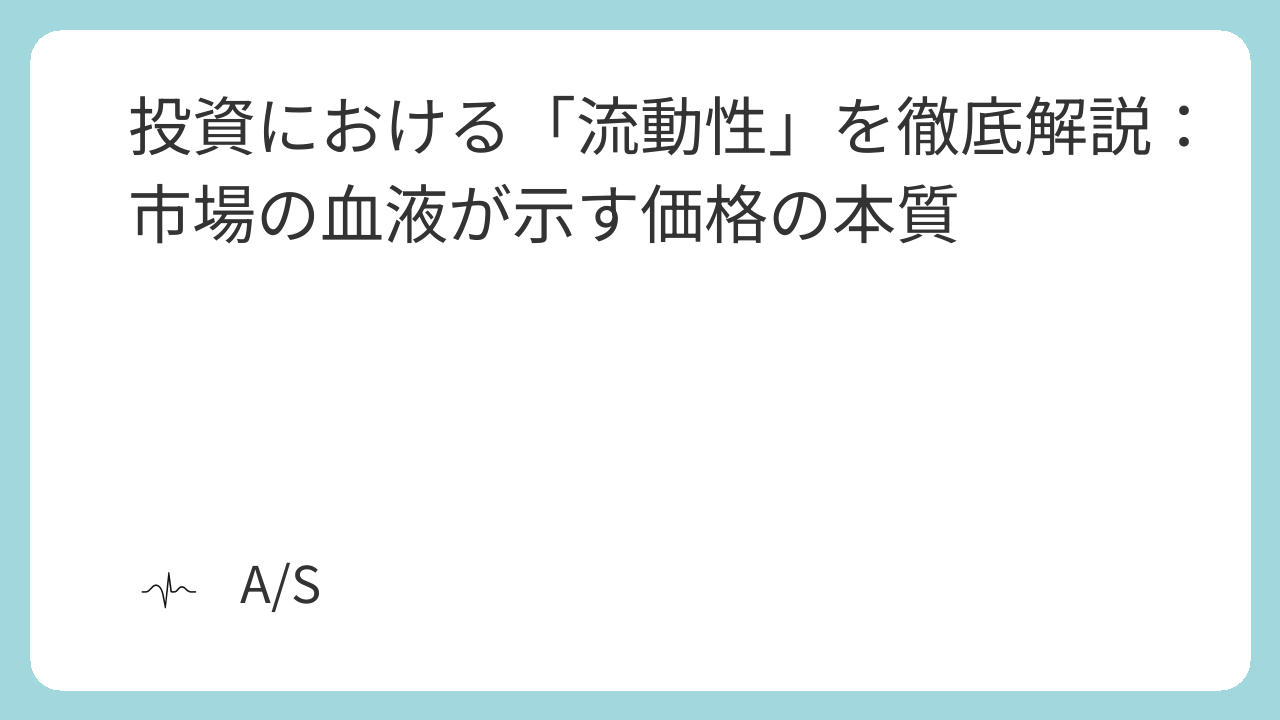
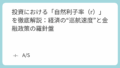
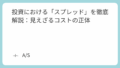
コメント