もし、コインを投げて表が出たら20万円もらえ、裏が出たら10万円を支払うというゲームがあったら、あなたは参加するでしょうか。このゲームの期待値を計算すると、プラス5万円(20万円 × 0.5 – 10万円 × 0.5)となり、計算上は「得な賭け」です。しかし、多くの人は参加をためらうかもしれません。なぜなら、失う10万円の「痛み」が、得る20万円の「喜び」を上回ると感じるからです。この直感的な判断のズレを説明するのが期待効用という概念です。
期待効用理論の源流は、18世紀の数学者ダニエル・ベルヌーイの研究にまで遡ります [1]。彼は、人々は金額そのものではなく、その金額から得られる「効用」、すなわち主観的な満足度に基づいて意思決定を行うと考えました。そして、富が増えるほど、追加的な富から得られる効用は小さくなる(限界効用の逓減)と指摘しました。つまり、資産がゼロの人にとっての10万円と、資産が1億円の人にとっての10万円では、後者の方が満足度の増加分がはるかに小さいのです。
投資の世界では、この考え方が極めて重要になります。投資とは、不確実な未来に対して資金を投じる行為です。単にリターンの期待値が高いという理由だけで投資先を選ぶのは、必ずしも合理的な判断とは言えません。期待効用理論は、それぞれの結果がもたらす満足度と、その結果が生じる確率を掛け合わせることで、投資家の個人的なリスク許容度を反映した、より本質的な意思決定の基準を提供します。この理論は後に、フォン・ノイマンとモルゲンシュテルンによって公理的な体系として整備され、経済学における不確実性下の意思決定モデルの根幹をなすことになりました [2]。
この記事では、期待効用という投資判断の羅針盤となるべき概念を深く掘り下げ、その重要性、限界、そして実際の投資にどう活かすべきかを、学術的な知見を基に解説していきます。
期待効用理論が投資判断の質を変える
期待効用を理解し、自身の投資判断に取り入れることは、単なる理論の学習にとどまらず、実践的な利益につながり、また大きな損失を回避するための強力な武器となります。
期待効用を知らないことのリスク
期待効用の概念を知らず、リターンの期待値だけで投資判断を下すことの最大のリスクは、自身の許容度を超えたリスクを無自覚に受け入れてしまうことです。例えば、期待リターンは20%と非常に高いものの、最悪の場合は投資額の90%を失う可能性がある金融商品があったとします。期待値だけを見れば魅力的に映るかもしれませんが、もしその90%の損失が、あなたの生活基盤を揺るがすほどのダメージを与えるなら、それは決して「良い投資」とは言えません。期待効用の視点がなければ、こうした「期待値の罠」にはまり、一度の失敗で再起不能な損失を被る危険性があるのです。
利益例:リスク回避的な意思決定による資産防衛
ある退職者が、退職金を元手に資産運用を考えているとします。選択肢は、期待リターン10%だが価格変動の激しい成長株ポートフォリオAと、期待リターンは4%と低いものの、価格が安定している高配当株と債券のポートフォリオBです。期待値だけを比べればAが優れています。しかし、この退職者は期待効用に基づき、大きな損失を被る可能性のあるAのリスクを重く見ました。彼にとって、資産を大きく増やす喜びよりも、老後の生活資金を失う痛みの方がはるかに大きいのです。そのため、彼はBを選択しました。その後、市場が暴落した際、Aの価値は半減しましたが、Bはわずかな下落にとどまりました。彼は期待効用を用いることで、目先の高いリターンよりも資産の保全を優先し、結果的に資産を守ることに成功したのです。
損失例:主観的確率の過信
期待効用理論は、客観的な確率だけでなく、投資家自身の「主観的な確率」にも適用できる形で発展しました [3]。これは、将来の株価動向のように明確な確率が分からない状況で特に重要になります。しかし、ここに落とし穴もあります。ある投資家が、特定のテクノロジーに未来があると信じ込み、その分野のスタートアップ企業Dの成功確率を極めて高く見積もったとします。彼は自身の主観的確率と期待効用に基づき、資産の大部分をD社に集中投資しました。しかし、彼の予測は楽観的すぎました。技術開発は難航し、D社は倒産。彼は資産のほとんどを失いました。これは、期待効用モデル自体が間違っていたのではなく、その入力値である主観的確率の評価を誤ったことが原因です。期待効用は強力なツールですが、その前提となる確率評価の精度に結果が大きく左右されるのです。
期待効用理論の公理とその現実からの乖離
期待効用理論は、いくつかの「公理」と呼ばれる基本的な前提条件の上に成り立っています。これらの公理を満たす限りにおいて、人間は合理的に期待効用を最大化するように行動するとされます [2]。しかし、現実の人間の行動は、必ずしもこの合理的なモデル通りではありません。
合理性の土台となる公理
期待効用理論を支える代表的な公理には、「完備性(どんな選択肢も比較可能)」「推移性(AがBより良く、BがCより良ければ、AはCより良い)」「独立性」などがあります。特に重要なのが独立性の公理です。これは、ある二つの選択肢に、全く無関係な第三の選択肢を同じ確率で加えても、元の二つの選択肢の間の好みの順序は変わらない、というものです。例えば、株式Aと株式BでAを好むなら、「50%の確率でA、50%の確率で映画のチケットがもらえる」くじと、「50%の確率でB、50%の確率で映画のチケットがもらえる」くじとでは、前者を選ぶべきだ、という考え方です。この公理があるからこそ、複雑な選択肢を単純な要素に分解して期待効用を計算できるのです。
理論と現実のギャップ:アノマリーの発見
しかし、実際の人間は、この独立性の公理に反するような行動を取ることが実験で示されています(アロのパラドックスなど)。このような理論からの逸脱は「アノマリー」と呼ばれ、なぜそうした非合理的な判断が生まれるのかを説明するために、様々な新しい理論が提唱されてきました。例えば、独立性の公理を緩和しても、意思決定の理論的枠組みを維持しようとする試み [4] や、人々が確率そのものを主観的に歪めて認識する傾向をモデルに組み込んだランク依存期待効用理論 [5] などが登場しています。これらは、標準的な期待効用理論が万能ではないことを示唆しており、投資の世界における人間の複雑な心理を理解する上で重要な視点を提供します。
期待効用に潜む非対称性と摩擦
当メディアの分析の核である「非対称性」と「摩擦」の観点から期待効用理論を捉え直すと、投資家がエッジを見出すための新たな洞察が得られます。
ポジティブファクター:非対称性(Asymmetry)
期待効用理論における非対称性は、理論的な「合理的人間」と、現実の「心理的な人間」との間に存在するギャップから生まれます。市場に参加している多くの人々が、標準理論の公理から逸脱した、心理的バイアスのかかった意思決定を行っています。例えば、損失を極端に嫌う「損失回避性」や、低い確率を過大評価し、高い確率を過小評価する傾向などがそれに当たります。
このギャップを深く理解している投資家は、非対称な収益機会を見出すことができます。市場全体が特定のリスクを過度に恐れ、ある資産がその本質的価値以下で取引されている場合、それは「恐怖」という感情が市場の期待効用を歪めているサインかもしれません。合理的な期待効用モデルと、現実の市場心理から生まれる価格との差を分析することで、割安な資産を発見するエッジ(優位性)が生まれるのです。標準理論の限界を指摘し、それを乗り越えようとする新しい理論 [4, 5] は、まさにこの非対称性を捉えるための分析ツールと言えるでしょう。
ネガティブファクター:摩擦(Friction)
期待効用を実践する上での「摩擦」は、主に投資家自身の内部に存在する認知的な、あるいは心理的な障害です。
第一に、「自己認識の摩擦」です。自分自身の真のリスク許容度、すなわち効用関数を正確に把握することは極めて困難です。市場が平穏な時には自分はリスクを取れると思っていても、暴落局面ではパニックに陥ってしまうかもしれません。この自己評価の不確実性が、一貫した合理的な意思決定を妨げる大きな摩擦となります。
第二に、「計算の摩擦」です。現実の投資シナリオは無数の可能性を内包しており、それら全ての確率と効用を算出して期待効用を計算することは、事実上不可能です。この情報処理能力の限界という摩擦が、人々をより単純なヒューリスティック(経験則)に頼らせ、結果として非合理的な判断を招く原因となります。
第三に、「モデルの摩擦」です。前述の通り、標準的な期待効用理論自体が現実の人間の行動を完全には説明しきれません。理論という地図が、現実という地形と完全には一致していないのです。このモデルの不完全性を理解せずに理論を盲信することは、かえって判断を誤らせるリスクとなり、これもまた意思決定における摩擦として機能します。
期待効用の知識を投資に活かすための具体的なアクション
期待効用理論は抽象的に聞こえるかもしれませんが、その本質を理解し、日々の投資活動に落とし込むための具体的な方法は存在します。
すぐできること
まず、投資判断を下す際に、単一の期待リターンだけでなく、複数のシナリオを考える習慣をつけましょう。「最もあり得るシナリオ(基本シナリオ)」に加えて、「最高の結果(楽観シナリオ)」と「最悪の結果(悲観シナリオ)」を具体的に想像するのです。そして、特に悲観シナリオが現実になった場合、それが自身の生活や精神にどのような影響を及ぼすかを自問自答してください。このプロセスは、数値化できない「効用」や「非効用(苦痛)」を意思決定に組み込むための簡単なトレーニングになります。
長期的に取り組むこと
長期的には、自分自身の「投資哲学」を明文化することをお勧めします。これは「投資方針書(Investment Policy Statement)」とも呼ばれます。そこには、自身の投資目的、投資期間、そして最も重要なリスク許容度を具体的に記述します。例えば、「1年間で最大〇%までの資産減少は、長期的な目標達成のためなら許容できる」といった具合です。このように自分自身の効用関数をあらかじめ定義しておくことで、市場の短期的な変動に惑わされず、一貫性のある意思決定を下すための強力な錨となります。また、アロのパラドックスに代表されるような、人間が陥りがちな意思決定の罠について学ぶ(行動経済学の知見に触れる)ことも、長期的にみて、より合理的な投資家へと成長するための助けとなるでしょう。
総括
この記事では、投資における意思決定の質を根底から変える力を持つ、期待効用理論について解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。
- 人々は金額の期待値ではなく、そこから得られる満足度、すなわち「期待効用」を最大化するように行動します。
- 期待効用理論は、資産が増えるほど追加的な資産から得られる満足度が減る「限界効用の逓減」を前提としています。
- 期待値だけで投資判断を行うと、自身の許容度を超えたリスクを取ってしまう危険性があります。
- 現実の人間の行動は、必ずしも理論通りではなく、心理的なバイアスから非合理的な判断を下すことがあります。
- 理論と現実のギャップは、市場の非効率性、すなわち「非対称な」収益機会の源泉となり得ます。
- 自身の効用関数を正確に把握することの難しさなどが、合理的な意思決定を妨げる「摩擦」として作用します。
用語集
- 期待値: ある試行によって得られる結果の数値と、その結果が起こる確率を掛け合わせ、全ての可能性について合計した値。確率的な事象における平均値。
- リスク回避: 同じ期待値の選択肢がある場合、よりリスク(結果のばらつき)が小さい方を好む選好のこと。効用関数が上に凸(凹関数)の形で表現される。
- 公理: ある理論体系を構築する上で、最も基本的な前提として置かれる仮定。証明なしに真であると認められる命題。
- 効用関数: 消費や資産の量から、個人が得る満足度(効用)を導出するための関数。
- 主観的確率: コインの裏表のように客観的に定まらない事象に対して、個人が自身の信念や情報に基づいて割り当てる確率のこと。
- アノマリー: 既存の標準的な理論ではうまく説明できない、経験則や市場の観測結果のこと。
参考文献一覧
[1] Bernoulli, D. (1738/1954英訳). “Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk.” Econometrica.
https://doi.org/10.2307/1909829
[2] Herstein, I. N., & Milnor, J. (1953). “An Axiomatic Approach to Measurable Utility.” Econometrica.
https://doi.org/10.2307/1905540
[3] Savage, L. J. (1954). The Foundations of Statistics.
※書籍です
[4] Machina, M. J. (1982). “Expected Utility Analysis without the Independence Axiom.” Econometrica.
https://doi.org/10.2307/1912631
[5] Quiggin, J. (1982). “A Theory of Anticipated Utility.” Journal of Economic Behavior & Organization.
https://doi.org/10.1016/0167-2681(82)90008-7
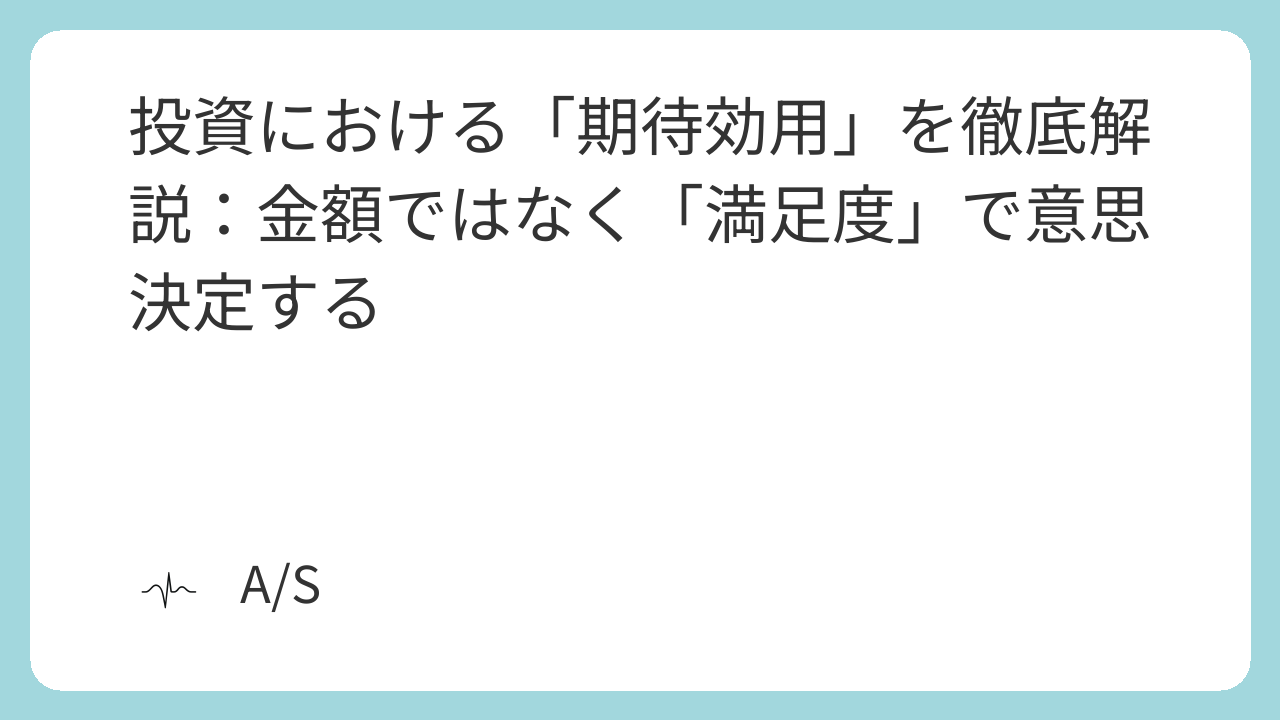
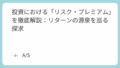
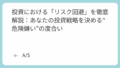
コメント