リスク回避は、経済学や金融の世界で人間の意思決定を理解するための根幹をなす概念です。一般的に「リスクを避けること」と理解されていますが、投資におけるリスク回避とは、より正確には「期待値が同じであれば、より確実性の高い選択肢を好む傾向」を指します。不確実性を嫌う度合い、と言い換えることもできるでしょう。
例えば、目の前に二つの選択肢があるとします。一つは、コインを投げて表が出れば20万円もらえ、裏が出れば何ももらえないという賭けです。もう一つは、無条件で確実に10万円がもらえるという選択肢です。どちらも得られる金額の期待値は10万円と同じですが、多くの人は後者の確実な10万円を選ぶでしょう。このような選好がリスク回避的な行動の典型です。
この現象は、伝統的な経済学において「期待効用理論」で説明されます。この理論の根底には「限界効用の逓減」という考え方があります。これは、得られる富が増えるほど、そこから得られる追加的な満足度(効用)は次第に減少していくという法則です。例えば、資産がゼロの人にとっての10万円と、資産が1億円の人にとっての10万円とでは、後者の方が満足度の増加ははるかに小さいはずです。この満足度の曲線の「曲がり具合」が、リスク回避の度合いを数学的に表現するものとなります。
このようなリスク回避の度合いを測定するための基礎を築いたのが、Pratt [1] とArrow [2] による研究です。彼らが提唱した計測方法は、現代の金融理論においてもポートフォリオ選択や資産価格決定モデルの根幹をなしており、投資を学ぶ上で避けては通れない重要な概念となっています。この記事では、このリスク回避という概念を学術的な知見を基に深く掘り下げ、投資家が自らの投資行動を理解するための一助となることを目指します。
リスク回避度があなたの投資リターンを決める
投資の世界において、自分自身のリスク回避度、すなわち「どれだけリスクを嫌うか」を理解することは、長期的に資産を形成していく上で極めて重要です。この度合いを無視して投資戦略を立てると、精神的な苦痛を伴うだけでなく、最終的に大きな損失を被る危険性があります。
リスク回避度を無視する危険性:パニック売りと機会損失
もしあなたが本質的にリスク回避度が高い(不確実性を強く嫌う)にもかかわらず、流行や他人の成功話に煽られてハイリスク・ハイリターンな株式に多額の資金を投じたとします。市場が好調な時は良いかもしれませんが、暴落局面が訪れた時、あなたはおそらく冷静ではいられないでしょう。資産価値が日に日に減少していく恐怖に耐えきれず、株価が底値に近いところで全ての株式を投げ売りしてしまう、いわゆる「狼狽売り(パニック売り)」をしてしまう可能性が非常に高いのです。これは、資産の大部分を失う典型的な失敗パターンです。
逆に、リスク許容度が比較的高いにもかかわらず、過度にリスクを恐れて元本保証の預金にばかり資産を置いているとどうなるでしょうか。インフレによって実質的な資産価値が目減りしていく中で、本来得られたはずの株式市場の成長リターンを取り逃がすことになります。これは「機会損失」と呼ばれるものです。
リスク回避度を理解する利益:最適なポートフォリオの構築
自分自身のリスク回避度を正しく把握することで、精神的に安寧を保ちながら、長期的な目標達成を目指せる最適な資産配分(ポートフォリオ)を構築することが可能になります。
リスク回避度の高い投資家は、国債や投資適格社債、あるいは預金といった安全資産の比率を高めに設定します。これにより、市場が急変しても資産価値の大きな下落を避け、精神的な平穏を保つことができます。一方で、リスク回避度の低い(リスク許容度が高い)若い投資家などは、株式や不動産といったリスク資産の比率を高めることで、より大きなリターンを積極的に狙っていく戦略を取ることができます。このように、リスク回避度は万人に共通の正解があるわけではなく、各々の投資家が自身の特性に合わせて投資戦略を調整するための羅針盤となるのです。
期待効用理論への挑戦:ラビンのキャリブレーション定理
伝統的な期待効用理論は、長らくリスク回避を説明する支配的なモデルでした。しかし、この理論が現実の人々の行動を完全には説明しきれないことも、次第に明らかになってきました。その限界を鋭く指摘したのが、経済学者マシュー・ラビンが提唱した「キャリブレーション定理」です。
Rabin [3] とRabin & Thaler [4] の研究は、期待効用理論が持つ根本的な矛盾を明らかにしました。彼らが示したのは、私たちが日常的に示すような、少額の賭けに対する穏当なリスク回避的な態度を伝統的な期待効用理論の枠組みで説明しようとすると、論理的にあり得ない結論が導かれてしまうというものです。
例えば、「50%の確率で11ドル儲かるか、10ドル損をする」という、少しだけ期待値がプラスの賭けを断る人がいたとします。これは、ごく自然なリスク回避行動に見えます。しかし、この行動を伝統的な限界効用の逓減で説明した場合、その人は「100ドルを失うリスクを避けるためなら、たとえ10億ドル儲かるチャンスがあってもその賭けを断る」という、極端すぎるリスク回避傾向を持つことになってしまいます。現実には、そのような人はいません。
このキャリブレーション(較正)論争は、期待効用理論が、特に少額のリスクと高額のリスクをまたがる人々の選択をうまく説明できないことを示しました。そして、損失を利益よりも重く評価する「損失回避」といった、新しい行動経済学の概念(プロスペクト理論など)が注目されるきっかけとなり、人間のリスクに対する態度がより複雑であることを学術的に明らかにしたのです。
マーケットに潜む非対称性と摩擦の視点から見たリスク回避
当メディアの核心的テーマである「非対称性」と「摩擦」の観点からリスク回避を分析すると、この概念がマーケットで果たす役割をより立体的に捉えることができます。
ポジティブファクター:リスク回避度の差が生む非対称な機会
株式市場には、さまざまなリスク回避度を持つ投資家が参加しています。このリスク選好の多様性こそが、市場に厚みをもたらし、非対称な収益機会を生み出す源泉となります。
例えば、リスク回避度の非常に高い投資家(年金基金など)は、価格変動の激しい小型成長株や新興国の株式を敬遠します。彼らがこれらの資産を避けることで、これらの市場には相対的に高い「リスクプレミアム」が生まれる可能性があります。リスクプレミアムとは、不確実性(リスク)を引き受けることに対する上乗せリターンのことです。この状況は、リスク許容度の高い別の投資家にとっては、非対称な収益チャンスとなります。他の人が避けるリスクをあえて引き受けることで、市場平均を上回るリターン(アルファ)を狙うことができるのです。市場は、リスクを避けたい人と、リスクを取ってリターンを得たい人の間の「リスクの移転」の場として機能していると言えます。
ネガティブファクター:リスク回避度を測る難しさという摩擦
投資における「摩擦」とは、合理的な意思決定を阻害する要因です。リスク回避に関して言えば、投資家が「自分自身の本当のリスク回避度を正確に把握できない」という問題が、最も大きな摩擦として作用します。
証券会社の口座開設時に行われるアンケートなどでリスク許容度を診断されますが、それだけで自身の本質的なリスク回避度を正確に知ることは困難です。多くの投資家は、市場が平穏な時には自分のリスク許容度を過大評価しがちです。そして、実際に暴落が起きた時に初めて、自分が思っていたよりもずっとリスク回避的であったことに気づき、パニックに陥るのです。このような自己認識のズレという「摩擦」は、不合理な売買を引き起こし、深刻な損失の源泉となります。この摩擦をいかにして低減するかは、投資家教育における重要な課題です。なお、Chettyの研究 [5] では、人々の労働供給に関するデータからリスク回避度を推定するという実証的な手法が提案されるなど、この摩擦を乗り越えようとする学術的な試みも進んでいます。
リスク回避の知識を投資に活かすための具体的なアクション
リスク回避という概念を理解したら、次はその知識を実際の投資行動に結びつけることが重要です。ここでは、明日から実践できる具体的なアクションプランを提案します。
すぐできること
まずは、あなた自身の金銭感覚と向き合うための簡単な思考実験をしてみましょう。もし、あなたが現在行っている投資の評価額が、今後半年間で半分になったと想像してみてください。その時、あなたは夜安心して眠れるでしょうか。日常生活に支障をきたすほど、不安になったり、仕事が手につかなくなったりするでしょうか。
この質問に対して、もし「耐えられない」と感じるのであれば、あなたは現在、自分のリスク許容度を超えたリスクを取っている可能性が高いです。これは、投資戦略を見直す必要があるという重要なサインです。このシンプルな問いかけは、抽象的なリスク回避度を、あなた自身のリアルな感情と結びつけるための第一歩となります。
長期的に取り組むこと
長期的な資産形成を成功させるための鍵は、感情に左右されない規律あるリスク管理です。そのために最も有効な戦略の一つが、あらかじめ定めた資産配分(アセットアロケーション)を維持し続けることです。
投資を始める前に、「株式に60%、債券に40%」といったように、自分のリスク回避度に合った資産配分を決定します。そして、市場の変動によってこの比率が崩れた場合(例えば、株価の上昇で株式の比率が70%になった場合)、定期的に元の比率に戻す「リバランス」を実行します。値上がりした株式の一部を売却し、その資金で債券を買い増すのです。このプロセスは、感情とは無関係に「高くなったものを売り、安くなったものを買う」という合理的な行動を機械的に実践させてくれます。これにより、リスクを取りすぎることなく、長期的なリターンの最大化を目指すことが可能になります。
総括
この記事では、投資戦略の基礎となるリスク回避の概念について、その本質から実践的な応用までを解説しました。以下に重要なポイントをまとめます。
- リスク回避とは、期待値が同じならより確実な結果を好む傾向であり、その度合いは「限界効用の逓減」によって説明される。
- 自分自身のリスク回避度を理解することは、パニック売りなどの失敗を避け、最適なポートフォリオを構築するための第一歩である。
- 伝統的な期待効用理論は、少額のリスクと高額のリスクを巡る人間の行動を完全には説明できないという矛盾が指摘されている(ラビンのキャリブレーション定理)。
- 市場では、リスク回避度の異なる投資家間の相互作用が、リスクプレミアムという非対称な収益機会を生み出している。
- 自身の本当のリスク回避度を正確に把握することの難しさは、不合理な投資行動を招く「摩擦」として作用する。
- 具体的な対策として、資産が半減した場合を想像する思考実験や、定期的なリバランスの実践が有効である。
用語集
- 期待効用理論: 不確実性下における意思決定を説明する理論。人々は金額の期待値ではなく、そこから得られる満足度(効用)の期待値を最大化するように行動すると仮定する。
- 限界効用: 財やサービスを1単位追加で消費することによって得られる満足度の増加分。
- ポートフォリオ: 投資家が保有する、株式、債券、不動産などの金融資産の組み合わせ、またその内容。
- リスクプレミアム: 不確実な資産を保有する対価として、安全資産のリターンを上回ることが期待される追加的なリターン。
- アセットアロケーション: 資産配分のこと。投資資金を株式、債券、不動産など異なる種類の資産に、どのような割合で配分するかを決定する投資戦略。
- リバランス: 資産配分の比率が市場の変動によって当初の計画から乖離した際に、資産の一部を売買して元の比率に戻す調整作業。
参考文献一覧
[1] Pratt, J. W. (1964). Risk Aversion in the Small and in the Large. Econometrica, 32(1/2), 122-136.https://doi.org/10.2307/1913738
[2] Arrow, K. J. (1965). Aspects of the Theory of Risk-Bearing. Yrjö Jahnsson Foundation.
※書籍です。
[3] Rabin, M. (2000). Risk Aversion and Expected-Utility Theory: A Calibration Theorem. Econometrica, 68(5), 1281-1292.https://escholarship.org/uc/item/731230f8
[4] Rabin, M., & Thaler, R. H. (2001). Anomalies: Risk Aversion. Journal of Economic Perspectives, 15(1), 219-232.
※書籍です。
[5] Chetty, R. (2006). A New Method of Estimating Risk Aversion. American Economic Review, 96(5), 1821-1834.
※書籍です。
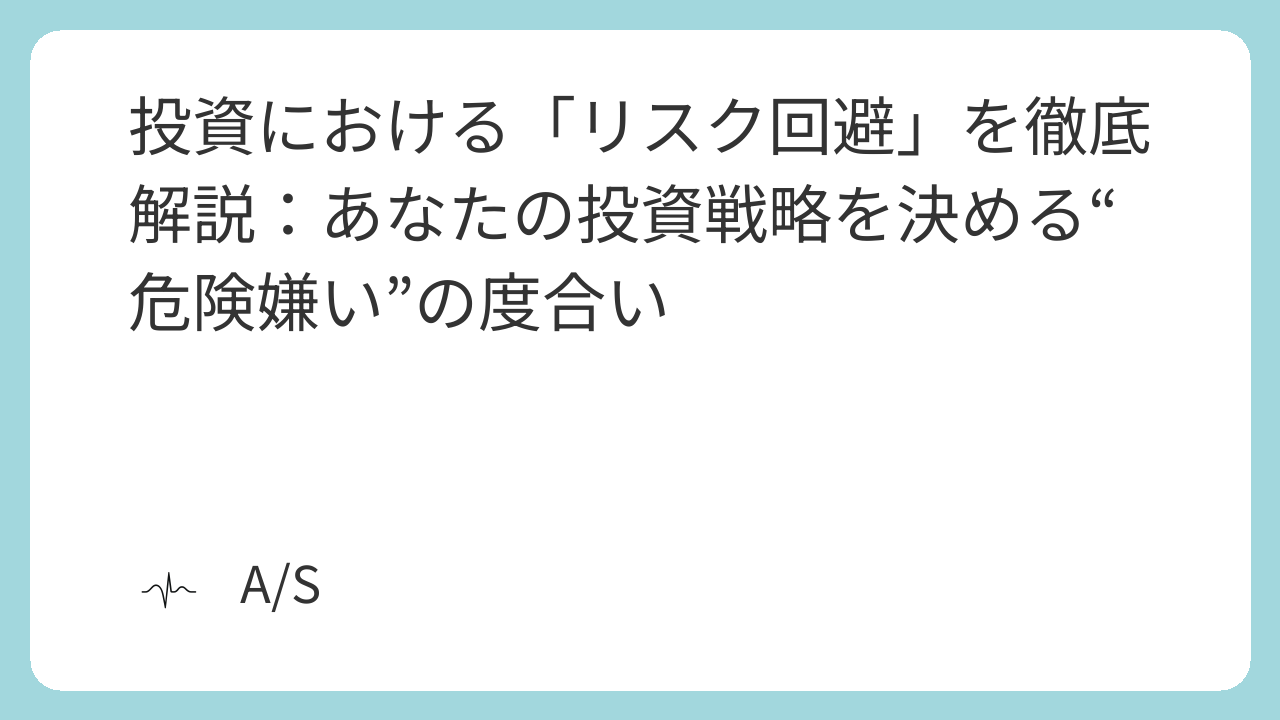
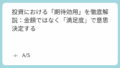
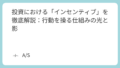
コメント