概論
ある銘柄について徹底的に分析し、「この株は絶対に上がる」という強い信念を持って大きなポジションを取ったとします。しかし、その直後から株価は下落を始め、含み損は日に日に拡大していく。この時、あなたの心の中では何が起こるでしょうか。
「自分の分析は正しかったはずだ」という信念と、「現実に損失が出ている」という客観的な事実。この二つの矛盾した認知は、私たちに強烈な心理的ストレス、すなわち認知的不協和(Cognitive Dissonance)をもたらします。
この理論は、社会心理学者のレオン・フェスティンガーが1957年の著作で提唱した、人間の心理に関する極めて影響力の大きい理論です [1]。フェスティンガーによれば、人間は、自らの信念や態度と、実際の行動や新しい情報との間に矛盾が生じると、不快な緊張状態(不協和)に陥ります。そして、私たちは、この不快感を解消するために、無意識のうちに、矛盾する認知のどちらかを変更したり、あるいは自分の行動を正当化するための新しい理屈を探し始めたりするのです。
この心理メカニズムを巧みに示したのが、フェスティンガーとカールスミスによる1959年の古典的な実験です [2]。彼らは、被験者に極めて退屈な作業をさせた後、次の被験者に対して「この作業は面白かった」と嘘をつくよう依頼しました。その際、あるグループには報酬として1ドルを、別のグループには20ドルを支払いました。
その後、被験者に作業の本当の感想を尋ねたところ、驚くべき結果が出ました。高額な報酬(20ドル)を得たグループは、嘘をついたことを「金のためだ」と簡単に正当化できたため、作業への評価は低いままでした。しかし、わずかな報酬(1ドル)しか得られなかったグループは、「たった1ドルのために嘘をついた」という強い不協和を解消するため、自らの記憶の方を修正し、「あの作業は、実はそれほど退屈ではなかった」と、本心から信じ込むようになっていたのです。
この強力な自己正当化のメカニズムは、トレーディングの世界において、投資家を深刻な判断ミスへと導く、最も危険な心理的罠の一つです。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
短所、弱み、リスクについて:不協和が引き起こす自己正当化の罠(損失事例)
認知的不協和を解消しようとする無意識の働きは、トレーダーに、損失をさらに拡大させるような、体系的に不合理な行動を取らせます。
コミットメントの段階的拡大(サンクコストの罠)
認知的不協和が引き起こす最も破壊的な行動の一つが、コミットメントの段階的拡大(Escalation of Commitment)、すなわち「サンクコストの罠」です。
バリー・ストウによる1976年の研究は、この問題を明らかにしました [3]。一度、あるプロジェクトに対して大きな投資(コミットメント)を行った後で、そのプロジェクトが失敗しつつあるというネガティブな情報に直面すると、意思決定者は強い認知的不協和に陥ります。「賢明な自分が、失敗するプロジェクトに投資したはずがない」という不協和を解消するため、彼らは当初の決定が正しかったと自分に言い聞かせ、失敗しているプロジェクトに、さらに追加の資金を投じてしまうのです。
これは、含み損を抱えたトレーダーが、損切りをする代わりにナンピン買いを繰り返す行動と全く同じです。「この銘柄を選んだ自分の判断は正しいはずだ」という信念を守るために、損失が出ているポジションに固執し、さらにリスクを拡大させてしまうのです。
ディスポジション効果の心理的背景
認知的不協和は、ディスポジション効果(利益が出ている株は早く売り、損失の出ている株は塩漬けにする)の背後にある、より深い心理的なメカニズムを説明します。
シェフリンとスタットマンの研究でも論じられているように、含み損のポジションを決済(損切り)する行為は、「自分の最初の判断が間違っていた」という事実を、自分自身に対して公式に認める行為です [4]。これは、自己イメージを傷つける、極めて痛みを伴う認知的不協和を生み出します。この不快感を避けるために、トレーダーは損切りを先延ばしにし、「いつか戻るはずだ」という希望的観測にすがるのです。
確証バイアスの強化
自らの判断が間違いであったかもしれない、という不協和を解消するもう一つの簡単な方法は、自分の判断が正しかったという証拠だけを探し、それに反する証拠は無視することです。これは確証バイアスとして知られています。
エイカーロフとディケンズによる1982年の研究は、認知的不協和が、人々をいかにして不都合な情報から目をそむけさせるかを経済モデルで示しました [5]。含み損を抱えたトレーダーは、その銘柄に関するポジティブなニュースや分析ばかりに目が行くようになり、ネガティブな情報を無意識のうちにフィルタリングしてしまうのです。
長所、強み、有用な点について:バイアスを理解し、自己を律する力
認知的不協和は、それ自体が利益を生むものではありません。しかし、この抗いがたい自己正当化のメカニズムが自分の中に存在することを深く理解することは、致命的な過ちから自らを守るための、最も強力な「強み」となります。
客観的なルールの設定
このバイアスを乗り越える唯一の方法は、取引を行う前に、客観的で、厳格なルール(トレーディングプラン)を設定し、感情を排してそれに従うことです。特に、「この水準まで価格が下落したら、いかなる理由があろうとも損切りする」というストップロス注文は、認知的不協和がもたらす自己正当化の罠に対する、最も有効な防衛策です。
トレーディング・ジャーナルの活用
自らの取引を記録し、その判断根拠を客観的に振り返るトレーディング・ジャーナルもまた、このバイアスと戦うための強力な武器です。不協和を解消するために後から作り上げた「言い訳」ではなく、取引時点での「事実」と向き合うことで、自らの判断パターンを客観的に分析し、改善していくことが可能になります。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、認知的不協和はこれほどまでに強力で、私たちの合理的な判断をいとも簡単に狂わせてしまうのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:信念と現実の「非対称性」
認知的不協和の根源には、私たちの内なる「信念の世界」と、外的な「現実の世界」との間に存在する、決定的な非対称性があります。
私たちは、「自分は賢明で、有能な意思決定者である」というポジティブな自己イメージ(信念)を維持したいと強く願っています。しかし、市場は容赦なく、私たちの判断が間違っていたという客観的な事実(損失)を突きつけてきます。この「かくありたい自分」と「かくある現実」との間のギャップこそが、不協和という心理的な痛みを生み出すのです。
そして、この痛みを解消しようとする人間の反応もまた、非対称です。合理的な人間であれば、新しい現実(損失)に合わせて、自らの信念(「私の分析は間違っていた」)を対称的に更新するはずです。しかし、人間の心は、信念よりも現実の方をねじ曲げて解釈しようとします。つまり、「私の分析は正しいままで、現実(市場)の方が一時的に間違っているのだ」と、信念を維持するために現実の解釈を非対称に歪めてしまうのです。この非対称な自己防衛メカニズムこそが、コミットメントの段階的拡大 [3]のような、非合理的な行動の源泉なのです。
Friction:「自己イメージ」という抗いがたい認知的摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、認知的不協和というバイアスは、私たちの自己認識そのものに根差した、極めて強力な「摩擦」によって増幅されます。
自我防衛という認知的摩擦
含み損を抱えたポジションを損切りする、という行為は、単なる金銭的な損失を確定させる以上の意味を持ちます。それは、「この銘柄を選んだ自分は、間違っていた」という事実を、自分自身に対して認め、受け入れるという、極めて苦痛な行為です。
この「自己イメージ(自我)を守りたい」という強烈な欲求が、合理的な判断を妨げる、最も強力な認知的な摩擦として機能します。損失を確定させる痛みを避けるために、私たちは、自分の間違いを正当化する様々な理由(「これは長期投資だ」「市場がパニックなだけだ」)を探し始め、その結果、客観的な判断能力を失ってしまうのです。
サンクコストという摩擦
あるポジションに時間、労力、そして感情的なエネルギーを注ぎ込めば注ぎ込むほど、そのポジションに対する「コミットメント(関与)」は深まっていきます。この、既につぎ込んでしまい、もはや取り戻すことのできないコスト(サンクコスト)が、不協和をさらに増幅させ、合理的な撤退を妨げる摩擦となります [3]。
多額の資金を投じたポジションほど、それを手仕舞うことは、自らの過去の判断全体を否定するような、より大きな心理的苦痛を伴います。この摩擦が、いわゆる「ナンピン買い」のような、失敗している戦略へのコミットメントをさらに拡大させるという、最悪の悪循環を生み出すのです。
総括
・認知的不協和とは、自らの信念と、現実の行動や新しい情報とが矛盾した際に生じる、不快な心理的緊張状態のことです [1]。
・人間は、この不快感を解消するために、自らの信念を維持するよう、行動や考え方を無意識のうちに正当化しようとします [2]。
・トレーディングにおいては、このバイアスが、「損切り」という合理的な行動を妨げ、損失が出ているポジションに固執し、さらに資金を投じてしまう「コミットメントの段階的拡大」の主要な原因となります [3]。
・また、利益が出た株を早く売り、損失が出た株を長く保有してしまう「ディスポジション効果」[4]や、自分に都合の良い情報ばかりを探す「確証バイアス」[5]の背後にも、この自己正当化のメカニズムが働いています。
用語集
認知的不協和 (Cognitive Dissonance) ある人の心の中に、矛盾する二つ以上の認知(信念、態度、行動など)が存在する時に生じる、不快な心理的ストレス。
認知バイアス (Cognitive Bias) 人間の思考の癖や、思い込みによって、非合理的な判断を下してしまう心理的な傾向のこと。
自己正当化 (Self-Justification) 自らの信念や行動が正しいと主張するために、あるいは認知的不協和を低減するために、その理由を後から合理化しようとする心理的なプロセス。
コミットメントの段階的拡大 (Escalation of Commitment) ある決定が、明らかに失敗しつつあるにも関わらず、それまでの投資(コミットメント)を正当化するために、その決定への関与をさらに深めてしまう現象。
サンクコスト (Sunk Cost) 埋没費用。すでに支払ってしまい、どのような意思決定を行っても回収することができない費用のこと。合理的な意思決定では、無視されるべきコスト。
ディスポジション効果 (Disposition Effect) 投資家が、利益の出ている資産は早く売り、損失の出ている資産は保有し続けるという体系的な行動バイアス。
確証バイアス (Confirmation Bias) 自らの仮説や信念を支持する情報ばかりを探し、それに反証する情報を無視または軽視してしまう傾向。
トレーディングプラン (Trading Plan) エントリー、エグジット(損切り、利食い)、ポジションサイジングなど、取引に関するルールを、事前に明確に定めた計画。
損切り (Stop-Loss) 損失が一定の水準に達した場合に、ポジションを決済して損失を確定させること。
プロスペクト理論 (Prospect Theory) 不確実性のある状況下での人間の意思決定を、心理学的な実験に基づいてモデル化した理論。
参考文献一覧
[1] Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.
※書籍です。
[2] Festinger, L., & Carlsmith, J. M. (1959). Cognitive consequences of forced compliance. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 58(2), 203–210.
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0041593
[3] Staw, B. M. (1976). Knee-deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action. Organizational Behavior and Human Performance, 16(1), 27-44.
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/0030-5073(76)90005-2
[4] Shefrin, H., & Statman, M. (1985). The disposition to sell winners too early and ride losers too long: Theory and evidence. The Journal of Finance, 40(3), 777-790.
https://doi.org/10.2307/2327802
[5] Akerlof, G. A., & Dickens, W. T. (1982). The economic consequences of cognitive dissonance. The American Economic Review, 72(3), 307-319.
https://www.jstor.org/stable/1831534
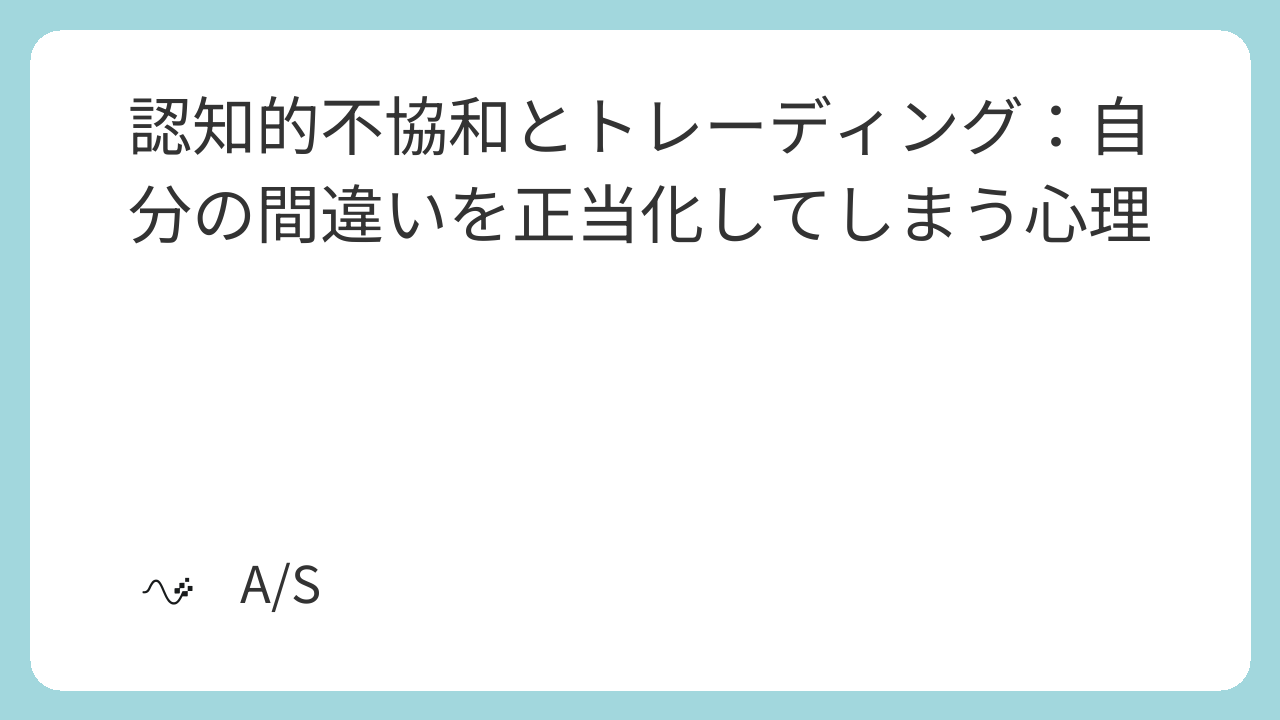
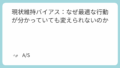
コメント