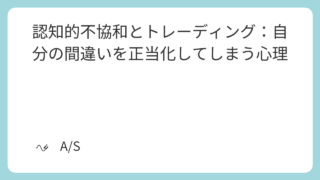 【行動ファイナンス】
【行動ファイナンス】 認知的不協和とトレーディング:自分の間違いを正当化してしまう心理
概論ある銘柄について徹底的に分析し、「この株は絶対に上がる」という強い信念を持って大きなポジションを取ったとします。しかし、その直後から株価は下落を始め、含み損は日に日に拡大していく。この時、あなたの心の中では何が起こるでしょうか。「自分の...
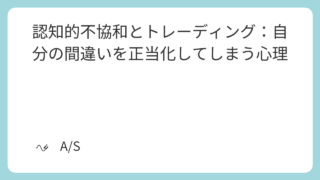 【行動ファイナンス】
【行動ファイナンス】 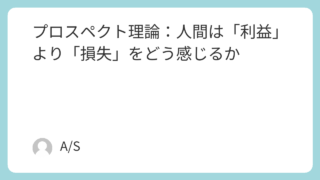 【行動ファイナンス】
【行動ファイナンス】 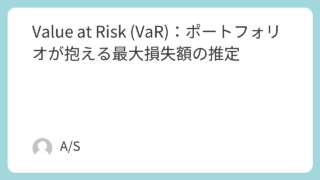 【ポートフォリオ理論とリスク管理】
【ポートフォリオ理論とリスク管理】 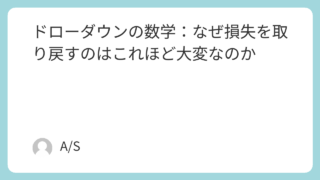 【ポートフォリオ理論とリスク管理】
【ポートフォリオ理論とリスク管理】  【統計学と計量ファイナンスの基礎】
【統計学と計量ファイナンスの基礎】 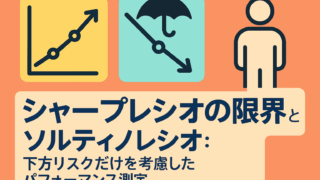 【統計学と計量ファイナンスの基礎】
【統計学と計量ファイナンスの基礎】 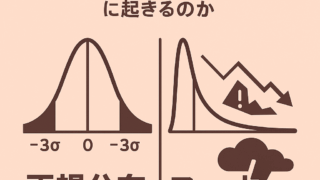 【統計学と計量ファイナンスの基礎】
【統計学と計量ファイナンスの基礎】  【株価アノマリー】
【株価アノマリー】 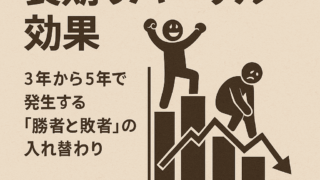 【モメンタム戦略】
【モメンタム戦略】 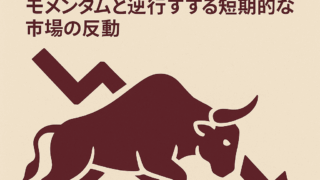 【モメンタム戦略】
【モメンタム戦略】