概論
トレーディングや投資のパフォーマンスを測る際、私たちはしばしばボラティリティ(標準偏差)という指標を用います。しかし、ボラティリティはリターンの上下のばらつきを対称に扱うため、投資家が実際に経験する「資産が減る痛み」を直接的に表現するものではありません。
この、投資家が直面する現実的な損失の規模を捉えるための指標がドローダウンです。ドローダウンとは、資産価値が過去の最高値(ピーク)からどれだけ下落したかを示す下落率を指します。特に、その期間中における最大の下落率は最大ドローダウン(Maximum Drawdown, MDD)と呼ばれ、投資戦略が抱えるリスクを評価するための極めて重要な指標として、ポートフォリオ最適化の研究などでも用いられています [1]。
ドローダウンがこれほどまでに重視されるのは、それが「損失を取り戻すことの困難さ」と数学的に直結しているからです。ここに、多くの投資家が軽視しがちな、単純でありながら残酷な非対称性が存在します。例えば、100万円の資金が50%のドローダウンを被り50万円になった場合、元の100万円に戻すためには50%ではなく100%のリターンが必要となります。
この損失と回復の非対称性は、多くの金融資産のリターンが正規分布に従わないという現実とも関連しています。現実のリターンはしばしば歪み(スキュー)を持つため、ボラティリティを基準としたシャープレシオのような伝統的な指標だけでは、パフォーマンスを十分に評価できない場合があります。そのため、下方リスクをより重視するドローダウンのような指標の重要性が指摘されています [2, 3]。この数学的な非対称性を理解することは、長期的に市場で生き残るための必須の知識です。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
このセクションでは、ドローダウンという指標を分析することの「有用性」と、大きなドローダウンがもたらす「リスク」について、その数学的な背景と共に掘り下げていきます。
長所、強み、有用な点について:ドローダウン分析の重要性
ドローダウンを分析することは、投資戦略の堅牢性を評価し、より現実に即したリスク管理を行う上で、計り知れない価値を持ちます。
より現実的なリスクの尺度
ドローダウンは、理論的な確率分布を仮定することなく、過去に実際に発生した最大の損失を直接的に示します。これにより、予測が困難な暴落(テールリスク)を含む、戦略が経験した最悪の事態を客観的に評価することができます。
リスク調整後リターンの高度な評価
優れた戦略は、単にリターンが高いだけでなく、いかにリスクを抑えながらリターンを上げたかが問われます。この評価のため、最大ドローダウンを用いたパフォーマンス指標が開発されてきました。その代表例が、テリー・W・ヤングによって考案されたカルマーレシオです [4]。この指標は、リターンを最大ドローダウンで割ることで、戦略が経験した「最大の痛み」に対して、どれだけ効率的にリターンを上げたかを評価します。
ポートフォリオ最適化への応用
ドローダウンは、単に過去を評価する指標に留まりません。将来のドローダウンを一定水準以下に抑えることを目的としてポートフォリオを構築する、といった直接的なリスク管理のアプローチも研究されています [1]。これは、特に大規模な資金を運用する上で、破滅的な損失を避けるための重要な技術となります。
短所、弱み、リスクについて:回復への険しい道のり
ドローダウンの本当の恐ろしさは、その非対称な回復計算にあります。損失が大きくなるほど、元の資産価値に復帰するために必要なリターン率は、指数関数的に増大していきます。
以下は、ドローダウンの大きさ(損失率)と、元のピークにまで回復するために必要な利益率の関係を示したものです。
- 10%のドローダウンからの回復には、約11.1%のリターンが必要
- 20%のドローダウンからの回復には、25.0%のリターンが必要
- 50%のドローダウンからの回復には、100.0%のリターンが必要
- 90%のドローダウンからの回復には、900.0%のリターンが必要
この計算が示すように、損失が深くなるにつれて、回復へのハードルは劇的に上昇します。この数学的な困難さに加え、プロの投資家の世界では、ドローダウンはさらに深刻な事態を引き起こします。ヘッジファンド業界を対象とした研究では、パフォーマンスと資金フローの間に密接な関係があることが示されています。具体的には、直近のパフォーマンスが良いファンドほど、より多くの資金が流入する傾向があるのです [5]。これは裏を返せば、パフォーマンスが悪化し、大きなドローダウンを経験したファンドは、投資家からの資金流出(解約)という厳しい現実に直面することを意味します。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、ドローダウンからの回復はこれほどまでに困難なのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことで、より深く理解することができます。
Asymmetry:損失と利益の「非対称なインパクト」
ドローダウンの問題の核心には、数学的、そして現実的なレベルでの深刻な「非対称性」が存在します。
数学的なペイオフの非対称性
本稿で繰り返し解説したように、損失からの回復計算は本質的に非対称です。10%の利益は10%の損失を埋め合わせることができず、損失が深くなるほど、その差は絶望的なまでに開いていきます。この非対称な構造こそが、「大きな損失を避ける」ことが、長期的には「大きな利益を狙う」ことよりも重要であると言われる数学的な根拠です。
リターン分布の非対称性
多くの金融資産のリターンは、正規分布のような対称な形をしておらず、歪み(スキュー)を持っています。特に、突然の暴落は大きなマイナスのリターンを生み出し、分布の左側の裾野を重くします(負のスキュー)。ドローダウンは、この非対称なリターン分布がもたらす現実的なリスクを捉える上で、対称的な指標であるボラティリティよりも優れています。パフォーマンス評価の研究において、シャープレシオを一般化し、このような分布の歪みを考慮に入れる試みがなされているのも、この非対称性への対応が重要であるためです [3]。
Friction:「合理的な判断」を妨げる現実の摩擦
もし市場が数学的な計算だけで動いているなら、ドローダウンは単なる数字の問題かもしれません。しかし、現実の市場は、合理的な判断と行動を妨げる様々な「摩擦」に満ちています。
パニックという感情的摩擦
大きなドローダウンは、投資家に強烈なストレスと恐怖を与えます。このパニックという強力な感情的摩擦は、合理的な思考を麻痺させ、多くの投資家を不適切な行動、すなわち損失に耐えきれずに最悪のタイミングで投げ売りしてしまうという行為に駆り立てます。これは、一時的であったかもしれないドローダウンを、確定的な永久損失に変えてしまう行為に他なりません。
資金流出という制度的摩擦
プロのファンドマネージャーの世界では、ドローダウンはさらに深刻な「制度的摩擦」を引き起こします。ヘッジファンドの研究が示すように、パフォーマンスが悪化すると、投資家は資金を引き揚げ始めます [5]。この資金流出(解約)に対応するため、ファンドマネージャーは、市場環境が悪いにもかかわらず、保有資産を不本意な価格で売却せざるを得なくなります。この強制的な売りが、さらなるパフォーマンスの悪化を招き、それがまた新たな解約を呼ぶという負のスパイラルに陥るのです。この制度的摩擦は、ドローダウンという数学的な問題を、ファンドの存続そのものを脅かす現実的な危機へと発展させます。
総括
- ドローダウンとは、資産価値が過去の最高値から下落した率のことであり、投資家が経験する現実的なリスクを測る上で重要な指標です [1, 2]。
- 損失からの回復には、被った損失率を上回る利益率が必要であり、この「数学的な非対称性」は、損失が深くなるほど顕著になります。
- ドローダウンは、カルマーレシオのような、より実践的なリスク調整後パフォーマンス指標の算出に用いられます [4]。
- 現実のリターン分布が持つ非対称性(歪み)を考慮すると、ボラティリティだけでなくドローダウンのような下方リスク尺度の重要性が増します [3]。
- 大きなドローダウンは、パニックという感情的摩擦や、顧客からの資金流出という「制度的摩擦」を引き起こし、一時的な損失を永続的なものに変えてしまう危険性をはらんでいます [5]。
用語集
ドローダウン ある期間における、資産価値の最大値(ピーク)から谷(トラフ)までの下落率のこと。
最大ドローダウン (Maximum Drawdown, MDD) 分析対象期間中に記録された、ドローダウンの最大値。戦略や資産が内包する最大潜在リスクを示す指標として重視される。
ボラティリティ 資産価格の変動の激しさを測る指標。一般的に標準偏差で測定され、リターンのばらつきを示すが、上昇と下落を区別しない。
リスク調整後リターン リターンの絶対額だけでなく、そのリターンを得るためにどれだけのリスクを取ったかを考慮に入れたリターンのこと。
シャープレシオ リターンをボラティリティで割ることで算出される、代表的なリスク調整後リターン指標。
カルマーレシオ リターンを最大ドローダウンで割ることで算出されるリスク調整後リターン指標。シャープレシオよりも下方リスクを重視した評価が可能。
正規分布 統計学で最も広く用いられる確率分布の一つ。平均値を中心に左右対称の釣鐘状の形をしている。
歪度 (スキュー) 確率分布が左右対称でない「歪み」の度合いを示す指標。負のスキューは、大きなマイナスリターンが起こりやすいことを示す。
複利効果 運用で得た収益を元本に加えて再投資することで、収益が収益を生み、資産が雪だるま式に増えていく効果。
テールリスク 確率分布の裾野(テール)で発生する、起こる確率は極めて低いものの、一度発生すると壊滅的な損失をもたらすリスク。
参考文献一覧
- Chekhlov, A., Uryasev, S., & Zabarankin, M. (2005). Drawdown measure in portfolio optimization. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 8(1), 13-58.
https://doi.org/10.1142/S0219024905002767 - Bacon, C. (2012). Practical portfolio performance measurement and attribution. John Wiley & Sons.
※書籍です。 - Zakamouline, V., & Koekebakker, S. (2009). Portfolio Performance Evaluation with Generalized Sharpe Ratios Beyond the Mean and Variance. Journal of Banking & Finance, 33(7), 1242-1254.
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.01.005 - Young, T. W. (1991). Calmar Ratio: A New Measure of Portfolio Performance. Futures Magazine, 20(2).
- Agarwal, V., Daniel, N. D., & Naik, N. Y. (2009). Flows, performance, and managerial incentives in the hedge fund industry. The Journal of Finance, 64(2), 835-875.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.424369
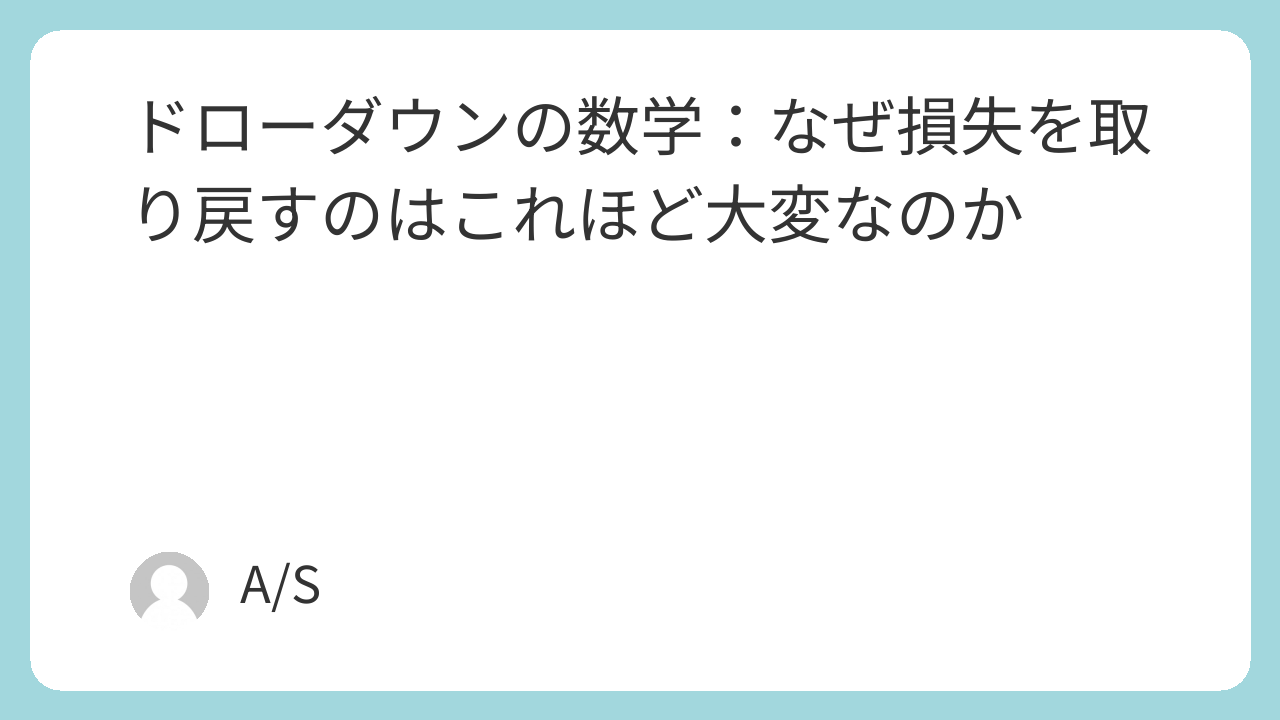
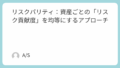
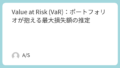
コメント