概論
伝統的な資産配分戦略の代表格である「株式60%、債券40%」ポートフォリオは、資本(金額)を基準に資産を配分します。しかしこのアプローチでは、ポートフォリオ全体のリスクの大部分が、価格変動の激しい株式に集中してしまうという構造的な偏りが生じます。このリスク集中の問題に対し、全く異なる哲学を提示するのがリスクパリティです 。
リスクパリティの基本的な考え方は、各資産クラスへの配分を特定の期待リターンやリスクの最適化に基づいて行うのではなく、それぞれの資産クラスがポートフォリオ全体の総リスクに対して与える影響、すなわち「リスク貢献度」が等しくなるようにポートフォリオを生成することです 。この「リスク貢献度」という概念こそが、当アプローチの解釈の中心となります 。具体的には、各資産のリスクを測定し、リスクの低い資産(例:債券)の配分比率を高め、リスクの高い資産(例:株式)の配分比率を低くすることで、すべての資産がリスク面で均等な発言権を持つポートフォリオを構築します 。
この戦略が有効性を持ちうる理論的な背景には、多くの投資家がレバレッジを避ける「レバレッジ嫌悪」という市場の傾向が存在します 。このため、レバレッジなしでリターンが期待できる高リスク資産は相対的に割高に、レバレッジをかけなければ十分なリターンを得られない低リスク資産は相対的に割安になるという価格の歪みが生まれる可能性があります。リスクパリティは、この歪みを利用し、レバレッジをかけて多様化された低リスク資産に投資することで、より優れたリスク調整後リターンを目指す試みと言えます 。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について
リスクパリティは、その独自のリスク管理アプローチにより、いくつかの注目すべき長所を持っています。
リスク配分における優れた分散
リスクパリティは、リスク貢献度を均等にすることで、伝統的なポートフォリオよりもリスク面で優れた分散を実現します 。特定の資産クラスの値動きがポートフォリオ全体に与える影響が平準化されるため、特定の市場環境への過度な依存を避けることができます。
リスク調整後リターンの歴史的な安定性
複数の資産配分戦略を比較した研究によれば、リスクパリティのシャープレシオ(リスク調整後リターン)は、過去30年間の10年ごとのサブ期間において、60/40ポートフォリオや他の最適化ポートフォリオよりもはるかに安定していたことが報告されています 。これは、様々な市場環境の変化に対して、より頑健なパフォーマンスを示してきたことを意味します。また、別の長期的な実証研究においても、レバレッジを利用したリスクパリティ戦略が、伝統的なポートフォリオと比較して優れたリスク調整後リターンを達成してきたことが示されています 。
短所、弱み、リスクについて
その一方で、リスクパリティは万能の戦略ではなく、その有効性にはいくつかの重要な前提条件と限界が存在します。
必ずしも他の単純な戦略を上回るわけではない
リスクパリティは、その洗練されたアプローチにもかかわらず、必ずしも全ての戦略を上回るわけではありません。比較研究によると、リスクパリティは最小分散や平均分散最適化といったポートフォリオに対しては有意に優れた成績を示したものの、資産を均等に配分するだけの「均等加重ポートフォリオ」に対しては、リスク調整後リターンで一貫してアウトパフォームするわけではなかった、という結果が報告されています 。
資産クラスの選定への高い依存度
リスクパリティ戦略のパフォーマンスは、ポートフォリオにどの資産クラスを含めるかという「投資ユニバースの選定」に大きく依存することが指摘されています 。つまり、この戦略を成功させるためには、資産クラスを慎重に選ぶことが極めて重要であり、その選定プロセスは理論に基づく数理的な作業というよりは、むしろ「アート(芸術)」に近いとされています 。これは、戦略の再現性や堅牢性に対する重大な課題と言えるでしょう。
パフォーマンスに関する様々な論点
リスクパリティは、そのパフォーマンスが特定の条件下でのみ発揮される可能性も指摘されています 。また、戦略のバリエーション(リスク指標の選択、レバレッジの利用方法、アクティブ運用かパッシブ運用かなど)によっても結果は大きく異なり、その有効性については様々な批判や議論が存在します 。
非対称性と摩擦の視点から
リスクパリティというアプローチがなぜ生まれ、そしてなぜその有効性が完全ではないのか。その本質は、「非対称性」と「摩擦」の観点から深く考察することができます。
Asymmetry:市場の非対称な価格形成を利用する
リスクパリティが収益機会を見出す源泉は、市場参加者の行動が生み出す「非対称性」にあります。
伝統的なポートフォリオが抱える最大の問題は、資本配分とリスク貢献度の間に存在する極端な非対称性です。例えば資本の60%を占める株式が、ポートフォリオのリスクの90%以上を占めることも珍しくありません。リスクパリティは、まずこのポートフォリオ内部の「リスクの非対称性」を破壊し、対称的な状態(均等リスク貢献)を作り出すことを目指します。
この戦略が利益を生む土壌となっているのが、投資家の「レバレッジ嫌悪」という非対称な心理・行動バイアスです 。多くの投資家は、明示的なレバレッジを必要とする低リスク資産よりも、それなしでリターンが期待できる高リスク資産を非対称に好みます。この行動が、市場において低リスク資産を過小評価させ、高リスク資産を過大評価させるという非対称な価格形成を生み出すのです 。リスクパリティは、この市場の非対称性を検出し、レバレッジを用いて体系的に利用することで、超過リターンを獲得しようとする試みと言えます。
Friction:理想の実現を阻む「制度と技術」の摩擦
もし市場が完全に滑らかであれば、上記のような価格の歪みは、プロの投資家によって即座に解消されるはずです。しかし、現実の市場には、リスクパリティの理想的な実行を阻む、根深い「摩擦」が存在します。
レバレッジという制度的摩擦
多くの機関投資家、特に年金基金などは、その運用規定によってレバレッジの使用が厳しく制限されています。この「レバレッジを使えない」という制度的な摩擦こそが、レバレッジ嫌悪アノマリーが市場に存続し続ける大きな理由となっています 。裁定機会が存在していても、多くのプレイヤーが制度的摩擦によって参加できないため、価格の歪みは簡単には解消されないのです。
資産選定という技術的摩擦
リスクパリティのパフォーマンスが、投資対象となる資産クラスの選定という「アート」に大きく依存するという事実は、この戦略が抱える最も大きな技術的摩擦です 。どの資産を組み合わせるか、どのリスク指標を用いるか、どの程度レバレッジをかけるかといった無数の選択肢が存在し 、その最適な組み合わせを見つけ出すための普遍的な公式は存在しません。この実装の複雑さと不確実性が、理論上の優位性を現実の利益へと転換する上での大きな障壁、すなわち摩擦として機能しているのです。
総括
- リスクパリティは、資本(金額)ではなく、各資産の「リスク貢献度」がポートフォリオ全体で均等になるように資産を配分するアプローチです 。
- その理論的背景には、多くの投資家がレバレッジを避ける「レバレッジ嫌悪」という市場の非対称な価格形成を利用する狙いがあります 。
- 長所として、リスク面で優れた分散を実現し、歴史的に見てシャープレシオが安定している傾向があります 。
- 短所として、均等加重のような他の単純な戦略を一貫して上回るわけではなく、そのパフォーマンスは投資対象となる資産クラスの選定に大きく依存するという重大な課題を抱えています 。
- レバレッジの利用や資産選定の難しさといった「摩擦」が、リスクパリティの理想的な実行を困難にしています 。
用語集
リスクパリティ ポートフォリオ内の各資産クラスが、全体の総リスクに対して均等に貢献するように資産を配分する投資戦略。資本の配分ではなく、リスクの配分に着目する。
リスク貢献度 ポートフォリオに組み入れられた個別の資産が、ポートフォリオ全体の総リスク(ボラティリティ)に対して、どの程度影響を与えているかを示す尺度。
60/40ポートフォリオ ポートフォリオの60%を株式に、40%を債券に配分する伝統的な資産配分戦略の代表例。
レバレッジ 借入金などの他人資本を利用することで、自己資本に対するリターンを高める効果のこと。リスクパリティ戦略では、全体の期待リターンを引き上げるために用いられることが多い。
シャープレシオ リターンを、そのリターンを得るために取ったリスク(ボラティリティ)で割った値。リスク調整後のパフォーマンスを測る代表的な指標で、数値が高いほど効率的な運用とされる。
均等加重ポートフォリオ ポートフォリオに組み入れる全ての資産に、同じ金額(ウェイト)を配分する単純な資産配分戦略。
最小分散ポートフォリオ 期待リターンを問わず、ポートフォリオ全体のリスク(分散)が最小になるように資産のウェイトを決定するポートフォリオ。
レバレッジ嫌悪 多くの投資家が、心理的あるいは制度的な制約から、レバレッジをかけることを避ける傾向があるというバイアス。
資産配分 投資資金を、株式、債券、不動産など、異なる種類の資産(アセットクラス)にどのように配分するかを決定すること。
最適化ポートフォリオ 平均分散モデルなどを用いて、特定のリスク水準で最大のリターンを得る、あるいは特定のリターン水準で最小のリスクになるように、数学的に計算されたポートフォリオ。
参考文献一覧
- Fabozzi, F. A., Simonian, J., & Fabozzi, F. J. (2021). Risk Parity: The Democratization of Risk in Asset Allocation. The Journal of Portfolio Management, 47(5), 41-50.
https://doi.org/10.3905/jpm.2021.1.228 - Chaves, D. B., Hsu, J. C., Li, F., & Shakernia, O. (2011). Risk Parity Portfolio vs. Other Asset Allocation Heuristic Portfolios. Journal of Investing, 20(1), 108-118.
https://ssrn.com/abstract=1917064 - Qian, E. (2006). On the financial interpretation of risk contribution: A new look at risk parity. The Journal of Portfolio Management, 32(4), 87-95.
https://doi.org/10.2139/ssrn.684221 - Maillard, S., Roncalli, T., & Teïletche, J. (2010). The properties of equally weighted risk contribution portfolios. The Journal of Portfolio Management, 36(4), 60-70.
https://doi.org/10.3905/jpm.2010.36.4.060 - Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2012). Leverage aversion and risk parity. Financial Analysts Journal, 68(1), 47-69.
https://doi.org/10.2469/faj.v68.n1.1 - Anderson, R. M., Bianchi, S. W., & Goldberg, L. R. (2012). Will my risk parity strategy outperform?. Financial Analysts Journal, 68(6), 55-69.
https://doi.org/10.2469/faj.v68.n6.7
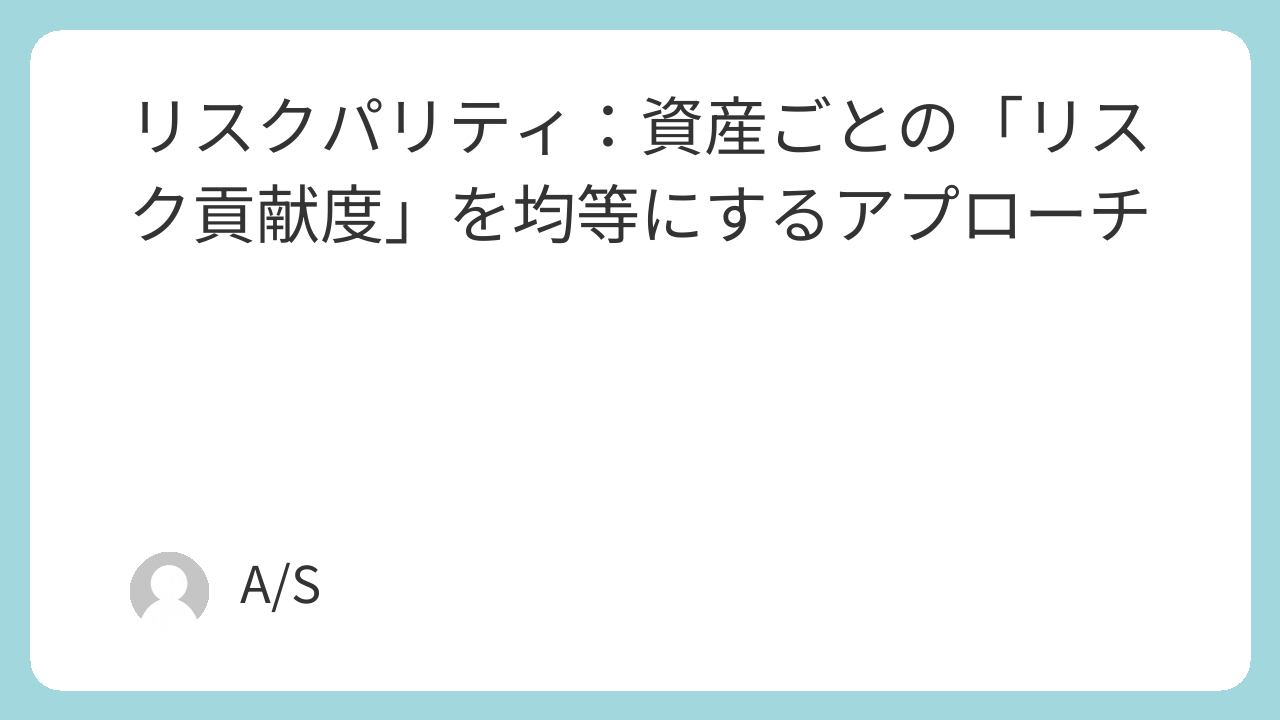
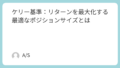
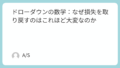
コメント