概論
伝統的なポートフォリオ構築では、「どの資産に、いくら資金を配分するか」という、資産配分(アセットアロケーション)が議論の中心でした。例えば、株式60%、債券40%という配分は、多くの投資家にとって馴染み深いものでしょう。しかし、このアプローチには一つの見過ごされがちな問題があります。それは、資金の配分と「リスク」の配分が、全く異なるということです。
株式60%、債券40%のポートフォリオでは、そのリスクの大部分(しばしば90%以上)が、わずか60%の資金を配分した株式に集中してしまいます。この、ポートフォリオのリスク源が特定の資産クラスに極端に偏っているという問題意識から生まれたのが、リスクバジェッティングという考え方です。
リスクバジェッティングとは、資金の配分ではなく、ポートフォリオ全体のリスク(ボラティリティ)を「予算」と捉え、そのリスクを各資産クラスや戦略にどのように配分するかを決定する、より洗練されたポートフォリオ構築の枠組みです。このアプローチの核心には、個々の資産がポートフォリオ全体のリスクにどれだけ貢献しているかを示す「リスク貢献度」という概念があります。ある研究によれば、このリスク貢献度は、各資産のポートフォリオ全体に対するベータと、その資産の配分額を掛け合わせることで数学的に算出され、全ての資産のリスク貢献度を合計すると、ポートフォリオ全体のトータルリスクと一致します [1]。
この考え方をさらに推し進め、各資産クラスのリスク貢献度が均等になるようにポートフォリオを構築する戦略は、特に「リスクパリティ」として知られています。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
リスクバジェッティング、特にその代表例であるリスクパリティ戦略は、伝統的な資産配分に対する強力な代替案として注目を集めてきましたが、その有効性は万能ではなく、市場環境によって長所と短所が明確に現れます。
長所、強み、有用な点について
リスクバジェッティングの最大の強みは、より真に分散されたポートフォリオを構築できる点にあります。伝統的な60/40ポートフォリオが株式リスクに大きく依存しているのに対し、リスクパリティは債券やその他の資産クラスにも均等にリスクを配分します。
このアプローチの有効性は、長期的な歴史的データによって裏付けられています。ある著名な研究では、リスクパリティ・ポートフォリオが、同じリスク水準に調整された市場ポートフォリオと比較して、1926年から2010年の米国市場で年間約4%アウトパフォームしたことが示されています [2]。
この優れたリスク調整後リターンの背景には、投資家がレバレッジを嫌う傾向(レバレッジ回避)から生じるリターンプレミアムが存在するという説があります。レバレッジをかけられない投資家が、高いリターンを求めて高リスク資産に資金を集中させる結果、相対的に低リスク資産のリスク調整後リターンが高くなる、というメカニズムです [2]。
理論的にも、リスクパリティ(論文中では均等リスク貢献ポートフォリオ)は、最小分散ポートフォリオと均等加重ポートフォリオの中間に位置する、非常によく分散されたポートフォリオであることが数学的に示されています [3]。
近年では、このリスクバジェッティングの考え方はさらに進化しています。資産クラスだけでなく、バリューやモメンタムといった投資「ファクター」に対してもリスクを配分するアプローチが提案されており、これにより伝統的な資産クラスのみのリスクバジェッティングよりも、さらに分散され、頑健なポートフォリオを構築できる可能性が示されています [6]。
短所、弱み、リスクについて
多くの利点を持つ一方で、リスクバジェッティングは決して「フリーランチ」ではなく、いくつかの深刻な弱点やリスクを内包しています。
最大の弱点は、その歴史的な好成績が、分析の開始日と終了日に大きく依存する可能性がある点です。ある研究では、数十年という長期のバックテストであっても、期間の取り方によって結果が大きく影響を受けることが報告されています。また、統計的に有意なリターンプレミアムが、将来の合理的な投資期間におけるアウトパフォームを保証するものではないことも指摘されています [4]。
また、リスクベースの資産配分は、そのパフォーマンスが特定の仮定に大きく依存するという批判もあります。特に、資産のボラティリティや相関が、期待リターンよりも安定的で予測可能であるという仮定が、その有効性の鍵を握っています [5]。もしこの前提が崩れれば、戦略の優位性は失われる可能性があります。
さらに、リスクベースの配分は、意図しないファクターやセクターへの賭けにつながる可能性も指摘されています [5]。これは、投資家が認識していないリスクをポートフォリオに抱え込むことになりかねないことを意味しており、リスクを均等に配分するという当初の目的とは裏腹な結果を招く危険性を示唆しています。
非対称性と摩擦の視点から
リスクバジェッティングの有効性と限界は、単なる数式上の議論に留まりません。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことで、この戦略がなぜ機能し、どのような困難に直面するのかを深く理解することができます。
Asymmetry:リスク貢献度の非対称性とレバレッジ回避の非対称性
リスクバジェッティングが取り組む根源的な問題は、伝統的なポートフォリオに内在する「リスク貢献度の非対称性」です。株式60%、債券40%という資金配分は一見バランスが取れているように見えますが、そのリスクの9割以上を株式が占めるという極端な非対称構造を持っています。リスクバジェッティングは、この非対称性を是正し、ポートフォリオのリスク源を均等に近づけることを目指します。
この戦略がリターンを生む背景には、投資家の行動における「レバレッジ回避の非対称性」が存在します。多くの投資家は、規制や心理的な抵抗から、レバレッジをかけることを極端に嫌います。そのため、高いリターンを求める投資家は、レバレッジをかける代わりに、本質的にリスクの高い資産(高ベータ資産である株式など)に過度に資金を集中させる傾向があります。リスクパリティ戦略は、この非対称性を逆手に取ります。すなわち、レバレッジを用いて低リスク資産(債券など)のポジションを拡大し、高リスク資産と同程度のリスクを取ることで、レバレッジ回避によって生じるリターンプレミアムを獲得しようとするのです [2]。
Friction:レバレッジと推定という二重の摩擦
リスクバジェッティング、特にリスクパリティ戦略の実践には、理論の美しさを損なう現実的な「摩擦」が常に伴います。
第一に、最も重要なのが「レバレッジの摩擦」です。リスクパリティ戦略が、低リスク資産である債券などに株式と同程度のリスクを割り当てるためには、レバレッジの活用が不可欠となります。しかし、多くの個人投資家や一部の機関投資家にとって、レバレッジの利用は、コスト、規制、あるいは心理的な障壁といった強い摩擦によって制限されています。この摩擦があるために、理論上は有効な戦略であっても、誰もが簡単に実行できるわけではないのです。また、レバレッジの使用は取引コストを増大させ、戦略の優劣を逆転させる可能性も指摘されています [4]。
第二に、「推定の摩擦」です。リスクバジェッティングは、将来のリターン予測への依存度が低いという強みを持ちますが、その代わりに、将来のボラティリティと資産間の相関を正確に「推定」できるという仮定に大きく依存しています [5]。しかし、これらのパラメータは決して安定したものではなく、特に金融危機のような市場の混乱期には、相関が劇的に変化することがあります。過去のデータから推定されたリスク構造が、未来も継続するという保証はどこにもありません。この「真のリスク構造を知り得ない」という根源的な情報の摩擦が、リスクバジェッティングのパフォーマンスに常に不確実性の影を落とします。
総括
- リスクバジェッティングは、資金配分ではなく、各資産の「リスク貢献度」に着目してポートフォリオを構築するアプローチです [1]。
- 主な長所は、リスク源を真に分散させることで、歴史的に見て高いリスク調整後リターン(シャープレシオ)と低いドローダウンを実現してきた点にあります [2, 3]。
- そのリターンの源泉の一つとして、多くの投資家がレバレッジを避けることによって生じる「レバレッジ回避プレミアム」が指摘されています [2]。
- 一方で、その有効性はバックテストの期間設定に大きく依存し、将来のアウトパフォームを保証するものではないという弱点を抱えています [4]。
- 実践においては、レバレッジの利用に伴うコストや制約、そしてリスク構造を正確に推定することの困難さという「摩擦」が、常に考慮されるべき課題となります。
用語集
リスクバジェッティング ポートフォリオ全体のリスクを所与の「予算」とみなし、そのリスクを各資産クラスや戦略にどのように配分するかを決定するポートフォリオ管理手法。
リスク貢献度 ポートフォリオ内の個々の資産が、ポートフォリオ全体のリスク(ボラティリティ)に対して、どれだけ貢献しているかを示す度合い。
リスクパリティ リスクバジェッティングの一種で、ポートフォリオ内の各資産クラスのリスク貢献度が、すべて均等になるように資産を配分する戦略。
シャープレシオ リターンを、そのリターンを得るために取ったリスク(標準偏差)で割った値。リスク調整後のパフォーマンスを測る代表的な指標。
ドローダウン 特定の期間において、資産価格が最高値から最安値まで下落した際の最大下落率のこと。
レバレッジ 借入などを利用して、自己資金よりも大きな金額の取引を行うこと。「てこ」の原理に由来する。
平均分散最適化 ハリー・マーコウィッツによって提唱された、期待リターンとリスク(分散)を基に、最も効率的なポートフォリオを数学的に導出する手法。
ファクター 株式などのリターンを長期的に説明するとされる、共通の性質や特徴のこと。バリュー、モメンタム、クオリティなどがある。
ボラティリティ 資産価格の変動の激しさを表す指標。一般的に、標準偏差で測定される。
相関 二つの異なる資産の値動きの関連性の強さを示す指標。-1から+1までの値をとり、+1に近いほど同じ方向に動き、-1に近いほど逆の方向に動く。
参考文献一覧
[1] Litterman, R. (1996). Hot spots and hedges. The Journal of Portfolio Management, 22(5), 52-64.
https://doi.org/10.3905/jpm.1996.052
[2] Asness, C., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2012). Leverage aversion and risk parity. Financial Analysts Journal, 68(1), 47-63.
https://doi.org/doi.org/10.2469/faj.v68.n1.1
[3]Maillard, S., Roncalli, T., & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. The Journal of Portfolio Management, 36(4), 60-70.
https://doi.org/10.3905/jpm.2010.36.4.060
[4]Anderson, R. M., Bianchi, S. W., & Goldberg, L. R. (2012). Will My Risk Parity Strategy Outperform?. Financial Analysts Journal, 68(6), 75-93.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2101898
[5] Lee, W. (2011). Risk-based asset allocation: A new answer to an old question?. The Journal of Portfolio Management, 37(4), 11-28.
https://doi.org/10.3905/jpm.2011.37.4.011
[6] Bender, J., Briand, R., Nielsen, F., & Stefek, D. (2010). Portfolio of risk premia: A new approach to diversification. The Journal of Portfolio Management, 36(2), 17-25.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2543991
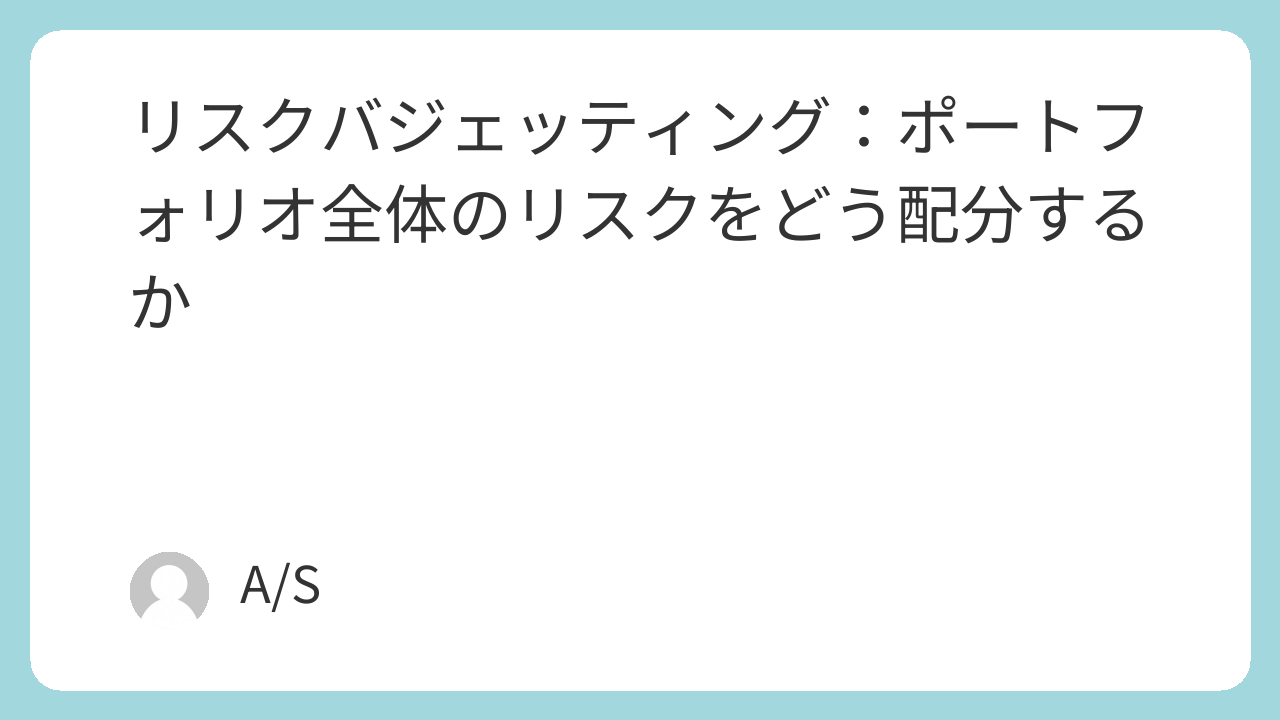
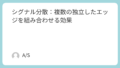
コメント