概論
「卵は一つのカゴに盛るな」――この格言に象徴される分散投資は、現代ポートフォリオ理論の根幹をなす、リスク管理の基本中の基本です。ハリー・マーコウィッツが示したように、互いに相関の低い資産を組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクを低減できることは、数学的に証明されています [1]。投資家は、この「相関」という統計的な性質を頼りに、株式と債券、あるいは国内資産と海外資産を組み合わせることで、安全なポートフォリオを構築しようと試みてきました。
しかし、この分散投資の美しい理論には、極めて厄介で、しばしば致命的な欠陥が存在します。それは、資産間の相関が、時間を通じて一定ではないという現実です。この、相関が時間と共に変化する性質を「相関の非定常性(Non-stationarity of Correlation)」と呼びます。
さらに深刻なのは、その変化の仕方が、投資家にとって最も都合の悪い形で現れる点です。
フランソワ・ロンジンとブルーノ・ソルニクによる1995年の画期的な研究は、この問題を白日の下に晒しました [2]。彼らは、1960年から1990年までの世界の主要な株式市場のリターンを分析し、市場が平穏な時期には国際市場間の相関は比較的低いものの、市場のボラティリティが急上昇する局面、すなわち暴落時において、相関は劇的に上昇することを発見したのです。
これは、投資家が最も分散効果を必要とする「いざという時」に、その効果が忽然と消え去ってしまうことを意味します。平時には別々の動きをしていたはずの資産が、危機が訪れた途端、まるで示し合わせたかのように一斉に下落する。この記事では、なぜこのような分散投資の「裏切り」が起こるのか、そのメカニズムを学術研究を基に深掘りしていきます。
長短の解説、利益例・損失例の紹介
短所、弱み、リスクについて:分散効果の消失(損失事例)
相関の非定常性がもたらす最大のリスクは、伝統的な分散投資戦略の破綻です。
過去の平穏な時代のデータに基づいて、「株式と不動産の相関は低い」「米国株と新興国株の相関は低い」といった前提でポートフォリオを構築しても、ひとたび世界的な金融危機が発生すれば、その前提は崩壊します。ロンジンとソルニクが示したように、全ての資産クラスがキャッシュへと逃避する「リスクオフ」の局面では、あらゆる資産の相関が1に近づき、分散効果はほとんど機能しなくなります [2]。
その結果、安全なはずだった分散ポートフォリオが、市場全体と同じような、あるいはそれ以上の下落に見舞われるという事態が発生します。これは、過去の平均的な相関という「静的な」データに基づいて、未来という「動的な」不確実性に対応しようとすることの限界を示しています。
長所、強み、有用な点について:なぜ相関は豹変するのか
この恐るべき現象を理解することは、より洗練されたリスク管理への第一歩となります。なぜ、危機時に相関は豹変するのでしょうか。その背景には、少なくとも3つのメカニズムが存在します。
変動する相関をモデル化する(計量経済学的アプローチ)
相関が時間と共に変化するという現実に、計量経済学は動的条件付き相関(Dynamic Conditional Correlation, DCC)モデルのような、より高度な統計ツールで応えました。
ロバート・エングルが2002年に提唱したDCC-GARCHモデルは、日々のリターンデータから、時間と共に変動する相関係数を推定することを可能にします [3]。このようなモデルを用いることで、市場のボラティリティが高まると相関も高まる、といった動的な関係性をリスク管理に織り込み、より現実的なポートフォリオのリスク量を把握することが可能になります。
金融市場のグローバル化と伝染(経済学的アプローチ)
危機時に相関が高まる背景には、グローバルに統合された金融システムの構造そのものがあります。フォーブスとリゴボンによる2002年の研究は、この現象が「伝染(Contagion)」によって引き起こされるのか、それとも元々存在する「相互依存(Interdependence)」が危機時に顕在化するだけなのか、という重要な論争を提起しました [4]。
いずれにせよ、一つの市場で発生したショックが、貿易、銀行貸付、投資家心理といった様々な経路を通じて、瞬時に世界中の市場へと伝播する。このグローバルな相互依存関係が、危機時における相関の急上昇の根本的な原因となっています。
投資家の群集行動(行動ファイナンス的アプローチ)
市場がパニックに陥ると、多くの投資家は、個々の資産のファンダメンタルズを冷静に分析することをやめてしまいます。代わりに、「とにかくリスク資産を全て売却する」という、画一的な「群集行動(Herding)」に走りがちです。
ベカード、ハーヴェイ、ラムズデインによる2002年の研究は、新興国市場において、このような投資家センチメントや資金フローの急変が、いかにして市場の連動性を高めるかを示しています [5]。全ての投資家が同じ出口に殺到すれば、資産の個別性に関係なく、全ての価格が同じ方向に動いてしまうのです。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、数学的に完璧に見える分散投資理論が、現実の市場ではしばしば裏切られるのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:相関の「非対称性」
分散投資が直面する最大の問題は、相関係数そのものが持つ「非対称性」にあります。
ロンジンとソルニクの研究が示したように、資産間の相関は、市場が平穏な上昇局面にある時と、パニック的な下落局面にある時とで、その値が全く異なります [2]。通常時は低い相関を示し、分散効果をもたらしてくれるはずの資産たちが、ひとたび市場が暴落すると、まるで示し合わせたかのように一斉に相関を高め、共に下落していくのです。
この「平時と有事で豹変する」という相関の非対称性こそが、分散投資の最も危険な罠です。多くのポートフォリオモデルは、過去の平均的な相関を用いて未来を予測しますが、そのモデルが最も必要とされる危機的状況下では、その前提そのものが崩壊してしまうのです。
この非対称な性質により、伝統的な分散ポートフォリオは、非対称なリスクプロファイルを持つことになります。すなわち、上昇局面では最もパフォーマンスの良い資産の上昇分の一部しか享受できない一方で、下落局面では全ての資産が連動して下落するため、損失を大きく被ってしまうのです。
Friction:相関の「推定誤差」という情報の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、相関という概念を現実の投資に応用する際には、より本質的で克服困難な「情報の摩擦」が存在します。
推定誤差という根源的な摩擦
ポートフォリオを最適化するためには、構成資産間の共分散(相関)を正確に知る必要があります。しかし、神ならぬ人間が、未来の真の相関を知ることはできません。我々にできるのは、ノイズに満ちた過去のデータからそれを「推定」することだけです。
マーコウィッツの理論 [1]を実践しようとすると、例えば100銘柄のポートフォリオでも、約5000個もの共分散を推定しなくてはなりません。これらの推定値の一つ一つが、「推定誤差」という避けられない不確実性を含んでいます。この推定誤差という情報の摩擦は非常に深刻であり、わずかな推定ミスが、計算上は「最適」なはずだったポートフォリオを、現実には全く機能しない「最悪」のポートフォリオに変えてしまう危険性をはらんでいます。
「相関は安定している」という認知の摩擦
投資家は、自らが構築したポートフォリオの前提(例えば、計算された相関係数)が、将来も安定的に続くと信じたい、という認知的なバイアスを持っています。しかし、前半で見たように、相関は本質的に不安定(非定常)です。
この「安定性への期待」という認知的な摩擦が、投資家に、市場のレジーム(構造)が変化している兆候を見過ごさせ、過去のデータに基づいて構築されたポートフォリオに固執させてしまいます。その結果、相関構造が豹変した際に、適切な対応が遅れ、大きな損失を被ることになるのです。
総括
・分散投資は、資産間の低い相関を利用してポートフォリオのリスクを低減する、伝統的金融理論の根幹です [1]。
・しかし、資産間の相関は常に一定ではなく(非定常性)、特に市場の暴落時には、全ての資産の相関が急上昇するという危険な性質を持っています [2]。
・この現象の背景には、グローバルな経済の相互依存関係 [4]や、危機時における投資家のパニック的な群集行動 [5]など、複数の要因が存在します。
・この相関の非定常性は、分散投資の有効性を根本から揺るがす問題であり、動的な相関をモデル化するDCC-GARCHのような高度な手法 [3]を用いても、その予測は極めて困難です。
用語集
相関の非定常性 (Non-stationarity of Correlation) 二つ以上の資産間の相関関係が、時間を通じて一定ではなく、市場の状況などに応じて変化する性質。
相関 (Correlation) 二つの資産のリターンが、どの程度同じ方向に、同じ強さで動くかを示す、-1から+1の範囲の値を取る統計的な指標。
分散投資 (Diversification) 異なる値動きをする(相関が低い)複数の資産に資金を分散させることで、ポートフォリオ全体のリスクを低減させる投資手法。
現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory) ハリー・マーコウィッツが提唱した、資産のリターン、リスク(分散)、およびそれらの間の相関を考慮して、最も効率的なポートフォリオを構築するための理論。
ボラティリティ (Volatility) 資産価格の変動の激しさを示す指標。リターンの標準偏差で測定されることが多い。
金融伝染 (Financial Contagion) ある国や市場で発生した金融危機が、他の国や市場へと波及していく現象。
群集行動 (Herding) 市場参加者が、自らの判断ではなく、他の大多数の投資家の行動に追随してしまうこと。パニック相場で顕著に見られる。
DCC-GARCHモデル 動的条件付き相関GARCHモデル。時間と共に変動する相関係数を統計的にモデル化するための、高度な計量経済学的手法。
リスクオフ (Risk-Off) 投資家がリスク回避的になり、株式などのリスク資産を売って、現金や安全資産へと資金を退避させる市場センチメントのこと。
ポートフォリオ 投資家が保有する、株式、債券、不動産などの金融資産の組み合わせ、またその一覧。
参考文献一覧
[1] Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
[2] Longin, F., & Solnik, B. (1995). Is the correlation in international equity returns constant: 1960–1990?. Journal of International Money and Finance, 14(1), 3-26.
https://doi.org/10.1016/0261-5606(94)00001-H
[3] Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350.
https://doi.org/10.1198/073500102288618487
[4] Forbes, K. J., & Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. The Journal of Finance, 57(5), 2223-2261.
https://doi.org/10.1111/0022-1082.00494
[5] Bekaert, G., Harvey, C. R., & Lumsdaine, R. L. (2002). The dynamics of emerging market equity flows. Journal of International Money and Finance, 21(3), 295-350.
https://doi.org/10.1016/S0261-5606(02)00001-3
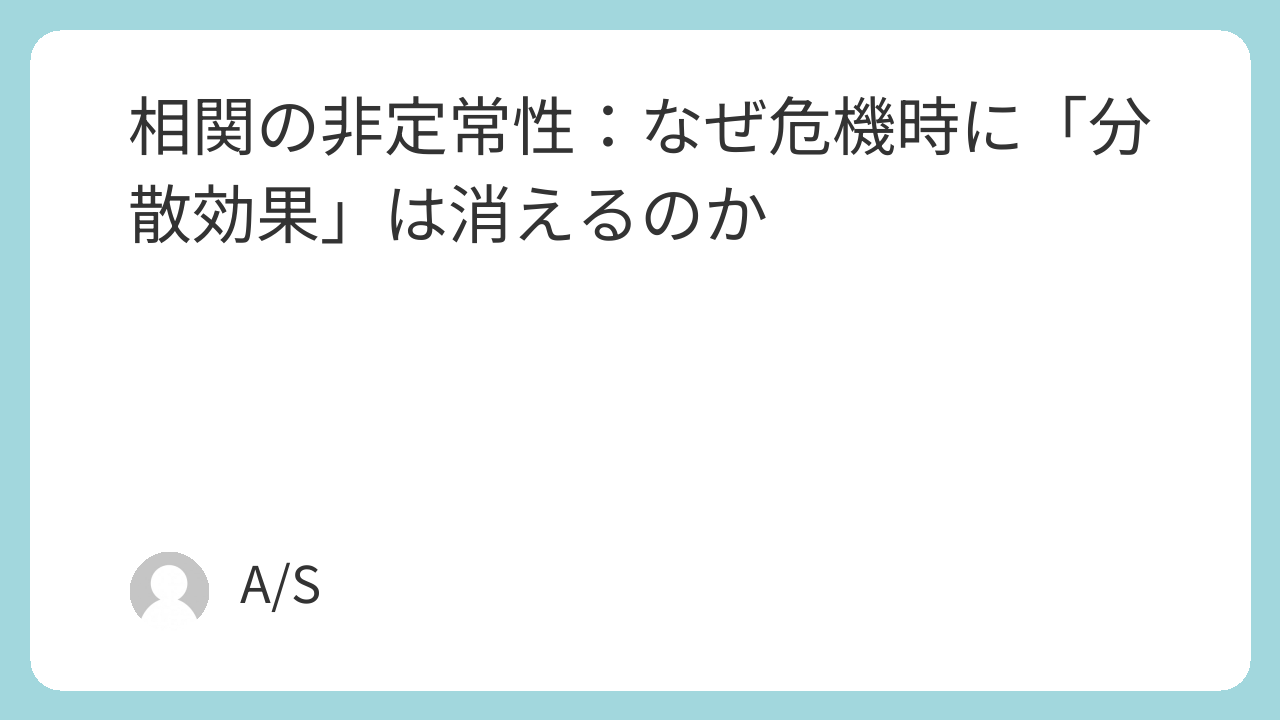
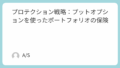
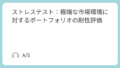
コメント