概論
株式投資における最大のリスクの一つは、予期せぬ市場の暴落による資産価値の大幅な下落です。多くの投資家は、資産の成長を期待する一方で、このダウンサイドリスクをいかに管理するかに頭を悩ませています。この問題に対する一つの古典的かつ強力な解決策が、本稿で解説するプロテクション戦略、すなわちプットオプションを用いたポートフォリオの保険です。
この戦略は、火災保険や自動車保険に例えると非常に分かりやすいでしょう。私たちは、万が一の事態に備えて保険料を支払うことで、壊滅的な損失から資産を守ります。プロテクション戦略は、これと全く同じ考え方を金融ポートフォリオに適用するものです。具体的には、株式や株価指数連動型ETFなどの現物資産を保有すると同時に、その資産を対象とするプットオプションを購入します。プットオプションとは、「特定の期日に、あらかじめ定められた価格(権利行使価格)で資産を売却する権利」です。この権利を保有することで、もし市場価格が権利行使価格を下回るほど暴落しても、投資家は保有資産をその価格で売却できるため、損失を一定の範囲内に限定することができます。つまり、ポートフォリオに損失の下限値を設定する「保険」として機能するのです。
このような金融商品を用いた保険の概念は、特に機関投資家の間で深く研究されてきました。誰が、そしてどのような目的でポートフォリオ保険を導入すべきかという問いは、学術的な議論の対象となっています [1]。この戦略の根幹にあるオプションの価値、すなわち「保険料」がどのように決まるかについては、金融工学の発展が大きく貢献しました。ブラック-ショールズモデルに代表されるオプション価格評価モデルは、この保険料が権利行使価格、原資産価格、満期までの期間、金利、そして将来の価格変動(ボラティリティ)といった複数の要因によって合理的に決定されることを理論的に示しています [2]。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所と収益事例
プロテクション戦略が提供する最大の長所は、その明確なリスク管理能力にあります。この戦略を導入することで、投資家はポートフォリオの最大損失を事前に確定させることができます。市場がどれほど下落しようとも、損失は「(資産の購入価格 − プットオプションの権利行使価格) + オプションの購入費用」までに限定されます。この損失の限定は、投資家に精神的な安心感をもたらし、パニック売りなどの非合理的な行動を抑制する効果も期待できます。
さらに重要な点は、ダウンサイドのリスクを限定しつつも、アップサイドの利益機会を放棄しない点です。もし市場が上昇した場合、プットオプションの権利は行使せずに放棄すればよく、投資家は保有する株式ポートフォリオの値上がり益をそのまま享受できます。もちろん、その利益からオプションの購入費用は差し引かれますが、利益の上限はありません。このように、損失は限定的、利益は無限定という非対称な損益構造を持つことが、この戦略の際立った特徴です。
この戦略の「収益」とは、単純なリターンの数値を追い求めることではなく、長期的な資産形成の観点から考える必要があります。市場の歴史において数年おきに発生する大規模なドローダウン(資産価値の下落)は、長期的な複利リターンを著しく毀損します。テールリスク、すなわち発生確率は低いものの甚大な損失をもたらすリスクをヘッジすることは、この大きな落ち込みを回避し、結果として長期的な資産の成長を安定させる上で有効であると主張されています [3]。つまり、短期的なコストを支払ってでも、壊滅的な損失を防ぐことが、長期的なリターン向上につながるという考え方です。
短所とリスク
一方で、この戦略には明確な短所、すなわちコストが存在します。保険が無料でないのと同様に、プットオプションによるプロテクションにも「保険料」にあたるオプションプレミアムの支払いが必要です。このコストは、特に市場が平穏な時期には安価に見えるかもしれません。しかし、ある研究によれば、ヘッジの真の費用対効果を決定するのはオプション価格の水準そのものではなく、市場が予測する将来の変動率(インプライド・ボラティリティ)と、実際に実現する変動率の差である「ボラティリティ・リスク・プレミアム」です。そして、このプレミアムの存在により、たとえ平穏な時期であってもプットオプションの買い手にとって期待収益はしばしば不利となり、結果としてプロテクション戦略が高コストになり得ることが示されています [4]。
さらに、この保険料は常に一定ではなく、市場環境によって大きく変動します。特に、市場参加者が将来の暴落を警戒し、保険の需要が高まる局面では、オプションの価格、特にその価格形成の重要な要素であるインプライド・ボラティリティ(市場が予測する将来の変動率)が上昇します。1987年のブラックマンデー以降、市場では「ボラティリティ・スマーク」と呼ばれる現象が観測されています。これは、権利行使価格が低い、つまり市場の深い下落に対する保険となるプットオプションほど、インプライド・ボラティリティが割高に評価される傾向を指します [5]。この現象は、暴落への備えとしての保険料が構造的に高く設定されていることを意味し、プロテクション戦略のコストをさらに押し上げる要因となっています。
この戦略の「損失」事例とは、暴落が起こらなかった多くの期間において、支払い続けた保険料がそのままコストとなり、単純なバイ・アンド・ホールド戦略にリターンで劣後する状況を指します。市場の恐怖感を反映するインプライド・ボラティリティは、実際にその後実現するボラティリティ(ヒストリカル・ボラティリティ)を平均的に上回る傾向があることが知られています [6]。これは、オプションの売り手がリスクプレミアムを要求するためであり、買い手であるプロテクション戦略の実行者は、平均して割高な保険料を支払い続けることになるのです。
非対称性と摩擦の視点から
ポジティブファクター:Asymmetry
プロテクション戦略の本質は、ポートフォリオの損益構造に意図的に「非対称性」を創り出す点にあります。これこそが、当メディア「Asymmetry Signal」が探求する核心的な概念です。
通常の株式保有(バイ・アンド・ホールド)における損益は、株価の変動に対して線形、つまり対称的です。株価が10%上昇すれば利益もそれに比例し、10%下落すれば損失も同様に比例します。しかし、プロテクション戦略を導入したポートフォリオの損益は、この対称性を破壊します。プットオプションが設定する損失の下限(フロア)を境に、損益曲線は折れ曲がります。下落局面では損失が限定される一方で、上昇局面では利益が無限定に拡大していくという、明らかに非対称な形を描くのです。
この戦略は、市場に内在する非対称なリスク、すなわちテールリスク(発生確率は低いが甚大な損失をもたらすリスク)に対する直接的な回答です。市場は平穏な上昇期間が長く続く一方で、下落は突発的かつ暴力的に発生する傾向があります。プロテクション戦略は、このネガティブな非対称性を持つリスクに対して、ポジティブな非対称性を持つ損益構造をぶつけることで対抗するアプローチと言えます。投資家は、小さな確実なコスト(プレミアム)を支払うことで、低確率で発生する壊滅的な損失という不確実性を回避し、安心して資産価格の上昇を追求する権利を確保するのです。この損益の非対称性こそが、投資家が対価を支払ってでも手に入れたい価値の源泉です。
ネガティブファクター:Friction
一方で、この戦略の有効性を常に蝕むのが「摩擦」の存在です。手数料やスプレッドといった基本的な取引コストももちろん摩擦の一部ですが、この戦略に特有の、より本質的な摩擦が存在します。
最大の摩擦は、前半の短所でも述べた「プレミアムの支払いがもたらす時間的価値の減価(セータ・ディケイ)」です。オプションの価値は、時間が経過するにつれて目減りしていきます。暴落が「起きない」全ての時間において、この保険料は静かに、しかし確実にリターンを蝕んでいきます。これは、戦略の有効性を維持するために常に乗り越えなければならない、継続的な向かい風と言えます。
もう一つの重要な摩擦は、市場参加者の恐怖感と期待感が織りなす「ボラティリティ・リスクプレミアム」です。プットオプションの価格、すなわち保険料は、市場が織り込む将来の予想変動率(インプライド・ボラティリティ)に大きく依存します。そして、市場は将来のリスクを過大に見積もる傾向があり、インプライド・ボラティリティは、事後的に実現する実際の変動率(ヒストリカル・ボラティリティ)を平均的に上回ることが多いのです。この差がボラティリティ・リスクプレミアムであり、オプションの売り手にとっては収益源泉となりますが、買い手であるプロテクション戦略の実行者にとっては、構造的に割高な保険料を支払わされることを意味する、極めて大きな摩擦となります。この摩擦の存在が、「保険は常に高くつく」という現実を投資家に突きつけるのです。
総括
この記事では、プットオプションを用いたプロテクション戦略について、その仕組みから長所・短所、そして非対称性と摩擦という独自の視点までを解説しました。
- プロテクション戦略は、株式などの資産を保有すると同時にプットオプションを購入することで、ポートフォリオに損失の下限を設定する「保険」のような手法です。
- 最大の長所は、損失を限定しつつも、価格上昇による利益は限定されないという「非対称な損益構造」を構築できる点にあります。
- 最大の短所は、保険料であるオプションプレミアムの支払いが継続的に発生し、市場の上昇・横ばい局面でリターンを押し下げるコスト(プレミアム・ドラッグ)となる点です。
- 非対称性は、テールリスクという市場の負の非対称性に対する直接的な防御策となり、投資家に安心感をもたらします。
- 摩擦としては、時間経過によるオプション価値の減価や、市場の恐怖感を反映して割高になりがちな保険料(ボラティリティ・リスクプレミアム)が、常にリターンを阻害する要因として存在します。
用語集
プットオプション 特定の資産を、定められた期日に、定められた価格(権利行使価格)で「売る権利」のこと。価格下落に対する保険として利用される。
プロテクション戦略 現物資産(株式など)を保有しながら、その資産に対するプットオプションを購入する戦略。日本語では保護的プットとも呼ばれる。
権利行使価格 オプションの権利を行使する際に適用される、あらかじめ定められた売買価格。ストライクプライスとも言う。
プレミアム オプションの買い手が、その権利を得るために売り手に支払う対価のこと。保険における「保険料」に相当する。
ダウンサイドリスク 資産価格が想定に反して下落することによって損失を被る危険性のこと。
ボラティリティ 資産価格の変動の激しさを表す指標。一般的に、ボラティリティが高いほどオプションのプレミアムは高くなる。
インプライド・ボラティリティ 現在のオプション価格から逆算して算出される、市場参加者が予想する将来のボラティリティのこと。「恐怖指数」とも呼ばれるVIX指数は、S&P500のインプライド・ボラティリティを基に算出される。
テールリスク 正規分布の両端(テール)で起こるような、発生確率は非常に低いものの、一度発生すると甚大な影響を及ぼすリスクのこと。市場の暴落などがこれにあたる。
アシンメトリー 非対称性のこと。投資においては、利益と損失の可能性が不均等である状態を指す。プロテクション戦略は、ポジティブなアシンメトリー(利益は大きく、損失は小さい)を創り出す。
ドローダウン 資産価値が、ある期間の最高値から下落した際の、その下落率のこと。
参考文献一覧
[1] Leland, H. E. (1980). Who Should Buy Portfolio Insurance?. The Journal of Finance, 35(2), 581-594.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1980.tb02190.x
[2] Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-654.
http://dx.doi.org/10.2307/1831029
[3] Bhansali, V. (2014). Tail risk hedging: Creating robust portfolios for volatile markets. McGraw-Hill Professional.
※書籍です
[4] Israelov, R., & Nielsen, L. N. (2015). Still Not Cheap: Portfolio Protection in Calm Markets. The Journal of Portfolio Management, 41(4), 108–120.
https://doi.org/10.3905/jpm.2015.41.4.108
[5] Rubinstein, M. (1994). Implied binomial trees. The Journal of Finance, 49(3), 771-818.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb00079.x
[6] Figlewski, S. (2009). Estimating the implied risk neutral density for the U.S. market portfolio. In Volatility and time series econometrics: Essays in honor of Robert F. Engle (pp. 1-37). Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199549498.003.0015
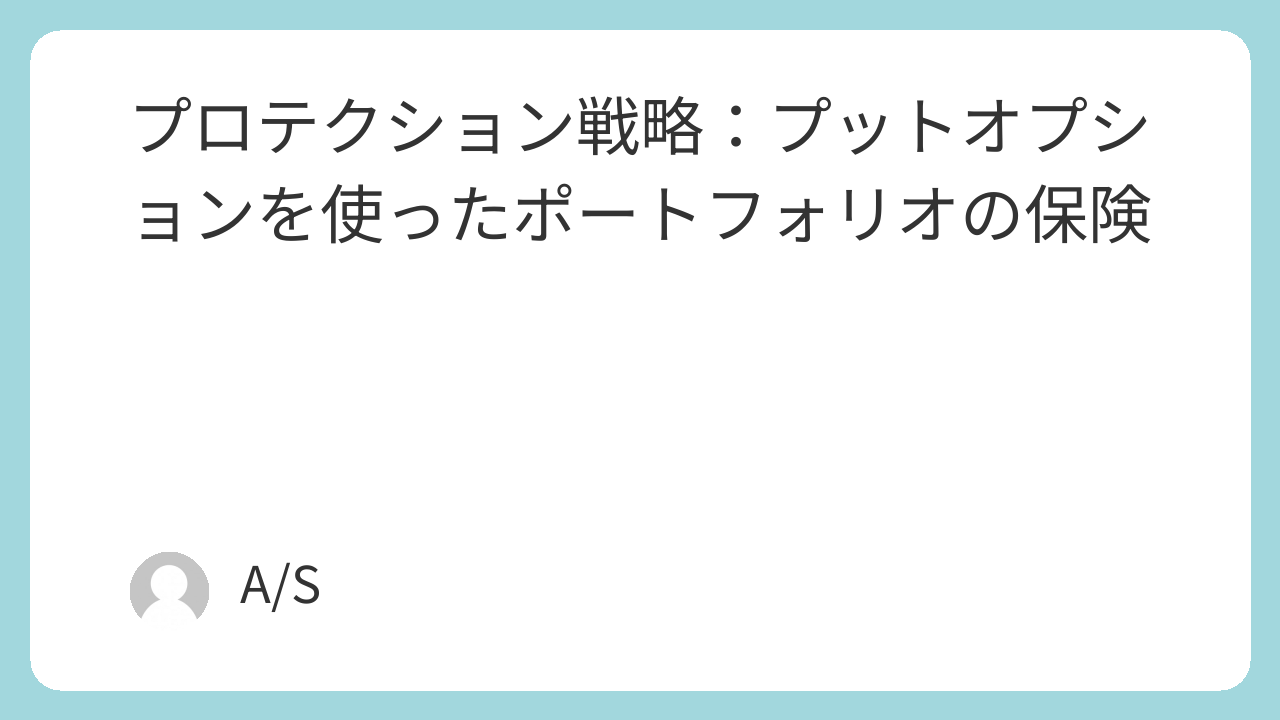
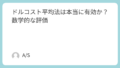
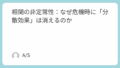
コメント