概論
ポートフォリオが抱えるリスクを、どのように測定し、管理すればよいのでしょうか。この問いに対する最もポピュラーな答えの一つが、バリュー・アット・リスク(Value at Risk, VaR)です。VaRは、「ある一定期間において、特定の確率で発生しうる最大の損失額」を一つの数値で示す、直感的で分かりやすいリスク指標です。例えば、「信頼水準99%で1日のVaRが100万円」であれば、「100日に99日は損失が100万円を超えることはない」と解釈できます。
しかし、このVaRには致命的な欠点があります。それは、「では、その最悪の1%のケースでは、いったいどれほどの損失が発生するのか」という問いに、何も答えてくれない点です。VaRは損失分布の「裾野」、すなわちテール部分で起こる壊滅的な損失の大きさを完全に無視してしまいます。このVaRが捉えきれない極端なリスクこそが、テールリスクです。
この深刻な問題を克服するために開発されたのが、コンディショナル・バリュー・アット・リスク(Conditional Value at Risk, CVaR)です。CVaRは、期待ショートフォール(Expected Shortfall, ES)とも呼ばれ、「損失額がVaRを超えた場合に、その損失額の平均がいくらになるか」を示します。つまり、VaRが「最悪の事態の一歩手前」までのリスクしか見ていないのに対し、CVaRは「本当に最悪の事態が起こった時、平均してどれくらいのダメージを受けるのか」という、テールリスクの深刻さを直接的に測定するのです。
CVaRの重要性は、その優れた数学的性質によっても裏付けられています。フィリップ・アルツナーらの研究は、VaRが分散投資の効果を正しく評価できない場合があるなど、望ましいリスク指標が満たすべき公理(コヒーレントなリスク尺度)の一部を満たしていないことを示しました。一方で、CVaR(ES)はこれらの公理をすべて満たす、理論的に優れたリスク指標であることが証明されています [1]。
このCVaRを、単なるリスク測定指標から、ポートフォリオ最適化の実用的なツールへと昇華させたのが、ロックフェラーとウリヤセフによる研究です。彼らは、CVaRを効率的に計算し、最小化するための数学的な枠組みを開発し、金融リスク管理の世界に大きな進歩をもたらしました [2]。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
CVaRはVaRの欠点を補う強力なツールですが、その利用には長所と短所の両方を理解しておく必要があります。
長所、強み、有用な点について
CVaRの最大の強みは、VaRが見過ごしてしまうテールリスクの大きさを定量化できる点にあります。これにより、投資家はポートフォリオが抱える「隠れた」壊滅的損失の可能性を、より現実的に評価することができます。
理論的な観点からは、CVaRが「コヒーレントなリスク尺度」であることが極めて重要です。特に、劣加法性という性質を満たす点がVaRに対する大きな優位性です [1, 3]。劣加法性とは、二つのポートフォリオを合算した際のリスクが、それぞれのリスクの合計よりも大きくはならない、という性質を指します。VaRはこの性質を満たさないため、複数の資産を組み合わせることでかえってVaRが増加するという直感に反する結果を生むことがありますが、CVaRではそのような問題は起こりません。これにより、分散投資によるリスク削減効果を常に正しく評価できます。
この優れた性質は、実践的なポートフォリオ最適化においても大きな力を発揮します。CVaRを最小化するようにポートフォリオを構築するアプローチは、VaRの最適化に比べて、より安定した頑健な結果をもたらすことが知られています。クロクマルらの研究は、CVaRを用いたポートフォリオ最適化が、現実的な制約の下で効率的に実行可能であることを示しました [4]。
特に、ヘッジファンドのように、リターン分布が正規分布から大きく乖離し、負の方向に大きな歪み(ネガティブ・スキュー)を持つような非対称な資産を扱う際に、CVaRは真価を発揮します。アガーワルとナイクの研究は、このような資産のリスクを伝統的な指標で評価することの難しさを指摘しており、テールリスクを捉えるCVaRが、より適切なリスク管理の枠組みを提供することを示唆しています [5]。
短所、弱み、リスクについて
多くの利点を持つCVaRですが、決して万能のリスク指標ではありません。いくつかの重要な限界と課題を抱えています。
第一に、計算の複雑さが挙げられます。VaRが比較的単純に計算できるのに対し、CVaRは損失分布のテール部分の平均を取るため、より多くの計算ステップとデータを必要とします。特に、多数の資産からなる大規模なポートフォリオのCVaRを、モンテカルロ・シミュレーションなどを用いて計算する際には、相応の計算資源が求められます。
第二に、テールリスクの推定におけるデータ依存性の問題です。CVaRはテール部分の損失を評価しますが、その評価はあくまで過去のデータに基づいています。もし、過去のデータに壊滅的な暴落のサンプルが十分にないと、将来のテールリスクを過小評価してしまう危険性があります。結局のところ、CVaRも過去に前例のない「未知の未知」のリスク(ブラックスワン)を予測することはできません。
また、CVaRが常に最適な選択を導くとは限らない状況も指摘されています。ある研究によれば、リスクフリー資産が存在しない場合、CVaR制約は極度にリスクを回避する投資家に対して、より標準偏差の大きいポートフォリオを選択させるという、意図に反する効果をもたらす可能性があることが示されています [6]。これは、CVaRがテールリスクを管理する上で強力なツールである一方、特定の条件下では投資家の選好と相容れない結果を生む可能性を示唆しています。
非対称性と摩擦の視点から
VaRからCVaRへの進化は、金融市場が持つ本質的な性質、すなわち「非対称性」と、それを測定しようとする際に直面する「摩擦」を浮き彫りにします。
Asymmetry:損失分布の非対称性
金融市場におけるリターンや損失の分布は、正規分布のような美しい対称形を描くことは稀です。現実の分布は、左側の裾野が長く伸びた「ファットテール」や「ネガティブ・スキュー」といった、非対称な特徴を持つことがほとんどです。これは、平穏な時期の小さな利益が、一度の暴落による巨大な損失で吹き飛ぶ可能性があることを意味します。
VaRは、この損失分布の非対称性を本質的に無視します。VaRが示すのは、ある信頼水準までの損失額であり、その閾値を超えた先の世界がどれほど悲惨であるかについては、何の情報も提供しません。
これに対し、CVaRは、まさにこの「非対称なテール部分」を測定するために設計された指標です。損失がVaRを超えたという条件下での期待損失を計算することで、テールリスクの深刻さを直接的に捉えます。ヘッジファンドの戦略など、ペイオフが極端に非対称となる可能性のある投資対象を評価する際、その真のリスクを暴き出すのはVaRではなくCVaRなのです [5]。CVaRは、市場に内在する非対称なリスクを認識し、それをポートフォリオ管理に組み込むための、強力なレンズと言えます。
Friction:推定と計算の摩擦
CVaRは理論的に優れていますが、その実用化には常に「摩擦」が伴います。手数料やスプレッドといった取引コストに加え、CVaRの計算と利用そのものに根差した、より根源的な摩擦が存在します。
第一に、「推定の摩擦」です。CVaRは、テール部分の損失の期待値を計算しますが、そのテール部分を構成するデータは、定義上、極めて稀にしか発生しません。限られた過去のデータから、将来起こりうるテールイベントの確率分布を正確に「推定」することは、統計的に極めて困難な作業です。この「真の分布を知り得ない」という根源的な情報の摩擦が、計算されたCVaRの信頼性に常に影を落とします。過去のデータに依存する限り、私たちは常にバックミラーを見ながら未来の崖に向かって運転しているようなものなのです。
第二に、「計算の摩擦」です。CVaRの計算、特に多数の資産を含むポートフォリオの最適化は、VaRに比べて計算負荷が大きくなります [2, 4]。これは、単純な分析ツールしか持たない個人投資家や、計算資源に限りがある小規模な組織にとっては、CVaRの導入を妨げる物理的な摩擦となり得ます。理論の優雅さと、実践の複雑さとの間には、常にこの計算コストという摩擦が存在するのです。
総括
- VaRは「特定の確率で発生しうる最大損失額」を示す一方、その確率を超えた場合の損失の大きさ(テールリスク)を無視するという致命的な欠点を持っています。
- CVaR(期待ショートフォール)は、損失がVaRを超えた場合の平均損失額を示すことで、このテールリスクを直接的に測定します。
- CVaRは、分散投資の効果を常に正しく評価できる「コヒーレントなリスク尺度」であり、VaRよりも理論的に優れていることが証明されています [1, 3]。
- CVaRを最小化するポートフォリオ最適化は、特にリターン分布が非対称な資産を扱う際に有効なリスク管理手法となります [2, 4, 5]。
- しかし、CVaRの計算は複雑であり、その精度はテールイベントに関する過去データに大きく依存するという「推定の摩擦」という弱点を抱えています。
用語集
バリュー・アット・リスク(VaR) ある一定の期間において、特定の信頼水準の下で、被る可能性のある最大損失額のこと。
コンディショナル・バリュー・アット・リスク(CVaR) 損失額がVaRを超えてしまうという条件下での、損失額の条件付き期待値。期待ショートフォール(ES)とも呼ばれる。
テールリスク 確率分布の裾野(テール)で発生する、起こる確率は極めて低いが、発生した場合の損失が非常に大きいリスクのこと。
コヒーレントなリスク尺度 望ましいリスク指標が満たすべきとされる、単調性、準加法性、正の同次性、並進不変性という4つの数学的公理。CVaRはこれを満たすが、VaRは準加法性を満たさない場合がある。
劣加法性(準加法性) 二つのポートフォリオを合算した際のリスクが、それぞれのリスクの合計よりも大きくはならないという性質。分散投資の効果を正しく評価するための重要な公理。
ポートフォリオ最適化 与えられたリスク水準の下でリターンを最大化する、あるいは与えられたリターン水準の下でリスクを最小化するように、資産の組み合わせ(ポートフォリオ)を決定すること。
正規分布 統計学で最も広く用いられる確率分布の一つ。平均値を中心に左右対称の釣鐘状の形をしている。多くの金融理論の前提となっているが、現実の市場リターンはこれに従わないことが多い。
ファットテール 確率分布において、平均から大きく離れた極端な事象(テールイベント)が、正規分布の予測よりも高い確率で発生する性質。
ネガティブ・スキュー 確率分布が左側(マイナス側)に長い裾野を持つ、非対称な歪みのこと。大きな損失が時折発生することを示す。
モンテカルロ・シミュレーション 乱数を用いて多数のシミュレーションを行い、確率的な事象の結果を推定する手法。金融工学において、ポートフォリオのリスク測定やデリバティブの価格評価などに広く用いられる。
参考文献一覧
[1] Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M., & Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. Mathematical Finance, 9(3), 203-228.
https://doi.org/10.1111/1467-9965.00068
[2] Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41.
https://doi.org/10.21314/JOR.2000.038
[3] Acerbi, C., & Tasche, D. (2002). On the coherence of expected shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503.
https://doi.org/10.1016/S0378-4266(02)00283-2
[4] Krokhmal, P., Palmquist, J., & Uryasev, S. (2002). Portfolio optimization with conditional value-at-risk objective and constraints. Journal of Risk, 4(2), 43-68.
http://dx.doi.org/10.21314/JOR.2002.057
[5] Agarwal, V., & Naik, N. Y. (2004). Risks and portfolio decisions involving hedge funds. The Review of Financial Studies, 17(1), 63-98.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhg044
[6] Alexander, G. J., & Baptista, A. M. (2004). A Comparison of VaR and CVaR Constraints on Portfolio Selection with the Mean-Variance Model. Management Science, 50(9), 1261-1273.
https://www.jstor.org/stable/30046232
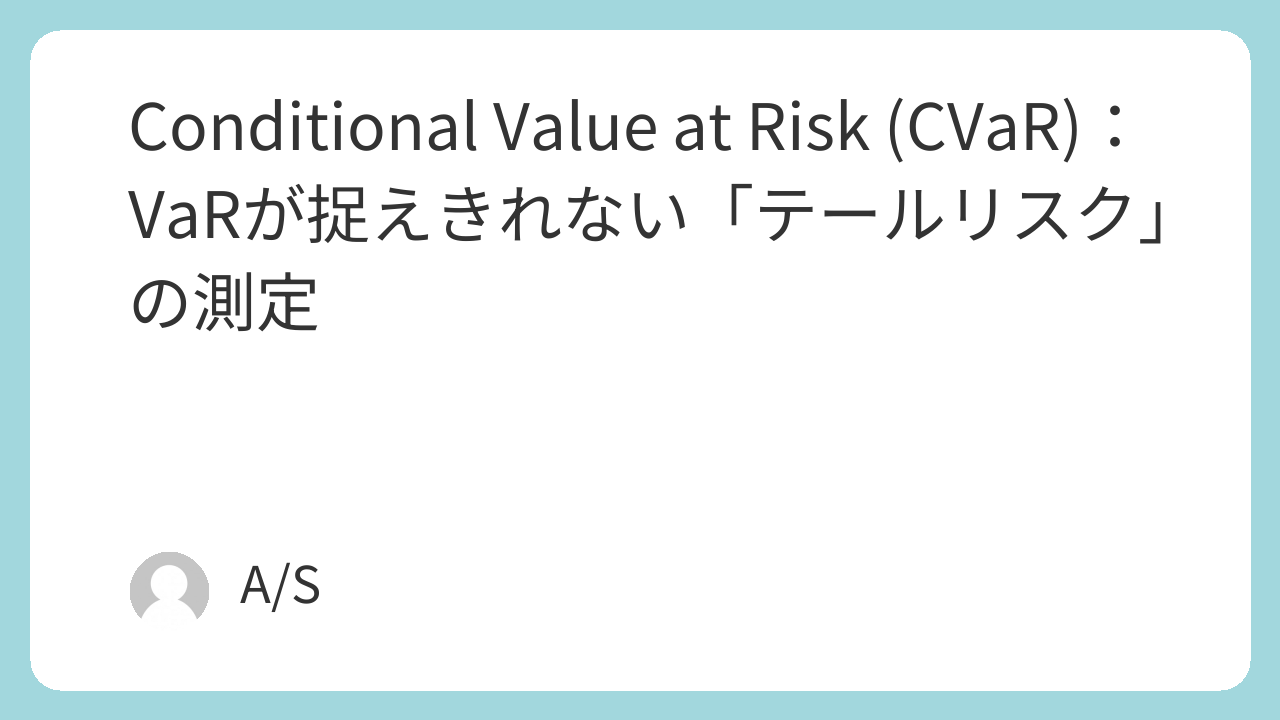
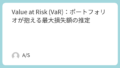
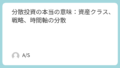
コメント