概論
ドルコスト平均法は、多くの個人投資家にとって、最もポピュラーで、かつ推奨されることが多い投資手法の一つです。「毎月1万円を投資信託に積み立てる」といったように、定期的に一定の金額を特定の金融商品に投資し続ける戦略を指します。
この手法の最大の魅力は、そのシンプルさと規律性にあります。価格が高い時には少なく、価格が安い時には多く購入単位を買い付けることになるため、自動的に平均購入単価を引き下げる効果が期待できます。また、市場のタイミングを計るという、プロでも難しい判断を回避できるため、感情に左右されずに投資を継続できるという心理的な利点も大きいとされています。この実践的な有用性から、著名な投資解説書の中でも、個人投資家が規律を保つための賢明な戦略としてしばしば紹介されています [1]。
しかし、この広く受け入れられているドルコスト平均法は、学術的な観点から見ると、必ずしも「最適」な戦略とは言えません。その有効性を巡る議論の核心には、「手元にまとまった資金がある場合、一度に全額を投資する『一括投資』と、分割して投資する『ドルコスト平均法』のどちらが、数学的に優れた結果をもたらすのか」という根源的な問いが存在します。
本記事では、このドルコスト平均法が持つ有効性の神話を、学術的な研究成果に基づき、その長所と短所の両面から数学的に評価していきます。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
ドルコスト平均法は、その実践しやすさから多くの支持を集めていますが、そのリターンは市場環境に大きく左右されます。その有効性を、批評的な視点から解説します。
長所、強み、有用な点について
ドルコスト平均法の最大の強みは、投資家を心理的な罠から守り、規律ある投資を可能にする点にあります。市場の頂点で一括投資してしまうことへの恐怖、いわゆる「高値掴み」のリスクを回避したいという感情は、多くの投資家が抱くものです。ドルコスト平均法は、この投資タイミングに関する後悔の念を和らげる効果があることが指摘されています [2]。
数学的な観点からは、価格が変動する市場において、ドルコスト平均法はリスクを低減させる効果があります。ある研究では、標準的な平均分散分析を用いて、ドルコスト平均法がリスクを低下させるために利用できることが示されています。その結果、投資家のリスク許容度によっては、ドルコスト平均法が最適な投資戦略となり得ることが示唆されています [3]。
また、多くの個人投資家にとって、給与などの定期的な収入から少しずつ投資資金を捻出するという状況はごく一般的です。このような場合、ドルコスト平均法は、投資を始めるための資金が貯まるのを待つ必要なく、すぐに投資を開始できるという、極めて実践的な戦略となります [1]。
短所、弱み、リスクについて
一方で、ドルコスト平均法が数学的に見て最適な戦略ではないことは、古くから指摘されてきました。その最大の弱点は、歴史的に見て右肩上がりの成長を続けてきた株式市場のような資産クラスにおいて、一括投資にリターンで劣後する傾向があるという、厳然たる事実にあります。
この問題の核心は、機会損失にあります。ドルコスト平均法は、投資資金の一部を現金として待機させることを意味します。市場が上昇トレンドにある場合、この待機資金は、本来得られたはずのリターンを逃してしまいます。ジョージ・コンスタンティニデスによる1979年の研究は、期待リターンがプラスである市場において、ドルコスト平均法が数学的に準最適であることを理論的に示しました [4]。
この理論的な指摘は、多くの実証研究によって裏付けられています。ある研究では、投資信託を対象としたシミュレーションにおいて、特に6年間という期間で見た場合、一括投資がドルコスト平均法やバリュー平均法をアウトパフォームしたことが報告されています [5]。
さらに、ドルコスト平均法には利益がないと結論付け、代替戦略であるバイ・アンド・ホールドの方が優れたパフォーマンスを達成するとした研究もあります [6]。これらの結果は、ドルコスト平均法がもたらす心理的な安心感と、数学的な期待リターンとの間にトレードオフが存在することを示唆しています。
非対称性と摩擦の視点から
ドルコスト平均法の有効性を巡る議論は、単なる数学的な優劣だけでは語れません。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことで、なぜこの戦略がこれほどまでに支持されるのかが見えてきます。
Asymmetry:後悔という感情の非対称性
ドルコスト平均法が持つ最大の価値は、投資家が直面する「後悔の非対称性」を緩和する点にあります。
行動ファイナンスの研究が示すように、人間は合理的な判断を常に行えるわけではありません。特に、投資の意思決定においては、「後悔」という感情が大きな影響を及ぼします。投資家が最も恐れる後悔は二つあります。一つは、一括投資した直後に市場が暴落し、「最高の値で買ってしまう」という行動の後悔。もう一つは、投資を見送っている間に市場が上昇し、「利益を取り逃がす」という非行動の後悔です。
研究によれば、多くの人々は、行動した後悔(高値掴み)の方を、非行動の後悔(機会損失)よりも、心理的に強く、そして痛みを伴うものとして感じます [2]。ドルコスト平均法は、この非対称な後悔の感情に対する、極めて有効な処方箋となります。投資を時間的に分散させることで、一括投資という大きな「決断」を回避し、最悪のタイミングで投資してしまうという、最も痛みを伴う後悔の可能性を劇的に低下させるのです。数学的なリターンを多少犠牲にしてでも、この心理的な安定を得られることが、ドルコスト平均法が選ばれる本質的な理由と言えるでしょう。
Friction:意思決定と機会損失という摩擦
ドルコスト平均法は、投資家が直面する二種類の「摩擦」を巧みに扱います。
第一に、「意思決定の摩擦」です。いつ投資を始めるべきか、という市場タイミングの問題は、投資家にとって非常に大きな精神的負担、すなわち認知的な摩擦となります。この摩擦は、多くの人々を行動できなくさせ、結果として投資を開始できないという最悪の事態を招きます。ドルコスト平均法は、「毎月決まった日に買う」というシンプルなルールを設けることで、この意思決定の摩擦を完全に取り除きます。これにより、投資家は悩むことなく、スムーズに投資プロセスへと移行できるのです [1]。
第二に、「機会損失の摩擦」です。これはドルコスト平均法の弱点そのものです。市場が上昇トレンドにある場合、投資されずに現金として待機している資金は、リターンを生みません。この待機資金の存在が、一括投資に対するパフォーマンスの劣後、すなわち機会損失という摩擦を生み出します [4, 5, 6]。ドルコスト平均法は、「意思決定の摩擦」を解消する代償として、この「機会損失の摩擦」を受け入れる戦略であると解釈することができます。どちらの摩擦をより重視するかは、投資家それぞれの合理性と感情のバランスに委ねられているのです。
総括
- ドルコスト平均法は、定期的に定額を投資する手法であり、平均購入単価を引き下げる効果や、規律ある投資を継続できる心理的利点があります [1]。
- 数学的には、期待リターンがプラスの市場(歴史的な株式市場など)において、投資資金を市場に長く晒すことができる「一括投資」の方が、ドルコスト平均法よりも高いリターンをもたらす傾向があります [4, 5, 6]。
- ドルコスト平均法の最大の価値は、一括投資直後の暴落という「高値掴みの後悔」を避けられる点にあり、これは多くの投資家にとって数学的なリターンの差を上回る心理的便益となり得ます [2]。
- ドルコスト平均法は、市場タイミングを計るという「意思決定の摩擦」を解消する一方で、資金を現金として待機させることによる「機会損失の摩擦」を受け入れる戦略と見なせます。
用語集
ドルコスト平均法 定期的に一定金額の金融商品を購入し続ける投資手法。価格が高い時には少なく、安い時には多く買うことで、平均購入単価を平準化する効果がある。
一括投資 手元にある投資資金を、時期を分散させずに一度に全額投資する手法。
平均購入単価 投資した金融商品の1単位あたりの平均取得価格。総投資額を購入した総数量で割って算出される。
機会損失 最善の意思決定をしなかったために、得られたはずの利益を逃してしまうこと。ドルコスト平均法では、待機資金が市場上昇の恩恵を受けられないことが機会損失となる。
ボラティリティ 資産価格の変動の激しさを表す指標。一般的に、標準偏差で測定される。
期待リターン ある投資から将来得られると期待される平均的なリターンのこと。
行動ファイナンス 心理学の知見を応用して、従来の経済学では説明できない非合理的な投資家行動や市場の動きを解明しようとする学問分野。
後悔理論 人々が意思決定を行う際に、選ばなかった選択肢がもたらしたであろう結果を想像し、「後悔」を最小化するように行動する傾向があるとする理論。
市場タイミング 市場の価格変動を予測し、最も有利な価格で売買しようとすること。
投資信託 多くの投資家から集めた資金を一つにまとめ、専門家が株式や債券などに分散投資する金融商品。
参考文献一覧
[1] Malkiel, B. G. (2019). A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing (12th ed.). W. W. Norton & Company.
※書籍です
[2] Statman, M. (1995). A behavioral framework for dollar-cost averaging. The Journal of Portfolio Management, 22(1), 75-81.
https://doi.org/10.3905/jpm.1995.409537
[3] Cho, D. D., & Kuvvet, E. (2015). Dollar-Cost Averaging: The Trade-Off Between Risk and Return. Journal of Financial Planning, 28(10), 52-58.
https://ssrn.com/abstract=4654709
[4] Constantinides, G. M. (1979). A note on the suboptimality of dollar-cost averaging as an investment policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 14(2), 443-450.
https://doi.org/10.2307/2330513
[5] Zein, M. M., & Darma, G. S. (2023). The Dollar Cost Averaging, Lump Sum, and Value Averaging Strategies in Mutual Fund Investments. Review of Quantitative Entrepreneurship, Management, and Science, 1(1), 1-10.
https://doi.org/10.35877/454RI.qems2068
[6] Knight, J. R., & Mandell, L. (1993). Nobody gains from dollar cost averaging: analytical, numerical and empirical results. Financial Services Review, 2(1), 51-58.
https://doi.org/10.1016/1057-0810(92)90015-5
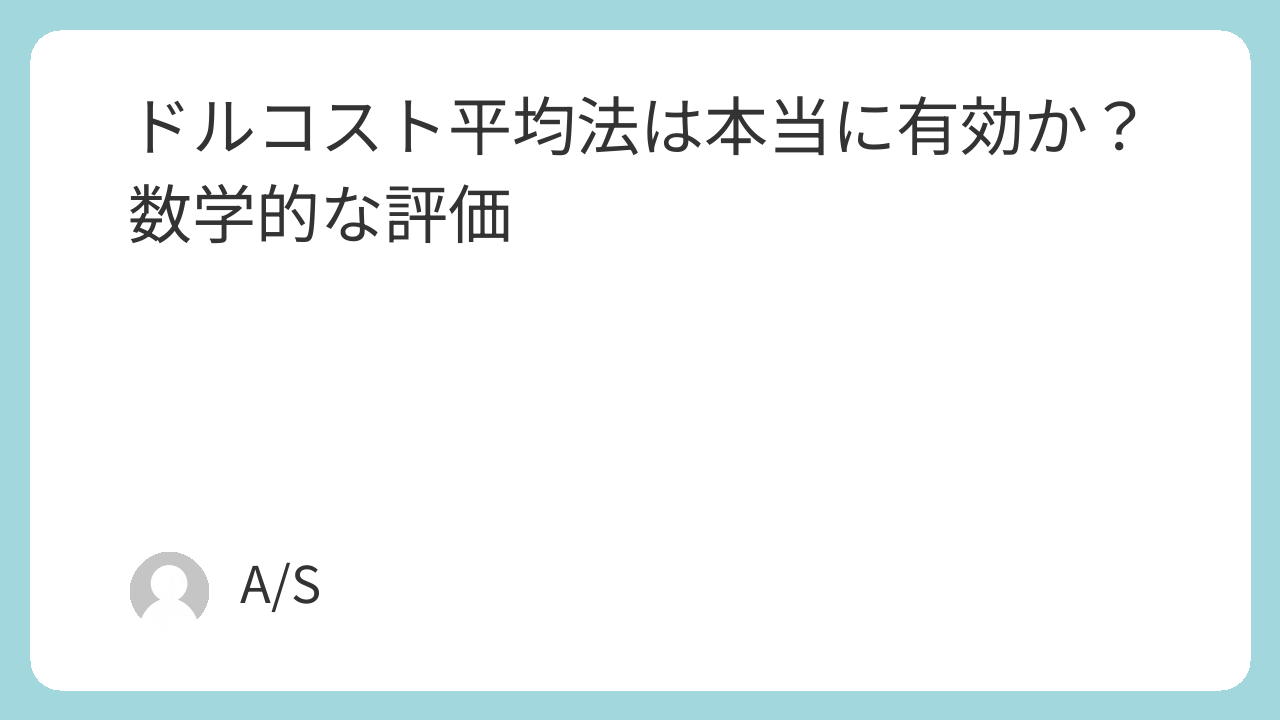
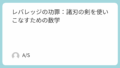
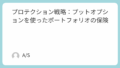
コメント