概論
ある投資戦略のパフォーマンスを評価する際、私たちはしばしば「リスクに見合ったリターン」を測るための物差しを必要とします。その代表格であるシャープレシオは、リターンのボラティリティ(標準偏差)をリスクとして用います [1]。しかし、多くのトレーダーや投資家にとって、統計的なばらつきを示すボラティリティよりも、もっと心に突き刺さる、直感的なリスクが存在します。それがドローダウンです。
ドローダウンとは、資産がある時点での高値からどれだけ下落したかを示す指標であり、特にその期間で最も大きな下落率を示した最大ドローダウン(Maximum Drawdown)は、その戦略が経験した「最大の痛み」を具体的に表します。ボラティリティがリターンの「ばらつき」という抽象的なリスクを示すのに対し、最大ドローダウンは「もし最悪のタイミングで投資を始めていたら、資産が最大何パーセント失われたか」という、極めて現実的で、心理的な影響の大きいリスクを示すのです。
この、投資家の心理的苦痛と直結するドローダウンを、リスク指標としてパフォーマンス測定に組み込んだのが、カルマーレシオとスターリングレシオです。
- カルマーレシオ:年率リターンを、その期間の最大ドローダウンで割ることで計算されます。
- スターリングレシオ:年率リターンを、その期間の平均ドローダウン(一定以上の規模のドローダウンの平均値)で割ることで計算されます。
これらの指標は、特にヘッジファンドやCTA(商品投資顧問業者)といった、リターン分布が正規分布に従わないことが多いオルタナティブ投資の世界で、その有用性が議論されてきました。なぜなら、これらの戦略はしばしば、コツコツと利益を積み上げた後に一度の大きな損失に見舞われる、といった非対称なリターン特性を持つため、ドローダウンがそのリスクをより的確に捉えるからです [2]。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について:投資家の「痛み」を測る
心理的なリスクの可視化
カルマーレシオやスターリングレシオの最大の強みは、投資家が経験する心理的な「痛み」をリスクとして直接的に評価する点にあります。
標準偏差は、好ましい上方へのブレもリスクとして計算してしまいますが、ドローダウンは純粋に損失の側面だけを捉えます。特に最大ドローダウンは、投資家がその戦略を継続するか、あるいは恐怖に駆られて投げ出してしまうかを決定づける、最も重要な経験の一つです。ゲットマンスキー、ロー、マカロフによる2004年の研究は、ヘッジファンドのリターン特性を分析する中で、投資家が過去のパフォーマンス、特に大きな損失の経験にどう反応するかという問題の重要性を示唆しています [3]。ドローダウンベースの指標は、このような投資家の行動に影響を与えるリスクを、より直感的に理解するための強力なツールとなります。
非正規分布リターンを持つ戦略の評価(収益事例)
これらの指標は、リターンが正規分布に従わない戦略の評価において、特にその真価を発揮します。
エリングとシューマッハーによる2007年の包括的な研究は、様々なパフォーマンス指標(シャープレシオ、ソルティノレシオ、カルマーレシオなど)を用いて、ヘッジファンドのランキングがどう変わるかを比較検証しました [2]。その結果、多くのヘッジファンドのリターンは正規分布から大きく逸脱しており、どのパフォーマンス指標を用いるかによって、ファンドの評価順位が大きく変動することが明らかになりました。これは、シャープレシオだけでは見えてこない、ドローダウンという側面から見た戦略の優劣が存在することを示唆しています。例えば、平均リターンとボラティリティが同じでも、最大ドローダウンが小さい戦略は、カルマーレシオでは高く評価されることになります。
短所、弱み、リスクについて:過去の「一点」に依存する危険性
ドローダウンベースの指標は直感的で有用ですが、その性質上、いくつかの深刻な弱点とリスクを内包しています。
過去の最大値への過度な依存(損失事例)
カルマーレシオの最も根本的な弱点は、その計算が過去の運用期間におけるたった一つの出来事、すなわち「最大ドローダウン」に完全に依存している点です。
チェクロフ、ウリヤセフ、ザバランキンによる2005年の研究でも論じられているように、最大ドローダウンは統計的に非常に扱いにくい性質を持っています [4]。もし、ある戦略の運用期間が比較的幸運で、まだ真のストレス期を経験していなければ、その最大ドローダウンは本来のリスクを過小評価しているかもしれません。逆に、一度でも極端な市場環境に見舞われれば、そのたった一度の出来事が、その後の長期間にわたってカルマーレシオを低く縛り付けてしまうのです。
測定期間への依存性
この問題は、測定期間をどう設定するかによって、さらに複雑になります。例えば、過去3年間の最大ドローダウンを基に算出したカルマーレシオと、過去10年間のそれを基にしたものでは、全く異なる評価になる可能性があります。短い期間では非常に優れたレシオを示していた戦略が、測定期間を延ばした途端に、過去の大きなドローダウンを含んでしまい、評価が暴落するということも起こり得ます。
パフォーマンスの操作可能性
ドローダウンベースの指標は、意図的な操作に対して脆弱である可能性も指摘されています。ゲッツマンらの2007年の研究は、ファンドマネージャーが、報告されるパフォーマンス指標を良く見せるために、リスクテイクのパターンを歪めるインセンティブを持つことを論じています [5]。例えば、まだ大きなドローダウンを経験していない期間においては、見かけ上のカルマーレシオを高く維持するために、テールリスク(稀だが巨大な損失が発生するリスク)を密かに積み上げる、といった行動が考えられます。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、ドローダウンという指標が、ボラティリティとは異なるリスクの側面を捉えることができるのでしょうか。そして、その指標にはどのような限界が潜んでいるのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:リターンの「経路」がもたらす非対称性
カルマーレシオやスターリングレシオが捉えようとしているリスクの本質は、リターンの「経路(パス)」が持つ非対称性にあります。
二つの異なる投資戦略が、最終的に同じ平均リターンとボラティリティを記録したとします。シャープレシオで評価すれば、この二つの戦略の優劣は同じです。しかし、そのリターンの「経路」は全く異なるかもしれません。一方は滑らかな右肩上がりの曲線を描いたのに対し、もう一方は途中で資産が半分になるほどの巨大なドローダウンを経験した後に、急回復して同じリターンに到達したかもしれません。
このリターン経路の非対称性こそが、投資家が実際に経験する損益の現実です。ドローダウンベースの指標は、この「途中でどれだけ苦しんだか」という、経路に依存した非対称なリスクを評価するための試みです。特にヘッジファンドのリターンを分析したゲットマンスキーらの研究が示唆するように、投資家の意思決定は、最終的なリターンだけでなく、そこに至るまでの過程、特に大きな損失の経験に強く影響されます [3]。カルマーレシオは、この非対称な投資家心理に寄り添ったリスク指標であると言えるのです。
Friction:過去の「一点」に囚われる情報の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、ドローダウンベースの指標には、その成り立ちに起因する、より本質的な「摩擦」が存在します。
過去の情報への依存という摩擦
カルマーレシオの計算に用いられる最大ドローダウンは、その定義上、過去のデータセットにおけるたった一つの最大値です。この「過去の一点」を、将来のリスクを代表する指標として用いることには、大きな情報の摩擦が伴います。
市場の環境(レジーム)は常に変化します。過去10年間が比較的穏やかな市場であった場合、その期間の最大ドローダウンは、その戦略が本来持つ真のリスクを著しく過小評価しているかもしれません。この「過去は未来を代表しない」という情報の摩擦は、カルマーレシオが、将来起こりうる未知の大きさのドローダウンに対して、投資家を無防備にしてしまう危険性をはらんでいます [4]。
指標を「ハック」する行動への摩擦
パフォーマンス指標は、それが広く使われるようになると、その指標を良く見せるために運用者が行動を歪める「ゲーミング(指標ハック)」の対象となるリスクがあります。
ゲッツマンらの研究が示すように、特定の指標を最大化しようとするインセンティブは、意図しないリスクテイクを助長する可能性があります [5]。例えば、カルマーレシオを高く維持するために、ファンドマネージャーが、頻繁には起こらないが一度起こると壊滅的な損失をもたらすテールリスクを、ポートフォリオに密かに積み上げるかもしれません。過去のデータ上では最大ドローダウンが小さく、見かけのカルマーレシオは非常に高くなりますが、その裏では巨大なリスクが育っているのです。この指標の抜け穴を突く行動は、投資家が真のリスクを認識することを妨げる、深刻な摩擦となります。
総括
・カルマーレシオとスターリングレシオは、伝統的なシャープレシオとは異なり、リスクを最大ドローダウンや平均ドローダウンで測定するパフォーマンス指標です。
・これらの指標は、ボラティリティという統計的なばらつきではなく、投資家が経験する心理的な「痛み」や、資産が過去の高値からどれだけ下落したかという現実的な損失を直接的に評価する点で優れています。
・特に、リターン分布が正規分布に従わないヘッジファンドなどの戦略評価において、シャープレシオとは異なる視点を提供します [2]。
・一方で、その計算が過去のたった一つの最大ドローダウンという単一の出来事に過度に依存しているため、将来のリスクを正確に予測できない、あるいは意図的に操作される可能性があるといった、深刻な弱点も抱えています [4, 5]。
用語集
カルマーレシオ (Calmar Ratio) 年率リターンを、その期間の最大ドローダウンで割って算出されるリスク調整後リターン指標。
スターリングレシオ (Sterling Ratio) 年率リターンを、その期間の平均ドローダウンで割って算出されるリスク調整後リターン指標。
最大ドローダウン (Maximum Drawdown) 特定の運用期間において、資産価格(価値)が過去の最高値から下落した際の、最大の下落率。
シャープレシオ (Sharpe Ratio) 超過リターンを、リターンの標準偏差(トータル・リスク)で割ることで算出される、最も一般的なリスク調整後リターン指標。
ソルティノレシオ (Sortino Ratio) 超過リターンを、リターンの下方偏差(ダウンサイド・リスク)で割ることで算出される、シャープレシオの改良版。
ボラティリティ (Volatility) 資産価格の変動の激しさを示す指標。リターンの標準偏差で測定されることが多い。
リスク調整後リターン リターンの絶対額だけでなく、そのリターンを得るためにどれだけのリスクを取ったかを考慮に入れたリターンのこと。
正規分布 統計学で最も広く用いられる確率分布の一つ。平均値を中心に左右対称であり、多くの伝統的金融モデルの前提となっている。
テールリスク (Tail Risk) 確率分布の裾(テール)の部分で発生する、確率は低いが、一度発生すると極めて甚大な損失をもたらすリスク。
CTA (商品投資顧問業者) 主に商品先物や通貨先物などを投資対象とし、トレンドフォロー戦略などを用いるヘッジファンドの一種。リターンが非正規分布を示すことが多い。
参考文献一覧
[1] Sharpe, W. F. (1994). The Sharpe ratio. The Journal of Portfolio Management, 21(1), 49-58.
https://doi.org/10.3905/jpm.1994.409501
[2] Eling, M., & Schuhmacher, F. (2007). Does the choice of performance measure influence the evaluation of hedge funds?. Journal of Banking & Finance, 31(9), 2632-2647.
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.09.015
[3] Getmansky, M., Lo, A. W., & Makarov, I. (2004). An econometric model of serial correlation and illiquidity in hedge fund returns. Journal of Financial Economics, 74(3), 529-609.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.04.001
[4] Chekhlov, A., Uryasev, S., & Zabarankin, M. (2005). Drawdown measure in portfolio optimization. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 8(1), 13-58.
https://doi.org/10.1142/S0219024905002767
[5] Goetzmann, W. N., Ingersoll Jr, J. E., Spiegel, M., & Welch, I. (2007). Portfolio performance manipulation and manipulation-proof performance measures. The Review of Financial Studies, 20(5), 1503-1546.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhm025
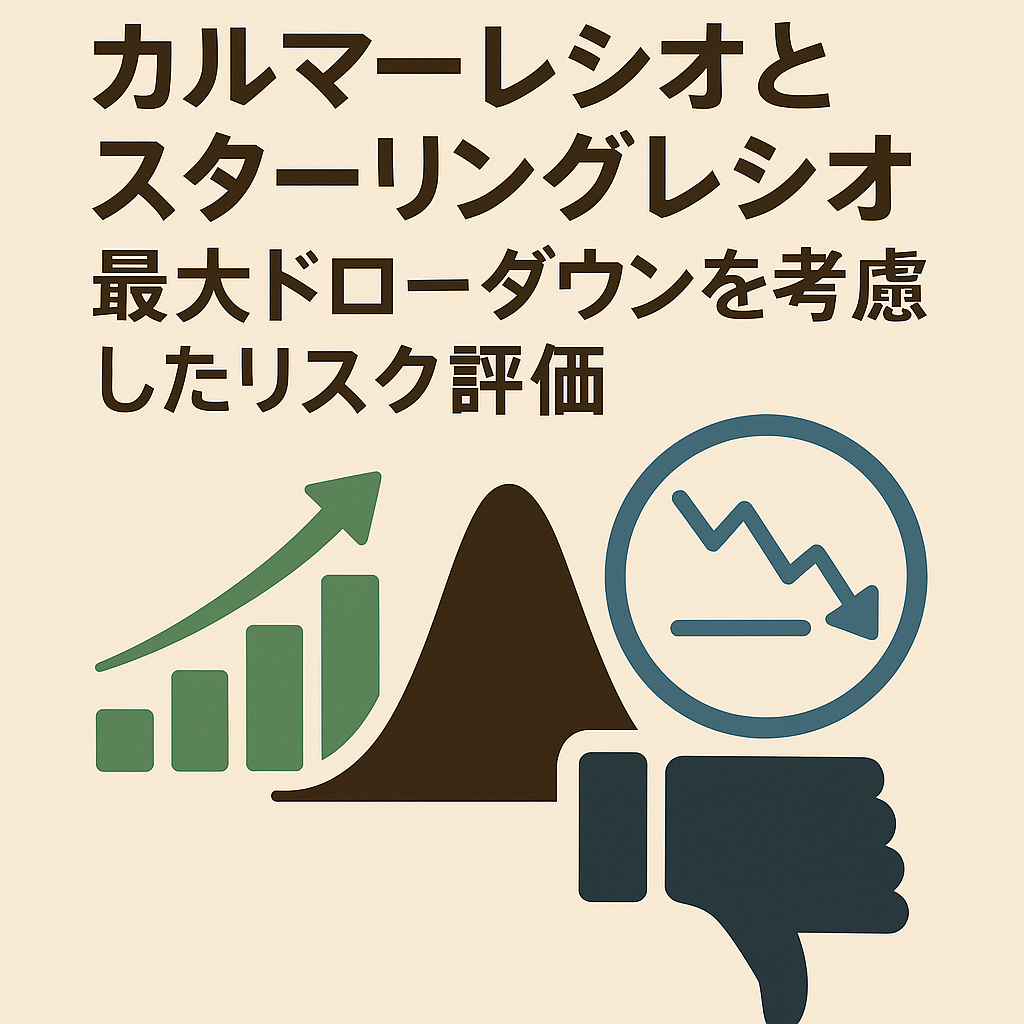
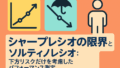
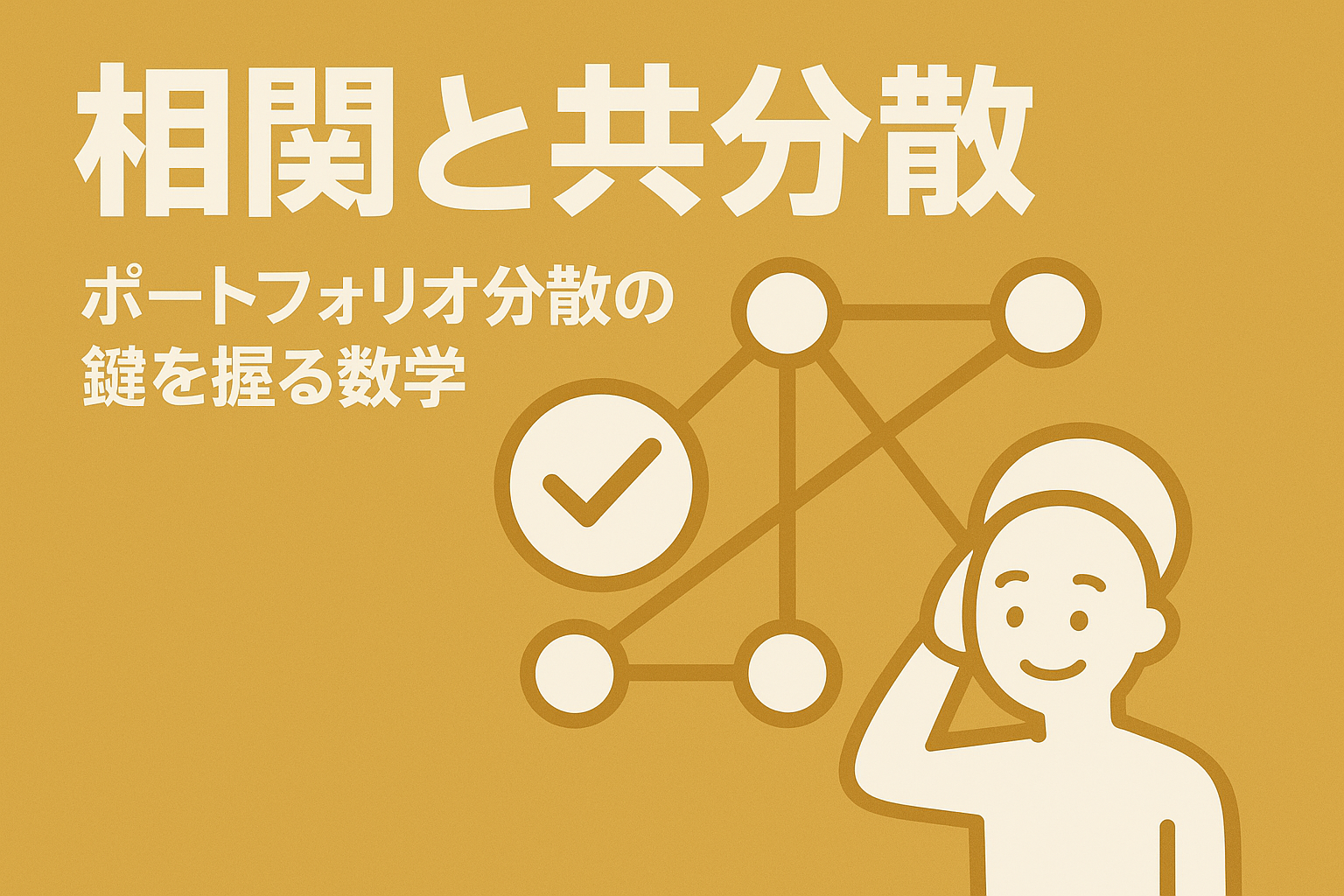
コメント