概論
市場のリスクや不確実性を測る際、私たちは伝統的に「ボラティリティ(標準偏差)」という物差しを用いてきました。しかし、ボラティリティはあくまでリターンの「ばらつきの大きさ」を測る指標であり、市場が持つ不確実性の、より本質的な側面を捉えきれていない可能性があります。もし、市場の「予測のしにくさ」そのものを、直接的に定量化できるとしたらどうでしょうか。
この問いに、全く異なる角度から光を当てたのが、20世紀の科学における金字塔の一つ、情報理論です。そして、その中核をなすのがエントロピーという概念です。
エントロピーは、元々は熱力学の分野で生まれましたが、クロード・シャノンが1948年に発表した歴史的な論文「A Mathematical Theory of Communication」によって、「情報量」、すなわち「ある事象がどれだけ不確実であるか(予測しにくいか)」を測る数学的な尺度として再定義されました [1]。
シャノンのエントロピーは、非常に直感的な概念です。例えば、イカサマが仕込まれ、99%の確率で「表」しか出ないコインがあったとします。このコインの次の結果を予測することは非常に簡単であり、そこから得られる「情報」はほとんどありません。この状態を「エントロピーが低い」と言います。一方で、完全に公正なコインは、表と裏が50%ずつの確率で出ます。次の結果は全く予測できず、不確実性は最大です。この状態を「エントロピーが高い」と言います。
この考え方を金融市場に適用すると、市場の「効率性」を測る新しい物差しが見えてきます。もし市場が完全に予測可能であれば、そのエントロピーはゼロです。逆に、ユージン・ファーマが提唱した効率的市場仮説が主張するように、株価がランダムウォークに従い、完全に予測不可能であるならば、その市場のエントロピーは最大となります [2]。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について:ボラティリティを超えたリスク測定
より一般的な分散投資の尺度として
エントロピーは、ポートフォリオの分散度合いを測る、より一般的で強力な指標となり得ます。伝統的なポートフォリオ理論は、資産間の相関に基づいて分散を考えますが、エントロピーはポートフォリオ全体の「集中の度合い」そのものを直接的に測定します。
フィリッパトスとウィルソンによる1972年の研究は、このエントロピーの概念をポートフォリオ選択に応用した、初期の代表的な試みです [3]。彼らは、ポートフォリオの構成銘柄のウェイトの分布をエントロピーで測ることで、特定の銘柄に資金が集中しすぎていないか、真に分散が効いているかを評価する枠組みを提示しました。
分布の仮定を必要としない頑健性
ボラティリティをリスク指標として用いる際には、しばしばリターンが正規分布に従うという、非現実的な仮定が置かれます。しかし、ブノワ・マンデルブロの研究が示したように、現実の市場リターンは、正規分布よりも遥かに極端な事象が起こりやすい「ファットテール」を持つことが知られています [4]。
エントロピーは、このような特定の確率分布を仮定しない「ノンパラメトリック」な指標です。そのため、ファットテールや歪みを持つ、より現実的なリターン分布の不確実性を、ボラティリティよりも頑健に捉えることができる可能性があります。
収益事例:最大エントロピー・ポートフォリオ
このエントロピーの概念をポートフォリオ構築に直接応用したのが、「最大エントロピー・ポートフォリオ」です。これは、特定の制約の下で、ポートフォリオのエントロピー(不確実性、分散度合い)を最大化するように資産のウェイトを決定する手法です。
ベラとパクによる2008年の研究は、この最大エントロピー原理を用いたポートフォリオが、伝統的な平均分散アプローチ(マーコウィッツ・モデル)と比較して、優れたパフォーマンスを示すことを実証しました [5]。特に、将来の未知のデータに対するパフォーマンス(アウト・オブ・サンプル性能)において、最大エントロピー・ポートフォリオは、より安定した結果を示したと報告されています。
短所、弱み、リスクについて:解釈と推定の難しさ
確率分布の推定という根源的な問題(損失事例)
エントロピーは強力な理論ですが、その計算には、分析対象の「真の確率分布」を知っている必要があります。しかし、現実の金融市場において、将来のリターンの確率分布を、限られた過去のデータから正確に推定することは、極めて困難です。
もし、誤った確率分布を仮定してエントロピーを計算してしまえば、その結果もまた、全く意味のないものになってしまいます。この確率分布の推定誤差という問題は、エントロピーを実用的なトレーディングに応用する上での、最も根本的で、かつ乗り越えることが難しい障壁です。
経済的な解釈の難しさ
エントロピーは、「不確実性」という抽象的な概念を一つの数値で示してくれますが、その数値がなぜ高いのか、あるいは低いのかという経済的な理由を直接的に教えてくれるわけではありません。
例えば、VIX指数であれば、その上昇は「市場参加者の恐怖心の高まり」という、直感的な経済的解釈と結びついています。一方で、市場のエントロピーが上昇したとしても、それが具体的にどのようなリスク(インフレリスク、信用リスクなど)の高まりを反映しているのかを解釈することは、容易ではありません。この解釈の難しさが、エントロピーを実践的なリスク管理指標として使いこなす上での、大きなハードルとなります。
非対称性と摩擦の視点から
エントロピーという概念は、なぜ市場の不確実性を捉える上で強力な視点を提供し、また、その応用にはどのような困難が伴うのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:情報の非対称性とカルバック・ライブラー情報量
エントロピーの概念をさらに発展させると、市場における情報の非対称性そのものを定量化するツールが見えてきます。
市場とは、異なる情報、異なる信念(確率分布)を持つ、無数の参加者の集合体です。あなたがある銘柄は上がると信じ、別の誰かは下がると信じている。この「信念の分布」の差異こそが、取引が成立する根源です。
情報理論には、カルバック・ライブラー情報量(あるいは相対エントロピー)という概念があります。これは、二つの確率分布が、どれだけ異なっているかという「距離」を測るための非対称な尺度です。これを市場に応用すれば、「あるトレーダーの相場観(確率分布P)」が、「市場全体のコンセンサス(確率分布Q)」と、どれだけ異なっているかを測定できます。
この情報の非対称性、すなわち市場コンセンサスとの「信念の乖離」こそが、アルファ(超過リターン)の源泉です。もし、あなたが持つ独自の分析や情報によって、市場コンセンサスよりも精度の高い未来予測(確率分布)を形成できるならば、その乖離の大きさが、あなたのエッジの大きさを示唆します。エントロピーの考え方は、情報の価値とは、それが市場のコンセンサスに対してどれだけの「驚き(Surprisal)」をもたらすか、という非対称な関係性にあることを教えてくれるのです。
Friction:確率分布の「推定」という情報の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、エントロピーを現実のトレーディングに応用する際には、その計算の前提に関わる、より根源的な「摩擦」が存在します。
確率分布の推定という情報の摩擦
エントロピーを計算するためには、その土台となる「真の確率分布」を知っている必要があります [1]。しかし、ここに最大の摩擦が存在します。すなわち、将来のリターンの真の確率分布を、人間が知ることは不可能である、という事実です。
我々にできるのは、ノイズに満ちた限られた過去のデータから、その分布を「推定」することだけです。この推定プロセスには、必ず誤差が伴います。特に、ファットテール [4]に代表されるような、稀にしか起こらない極端な事象の発生確率を、過去のデータから正確に推定することは、統計的に極めて困難です。この「真の分布を知り得ない」という根源的な情報の摩擦が、計算されたエントロピーの信頼性に、常に大きな不確実性の影を落とします。
次元の呪いという計算上の摩擦
もう一つの深刻な摩擦が、「次元の呪い」として知られる、計算上の問題です。
単一の資産のリターン分布を推定するだけでも困難ですが、これが数十、数百の銘柄からなるポートフォリオとなると、その同時確率分布(全ての資産が、どのような組み合わせでリターンを発生させるかの確率)を推定することは、計算量的にほぼ不可能になります。変数の数(次元)が増えるほど、必要なデータ量は指数関数的に増大し、計算は現実的でなくなります。
この技術的な摩擦があるため、最大エントロピー・ポートフォリオのようなアプローチ [5]も、実際には何らかの簡略化された仮定を置かざるを得ません。この摩擦が、理論の美しさと、実践の難しさとの間の大きなギャップを生み出しているのです。
総括
・エントロピーとは、情報理論の父クロード・シャノンによって定式化された、ある事象の「不確実性」や「予測のしにくさ」を測る数学的な尺度です [1]。
・金融市場においては、ボラティリティとは異なる視点からリスクを捉えることができ、ポートフォリオの分散度合いを測る指標 [3]や、ポートフォリオ構築の原理 [5]として応用研究がなされています。
・特定の確率分布(正規分布など)を仮定しないノンパラメトリックな性質を持つため、ファットテール [4]といった市場の現実を、より頑健に捉えられる可能性があります。
・しかし、その計算には「真の確率分布」が必要であり、それを限られた過去のデータから正確に推定することが極めて困難であるという、根源的な弱点を抱えています。
用語集
エントロピー (Entropy) ある確率分布が持つ「不確実性」「無秩序さ」「情報量」を測るための指標。結果が予測しにくいほど、エントロピーは高くなる。
情報量 (Information) ある事象が起こったと知らされた時に得られる「驚き」の大きさ。発生確率が低い事象ほど、情報量は大きい。エントロピーは、情報量の期待値として定義される。
情報理論 (Information Theory) 情報の伝達と処理を数学的にモデル化する理論。クロード・シャノンによって創始された。
確率分布 (Probability Distribution) ある確率変数が、それぞれの値をどれくらいの確率で取るかを示す関数、あるいはグラフ。
正規分布 統計学で最も広く用いられる確率分布の一つ。平均値を中心に左右対称の釣鐘状の形をしている。
ファットテール 確率分布において、平均から大きく離れた極端な事象(テールイベント)が、正規分布の予測よりも高い確率で発生する性質。
ノンパラメトリック 分析を行う際に、データの母集団が特定の確率分布(正規分布など)に従うという仮定を必要としない統計的手法のこと。
ポートフォリオ 投資家が保有する、株式、債券、不動産などの金融資産の組み合わせ、またその一覧。
効率的市場仮説 市場価格は利用可能な全ての情報を即座に織り込んでいるため、継続的に市場を上回ることはできないとする仮説。完全に効率的な市場は、エントロピーが最大となる。
リスク 金融の世界では、一般的にリターンの不確実性やばらつきを指す。ボラティリティ(標準偏差)が代表的な指標。
参考文献一覧
[1] Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423.
https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x
[2] Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x
[3] Philippatos, G. C., & Wilson, C. J. (1972). Entropy, market risk, and the selection of efficient portfolios. Applied Economics, 4(3), 209-220.
https://doi.org/10.1080/00036847200000017
[4] Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. The Journal of Business, 36(4), 394-419.
https://doi.org/10.1086/294632
[5] Bera, A. K., & Park, S. Y. (2008). Optimal portfolio diversification using the maximum entropy principle. Econometric Reviews, 27(4-6), 484-512.
https://doi.org/10.1080/07474930801960394

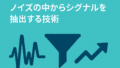
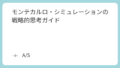
コメント