概論
「ある投資戦略が、将来も有効である確率はどのくらいか?」――この問いに、伝統的な統計学(頻度論)は、「その戦略が有効か無効か、どちらかの仮説を棄却する」という形で間接的にしか答えてくれません。しかし、私たちが本当に知りたいのは、新しいデータ(バックテストの結果など)を得た上で、「で、結局、この戦略が本物である確率は何パーセントなのか?」という、より直接的な信念の度合いではないでしょうか。
この、私たちの主観的な「確信度」を、新しい証拠に基づいて、数学的に、そして合理的に更新していくための強力な思考の枠組みを提供するのが、ベイズ統計学です。
その中核をなすのが、18世紀の数学者であり牧師であったトーマス・ベイズによって発見されたベイズの定理です [1]。この定理は、私たちの信念の更新プロセスを、以下の3つの要素で定式化します。
- 事前確率 (Prior Probability): 新しいデータを得る前の、ある事象に対する私たちの初期の確信度。
- 尤度 (Likelihood): もしその確信度が正しいとした場合に、新しいデータが観測されるもっともらしさ。
- 事後確率 (Posterior Probability): 新しいデータを考慮に入れた後の、更新された確信度。
ベイズ統計学は、この定理を用いて、「事前確率」という私たちの初期の知識や信念を、観測された「データ(尤度)」を通じて、より精緻な「事後確率」へと継続的にアップデートしていくプロセスそのものです。
これは、多くの優れたトレーダーや投資家が、無意識的に行っている思考プロセスと一致します。最初に持っていた相場観(事前確率)を、新しいニュースや値動き(データ)によって、日々刻々と修正していく(事後確率を更新する)。ベイズ統計学は、この学習プロセスを、数学的な規律の下で行うための言語なのです。
この「信念の度合い」を確率として扱うアプローチは、確率を「長期間における試行の頻度」と定義する伝統的な頻度論的統計学とは、根本的に異なる哲学に基づいています。この哲学の違いについては、著名な統計学者であるブラッドリー・エフロンによる2005年の論文などで、その特徴が分かりやすく解説されています [2]。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について:不確実性を飼いならす思考法
パラメータ推定問題への強力な解決策(収益事例)
ベイズ統計学が金融実務で大きな成功を収めた分野の一つが、ポートフォリオ最適化におけるパラメータ推定問題です。
これまでの記事で解説したように、期待リターンなどのパラメータを過去のデータから推定する作業は、極めて大きな誤差を伴います。この問題を解決するために、フィッシャー・ブラックとロバート・リッターマンが1992年に開発したのが、ベイズの定理を応用したブラック・リッターマン・モデルです [3]。
このモデルは、何の根拠もない過去のデータだけに頼るのではなく、まず「市場全体のポートフォリオが効率的である」という、経済学的に見て妥当な事前確率を設定します。その上で、投資家自身の独自の相場観(新しい情報)を加えて、より安定的で、直感に合った事後確率としてのポートフォリオを算出します。これは、ベイズ統計学が、理論と現実、そして主観と客観を統合するための強力なツールであることを示す代表例です。
モデル比較への応用
ベイズ統計学は、どちらのモデルがより「正しい」かを、確率的に評価するための直感的な枠組みを提供します。伝統的な仮説検定が「あるモデル(帰無仮説)を棄却できるか」しか答えられないのに対し、ベイズ的アプローチでは、「データを見た後で、モデルAが正しい確率はX%、モデルBが正しい確率はY%」といった、より直接的な比較が可能になります。
パストールとスタンバーによる2000年の研究は、このベイズ的アプローチを用いて、CAPMやファーマ=フレンチ3ファクターモデルといった、競合する資産価格モデルの優劣を比較評価しました [4]。
短所、弱み、リスクについて:「神の視点」と主観性の罠
「事前確率」の主観性という根源的な問題(損失事例)
ベイズ統計学に対する最も根源的で、かつ強力な批判が、事前確率を誰が、どのように決めるのか、という問題です。
ベイズの定理から導かれる事後確率は、入力として与えられた事前確率に大きく依存します。もし、分析者が用いた事前確率が、その人の強い偏見や誤った信念に基づいていた場合、たとえ客観的なデータを用いて更新したとしても、導き出される事後確率は、大きく歪んだものになってしまいます。この「主観性」こそが、ベイズ統計学の最大の強みであると同時に、その信頼性を揺るがしかねないアキレス腱でもあるのです。ジェイ・シャンケンによる1987年の研究も、資産価格モデルの検証にベイズ的アプローチを適用する際の、事前確率設定の難しさを論じています [5]。
計算の複雑性
ベイズ統計学の実践は、しばしば膨大な計算量を要求します。特に、複雑なモデルの事後確率分布を解析的に求めることは不可能であり、マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)のような、高度なシミュレーション手法が必要となります。この計算上の複雑性が、ベイズ統計学を、一部の専門家しか扱えない難解なツールにしてしまっている側面は否定できません。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、ベイズ統計学はこれほどまでに強力な理論でありながら、伝統的な頻度論的統計学を完全に置き換えるには至っていないのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:信念の「更新」という非対称なプロセス
ベイズ統計学の思考プロセスの核心には、「学習」という本質的に非対称なプロセスが存在します。
ベイズの定理が示すのは、「過去(事前確率)」が「現在(新しいデータ)」によって一方的に更新され、「未来(事後確率)」の信念を形成するという、時間の流れに沿った非対称な情報の流れです。これは、過去のデータセットをそれぞれ独立したものとして扱い、事前情報という概念を公式には持たない伝統的な頻度論的統計学との、根本的な違いです [2]。
また、この更新プロセス自体も非対称です。私たちの当初の信念(事前確率)を強く裏付けるデータが得られた場合、確信度は少し強まるだけです。しかし、当初の信念とは全く相容れない、極めてサプライズの大きいデータが得られた場合、私たちの信念(事後確率)は劇的に変化します。この、予期せぬ情報に対する非対称な反応性こそが、ベイズ的学習プロセスのダイナミズムであり、市場が時に見せるパラダイムシフトを理解する上での鍵となります。
このアノマリーにおける収益機会とは、市場の大多数が古い情報(過去の常識)に固執している中で、新しい情報に基づいて、誰よりも早く、そして合理的に自らの信念を更新していく、規律あるベイジアンとして行動することで生まれるのです。
Friction:「事前確率」の決定という主観性の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、ベイズ統計学の実践には、その哲学の根幹に関わる、より深刻な「摩擦」が存在します。
主観性という根源的な摩擦
ベイズ統計学に対する最も古く、そして最も根源的な批判が、その「主観性」です。
ベイズの定理が導き出す結論(事後確率)は、計算の出発点となる事前確率の選び方に、決定的に依存します。しかし、その肝心な事前確率を、一体誰が、どのようにして決めれば良いのでしょうか。もし、分析者が強い偏見や希望的観測に基づいて事前確率を設定してしまえば、どんなに客観的なデータを投入したとしても、最終的な結論は、その偏見を追認するだけの「結論ありき」のものになってしまいます。
この「事前確率の主観性」という摩擦が、ベイズ統計学の結果の客観性や再現性に、常に疑問符を投げかける原因となっています [5]。
計算コストという技術的摩擦
ベイズ統計学を現実の問題に応用しようとすると、しばしば膨大な計算量という技術的な摩擦に直面します。
ブラック・リッターマン・モデルのような応用例もありますが [3]、少しでも複雑なモデルになると、ベイズの定理が要求する計算(特に、事後確率分布の計算)は、解析的に解くことが不可能になります。そのため、研究者や実務家は、マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)に代表される、コンピュータによる高度なシミュレーション技術に頼らざるを得ません。この技術的な参入障壁の高さが、ベイズ統計学が、一部の専門家のための難解なツールというイメージから、なかなか脱却できない一因となっているのです。
総括
・ベイズ統計学は、私たちの初期の信念(事前確率)を、新しいデータ(尤度)に基づいて、合理的に更新し、新しい信念(事後確率)を形成するための、数学的な枠組みです [1]。
・その最大の強みは、人間の学習プロセスと親和性が高く、特に金融市場におけるパラメータの不確実性といった問題を、より現実的に扱うことができる点にあります。ブラック・リッターマン・モデルはその代表的な成功例です [3]。
・伝統的な統計学(頻度論)とは異なり、複数のモデルの「どちらがより尤もらしいか」を確率的に比較できるなど、直感的な結論を導きやすいという利点もあります [4]。
・一方で、その結論は計算の出発点となる「事前確率」の選び方に大きく依存するという主観性の問題を常に抱えており、これが最大の弱点かつ論争の的となっています [2, 5]。
用語集
ベイズ統計学 (Bayesian Statistics) 確率を「信念の度合い」と解釈し、新しいデータを得ることで、その信念(確率)を更新していくという考え方に基づく統計学の一派。
ベイズの定理 (Bayes’ Theorem) 事前確率と尤度から、事後確率を計算するための数学的な定理。ベイズ統計学の根幹をなす。
事前確率 (Prior Probability) 新しいデータや証拠を観測する前に、ある事象に対して持っている主観的な確信度。
事後確率 (Posterior Probability) 新しいデータや証拠を観測した後に、ベイズの定理を用いて更新された、より精緻な確信度。
尤度 (Likelihood) ある仮説(モデルやパラメータ)が正しいとした場合に、観測されたデータがどれだけ「もっともらしい」かを示す尺度。
頻度論的統計学 (Frequentist Statistics) 確率を「ある試行を無限に繰り返した際の、特定の事象が起こる頻度」と解釈する、伝統的な統計学の一派。p値や信頼区間といった概念は、この考え方に基づく。
期待効用理論 人々は金額の期待値を最大化するのではなく、その金額から得られる「効用(満足度)」の期待値を最大化するように行動するという理論。
プロスペクト理論 期待効用理論さえも成り立たない、現実の人間の非合理的な意思決定を説明する理論。
ブラック・リッターマン・モデル ベイズ統計学の考え方を応用し、市場の均衡リターン(事前確率)と、投資家自身の独自の相場観を組み合わせることで、より安定的なポートフォリオを構築するモデル。
パラメータ (Parameter) 数理モデルの挙動を決定する、母数や係数のこと。期待リターン、ボラティリティ、相関などが含まれる。
参考文献一覧
[1] Bayes, T. (1763). An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 53, 370-418.
https://doi.org/10.1098/rstl.1763.0053
[2] Efron, B. (2005). Bayesians, frequentists, and scientists. Journal of the American Statistical Association, 100(469), 1-5.
https://doi.org/10.1198/016214505000000033
[3] Black, F., & Litterman, R. (1992). Global portfolio optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43.
https://doi.org/10.2469/faj.v48.n5.28
[4] Pástor, Ľ., & Stambaugh, R. F. (2000). Comparing asset pricing models. The Journal of Finance, 55(2), 527-573.
https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00044-1
[5] Shanken, J. (1987). A Bayesian approach to testing portfolio efficiency. Journal of Financial Economics, 19(2), 195-215.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(87)90002-X
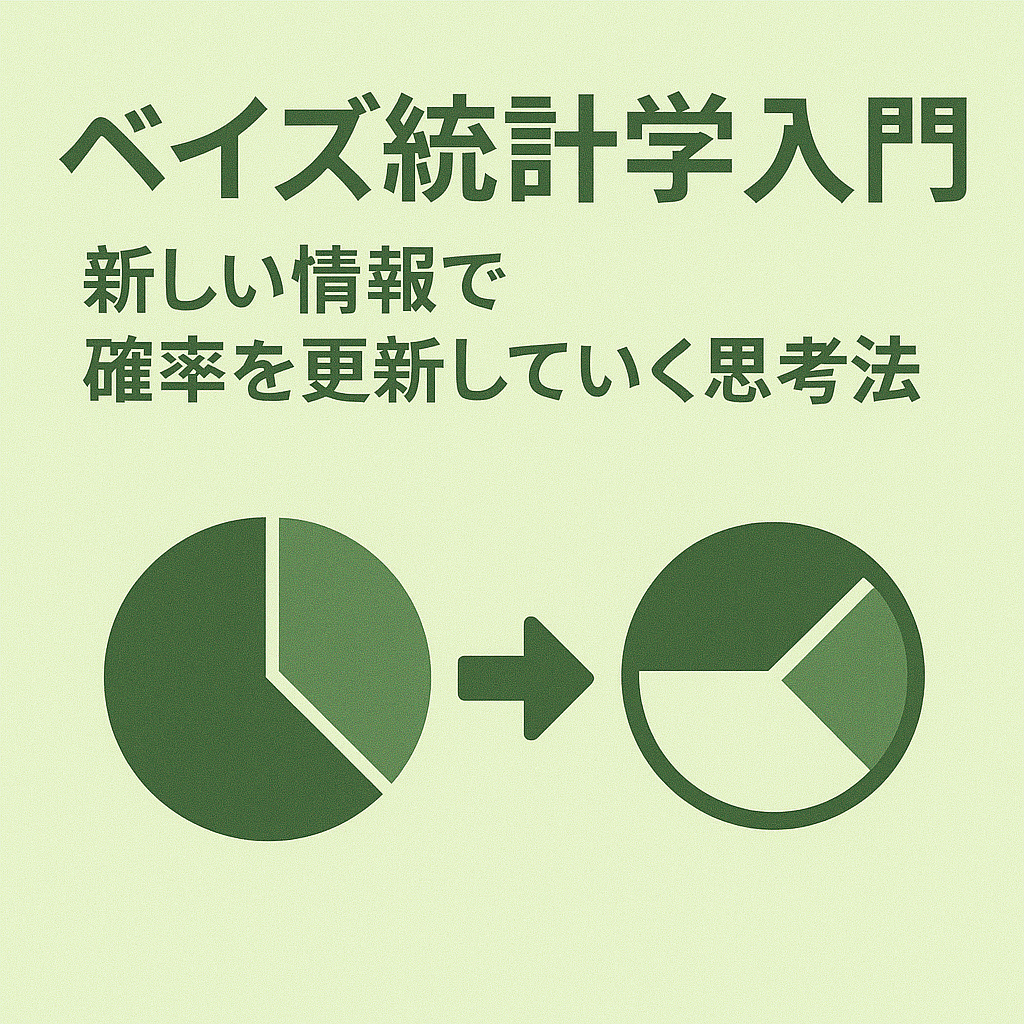

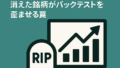
コメント