概論
ある投資戦略が、もう一つの戦略よりも「優れている」とは、どういうことでしょうか。単にリターンが高ければ良いのでしょうか、それともリスクが低ければ良いのでしょうか。この「リスクに見合ったリターン」を測るための、最も普遍的で強力な物差しが、ノーベル経済学賞受賞者であるウィリアム・シャープによって1966年に提唱されたシャープレシオです [1]。
シャープレシオは、ある資産のリターンから無リスク資産のリターンを差し引いた「超過リターン」を、そのリターンの「標準偏差(ボラティリティ)」で割ることで計算されます。これは直感的に、「取ったリスク1単位あたり、どれだけのリターンを得られたか」を示す、投資の「効率性」を測る指標です。この分かりやすさと汎用性から、シャープレシオは長年にわたり、学術界と実務界の両方で、パフォーマンス測定のゴールドスタンダードとして君臨してきました。
しかし、この万能に見える指標には、ある重大な、そしてしばしば誤解を招く「死角」が存在します。それは、リスクの測定に標準偏差を用いている点です。
標準偏差は、リターンの平均からのばらつきを測る指標ですが、リターンが平均を上回る方向への大きなばらつき(ポジティブなサプライズ)も、下回る方向への大きなばらつき(ネガティブなサプライズ)も、全く同じように「リスク」として扱ってしまうのです。
しかし、投資家にとって、リターンが想定以上に跳ね上がることは喜ばしいことであり、真に避けたいのは想定外の損失、すなわち下方リスク(ダウンサイド・リスク)のはずです。このシャープレシオが内包する矛盾と、その矛盾を克服するために生まれたソルティノレシオについて、学術的な背景と共に深掘りしていきます。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
短所、弱み、リスクについて:シャープレシオの限界
シャープレシオは、リターンの分布が正規分布のように左右対称である場合には、非常に有効な指標です。しかし、現実の投資戦略、特に優れたエッジを持つ戦略のリターンは、しばしば非対称な分布を描きます。このような場合に、シャープレシオは誤った結論を導く危険性があります。
非対称なリターン分布への不適合
例えば、稀に大きな利益を生む「宝くじ」的な性質を持つ戦略を考えてみましょう。このような戦略は、リターン分布が右側に長く伸びた「正の歪度」を持つことになります。
クラウスとリッツェンバーガーによる1976年の研究が示すように、投資家は一般的に、このような正の歪度を好む傾向があります [2]。しかし、シャープレシオは、この好ましいはずの巨大な上方へのばらつきを「リスク」として計算に含めてしまうため、戦略の魅力を過小評価してしまうのです。
損失回避という人間の本質との乖離
シャープレシオが上方と下方のばらつきを対称に扱うことは、人間の心理的な本質とも乖離しています。ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーのプロスペクト理論が明らかにしたように、人間は利益を得る喜びよりも、同額の損失を被る苦痛を2倍以上強く感じる「損失回避」という強いバイアスを持っています [3]。
投資家が真に恐れているのは、ボラティリティそのものではなく、「損失」です。この心理的な現実を、シャープレシオは全く考慮していません。
戦略の誤ったランク付け(損失事例)
この欠点は、実践において、より優れた戦略を誤って棄却してしまうという深刻な問題を引き起こします。イスラエルセンによる2005年の研究でも、シャープレシオが非正規分布のリターンを持つ戦略の評価には不向きであることが論じられています [4]。
例えば、以下の二つの戦略を比較してみましょう。
- 戦略A:毎月安定的に+1%のリターンを上げる。
- 戦略B:11ヶ月間は0%のリターンだが、1年に一度だけ+12%の大きなリターンを上げる。
この二つの戦略の年平均リターンは同じですが、戦略Bはリターンのばらつきが大きいため、シャープレシオは戦略Aよりも著しく低くなります。しかし、多くの投資家にとって、損失を出さずに大きなアップサイドを持つ戦略Bは、決して劣った戦略ではないはずです。シャープレシオは、このような戦略の真の価値を捉えきれないのです。
長所、強み、有用な点について:ソルティノレシオによる改善
シャープレシオが抱えるこれらの問題を克服するために、下方リスクのみに着目したパフォーマンス指標が開発されました。その代表がソルティノレシオです。
下方リスクの測定
ソルティノレシオは、フランク・ソルティノらによって1990年代初頭に提唱された概念で、シャープレシオの計算式における分母を、標準偏差から下方偏差(ダウンサイド・ディビエーション)に置き換えたものです [5]。
下方偏差とは、リターンが投資家が設定した「最低目標収益率(MAR)」を下回った場合(つまり、損失または期待外れの結果となった場合)のばらつきだけを測定したものです。MARを上回った好ましいリターン(上方へのばらつき)は、計算上完全に無視されます。
より直感的なパフォーマンス評価(収益事例)
この修正により、ソルティノレシオは、投資家の実感により近い、直感的なパフォーマンス評価を可能にします。先ほどの戦略Aと戦略Bの例で言えば、両者ともMAR(例えば0%)を下回るリターンは一度も出していないため、その下方偏差はゼロに近い値となります。結果として、戦略Bのソルティノレシオは、シャープレシオとは異なり、非常に高い値を示し、その「損失を出さずに大きな利益を狙える」という優れた特性を正しく評価することができるのです。
特に、リターン分布が負の歪度を持つ(稀に大きな損失を出す)オプションの売り戦略や、正の歪度を持つ(稀に大きな利益を出す)トレンドフォロー戦略などのパフォーマンスを評価する際には、シャープレシオよりもソルティノレシオの方が、そのリスク・リターンの実態を遥かに正確に映し出すことができます。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、シャープレシオという不完全な指標が長年にわたり使われ続け、ソルティノレシオのような、より直感的な指標がそれを完全に置き換えるに至っていないのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:上方リスクと下方リスクの「非対称性」
このテーマの核心は、リターンがもたらす価値の「非対称性」と、それを評価する尺度の非対称性にあります。
投資家にとって、リターン分布の上方へのばらつき(アップサイド・ボラティリティ)と、下方へのばらつき(ダウンサイド・ボラティリティ)が持つ意味は、全く異なります。前者は歓迎すべき「幸運」であり、後者は避けるべき「危険」です。この上方リスクと下方リスクの価値における、構造的な非対称性こそが、全ての投資判断の根底に流れています。
シャープレシオは、標準偏差を用いることで、この二つを区別なく「リスク」として扱い、対称的な尺度で非対称な現実を測ろうとします。その結果、好ましいはずのアップサイド・ボラティリティを持つ戦略を、不当に低く評価してしまうという歪みを生み出します。
一方で、ソルティノレシオは、下方偏差を用いることで、下方リスクのみを測定します。これは、非対称な現実を、非対称な尺度で評価する試みです。この尺度の非対称性こそが、プロスペクト理論が示すような、損失を極端に嫌う人間の心理的非対称性 [3]と合致し、より投資家の実感に近いパフォーマンス評価を可能にするのです。このアノマリーにおける収益機会とは、シャープレシオという対称的な物差しによって見過ごされている、非対称なリターン分布を持つ優れた戦略の真の価値を、ソルティノレシオという非対称な物差しで見つけ出すことにあります。
Friction:思考の「慣性」という認知的摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、シャープレシオが依然として広く使われ続けている背景には、人間の思考や組織の慣性に根差した、強力な「摩擦」が存在します。
思考の慣性という認知的摩擦
シャープレシオは、半世紀以上にわたって金融教育の基礎として教えられ、業界の標準として使われ続けてきました。その結果、多くの投資家や実務家の思考様式に深く根付いています。新しい概念であるソルティノレシオや下方偏差を理解し、計算するためには、この長年の「思考の慣性」を乗り越える必要があります。
下方偏差の計算は、標準偏差の計算よりも僅かに複雑です。この僅かな複雑さが、多くの人々が、欠点を認識しつつも、使い慣れたシャープレシオに固執させる認知的な摩擦として機能します。
業界標準という制度的摩擦
大手評価機関や金融情報データベースは、そのシステムの根幹にシャープレシオを組み込み、何十年分ものデータを蓄積しています。全てのファンドや戦略を、シャープレシオという統一された基準で比較できることは、業界全体にとって大きな利便性をもたらしてきました。
もし、業界の標準をソルティノレシオに移行しようとすれば、これらの巨大な既存システムを根本から改修する必要があり、過去のデータとの比較可能性も失われてしまいます。この莫大な「スイッチング・コスト」が、より優れた指標への移行を妨げる、極めて強力な制度的摩擦となっているのです。その結果、多くの投資家は、非対称なリターンを持つ戦略を評価する際に、不適切な物差しを使い続けることを余儀なくされています。
総括
・シャープレシオは、リスク調整後リターンを測るための業界標準ですが、リスクを標準偏差で測定するため、好ましい上方へのばらつきも「リスク」としてペナルティを課してしまうという重大な欠陥を持っています [1]。
・この欠陥は、リターン分布が非対称な(歪度を持つ)戦略を評価する際に、特に大きな問題となります [2, 4]。
・ソルティノレシオは、リスクを「下方偏差」(目標を下回ったリターンのみのばらつき)で測定することで、この問題を解決し、損失回避といった投資家の心理 [3]にも合致した、より直感的なパフォーマンス評価を可能にします [5]。
・シャープレシオが依然として広く使われている背景には、長年の慣習という認知的な摩擦と、業界標準という制度的な摩擦が存在します。
用語集
シャープレシオ (Sharpe Ratio) 超過リターンを、リターンの標準偏差(トータル・リスク)で割ることで算出される、リスク調整後のパフォーマンス指標。
ソルティノレシオ (Sortino Ratio) 超過リターンを、リターンの下方偏差(ダウンサイド・リスク)で割ることで算出される、リスク調整後のパフォーマンス指標。シャープレシオの改良版。
リスク調整後リターン リターンの絶対額だけでなく、そのリターンを得るためにどれだけのリスクを取ったかを考慮に入れたリターンのこと。
標準偏差 (Standard Deviation) データのばらつきの大きさを測る最も一般的な統計的指標。リターンの標準偏差はボラティリティとも呼ばれる。
下方偏差 (Downside Deviation) リターンが、予め定めた最低目標収益率(MAR)を下回った場合のみを対象として計算される、下方へのばらつきの大きさを示す指標。
正規分布 統計学で最も広く用いられる確率分布の一つ。平均値を中心に左右対称であり、シャープレシオが最も有効に機能する前提となる。
歪度 (Skewness) 確率分布の非対称性を示す統計的な指標。歪度を持つ分布の評価において、シャープレシオの限界が露呈する。
プロスペクト理論 不確実性のある状況下での人間の意思決定を説明する理論。損失回避という概念は、下方リスクを重視するソルティノレシオの理論的支柱となる。
損失回避 (Loss Aversion) 同じ金額であれば、利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛の方を精神的に重く受け止めてしまうという人間の心理的傾向。
無リスク資産 (Risk-Free Asset) 元本が保証されており、リスクがゼロと見なされる資産。通常は、短期国債などが代理として用いられる。シャープレシオの計算で超過リターンを求める際に基準となる。
参考文献一覧
[1] Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. The Journal of Business, 39(1), 119-138.
https://doi.org/10.1086/294846
[2] Kraus, A., & Litzenberger, R. H. (1976). Skewness preference and the valuation of risk assets. The Journal of Finance, 31(4), 1085-1100.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1976.tb01961.x
[3] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
https://doi.org/10.2307/1914185
[4] Israelsen, C. L. (2005). A refinement to the Sharpe ratio and information ratio. Journal of Asset Management, 5(6), 423-427.
https://doi.org/10.1057/palgrave.jam.2240158
[5] Sortino, F. A., & van der Meer, R. (1991). Downside risk. The Journal of Portfolio Management, 17(4), 27-31.
https://doi.org/10.3905/jpm.1991.409343
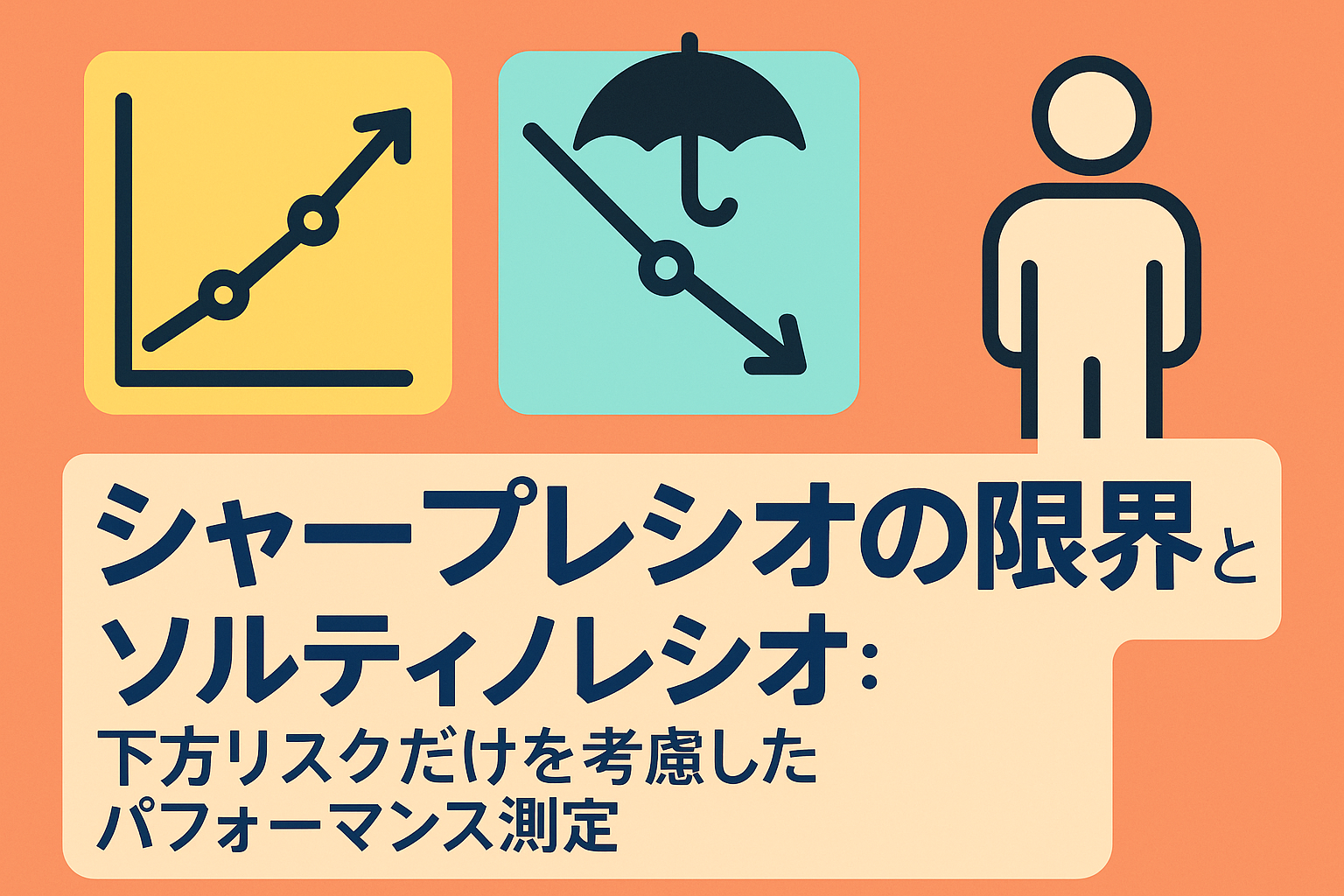
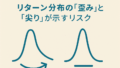
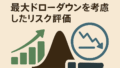
コメント