概論:未来を映す不完全な水晶玉
インプライド・ボラティリティ(Implied Volatility, IV)は、金融市場、特にデリバティブの世界において、未来を読み解くための最も重要な指標の一つです。多くの金融指標が過去の実績を分析する「バックミラー」であるのに対し、インプライド・ボラティリティは市場参加者が将来の価格変動をどのように見ているかを示す「フロントガラス」の役割を果たします。
その本質は、単なる将来予測ではありません。インプライド・ボラティリティとは、現在市場で取引されているオプションの価格を、ある標準的な理論モデルに当てはめた場合に、その価格を数学的に説明できる唯一の変数です。言い換えれば、それは市場参加者の総意によって形成された、将来の不確実性に対する「現在の価格」そのものなのです 。
この概念の理論的な起源は、1973年にフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズが発表した、ノーベル経済学賞の受賞理由ともなった画期的なオプション価格決定モデルに遡ります 。このブラック=ショールズ・モデルは、無裁定の原理に基づき、オプションの理論価格を決定する数式を導き出しました。この数式において、原資産価格、権利行使価格、満期までの期間、金利といった変数はすべて市場で観測可能ですが、唯一「ボラティリティ」だけは未知数です。そこで、市場で実際に成立しているオプションの価格をこの数式に代入し、逆算することで、市場が暗黙のうちに織り込んでいるボラティリティ、すなわちインプライド・ボラティリティが求められます 。
しかし、このエレガントな理論には、現実との間に大きな隔たりを生む、ある致命的な仮定が存在します。それは、「原資産のボラティリティは、オプションの満期まで一定である」というものです 。現実の市場のボラティリティが常に変動していることは自明であり、この理論上の仮定と現実とのギャップこそが、インプライド・ボラティリティという指標を読み解く上で最も興味深く、また収益機会の源泉となる数々の現象を生み出しています。
このインプライド・ボラティリティという抽象的な概念を、最も実用的かつ広く知られた形にしたのが、シカゴ・オプション取引所(CBOE)が算出するVIX指数、通称「恐怖指数」です 。VIX指数は、米国の主要株価指数であるS&P 500の多種多様なオプション価格を合成することで、市場全体の今後30日間の期待変動率を指数化したものです。その計算方法は、特定の価格モデルに依存しない「モデルフリー」なアプローチを採用しており、市場参加者の集合的な心理状態、特に「恐怖」や「不確実性」を映す鏡として、世界中の投資家から注視されています 。
インプライドボラティリティの計算方法:市場コンセンサスの抽出プロセス
インプライドボラティリティは、将来の原資産価格の変動に関する市場参加者の総意、すなわち「市場のコンセンサス」を反映した指標です。しかし、この数値は直接観測できるものではなく、実際に市場で取引されているオプションの価格から「逆算」して求められます。ここでは、その計算の理論的背景と、その本質的な意味について解説します。
理論的背景:ブラック・ショールズモデルからの逆算
インプライドボラティリティの計算は、1973年に発表されたブラック・ショールズモデル(Black-Scholes Model)を基礎としています。このモデルは、特定の条件下でオプションの理論価格を算出するための数式であり、現代金融工学の礎とされています。
ブラック・ショールズモデルにおけるコールオプションの価格 C は、以下の式で表されます。
C = S₀ * N(d₁) – K * e^(-rT) * N(d₂)
ここで、 d₁ = [ln(S₀/K) + (r + σ²/2)T] / (σ√T) d₂ = d₁ – σ√T
この数式に含まれる各変数は以下の通りです。
- C: コールオプションの理論価格
- S₀: 現在の原資産価格(株価など)
- K: オプションの権利行使価格
- T: 満期までの期間
- r: 無リスク金利
- σ: ボラティリティ(価格変動率)
- N(): 標準正規分布の累積分布関数
インプライドボラティリティを求める際、私たちは市場で実際に取引されているオプションの価格、つまり C が既に分かっています。同様に、現在の株価 S₀、権利行使価格 K、満期までの期間 T、そして無リスク金利 r も市場から観測できる既知の値です。
つまり、インプライドボラティリティの計算とは、この方程式において唯一の未知数である σ(ボラティリティ) を、実際のオプション価格 C に合致するように逆算して求める作業に他なりません。
数値計算による探求:なぜ解析的に解けないのか
ブラック・ショールズモデルの数式を見ると、σ は非常に複雑な形で式の中に組み込まれています。そのため、「σ = …」という形に式を変形して直接解を求めること(解析的に解くこと)はできません。
そこで、コンピュータを用いて反復計算を行い、理論価格が市場価格と一致するようなσの値を近似的に見つけ出します。この計算には、ニュートン法や二分法といった数値解析の手法が用いられます。具体的には、まずσの値を仮定して理論価格を計算し、それが市場価格より高ければσの仮定値を下げ、低ければ上げるといったプロセスを、誤差が許容範囲内に収まるまで繰り返すことで、最適なσの値、すなわちインプライドボラティリティを導出します。
【解説】計算の本質:「将来の予想変動率」を市場価格から読み解く
ここまでの説明は数理的に複雑ですが、その本質を掴むことは難しくありません。インプライドボラティリティの計算を、より直感的に理解してみましょう。
これを「パンの値段」に例えることができます。パンの値段(オプション価格)は、小麦の値段(原資産価格)、作るのにかかる時間(満期までの期間)、パンを焼くオーブンの温度(金利)といった様々な要因で決まります。
しかし、それだけではありません。パンの値段には、「この先、小麦が不作になるかもしれない」とか「新しいベーカリーができて競争が激しくなるかもしれない」といった、将来の不確実性に対する人々の『予想』や『不安』も織り込まれています。
インプライドボラティリティの計算とは、このパンの値段から、材料費などの確定的な要素をすべて差し引いて、最終的に残った「人々の『予想』や『不安』の大きさ(インプライドボラティリティ)」を抽出する作業に似ています。
つまり、私たちは複雑な数式を使って何かを「計算」しているというよりは、市場価格という事実の中から、そこに織り込まれている「市場参加者の将来に対する共通見解」を「読み解いている」のです。この数値が高いということは、市場参加者が今後、価格が大きく動く可能性が高いと見込んでいることを意味します。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所:市場心理の可視化とリスク管理への応用
インプライド・ボラティリティの最大の強みは、ブラック=ショールズ・モデルという理論的な理想からの「逸脱」そのものに、市場のより深い情報が含まれている点にあります。
もしブラック=ショールズ・モデルの仮定が正しければ、同じ原資産、同じ満期日を持つ全てのオプション(権利行使価格が異なっていても)から逆算されるインプライド・ボラティリティは、全て同じ値になるはずです。しかし、現実の市場ではそうはなりません。横軸に権利行使価格、縦軸にインプライド・ボラティリティを取ってプロットすると、グラフは直線ではなく、歪んだ曲線を描きます。これが「ボラティリティ・スマイル」または「ボラティリティ・スキュー」として知られる現象です 。
特に、1987年のブラックマンデー以降の株式指数オプション市場では、権利行使価格が低い(すなわち、市場の暴落に備える)アウト・オブ・ザ・マネーのプットオプションのインプライド・ボラティリティが、アット・ザ・マネーやアウト・オブ・ザ・マネーのコールオプションのそれよりも体系的に高くなる、左に歪んだ「スキュー(skew)」または「スマーク(smirk)」と呼ばれる形状が常態化しています 。
このスキューの存在は、市場参加者が株価の緩やかな上昇よりも、突発的な急落(テールリスク)をはるかに強く警戒していることの直接的な証拠です。彼らは、その恐怖に対する「保険」として機能するプットオプションに対し、理論値よりも高い保険料を支払うことを厭わないのです。このインプライド・ボラティリティの構造を分析することで、単一の数値では捉えきれない、市場が織り込む将来のリターン分布の非対称性(歪度)や極端な事象の発生確率(尖度)といった、より詳細なリスク情報を読み解くことが可能になります。バクシ、カパディア、マダンによる2003年の研究は、様々な権利行使価格のオプション価格を組み合わせることで、これらのリスク中立確率分布の高次モーメントをモデルに依存せずに抽出する汎用的な手法を提示し、インプライド・ボラティリティが持つ情報価値を飛躍的に高めました 。
収益事例:ボラティリティ・リスクプレミアムという「エッジ」
インプライド・ボラティリティが提供する最も体系的な収益機会の一つが、「ボラティリティ・リスクプレミアム(Volatility Risk Premium, VRP)」の存在です。これは、オプション価格から算出されるインプライド・ボラティリティが、その後の期間で実際に観測されるヒストリカルなボラティリティ(実現ボラティリティ)を、長期間にわたって平均的に上回り続けるというアノマリーです 。
この現象は、投資家が将来の不確実性に対する保険(オプション)に対して、統計的に公正な価格以上の保険料を支払う傾向があることを意味します。この体系的な価格の歪み、すなわちVRPを収益源とする代表的な戦略が、プットオプションの売り(プット・ライティング)です。プットオプションを売ることは、市場参加者にダウンサイドリスクに対する保険を提供し、その対価としてプレミアムを受け取る行為に他なりません。
理論的にも、コヴァルとシャムウェイによる2001年の研究は、いくつかの穏当な仮定の下で、プットオプションの期待リターンはリスクフリーレートを下回るべき(つまり、売り手にとって期待値がプラスであるべき)ことを示唆しています 。この理論は、現実のデータによっても裏付けられています。例えば、CBOEが算出するS&P 500のキャッシュ・セキュアード・プットライト戦略のパフォーマンスを示すPUT指数は、1986年からの長期データにおいて、S&P 500指数とほぼ同等のリターンを、著しく低いボラティリティ(リスク)で達成してきたことが報告されています 。
短所と損失事例:「テールリスク」という致命的弱点
しかし、VRPの収穫は決して「フリーランチ」ではありません。オプション売り戦略には、その収益構造に起因する致命的な弱点が内包されています。それは、損益プロファイルの極端な非対称性、すなわち「テールリスク」です 。
この戦略は、市場が平穏な、あるいは緩やかに上昇する期間においては、受け取ったプレミアムが着実に利益として積み重なっていきます。これは「コツコツ」と利益を稼ぐフェーズです。しかし、ひとたび2008年の世界金融危機のような市場の暴落が発生すると、状況は一変します。売却したプットオプションの価値は、原資産価格の下落とインプライド・ボラティリティの急騰という二重の打撃によって天文学的に上昇し、売り手は一夜にして数年分の利益を失うか、それ以上の壊滅的な損失(ドカン)を被る可能性があります 。
この「頻繁な小さな利益」と「稀な巨大な損失」という損益構造は、オプション売り戦略が本質的に、市場の安定性に賭け、市場のテールリスクを引き受ける行為であることを意味します。したがって、VRPから得られるリターンは、単なる市場の非効率性から生まれるアルファではなく、この引き受けたテールリスクに対するリスクプレミアムである、という解釈が一般的です。このリスクを理解せずにVRPを追求することは、極めて危険な行為と言えるでしょう。
非対称性と摩擦の視点
なぜインプライド・ボラティリティの世界には、VRPやボラティリティ・スキューといった、理論からの体系的な逸脱が存在し続けるのでしょうか。その本質は、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」という二つのレンズを通して解き明かすことができます。「非対称性」が収益機会の源泉を生み出し、「摩擦」がその機会が完全に消滅することを防いでいるのです。
Asymmetry:収益機会の源泉としての「非対称な恐怖」
インプライド・ボラティリティにまつわるアノマリーの根源には、人間の心理に深く根差した「非対称性」が存在します。
市場参加者は、株価が10%上昇する喜びよりも、10%下落する苦痛をはるかに強く感じる傾向があります。この「損失回避性向」として知られる心理的な非対称性が、ポートフォリオの価値が急落することから身を守るための「保険」に対する、構造的で根強い需要を生み出します。金融市場におけるこの保険とは、まさにプットオプションに他なりません。株価上昇の利益を狙うコールオプションへの需要と比較して、下落に備えるプットオプションへの需要は、本質的に非対称な形で大きくなるのです。
この非対称な需要構造を決定的にしたのが、1987年のブラックマンデーであると、マーク・ルビンシュタインは1994年の論文で指摘しています 。この歴史的な暴落を経験して以降、市場には「クラッシュ恐怖症(Crash-o-phobia)」とも言うべき集団心理が定着しました 。これは、発生確率は極めて低いものの、一度起これば再起不能なほどの損失をもたらす市場の暴落、すなわちテールリスクを、投資家がその統計的な発生確率以上に過大評価してしまう傾向を指します 。この非対称な恐怖こそが、テールリスクを直接的にヘッジするアウト・オブ・ザ・マネーのプットオプションに持続的な需要プレミアムを生み出し、ボラティリティ・スキューという歪んだ価格体系を形成する主要因となっています。
さらに、市場全体のセンチメントも、この非対称性を増幅させます。ビーョン・ハンによる2008年の研究は、市場センチメントが悲観的(ベアッシュ)になると、投資家の恐怖心が増幅され、ダウンサイドへの警戒感が一層強まることを示しました。その結果、ボラティリティ・スマイルの傾きはより急になり(スキューが深まり)、市場が織り込む将来のリターン分布の左側の裾が厚くなる(=暴落確率の高まりを織り込む)ことが実証されています 。これは、市場全体の「気分」という非合理的な要因が、オプション価格という合理的なはずの市場に、明確かつ非対称な影響を与えていることを示す強力な証拠です。
Friction:収益を阻害し、アノマリーを存続させる「諸悪の根源」
もし市場が完全に効率的で滑らか(frictionless)な理想郷であれば、上記のような非対称な恐怖によって生じた価格の歪みは、プロの投資家による裁定取引によって瞬時に解消されるはずです。しかし、現実の市場は、リターンの獲得を妨げ、アノマリーの存続を許す様々な「摩擦(Friction)」に満ちています。
最も分かりやすい摩擦は、ビッド・アスク・スプレッドや手数料といった直接的な取引コストです 。特にオプション市場では、原資産である株式市場に比べて流動性が低く、スプレッドが広くなる傾向があります。スキューが最も大きく、理論上の裁定機会が最も魅力的に見えるディープ・アウト・オブ・ザ・マネーのオプションほど、流動性が乏しく取引コストが高くなるというジレンマが存在します。この摩擦によって、理論上の利益の多くが削り取られ、小規模な裁定取引は不採算なものとなります 。
しかし、より本質的で強力な摩擦は、「裁定取引の限界」そのものにあります。VRPを収益源とするオプション売り戦略は、期待値がプラスである一方で、無限大の損失を被るテールリスクを内包しています。プロの裁定取引者であるヘッジファンドでさえ、その資本には限りがあり、無限のリスクを取ることはできません。市場のクラッシュ時に発生しうる莫大な損失と、それに伴う追証(マージンコール)のリスクは、彼らがVRPを完全に解消するほど巨大なポジションを構築することを物理的に妨げます。この資本の制約とリスク許容度の限界という根源的な摩擦こそが、ボラティリティ・リスクプレミアムというエッジが、市場から完全には消え去らずに存続し続けることを可能にしているのです。
アクション
今回のテーマを活用してすぐにできること
VIX指数を日々の市場分析のダッシュボードに加え、現在の市場の「恐怖レベル」を客観的に把握することから始めましょう。一般的に、VIXが20未満は平穏、30以上は高い警戒状態を示唆するとされています 。この数値を定点観測することで、市場全体のセンチメントの変化を捉えることができます。また、自身が保有するポートフォリオについて、VIXが急騰するような大きな市場下落が起きた場合にどの程度の損失が見込まれるかをシミュレーションし、テールリスクへの具体的な意識を高めることが重要です。
時間はかかるがじっくりやること
ボラティリティ・リスクプレミアムを収益源とするオプション売り戦略のリスク・リターン特性を深く研究することが、次のステップです。VRPは魅力的なリターンの源泉ですが、その裏には壊滅的な損失リスクが潜んでいます。安易な実行は大きな失敗に繋がるため、まずは少額のペーパートレードから始め、その非対称な損益プロファイルを肌で感じることが不可欠です。同時に、ボラティリティ・スキューの形状変化を継続的に観測する習慣をつけましょう。スキューの傾きが急になることは、市場参加者のダウンサイドへの警戒感が質的に高まっているシグナルであり、自身のポートフォリオのリスク管理体制を見直すための重要なインプットとなり得ます。
総括
- インプライド・ボラティリティ(IV)は、ブラック=ショールズ・モデルを介してオプションの市場価格から逆算される、市場の将来変動に対するフォワードルッキングな期待値です。
- 理論上の「ボラティリティは一定」という仮定とは異なり、現実のIVは権利行使価格によって異なる「ボラティリティ・スキュー」を示します。これは市場が株価の急落(テールリスク)を強く警戒していることの現れです。
- IVは、その後に実現するボラティリティを体系的に上回る傾向があり、この「ボラティリティ・リスクプレミアム(VRP)」はオプション売り戦略の収益源となりますが、それには壊滅的なテールリスクが伴います。
- VRPとスキューの根源には、投資家の損失回避性向やクラッシュ恐怖症といった「非対称な恐怖」が存在します。そして、取引コストや裁定取引の限界といった「摩擦」が、このアノマリーが市場に存続することを許しています。
用語集
- インプライド・ボラティリティ (Implied Volatility, IV) オプションの市場価格から、ブラック=ショールズなどの価格決定モデルを用いて逆算された、将来の原資産価格の変動率(ボラティリティ)の予測値。
- ブラック=ショールズ・モデル (Black-Scholes Model) 1973年に発表された、オプションの理論価格を計算するための画期的な数式。無裁定の原理に基づいているが、ボラティリティが一定であるなど、いくつかの非現実的な仮定を置いている 。
- ボラティリティ・スマイル/スキュー (Volatility Smile/Skew) 同じ原資産、同じ満期日のオプションにおいて、権利行使価格が異なるとインプライド・ボラティリティも異なる現象。特に株価指数オプションでは、権利行使価格が低い(下落に備える)プットのIVが高くなる「スキュー(歪み)」が見られる 。
- VIX指数 (VIX Index) S&P 500指数のオプション価格から算出される、市場全体の今後30日間のインプライド・ボラティリティを示す指数。市場の不安心理を反映するため「恐怖指数」とも呼ばれる 。
- ボラティリティ・リスクプレミアム (Volatility Risk Premium, VRP) インプライド・ボラティリティが、その後に実現するヒストリカル・ボラティリティを平均的に上回る差額のこと。オプションの売り手が受け取るリスクプレミアムとされる 。
- 実現ボラティリティ (Realized Volatility) 過去の価格データから統計的に計算された、実際に起こった価格変動の大きさ。ヒストリカル・ボラティリティ(HV)とほぼ同義。
- プット・ライティング (Put Writing) プットオプションを売却する戦略。相場が安定しているか上昇するとプレミアム収入を得られるが、相場が急落すると大きな損失を被るリスクがある。
- テールリスク (Tail Risk) 発生確率は極めて低いものの、一度発生すると資産価格に壊滅的な影響を与えるリスク。確率分布の裾(テール)の部分で起こる事象であることから名付けられた 。
- リスク中立確率 (Risk-Neutral Probability) 全ての資産の期待収益率がリスクフリーレートと等しくなるように調整された、理論上の確率。オプション価格の評価に用いられる。
- 裁定取引 (Arbitrage) 同一の価値を持つ資産間で価格差が生じた際に、割安な方を買い、割高な方を売ることで、リスクなく利益を得ようとする取引。価格の歪みを是正する力となる。
参考文献一覧
Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654.
Cboe Global Markets. (2019). Cboe VIX White Paper. Rubinstein, M. (1994). Implied Binomial Trees. The Journal of Finance, 49(3), 771–818.
Bakshi, G., Kapadia, N., & Madan, D. (2003). Stock Return Characteristics, Skew Laws, and the Differential Pricing of Individual Equity Options. The Review of Financial Studies, 16(1), 101–143.
Coval, J. D., & Shumway, T. (2001). Expected Option Returns. The Journal of Finance, 56(3), 983–1009.
Bondarenko, O. (2019). Historical Performance of Put-Writing Strategies. Cboe Global Markets. Han, B. (2008). Investor Sentiment and Option Prices. The Review of Financial Studies, 21(1), 387–414.
Constantinides, G. M. (1999). Transaction Costs and the Pricing of Financial Assets. Multinational Finance Society. Bollerslev, T., Tauchen, G., & Zhou, H. (2009). Expected stock returns and variance risk premia. The Review of Financial Studies, 22(11), 4463-4492.
Cheng, I. H. (2018). The behavior of volatility risk premia. Staff Report, Federal Reserve Bank of New York. Prokopczuk, M., & Wese Simen, C. (2014). The importance of the volatility risk premium for volatility forecasting. Journal of Banking & Finance, 40, 303-320.
Bollerslev, T., & Todorov, V. (2011). Tails, fears, and risk premia. The Journal of Finance, 66(6), 2165-2211.
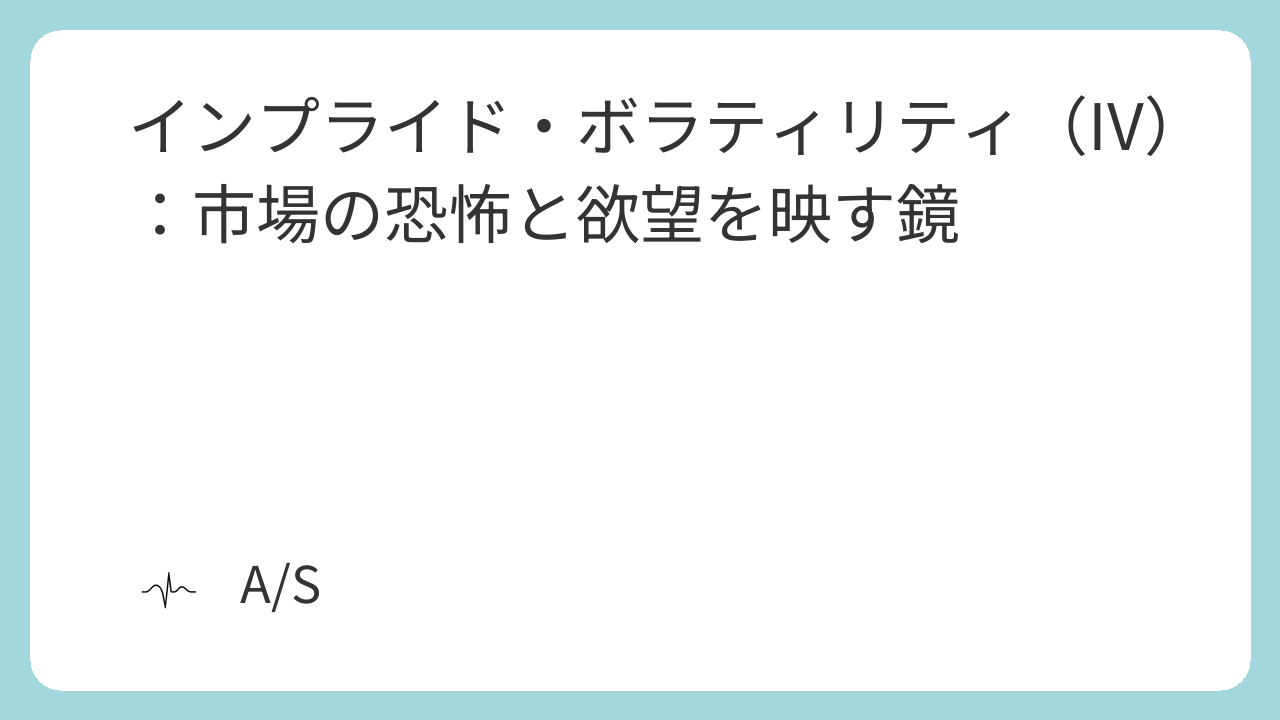
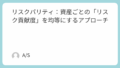
コメント