概論
「卵は一つのカゴに盛るな」――これは、投資の世界における最も古く、そして最も重要な格言の一つです。異なる種類の資産に資金を分散させることで、リスクを軽減できるというこの直感的な知恵を、数学的な厳密さをもって体系化したのが現代ポートフォリオ理論(Modern Portfolio Theory)であり、その心臓部に位置するのが相関(Correlation)と共分散(Covariance)という概念です。
共分散は、2つの資産のリターンが、どの程度同じ方向に動くかを示す統計的な指標です。
- 正の共分散:一つの資産のリターンが上がると、もう一つも上がる傾向がある。
- 負の共分散:一つの資産のリターンが上がると、もう一つは下がる傾向がある。
しかし、共分散は単位を持たないため、その関係の強さを直感的に理解することが困難です。そこで、共分散を各資産の標準偏差で割って、-1から+1の範囲に標準化したものが相関係数、すなわち相関です。
- 相関 +1:二つの資産が完全に同じ方向に動く。
- 相関 -1:二つの資産が完全に逆の方向に動く。
- 相関 0:二つの資産の間に、直線的な関係性が見られない。
この概念が金融の世界に革命をもたらしたのは、ハリー・マーコウィッツが1952年に発表した論文「ポートフォリオ選択」でした [1]。彼の独創的な洞察は、「ポートフォリオ全体のリスクは、構成資産それぞれの単独のリスクの単純な合計ではなく、それらの資産間の共分散(すなわち相関)に大きく依存する」という点にありました。たとえ個々のリスクが高い資産であっても、互いに相関が低ければ、組み合わせることでポートフォリオ全体のリスクを劇的に低減できることを、彼は数学的に証明したのです。
この理論は、多数の資産間の共分散をすべて計算する必要があるなど、実践上の困難も抱えていましたが、ウィリアム・シャープによる1963年の研究(後のCAPMの基礎となる)などが、その計算を簡略化する道筋を示しました [2]。相関と共分散は、単なる統計学の用語ではなく、リスクをコントロールするための最も強力なツールなのです。
長短の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について:リスク削減の「フリーランチ」
国際分散投資によるリスク低減(収益事例)
相関の概念がもたらす最大の恩恵は、分散投資によるリスク低減効果です。これはしばしば「金融における唯一のフリーランチ」とも呼ばれます。
この「フリーランチ」の有効性を世界に知らしめたのが、ブルーノ・ソルニクによる1974年の古典的な研究です [3]。彼は、米国の投資家が、国内株式だけでなく、相関の低い海外の株式市場にも投資を分散させることで、同じリターンをより低いリスクで達成できる、あるいは同じリスクでより高いリターンを追求できる「国際分散投資」の優位性を明確に示しました。異なる国の経済は異なるサイクルで動くため、それらの株式市場の相関は低く、組み合わせることでポートフォリオが安定したのです。
ファクター分散によるリターン平準化(収益事例)
この分散投資の考え方は、株式や債券といった伝統的な資産クラスだけでなく、ファクターの世界にも応用できます。
クリフ・アスネス、トビアス・モスコウィッツ、ラッセ・ペデルセンによる2013年の研究は、バリューファクターとモメンタムファクターの間に、安定した負の相関関係が存在することを明らかにしました [4]。つまり、バリューが好調な時期にはモメンタムが不調になりやすく、その逆もまた然り、という関係です。この性質を利用して二つのファクターを組み合わせることで、それぞれのファクターが持つドローダウン期間を互いに補い合い、より滑らかで、リスク調整後のリターンが高いポートフォリオを構築することが可能になります。
短所、弱み、リスクについて:相関の「裏切り」
分散投資の有効性は、計算に用いた相関係数が、将来も安定しているという前提の上に成り立っています。しかし、現実の市場では、この前提が崩れることがしばしばあります。
市場危機における相関の急上昇(損失事例)
分散投資が直面する最大のリスクは、「市場が危機的な状況に陥った際に、すべての資産の相関が1に近づいていく」という現象です。
ロンジンとソルニクによる1995年の研究は、この問題を鋭く指摘しました [5]。彼らの分析によれば、平時の市場では国際株式間の相関は比較的低いものの、市場のボラティリティが極端に高まる局面、すなわち暴落時において、相関は劇的に上昇することが示されました。これは、投資家が最も分散効果を必要とするパニック相場において、その効果が失われてしまうという、分散投資の痛い「裏切り」を意味します。
過大評価される分散効果
さらに、グローバル化が進んだ現代においては、国際分散投資によるリスク低減効果そのものが、過去に比べて小さくなっている可能性も指摘されています。
バトラーとホアキンによる2002年の研究は、多くの分析が国際分散投資のメリットを過大評価している可能性を論じています [6]。彼らは、過去数十年にわたり、世界の株式市場の連動性が高まる傾向にあることを示しました。これは、グローバルな経済統合や情報の瞬時の伝達によって、各国の市場が同じ要因で動くようになり、伝統的な国境を越えた分散投資の有効性が薄れてきていることを示唆しています。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、数学的に完璧に見える分散投資理論が、現実の市場ではしばしば裏切られるのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:相関の「非対称性」と非線形性
分散投資が直面する最大の問題は、相関係数そのものが持つ「非対称性」にあります。
ロンジンとソルニクの研究が示したように、資産間の相関は、市場が平穏な上昇局面にある時と、パニック的な下落局面にある時とで、その値が全く異なります [5]。通常時は低い相関を示し、分散効果をもたらしてくれるはずの資産たちが、ひとたび市場が暴落すると、まるで示し合わせたかのように一斉に相関を高め、共に下落していくのです。
この「平時と有事で豹変する」という相関の非対称性こそが、分散投資の最も危険な罠です。多くのポートフォリオモデルは、過去の平均的な相関を用いて未来を予測しますが、そのモデルが最も必要とされる危機的状況下では、その前提そのものが崩壊してしまうのです。
また、相関係数は、あくまで二つの資産間の「直線的な」関係性を測る指標に過ぎません。しかし、現実の市場における資産間の関係は、より複雑な「非線形」の関係を持つことが多々あります。この「線形的な測定尺度」と「非線形な現実」との間の非対称性が、伝統的な分散投資理論の死角となっているのです。
Friction:相関の「推定誤差」という情報の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、相関という概念を現実の投資に応用する際には、より本質的で克服困難な「情報の摩擦」が存在します。
推定誤差という根源的な摩擦
ポートフォリオを最適化するためには、構成資産間の共分散(相関)を正確に知る必要があります。しかし、神ならぬ人間が、未来の真の相関を知ることはできません。我々にできるのは、ノイズに満ちた過去のデータからそれを「推定」することだけです。
マーコウィッツの理論 [1]を実践しようとすると、例えば100銘柄のポートフォリオでも、約5000個もの共分散を推定しなくてはなりません。これらの推定値の一つ一つが、「推定誤差」という避けられない不確実性を含んでいます。この推定誤差という情報の摩擦は非常に深刻であり、わずかな推定ミスが、計算上は「最適」なはずだったポートフォリオを、現実には全く機能しない「最悪」のポートフォリオに変えてしまう危険性をはらんでいます。
非定常性という時間の摩擦
過去のデータから推定された相関が、将来も同じであるという保証はどこにもありません。グローバル化の進展や技術革新によって、資産間の関係性は常に変化し続けています。このような、統計的な性質が時間と共に変化していくことを「非定常性(Non-stationarity)」と呼びます。
バトラーとホアキンが示唆するように、世界の株式市場の相関は、長期的には上昇傾向にあります [6]。この「相関は一定ではない」という時間の摩擦は、過去のデータに依存する分散投資モデルの有効性を、根本から揺るがす問題なのです。過去の低い相関に基づいて構築されたポートフォリオは、相関が高まった未来の世界では、もはや期待されたリスク低減効果を発揮しないかもしれません。
総括
・相関と共分散は、ポートフォリオ全体のリスクが、構成資産間の相互作用によって決まることを示した、現代ポートフォリオ理論の根幹をなす概念です [1]。
・異なる資産(国際株式 [3]やファクター [4]など)のうち、相関が低いものを組み合わせることで、リスクを低減する「分散効果」が期待できます。
・しかし、その最大の弱点は、相関が常に一定ではないことです。特に市場の暴落時には、多くの資産の相関が急上昇し、分散効果が失われる傾向があります [5]。
・また、過去のデータから将来の相関を正確に「推定」することは極めて困難であり、この「推定誤差」と「非定常性」という情報の摩擦が、理論通りの分散投資を現実には難しくしています。
用語集
相関 (Correlation) 二つの資産のリターンが、どの程度同じ方向に、同じ強さで動くかを示す、-1から+1の範囲の値を取る統計的な指標。
共分散 (Covariance) 二つの資産のリターンが、同じ方向に動くか、逆の方向に動くかを示す指標。正の値は同じ方向、負の値は逆の方向を意味する。
現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory) ハリー・マーコウィッツが提唱した、資産のリターン、リスク(分散)、およびそれらの間の相関を考慮して、最も効率的なポートフォリオを構築するための理論。
分散投資 (Diversification) 異なる値動きをする(相関が低い)複数の資産に資金を分散させることで、ポートフォリオ全体のリスクを低減させる投資手法。
ポートフォリオ 投資家が保有する、株式、債券、不動産などの金融資産の組み合わせ、またその一覧。
標準偏差 (Standard Deviation) データのばらつきの大きさを測る最も一般的な統計的指標。リターンの標準偏差は、その資産のリスク(ボラティリティ)として用いられる。
シャープレシオ (Sharpe Ratio) リターンの大きさを、そのリターンを得るために取ったリスク(標準偏差)で割った、リスク調整後のパフォーマンス指標。
効率的フロンティア (Efficient Frontier) 現代ポートフォリオ理論において、ある与えられたリスク水準で、最大のリターンを達成できるポートフォリオの集合が描く曲線のこと。
非対称性 (Asymmetry) ある事象や関係が、対称的でないこと。金融市場では、上昇局面と下落局面で相関が異なるなど、多くの非対称性が観測される。
非定常性 (Non-stationarity) 時系列データの統計的な性質(平均、分散、相関など)が、時間と共に変化していくこと。
参考文献一覧
[1] Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
https://doi.org/10.2307/2975974
[2] Sharpe, W. F. (1963). A simplified model for portfolio analysis. Management Science, 9(2), 277-293.
https://doi.org/10.1287/mnsc.9.2.277
[3] Solnik, B. H. (1974). Why not diversify internationally rather than domestically?. Financial Analysts Journal, 30(4), 48-54.
https://doi.org/10.2469/faj.v30.n4.48
[4] Asness, C. S., Moskowitz, T. J., & Pedersen, L. H. (2013). Value and Momentum Everywhere. The Journal of Finance, 68(3), 929-985.
https://doi.org/10.1111/jofi.12021
[5] Longin, F., & Solnik, B. (1995). Is the correlation in international equity returns constant: 1960–1990?. Journal of International Money and Finance, 14(1), 3-26.
https://doi.org/10.1016/0261-5606(94)00001-H
[6] Butler, K. C., & Joaquin, D. C. (2002). Are the gains from international portfolio diversification exaggerated? The influence of the domestic-market benchmark. Journal of International Money and Finance, 21(7), 981-1002.
https://doi.org/10.1016/S0261-5606(02)00048-7
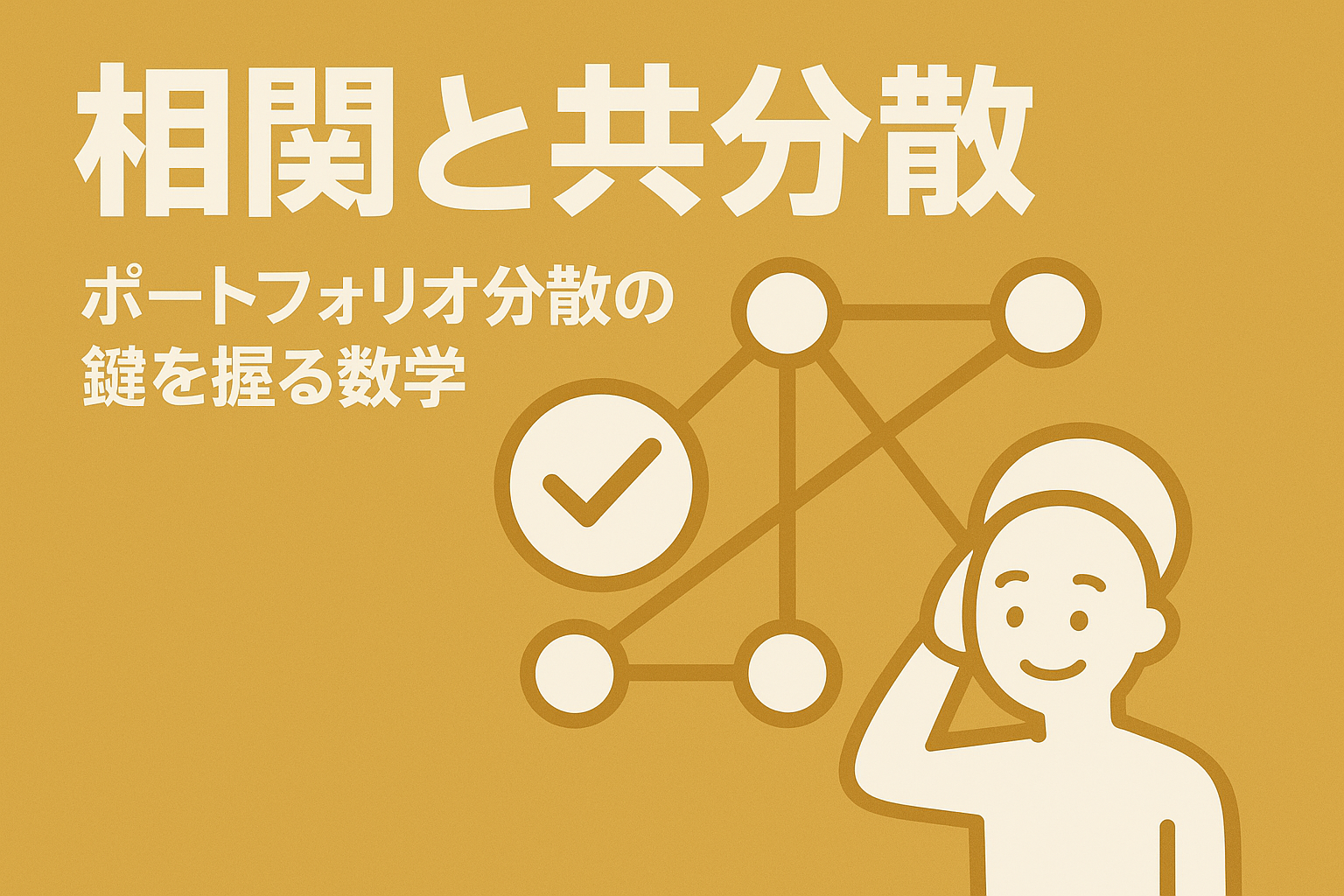
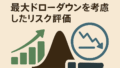

コメント