概論
ある投資ファンドが年間20%という素晴らしいリターンを上げたとします。このリターンは、果たしてファンドマネージャーの卓越した「腕前(スキル)」によるものなのでしょうか。それとも、単に市場全体が好調だった「幸運(マーケット)」に乗っただけなのでしょうか。この、パフォーマンスの要因を客観的に分解し、その本質を解き明かすための、最も強力な統計ツールが回帰分析(Regression Analysis)です。
回帰分析とは、ある変数(目的変数)の動きを、一つまたは複数の別の変数(説明変数)の動きによって、どの程度説明できるかを統計的にモデル化する手法です。金融の世界では、ある資産(ファンドや個別株)の超過リターンを目的変数とし、市場全体の超過リターンを説明変数として回帰分析を行うのが最も基本的な使い方です。
この分析によって、主に二つの重要な数値が算出されます。
- ベータ(β):回帰直線の「傾き」。市場が1%動いたときに、その資産が何%動くかという「市場感応度」を示します。
- アルファ(α):回帰直線の「切片」。市場の動きでは説明できない、その資産固有のリターンを示し、しばしば「運用者のスキル」や「エッジ」の代理指標と見なされます。
そして、この回帰モデルが、資産のリターンをどれだけうまく説明できているかの「当てはまりの良さ」を示すのが、決定係数(R-squared, R²)です。決定係数は0から1の間の値をとり、1に近いほど、その資産の動きの大部分が市場の動きによって説明できることを意味します。
この枠組みは、資本資産評価モデル(CAPM)の実証テストにおいて中心的な役割を果たしてきました。ブラック、ジェンセン、ショールズによる1972年の研究は、この回帰分析を用いて、CAPMが予測する理論的なリターンと、現実のリターンとの乖離(アルファ)を検証した、初期の代表的な研究です [1]。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について:パフォーマンスを分解する「レントゲン写真」
スキルとマーケットの分離(収益・活用事例)
回帰分析の最大の有用性は、パフォーマンスを市場連動部分(ベータ)と独自のリターン(アルファ)に分解できる点にあります。これは、ファンドのパフォーマンスを評価する上で、強力な「レントゲン写真」のような役割を果たします。
マイケル・ジェンセンが1968年に行った、ミューチュアル・ファンドのパフォーマンスに関する古典的な研究は、この手法の威力を世に知らしめました [2]。彼は、多数のファンドのリターンを市場リターンに対して回帰分析し、手数料を控除した後の平均的なアルファ(ジェンセンのアルファ)が、統計的にゼロと区別できない、すなわち、プロのファンドマネージャーが平均して市場を上回るスキルを持っていた証拠は見られない、という衝撃的な結論を導きました。
マルチファクターモデルへの拡張
回帰分析は、単一の説明変数(市場リターン)だけでなく、複数の説明変数を用いて、リターンをより精緻に分解することも可能です。
ファーマとフレンチによる1993年の研究は、市場リターンに加えて、サイズ(SMB)とバリュー(HML)という二つのファクターを説明変数に加えた3ファクター・回帰モデルを提唱しました [3]。さらに、マーク・カーハートは1997年に、モメンタム(UMD)を加えた4ファクターモデルを開発し、これを用いてファンドのパフォーマンスを分析しました [4]。これにより、あるファンドの高いリターンが、マネージャーの銘柄選択能力によるものなのか、それとも特定のファクター(例えば、小型割安株)へのエクスポージャーが高かっただけなのかを、より詳細に分析できるようになったのです。
統計的妥当性の追求
金融学の研究者たちは、回帰分析を金融データに適用する際に生じる統計的な問題を克服するため、様々な工夫を凝らしてきました。ファーマとマクベスが1973年に開発したファーマ=マクベス回帰は、その代表例です [5]。これは、時系列データとクロスセクション・データを組み合わせた特殊な2段階の回帰分析を行うことで、より信頼性の高い形で資産価格モデルを検証する手法であり、その後の実証ファイナンス研究の標準的な手法の一つとなりました。
短所、弱み、リスクについて:統計ツールの限界と誤用
回帰分析は強力なツールですが、その結果を解釈する際には、いくつかの根源的な限界と誤用のリスクを理解しておく必要があります。
「真の市場」は観測不可能(ロールの批判)
回帰分析を用いてアルファとベータを測定する際の、最も根源的な問題が、「真の市場ポートフォリオは、観測不可能である」という点です。
リチャード・ロールが1977年に提唱したこの「ロールの批判」は、CAPMの実証テストに対する強烈な問題提起です [6]。私たちが回帰分析で用いるTOPIXやS&P500といった株価指数は、あくまで「真の市場ポートフォリオ(株式、債券、不動産、人的資本など、全ての資産を含む)」の代理(プロキシ)に過ぎません。もし、用いた代理指数が不適切であった場合、それに基づいて計算されたアルファとベータもまた、全く意味のない数値になってしまう、とロールは主張しました。
決定係数の誤った解釈
決定係数(R-squared)の解釈も、注意が必要です。例えば、あるアクティブファンドの決定係数が0.98と非常に高かった場合、それはそのファンドの動きの98%が市場インデックスの動きで説明できることを意味し、高い手数料を払う価値のない「隠れインデックスファンド(クローゼット・インデクサー)」である可能性を強く示唆します。
逆に、決定係数が非常に低い場合、それは必ずしも悪いことではありません。もし、そのファンドが市場とは全く相関しない、独自のアルファの源泉を持っているならば、決定係数は低くなり、ポートフォリオの分散効果を高める上で非常に価値のある存在となります。
非対称性と摩擦の視点から
回帰分析は、一見すると客観的で科学的なツールに見えます。しかし、その応用と解釈には、市場の非対称な現実と、人間の認知的な摩擦が深く関わっています。
Asymmetry:アルファの「非対称性」とモデルの限界
回帰分析が算出するアルファは、分析期間を通じて一定の「平均値」です。しかし、真のスキル(エッジ)は、常に一定であるとは限りません。ここにアルファの「非対称性」という問題が潜んでいます。
例えば、あるトレーダーが、市場が安定している平常時には優れたアルファを生み出す一方で、市場が混乱する危機時には大きなマイナスのアルファを出してしまうとします。これを長期間で平均して回帰分析にかけると、アルファはゼロに近い値になるかもしれません。このモデルは、平常時と危機時でパフォーマンスが非対称であるという、トレーダーの最も重要な特性を見過ごしてしまうのです。
また、標準的な回帰分析は、その計算の過程で、モデルで説明できない誤差(残差)が正規分布に従うことを仮定しています。しかし、現実の市場リターンは、しばしばファットテールや歪度を持つ非対称な分布を示します。もし、ある戦略のアルファが、稀に起こる壊滅的な損失によって成り立っている場合、回帰分析が示す平均的なアルファは、その戦略が抱える非対称なテールリスクを隠してしまう危険性があるのです。
Friction:モデルの「誤用」という情報の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、回帰分析というツールそのものが、誤用された場合には、投資家の判断を誤らせる「情報の摩擦」を生み出す源泉となります。
1.「見せかけの精度」という認知的摩擦
回帰分析は、「アルファは年率2.5%」「ベータは1.15」といった、非常に正確に見える数値を出力します。この「見せかけの精度」は、投資家に過剰な自信を与えてしまう認知的な摩擦として機能します。
しかし、これらの数値はあくまで過去のデータに基づく「推定値」であり、必ず統計的な不確実性(標準誤差)を伴います。算出されたアルファが、統計的に本当にゼロと区別できるのか、あるいは単なる偶然の産物なのかを厳密に評価しなければ、ノイズをシグナルと誤認してしまう危険性があります。
2.ベンチマーク選択という恣意性の摩擦
回帰分析の結果は、説明変数として何を選ぶか、すなわち「どのベンチマーク(基準)で測るか」に根本的に依存します。このベンチマークの選択に、恣意性が入り込む余地があることが、情報の摩擦となります。
ロールの批判が指摘するように、もし不適切なベンチマークを用いて分析を行えば、算出されるアルファとベータは全く意味のないものになります [6]。例えば、あるファンドマネージャーは、自分の戦略と無関係なベンチマークを選ぶことで、見かけ上のアルファを人為的に高く見せることができるかもしれません。正しいベンチマークを選ぶことの難しさと、そこに介在する恣意性の可能性は、回帰分析の結果を解釈する際に常に念頭に置くべき、重大な摩擦なのです。
総括
・回帰分析は、ある資産のリターンを、市場全体の動きに連動する部分(ベータ)と、市場とは独立した部分(アルファ)に分解するための強力な統計ツールです。
・ジェンセンのアルファ [2]や、ファーマ=フレンチの3ファクターモデル [3]など、ファンドのパフォーマンス評価や資産価格モデルの検証に広く用いられてきました。
・決定係数(R-squared)は、そのモデルがリターンの何パーセントを説明できているかを示し、モデルの当てはまりの良さを評価する指標です。
・しかし、その結果は、用いるベンチマークが不適切であれば意味をなさないという根源的な問題を抱えています(ロールの批判)[6]。
・また、回帰分析が出力する数値は、あくまで統計的な推定値であり、その不確実性を無視して過信することは、誤った投資判断に繋がる危険性があります。
用語集
回帰分析 (Regression Analysis) ある変数(目的変数)の動きを、一つまたは複数の別の変数(説明変数)の動きによって、どの程度説明できるかを統計的にモデル化する手法。
アルファ (Alpha) 回帰分析における切片。市場や他のファクターの動きでは説明できない、その資産固有の超過リターン。運用者のスキルやエッジの指標とされる。
ベータ (Beta) 回帰分析における傾き。市場などの説明変数が1単位動いたときに、その資産が何単位動くかという感応度を示す。
決定係数 (R-squared) 回帰モデルが、目的変数のばらつきをどれだけ説明できたかを示す、0から1の間の値を取る指標。モデルの当てはまりの良さを示す。
CAPM (資本資産評価モデル) 資産の期待リターンが、その資産のベータ(市場リスク)の大きさに比例して決まるという理論。アルファとベータの概念の理論的基礎となる。
ジェンセンのアルファ (Jensen’s Alpha) CAPMに基づき、市場リターンに対する単回帰分析によって算出されたアルファのこと。
3ファクターモデル ファーマとフレンチが提唱した、市場リスク、サイズ、バリューの3つの要因で株式リターンを説明するモデル。マルチファクター回帰分析の代表例。
ロールの批判 (Roll’s Critique) 真の市場ポートフォリオは観測不可能であるため、CAPMを実証的にテストすることは不可能であるという、リチャード・ロールによる批判。
標準誤差 (Standard Error) 回帰分析によって得られたアルファやベータといった推定値が、統計的にどれくらいの誤差を含んでいるかを示す指標。
残差 (Residuals) 回帰モデルによる予測値と、実際の観測値との差。モデルで説明できなかった誤差の部分。
参考文献一覧
[1] Black, F., Jensen, M. C., & Scholes, M. (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests. In M. C. Jensen (Ed.), Studies in the Theory of Capital Markets (pp. 79-121). Praeger Publishers.
※書籍です
[2] Jensen, M. C. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. The Journal of Finance, 23(2), 389-416.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00815.x
[3] Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5
[4] Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance, 52(1), 57-82.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x
[5] Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636.
https://doi.org/10.1086/260061
[6] Roll, R. (1977). A critique of the asset pricing theory’s tests Part I: On past and potential testability of the theory. Journal of Financial Economics, 4(2), 129-176.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90009-5
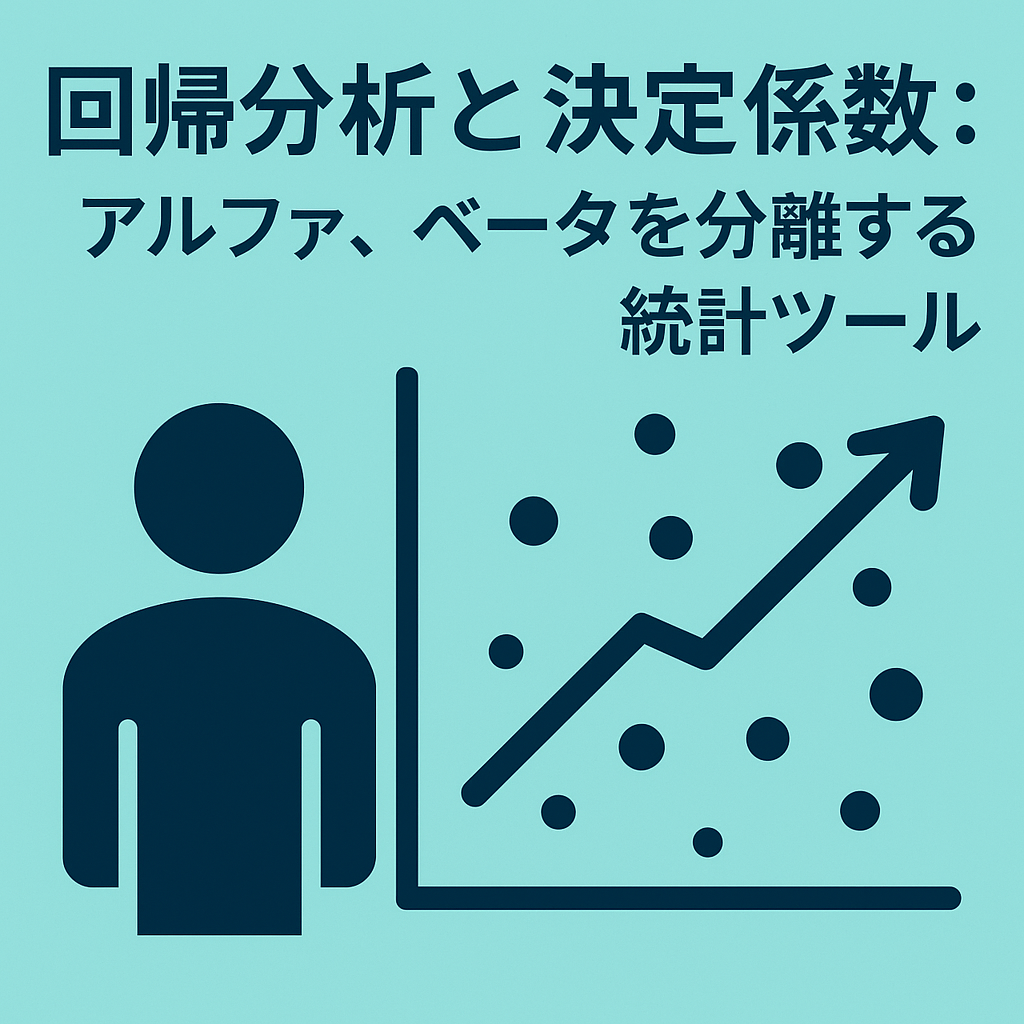
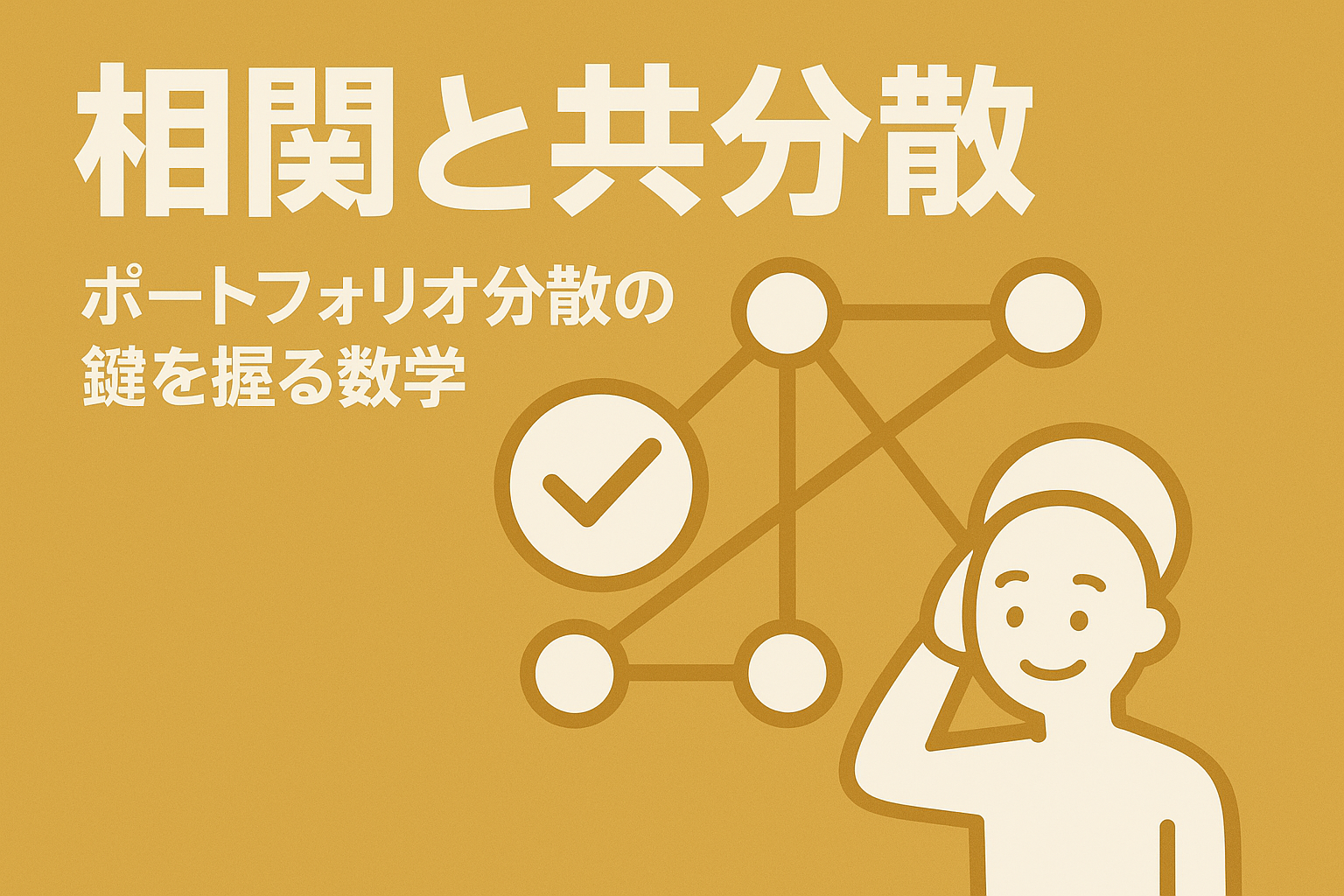

コメント