概論
ある株式に投資する際、私たちはどれくらいのリターンを期待すべきでしょうか。そのリターンは、どのようなリスクによって決まるのでしょうか。この根源的な問いに対し、驚くほどシンプルで美しい回答を与えたのが、資本資産価格モデル(Capital Asset Pricing Model)、通称CAPMです。
CAPMは、現代ファイナンス理論の礎を築いた金字塔であり、その核心的な主張は「ある資産に期待されるリターンは、リスクのない資産のリターン(リスクフリーレート)と、その資産が市場全体のリスクをどれだけ引き受けるか、という唯一の要因だけで決まる」というものです。この市場全体のリスクへの感応度は、ベータ(β)という指標で測定されます。
この理論は、ウィリアム・シャープやジョン・リントナーらによって1960年代に独立して提唱され、シャープはこの功績により後にノーベル経済学賞を受賞しました [1]。CAPMがもたらした最大の功績は、資産のリスクを二種類に分解した点にあります。一つは、市場全体の動きと連動し、分散投資を行っても消すことができない「システマティック・リスク」。もう一つは、その企業固有の要因による「個別リスク(非システマティック・リスク)」です。
CAPMの世界では、合理的な投資家は多数の銘柄に分散投資を行うため、個別リスクは互いに相殺しあって無視できるほど小さくなります。その結果、投資家がリターンを要求できるのは、引き受けることを避けられないシステマティック・リスクに対してのみである、と結論付けられます。この考え方は、その後の金融工学やポートフォリオ運用の世界に革命的な影響を与えました。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
CAPMは、その理論的な美しさと実用性から広く受け入れられましたが、その後の研究によって、現実の市場を説明するには多くの限界があることも明らかになってきました。
長所、強み、有用な点について
CAPMの最大の強みは、その理論的な簡潔さと直感的な分かりやすさにあります。複雑な資産価格の決定メカニズムを、たった一つの変数であるベータで説明しようとするエレガントなモデルであり、金融を学ぶ者にとって最初の重要な道標となります。
実務の世界においても、CAPMは企業の資本コストを推定したり、投資プロジェクトの採算性を評価するための割引率(ハードルレート)を設定したりする際の標準的なツールとして、長年にわたり広く利用されてきました。
学術的にも、CAPMはその登場によって、リスクとリターンの関係性を実証的に検証する研究の爆発的な増加を促しました。初期の実証研究の中には、CAPMを支持するものもありました。例えば、フィッシャー・ブラック、マイケル・ジェンセン、マイロン・ショールズによる1972年の研究では、高ベータのポートフォリオは低ベータのポートフォリオよりも高いリターンを生む傾向があることが示され、CAPMの基本的な考え方にある程度の妥当性を与えました [2]。
短所、弱み、リスクについて
しかし、CAPMの黄金時代は長くは続きませんでした。1970年代後半から、研究者たちはCAPMの理論的な予測とは全く整合しない、数々のアノマリー(経験則)を次々と発見していったのです。これらは、CAPMが現実の市場のリターンを説明する上で、致命的な欠陥を抱えていることを示唆していました。
その代表例が「サイズ効果」です。ロルフ・バンツが1981年に発表した研究は、企業の時価総額が小さい(小型株)ほど、CAPMの予測を体系的に上回る高いリターンを上げる傾向があることを発見しました [3]。ベータだけでは、この小型株の超過リターンを説明することはできませんでした。
さらに決定的だったのが、ユージン・ファーマとケネス・フレンチによる1992年の研究です。彼らは、米国の株式リターンを詳細に分析し、株価のベータは、リターンを説明する上でほとんど何の力も持たないことを示しました。そして、ベータに代わってリターンを強力に予測したのは、企業の時価総額(サイズ)と、簿価時価比率(バリュー、割安度を示す指標)という二つの要因だったのです [4]。これは、CAPMの理論的根幹を揺るがす、極めて衝撃的な発見でした。
それに追い打ちをかけるように、ナラシムハン・ジェガディッシュとシェリダン・ティットマンは1993年に「モメンタム効果」を発見します。これは、過去3ヶ月から12ヶ月の間に株価が上昇した銘柄は、その後も上昇し続け、下落した銘柄は下落し続けるという強力なアノマリーです [5]。この現象は、価格がランダムに動くとするCAPMの前提とは全く相容れないものでした。
近年では、CAPMの予測と正反対の現象さえ報告されています。アンドレア・フラッツィーニとラッセ・ペデルセンによる2014年の研究は、「ベッティング・アゲインスト・ベータ」戦略を提唱しました。これは、CAPMの予測に反して、低ベータ(低リスク)の株式ポートフォリオが、高ベータ(高リスク)の株式ポートフォリオよりも、リスク調整後のリターンで見て高いパフォーマンスを上げるというアノマリーを利用するものです [6]。理論上はリスクが高いほどリターンが高くなるはずが、現実にはその逆が観測されたのです。これらの数々の反証は、CAPMが美しい理論ではあっても、現実の市場を記述するモデルとしては不完全であることを明確に示しています。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、これほどまでにエレガントな理論が、現実の市場の前では力を失ってしまうのでしょうか。その本質は、CAPMが前提としている「完璧な世界」と、私たちが生きる「不完全な現実」とのギャップにあります。このギャップを、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かします。
Asymmetry:期待と情報の非対称性
CAPMが崩壊する根源には、市場参加者の間に存在する「情報の非対称性」があります。CAPMは、全ての投資家が同じ情報を持ち、将来について同じ期待を形成するという、極めて強い仮定を置いています。しかし、現実は全く異なります。一部の投資家は他の投資家よりも優れた情報を持ち、より深い分析を行うことができます。この情報の非対称性こそが、CAPMでは説明できない超過リターン、すなわち「アルファ」の源泉となります。
また、CAPMはリターンが正規分布に従うという、対称な世界を仮定していますが、現実の市場リターンは対称ではありません。突然の暴落(ネガティブ・スキュー)など、分布には歪みがあります。CAPMは、このような非対称なテールリスクを適切に評価することができません。投資家は、ベータでは測定できない、暴落に対する脆弱性といった非対称なリスクを嫌い、それを避けるためにより高いリターンを要求するかもしれません。この期待の非対称性が、ベータとリターンの間に単純な線形関係が成り立たない一因となっているのです。
Friction:理想と現実を隔てる摩擦
CAPMは、取引コストや税金が存在せず、誰もが同じリスクフリーレートで自由に資金を借り入れできるという「完全市場(摩擦のない世界)」を前提としています。しかし、現実の市場は、リターンの獲得を妨げる様々な「摩擦」に満ちています。
手数料やスプレッドといった直接的な取引コストは、理論上の裁定機会を不採算なものにし、アノマリーの存続を許します。しかし、より根源的な摩擦が「借入制約」です。
現実には、多くの投資家、特に個人投資家や一部の機関投資家は、CAPMが仮定するようにリスクフリーレートで無制限に資金を借りることはできません。高いリターンを狙いたいが、レバレッジをかける能力に制約がある投資家は、どうするでしょうか。彼らは、本来のポートフォリオにレバレッジをかける代わりに、本質的にレバレッジがかかっているのと同じ効果を持つ「高ベータ株」を、その代替として選好するようになります [6]。
この高ベータ株への需要の集中が、その価格を本来あるべき水準以上に押し上げ、結果として将来の期待リターンを押し下げてしまうのです。これが、「ベッティング・アゲインスト・ベータ」アノマリー、すなわち低ベータ株が高ベータ株をアウトパフォームするという、CAPMの予測と正反対の現象が起こるメカニズムです。借入が自由にできないという「摩擦」が、市場に巨大な歪みを生み出しているのです。
総括
- 資本資産価格モデル(CAPM)は、資産の期待リターンが、市場全体のリスクへの感応度(ベータ)のみによって決定されるとする、シンプルで強力な理論です [1]。
- その簡潔さから、企業の資本コスト計算など実務で広く応用され、その後の金融研究の発展に大きく貢献しました [2]。
- しかし、その後の研究で、サイズ効果 [3]、バリュー効果 [4]、モメンタム効果 [5]など、CAPMでは説明できない数々のアノマリーが発見され、その限界が明らかになりました。
- 近年では、低ベータ株が高ベータ株をアウトパフォームするという、CAPMの予測と正反対の現象(ベッティング・アゲインスト・ベータ)も報告されています [6]。
- CAPMの限界の背景には、全ての投資家が同じ情報を持ち、合理的に行動するという非現実的な「非対称性の欠如」の仮定や、借入制約といった現実世界の「摩擦」の存在があります。
用語集
資本資産価格モデル(CAPM) ある資産の期待リターンが、リスクフリーレートと、市場ポートフォリオのリターンに対する感応度(ベータ)によって決まるとする理論モデル。
ベータ(β) 個別の資産が、市場全体の動きに対してどれくらい敏感に反応するかを示す指標。ベータが1であれば市場と同じように動き、1より大きければ市場より大きく動く。
システマティック・リスク 市場全体に関連するリスクであり、分散投資によっても取り除くことができないリスク。市場リスクとも呼ばれる。
個別リスク(非システマティック・リスク) 特定の企業や産業に固有のリスクであり、多数の銘柄に分散投資を行うことで低減できるリスク。
リスクフリーレート 国債など、理論上リスクがゼロと見なされる安全資産から得られるリターンのこと。
アノマリー 現代ファイナンス理論の常識では説明できないが、市場で経験的に観測されるリターンの規則性のこと。
サイズ効果 企業の時価総額が小さい株式(小型株)ほど、平均的にリターンが高くなる傾向があるというアノマリー。
バリュー効果 企業の純資産などに対して株価が割安な株式(バリュー株)ほど、平均的にリターンが高くなる傾向があるというアノマリー。
モメンタム効果 過去に価格が上昇した資産は将来も上昇しやすく、過去に下落した資産は将来も下落しやすいという傾向があるアノマリー。
アルファ 市場全体の動き(ベータ)や、既知のファクターでは説明できない、純粋な超過リターンのこと。
参考文献一覧
[1] Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425-442.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x
[2] Black, F., Jensen, M. C., & Scholes, M. S. (1972). The capital asset pricing model: Some empirical tests. In M. C. Jensen (Ed.), Studies in the Theory of Capital Markets (pp. 79-121). Praeger Publishers.
※書籍です
[3] Banz, R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9(1), 3-18.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(81)90018-0
[4] Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x
[5] Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65-91.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x
[6] Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2014). Betting against beta. Journal of Financial Economics, 111(1), 1-25.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.10.005
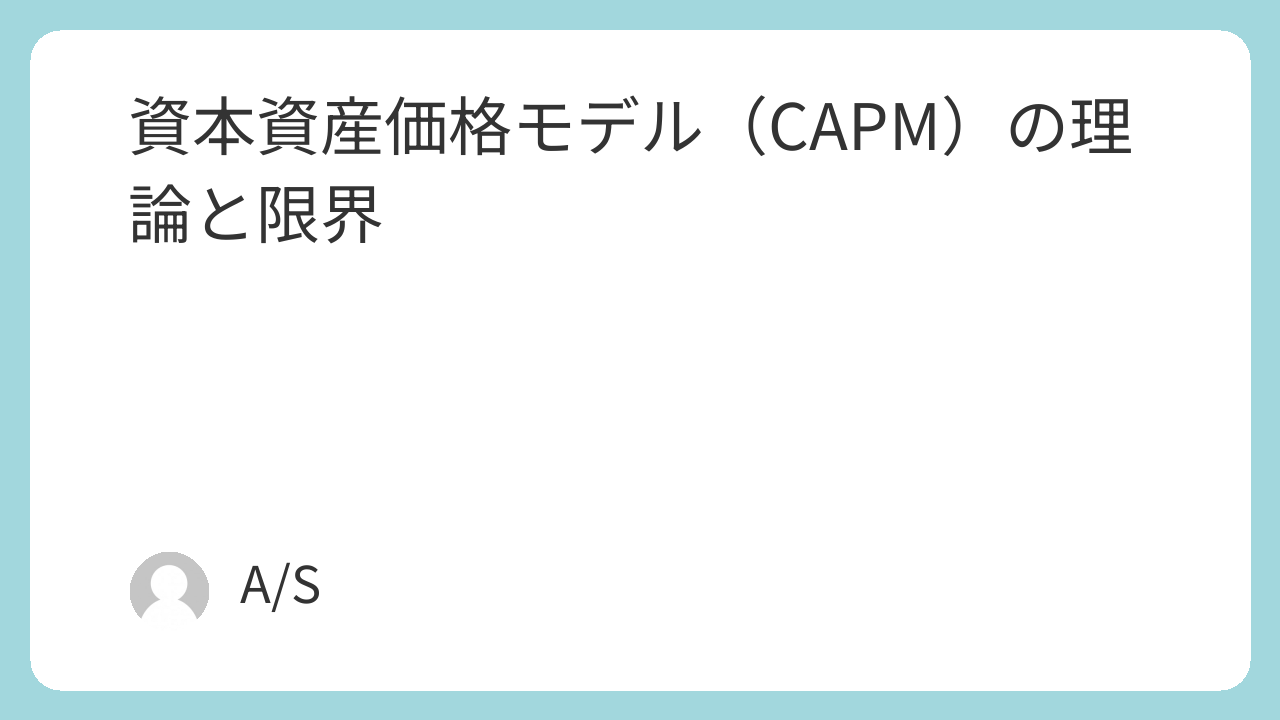
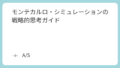
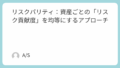
コメント