概論:市場の「行き過ぎ」とその揺り戻し
市場には、「トレンドは友」という言葉がある一方で、「人の行く裏に道あり花の山」という逆張りの格言も存在します。この二つの相場観は、時間軸によってその有効性を変えることが、学術研究によって示されています。中期的なモメンタム効果とは対照的に、3年から5年という長い時間軸で市場を観測すると、全く逆の現象、すなわち長期リバーサル効果が現れるのです。
長期リバーサル効果とは、過去3〜5年間にわたって株価パフォーマンスが最も悪かった銘柄群(過去の敗者、Losers)が、その後の3〜5年間で、過去のパフォーマンスが最も良かった銘柄群(過去の勝者、Winners)を、体系的にアウトパフォームするというアノマリー(経験則)を指します。
この現象を学術的に初めて発見し、行動ファイナンスの扉を開いたのが、ワーナー・デボンとリチャード・セイラーによる1985年の金字塔的な論文「Does the Stock Market Overreact?」です [1]。彼らは、1926年から1982年までのニューヨーク証券取引所のデータを分析し、過去3〜5年間の「敗者ポートフォリオ」が、その後の3〜5年間で「勝者ポートフォリオ」のリターンを劇的に上回ることを発見しました。
彼らは、この現象の原因を、投資家が過去の出来事やトレンドを過度に重視し、将来の予測に過剰に反映させてしまう「過剰反応(Overreaction)」という行動バイアスにあると主張しました。良いニュースが続いた企業の将来を過度に楽観視して買い上げ、悪いニュースが続いた企業の将来を過度に悲観視して売り叩く。この市場参加者の「行き過ぎた」感情が、株価を本来の価値から大きく乖離させ、その後の長い時間をかけた「揺り戻し」の過程で、リバーサル効果が生まれるというのです。
この「過剰反応」の背景にある人間の心理的メカニズムは、ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによるプロスペクト理論などで説明されています [2]。特に、人々が最近の出来事や目立つ情報に基づいて判断を下しやすい代表性ヒューリスティックという認知バイアスが、過去のパフォーマンスを将来に過度に投影させてしまう一因と考えられています。
長短の解説と損益の事例紹介
長期リバーサル効果は、市場の非効率性を利用する逆張り戦略の理論的な支柱です。しかし、その実践は、リスクベースの合理的な説明という強力な反論にも晒されています。
長所、強み、有用な点について:市場の「行き過ぎ」を利用する
収益事例:歴史が示す驚異的なリターン
長期リバーサル戦略が示す歴史的なリターンは、極めて強力です。デボンとセイラーの最初の研究では、「敗者ポートフォリオ」は、「勝者ポートフォリオ」を、その後の3年間で平均して約25%もアウトパフォームしたと報告されています [1]。市場全体のリターンを差し引いた超過リターンでも、敗者ポートフォリオは勝者ポートフォリオを大きく上回っており、この効果が単なる市場リスクの違いだけでは説明できないことを示唆していました。
バリュー投資との深い関係
長期リバーサル効果は、ベンジャミン・グレアム以来の伝統を持つバリュー投資の有効性を、行動ファイナンスの観点から裏付けるものと広く考えられています。
ラコニショック、シュライファー、ヴィシュニーによる1994年の研究は、この関係性を明確にしました [3]。彼らの分析によれば、投資家が過去の成長率を過度に外挿する結果、過去の成長率が低い「バリュー株(割安株)」は不当に安値で放置され、過去の成長率が高い「グロース株(成長株)」は過大評価される傾向があります。バリュー投資とは、本質的に、この市場の「行き過ぎ」に対して逆張りを行う戦略であり、長期リバーサル効果を利用しているのです。
国際的な市場での観測
この効果の根底にあると考えられるバリュー・プレミアム(割安株の超過リターン)は、米国内だけでなく、グローバルな市場でも観測されています。ファーマとフレンチによる2012年の国際市場を対象とした大規模な研究は、バリュー・プレミアムが多くの先進国市場で普遍的に見られる現象であることを示しており、長期リバーサル効果の背景にある投資家心理が、国や文化を超えて共通している可能性を示唆しています [4]。
短所、弱み、リスクについて:それは本当に非効率性か?
リスクに基づく合理的な説明
長期リバーサル効果が、単なる投資家の非合理的な行動の結果である、という見方には、強力な反論が存在します。それは、「敗者ポートフォリオは、本質的により高いリスクを抱えているため、その対価として高いリターンを得ているに過ぎない」という、効率的市場仮説の立場からの説明です。
ファーマとフレンチは1996年の論文で、デボンとセイラーが発見したリバーサル効果の大部分が、彼らの3ファクターモデル(市場、サイズ、バリュー)で説明できると主張しました [5]。彼らの分析によれば、「敗者ポートフォリオ」は、規模が小さく(サイズファクター)、かつ割安な(バリューファクター)企業を多く含む傾向があります。したがって、その高いリターンは、投資家の過剰反応を利用した「フリーランチ」なのではなく、これらの体系的なリスクファクターに晒されていることへの、合理的な報酬(リスクプレミアム)である、というわけです。
「敗者の罠(Loser’s Trap)」
長期リバーサル戦略を実践する上での最大の危険は、「敗者の罠」です。過去の敗者の中から、市場に過度に悲観視されているだけで、事業価値はやがて回復する「ダイヤの原石」を見つけ出す必要があります。しかし、多くの敗者銘柄は、ビジネスモデルが崩壊していたり、技術革新に取り残されていたりと、株価が低迷するだけの合理的な理由を持っています。このような「正真正銘の敗者」に投資してしまえば、リバーサルは起こらず、損失は拡大し続けることになります。
非対称性と摩擦の視点
なぜ、市場は数年という長い時間軸で、これほどまでに劇的な「行き過ぎ」と「揺り戻し」を見せるのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:期待の「過剰反応」という非対称性
長期リバーサル効果の根源には、投資家が情報を処理する際の「期待形成の非対称性」が存在します。
デボンとセイラーが指摘した「過剰反応」とは、まさにこの非対称な期待形成のことです [1]。過去数年間にわたって素晴らしい業績を上げてきた「勝者」企業に対して、投資家はその成功体験から、将来も同様の成長が永遠に続くかのように過度に楽観的な期待を抱きます。逆に、数年間業績が悪かった「敗者」企業に対しては、その失敗体験から、将来も回復することなく凋落し続けるかのように過度に悲観的な期待を抱いてしまうのです。
この楽観と悲観の方向への、非対称な「行き過ぎ」こそが、株価をその本質的な価値から大きく乖離させる原因となります。プロスペクト理論が示すように、人間はトレンドやパターンを将来に当てはめて考えてしまう認知バイアス(代表性ヒューリスティック)を持っています [2]。この非対称な心理的バイアスが、市場にリバーサルという収益機会を生み出すのです。勝者が永遠の勝者ではなく、敗者が永遠の敗者でもないと気づいた時、行き過ぎた期待は剥落し、価格は平均へと回帰していきます。
Friction:ストーリーへの固執と「キャリアリスク」という摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、長期リバーサルという時間のかかるアノマリーの存続を許している、より強力で根深い摩擦が存在します。
1.「ストーリー」への固執という認知的摩擦
企業には、その株価の推移と共に、強力な「ストーリー(物語)」が形成されます。「勝者」企業は革新的で時代の寵児という輝かしい物語を持ち、「敗者」企業は時代遅れの斜陽産業という烙印を押されます。一度形成されたこのストーリーは非常に根強く、投資家の判断を長期間にわたって縛る「認知的な摩擦」として機能します。
たとえ敗者企業のファンダメンタルズに回復の兆しが見えても、投資家は「あの会社はもうダメだ」という過去の物語に固執し、その変化をなかなか受け入れることができません。この認知の遅れが、株価の割安な放置を長引かせ、リバーサル・アノマリーが簡単には消滅しない土壌を提供しているのです [3]。
2.「キャリアリスク」という制度的摩擦
長期リバーサル戦略は、その効果が発現するまでに3年から5年という非常に長い時間を要します。これは、多くのプロの投資家(ファンドマネージャー)にとって、耐え難いほどの長さです。
なぜなら、彼らの多くは、四半期や1年といった短い期間のパフォーマンスで評価されるからです。不人気な敗者銘柄に投資する戦略は、短期的には市場平均に劣後する可能性が非常に高いです。もし、リバーサルが起こる前に運用成績の不振が続けば、彼らは顧客から資金を引き揚げられ、職を失う「キャリアリスク」に直面します。この制度的な摩擦が、多くのプロ投資家が、たとえ長期的には有効だと分かっていても、この戦略を本格的に実行することを躊躇させる大きな原因となっているのです。
総括
・長期リバーサル効果とは、過去3〜5年間の「敗者」株式ポートフォリオが、その後の3〜5年間で「勝者」株式ポートフォリオを大幅にアウトパフォームするというアノマリーです [1]。
・この現象の主な原因は、投資家が過去のトレンドを将来に過度に投影してしまう「過剰反応」という行動バイアスにあると考えられています [1, 2]。
・この戦略は、市場で不人気な銘柄を安値で買う「バリュー投資」と密接に関連しており、その理論的支柱の一つとなっています [3]。
・一方で、敗者ポートフォリオの高いリターンは、単にそのポートフォリオが持つ高いリスク(サイズやバリューファクターへのエクスポージャー)への合理的な対価である、という効率的市場仮説の立場からの強力な反論も存在します [5]。
用語集
長期リバーサル効果 過去3〜5年といった長期間の株価パフォーマンスが最も悪かった銘柄群が、その後の同程度の期間で、最も良かった銘柄群を上回るリターンを上げる傾向。
過剰反応 (Overreaction) 投資家が、特定のニュースや過去のトレンドに対して、その情報が持つ本来の価値以上に、感情的に大きく、そして持続的に反応してしまう行動バイアス。
プロスペクト理論 不確実性のある状況下での人間の意思決定を説明する理論。人々が利益と損失をどのように評価し、確率をどのように認識するかの歪みをモデル化したもの。
代表性ヒューリスティック (Representativeness Heuristic) 人々が、物事の確率を、それが典型的な事例(ステレオタイプ)にどれだけ似ているかに基づいて判断してしまうという認知バイアス。
バリュー投資 企業の本来的な価値(ファンダメンタルズ)に比べて、株価が割安に評価されている銘柄に投資する手法。
グロース株 (成長株) 売上や利益が高い成長率を示している企業の株式。長期リバーサル効果における「勝者」銘柄と重なることが多い。
逆張り戦略 (Contrarian Strategy) 市場の大多数の投資家の意見や行動とは逆のポジションを取る投資戦略。長期リバーサル戦略は、その代表例。
3ファクターモデル ファーマとフレンチが提唱した、市場リスク、サイズ、バリューの3つの要因で株式リターンを説明するモデル。
リスクプレミアム ある資産を保有する際に、その資産が持つリスクを引き受けることへの対価として、無リスク資産のリターンを上回って期待される追加的なリターンのこと。
効率的市場仮説 市場価格は利用可能な全ての情報を即座に織り込んでいるため、継続的に市場を上回ることはできないとする理論。
参考文献一覧
[1] De Bondt, W. F., & Thaler, R. H. (1985). Does the stock market overreact?. The Journal of Finance, 40(3), 793-805.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x
[2] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
https://doi.org/10.2307/1914185
[3] Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. The Journal of Finance, 49(5), 1541-1578.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb04772.x
[4] Fama, E. F., & French, K. R. (2012). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of Financial Economics, 105(3), 457-472.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.05.011
[5] Fama, E. F., & French, K. R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. The Journal of Finance, 51(1), 55-84.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05202.x
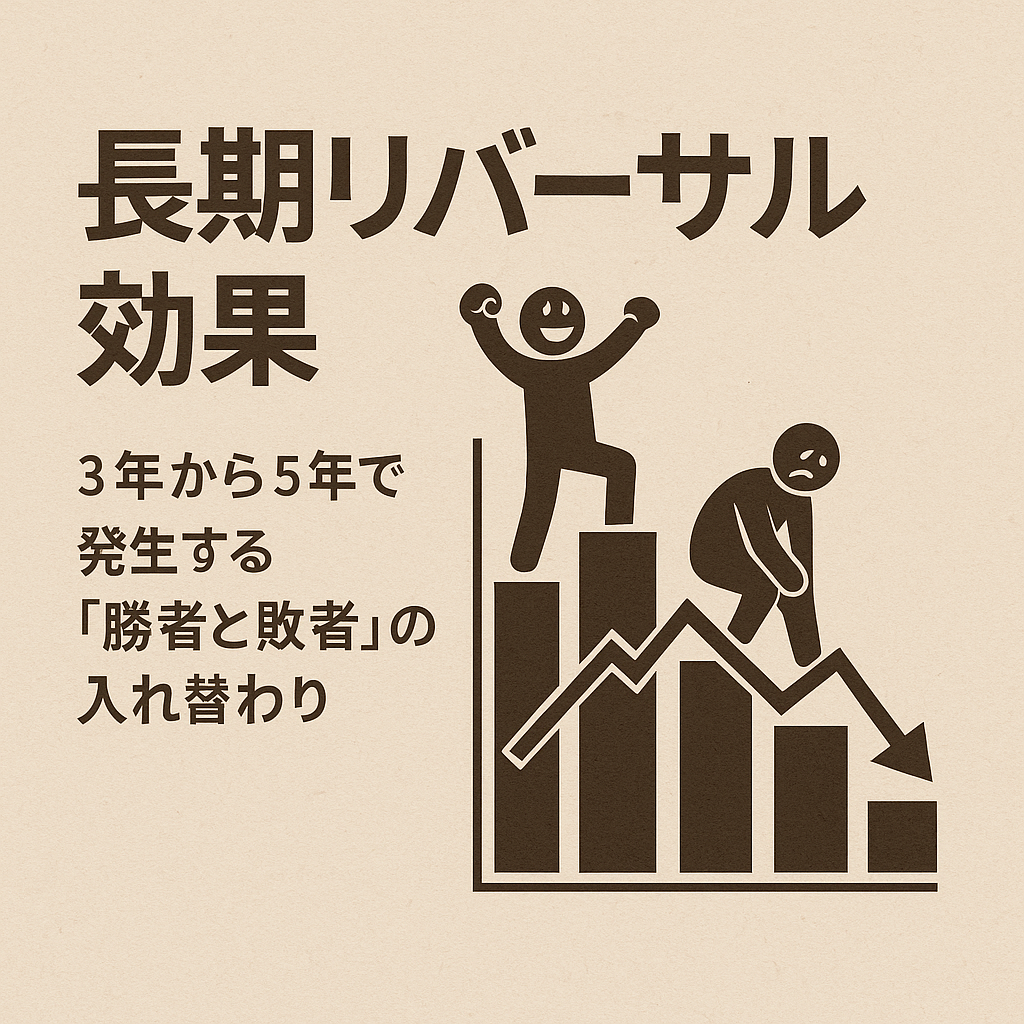
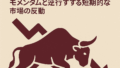
コメント