これまでの連載(第1部・第2部)で、モメンタム効果の基礎理論(第1部)と、古典的なモメンタム戦略の具体的な構築方法、そしてその致命的な弱点である「モメンタム・クラッシュ」(第2部)について学んできました。
古典的戦略は強力なリターンの源泉となる一方、市場の急変時に全てを失いかねないテールリスクを内包しています。この事実は、トレーダーに新たな問いを突きつけます。「モメンタムの強力なリターンを享受しつつ、この壊滅的なクラッシュのリスクをいかにして軽減、あるいは回避すればよいのか?」
この極めて実践的な課題に対し、現代の学術研究は驚くほど多様な「回答」を提示しています。今回は3部作の締めくくりとして、それぞれアプローチが異なる3つの洗練された「進化形」の戦略を分析・批評し、モメンタム戦略の最前線を探ります。
アプローチ1:ボラティリティ調整(リスクの平準化)
最初に紹介する進化形は、モメンタム戦略が抱える「リスクの大きさ」そのものを直接コントロールしようとするアプローチです。Fan, Li, & Liu (2018)の研究は、この代表例です。
核心的なアイデア
この戦略の核心は、ポートフォリオのボラティリティが常に一定の目標値(例:年率12%)になるように、投資比率(エクスポージャー)を動的に調整する「コンスタント・ボラティリティ・スケーリング(CVS)」という手法にあります。市場が不安定でボラティリティが高い時期には投資比率を下げてリスクを抑制し、逆に安定している時期にはレバレッジをかけてリターンを高めます。
パフォーマンス
1991年から2017年にかけて、55種類のグローバルな流動性先物を対象とした検証では、このCVS戦略は年率15.3%という高いリターンを記録しました。しかし、そのリターンは年率39.1%という非常に高いボラティリティを伴うものであり、シャープ・レシオは0.392と、リスク調整後のリターン効率が必ずしも改善するわけではないことを示しています。このアプローチは、クラッシュのダメージを完全に回避するというよりは、リスクを取るべき局面とそうでない局面を見極めることで、長期的なリターンを最大化することを目的としていると言えます。
アプローチ2:レバレッジの戦略的活用(ショートサイドの選別)
第二の進化形は、企業のファンダメンタルズ情報、特に「財務レバレッジ」を用いて、モメンタム戦略の精度を高めるアプローチです。Forner, Muradoglu, & Sivaprasad (2018)の研究がこれにあたります。
核心的なアイデア
この研究の最も重要な発見は、モメンタム効果の現れ方が、企業のレバレッジ水準によって非対称であることです。分析の結果、「敗者」銘柄がその後も下落し続ける負のモメンタムは、主に「高レバレッジ」の銘柄で強く観測されました。
この発見に基づき、戦略を「勝者銘柄を(レバレッジに関わらず)ロングし、敗者銘柄の中でも特にレバレッジが高い銘柄のみをショートする」というルールに洗練させます。
パフォーマンス
1982年から2016年にかけての英国株式市場での検証では、この組み合わせ戦略は、Fama-Frenchモデルでリスク調整した後でも、年率15.66%という極めて高いアルファを生み出しました。これは、単独のモメンタム戦略(年率7.96%)やレバレッジ戦略(年率7.70%)をほぼ2倍上回る驚異的な結果です。この戦略は、モメンタム・シグナルと、企業の財務的な脆弱性を示すシグナルを組み合わせることで、特にショートサイドの精度を劇的に向上させています。
アプローチ3:2次元モメンタム(シグナルの再定義)
第三の進化形は、戦術的な調整に留まらず、モメンタムという「シグナル」そのものをより強力なものへと再定義する、根源的なアプローチです。Xu, Zhao, & Zheng (2020)が提唱した「投資モメンタム(InvMom)」戦略が、その最たる例です。
核心的なアイデア
この戦略は、従来の「価格モメンタム」に、企業の「投資モメンタム」という新しい次元を加えます。「投資モメンタム」とは、企業の資産成長率が低い(=投資を抑制している)企業ほど、その後のリターンが高くなる傾向があるというアノマリーです。
この2つの次元を組み合わせ、「価格モメンタムが高く、かつ投資モメンタムが低い」企業をロングし、「価格モメンタムが低く、かつ投資モメンタムが高い」企業をショートします。
パフォーマンス
1965年から2015年という半世紀にわたる米国株式市場での長期検証において、このInvMom戦略は驚異的な結果を示しました。
年率リターンは18.74%、そしてシャープ・レシオは1.21という、極めて高いリターン効率を記録しました。特筆すべきは、この戦略がモメンタム・クラッシュに対して高い耐性を持ち、多くのアノマリーが減衰した2000年以降も、統計的に有意なリターンを維持し続けた点です。これは、異なる性質を持つ2つのシグナルを組み合わせる「シグナル分散」が、いかに戦略を頑健にするかを示す強力な証拠です。
総評と比較:どの進化形が最も有望か?
3つのアプローチは、それぞれ異なる哲学と特性を持っています。
| アプローチ | 核心的な手法 | 長所 | 短所・課題 |
| ボラティリティ調整 | リスク量を一定に保つ戦術的調整 | 高い年率リターン(15.3%) | リターン効率(シャープ・レシオ)は改善せず、高いボラティリティとドローダウンを伴う |
| レバレッジ活用 | ショートサイドを財務情報で選別 | 極めて高いアルファ(15.66%) | 英国市場に限定された検証。レバレッジ銘柄のショートは高いコストやリスクを伴う可能性 |
| 2次元モメンタム | シグナル自体を根源的に強化 | 高いリターン(18.74%)と最高のリターン効率(シャープ・レシオ1.21)を両立。クラッシュ耐性と持続性 | 企業の財務データが必要で、分析がより複雑 |
どの戦略が絶対的に優れていると断じることはできません。しかし、長期的なエッジの探求という観点から見れば、その示唆は明確です。
ボラティリティ調整やレバレッジ活用は、既存のシグナルに対する「戦術的な最適化」です。これらは市場環境やコスト構造の変化に影響されやすい可能性があります。一方で、2次元モメンタムは、「シグナルそのものの質」を根源的に高めるアプローチです。より本質的で、異なる経済的背景を持つ複数の非効率性を捉えることで、頑健性と持続性を実現しています。
結論として、モメンタム戦略の弱点を克服するための最も有望な道筋は、単なるリスク管理やリターン増幅に留まらず、より高品質で多角的なシグナルを構築することにある、と考えます。この「投資モメンタム」という発見は、我々が新たなエッジを探求する上で、極めて重要な示唆を与えてくれるでしょう。
参考文献
- Fan, M., Li, Y., & Liu, J. (2018). Risk adjusted momentum strategies: a comparison between constant and dynamic volatility scaling approaches. Research in International Business and Finance, 46, 131-140.
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.12.004 - Forner, C., Muradoglu, Y. G., & Sivaprasad, S. (2018). Enhancing momentum investment strategy using leverage. Journal of Forecasting, 37(5), 573–588.
https://doi.org/10.1002/for.2522 - Xu, F., Zhao, H., & Zheng, L. (2020). Investment momentum: A two-dimensional behavioural strategy. International Journal of Finance & Economics, 27(1), 75-97.
https://doi.org/10.1002/ijfe.2208
巻末用語集
モメンタム・クラッシュ (Momentum Crash)
モメンタム戦略が、短期間で突発的かつ壊滅的な損失を被る現象のこと。特に、金融危機など弱気相場の後の急反発局面で発生しやすいとされています。このクラッシュにより、数年かけて積み上げた利益が一気に失われることもあるため、古典的モメンタム戦略の最大のリスク(アキレス腱)と見なされています。
ボラティリティ・スケーリング (Volatility Scaling)
ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)を、常に一定の水準に保つように、投資比率を動的に調整するリスク管理手法。市場が不安定でボラティリティが高い時期には投資比率を下げ(時には現金を増やし)、市場が安定してボラティリティが低い時期には投資比率を上げる(時にはレバレッジをかける)ことで、リスクを平準化し、パフォーマンスの安定化を目指します。
CVS (Constant Volatility Scaling)
ボラティリティ・スケーリングの一種で、過去の実現ボラティリティを基に、常にボラティリティが一定の目標値になるように調整する、比較的シンプルなアプローチです。Fan, et al. (2018)の論文では、この手法が最も高いリターンを記録しました。
DVS (Dynamic Volatility Scaling)
ボラティリティ・スケーリングのもう一つのアプローチで、将来の期待リターンなども考慮に入れて、より動的に投資比率を調整する、より複雑な手法です。
最大ドローダウン (Maximum Drawdown)
特定の期間において、資産価格が最高値から最安値まで下落した際の最大下落率のこと。戦略が抱える最大のリスク量を測るための重要な指標です。例えば、最大ドローダウンが-60%であれば、その戦略を運用中に資産が一時的に60%減少する局面があったことを意味します。
シャープレシオ (Sharpe Ratio)
リターンを、そのリターンを得るために取ったリスク(標準偏差)で割った値。リスク調整後のパフォーマンスを測る代表的な指標です。単純なリターンの高さだけでなく、「どれだけ効率的にリターンを上げたか」を示します。一般的に、この数値が高いほど、運用成績が優れていると評価されます。
財務レバレッジ (Financial Leverage)
企業の総資本における負債の比率。自己資本に対してどれだけ他人資本(借入金など)を利用して事業を行っているかを示します。一般的に、レバレッジが高い企業は、好況期には高い収益性を期待できる一方で、不況期には財務的な脆弱性が増し、倒産リスクが高まるとされます。
エクスポージャー (Exposure)
ある特定の資産や戦略に対して、投資家が投じている資金の量、つまり価格変動のリスクに晒されている金額のこと。例えば、ある戦略に自己資金の80%を投じている場合、その戦略へのエクスポージャーは80%となります。ボラティリティ調整戦略では、このエクスポージャーを市場環境に応じて100%以上にしたり(レバレッジをかける)、100%未満にしたり(一部を現金化する)します。
投資モメンタム / 投資ファクター (Investment Momentum / Investment Factor)
企業の投資行動(総資産の成長率など)と、その後の株価リターンの間に見られるアノマリー。「投資を抑制している(資産成長率が低い)」企業群は、「積極的に投資している(資産成長率が高い)」企業群よりも、統計的に高いリターンを上げる傾向があります。
2次元モメンタム / ハイブリッド戦略 (2D Momentum / Hybrid Strategy)
従来の「価格モメンタム」という1つの次元だけでなく、「投資モメンタム」や「財務レバレッジ」といった、異なる性質を持つ別の次元(ファクター)を組み合わせて構築された戦略のこと。異なる角度から銘柄を選別することで、より頑健で持続性のあるエッジを生み出すことを目指します。
テールリスク (Tail Risk)
正規分布では起こる確率が極めて低い(グラフの裾野=テール部分で発生する)はずの、壊滅的な損失が発生するリスクのこと。「モメンタム・クラッシュ」は、モメンタム戦略が抱える典型的なテールリスクです。
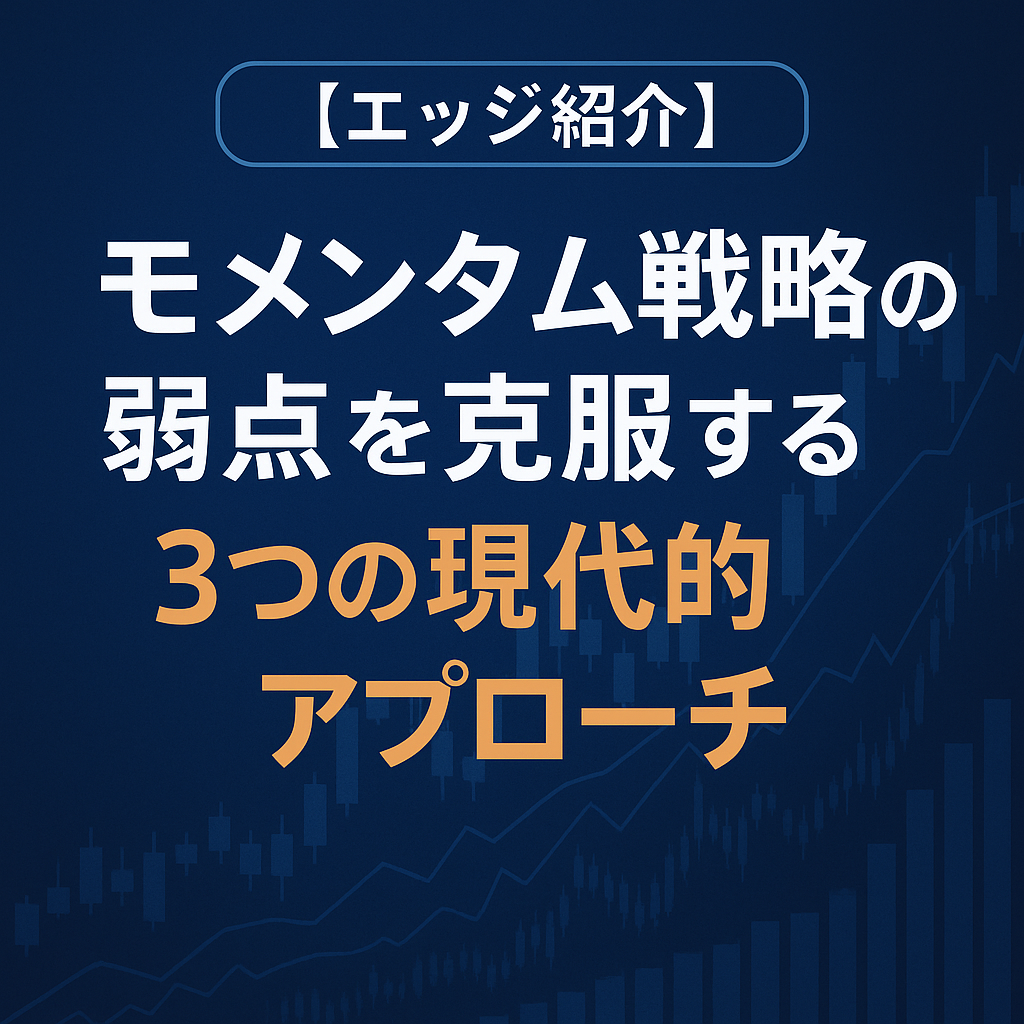
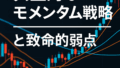
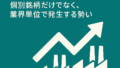
コメント