前回の記事では、モメンタム効果が学術的に確立されたアノマリーであり、その背景には投資家の心理や市場の情報伝達構造が関係していることを解説しました。次のステップはそれを実践的なトレーディング戦略へとつなげることです。
今回は、モメンタム研究の原典である論文で提示された古典的な戦略の具体的な構築方法を解説します。さらに、この戦略が金融理論の標準モデルに組み込まれていった経緯を追います。最後に、多くのトレーダーを破滅させてきた、この戦略に内包される致命的な弱点「モメンタム・クラッシュ」のリスクを詳細に分析します。
古典的モメンタム戦略の構築法:Jegadeesh and Titmanの「J/Kポートフォリオ」
モメンタム戦略の具体的な構築方法は、オリジナルの発見者であるジェガディッシュとティットマンの1993年の論文にその原型があります。彼らが用いた手法は「J/Kポートフォリオ戦略」として知られており、その後の多くのモメンタム研究の基礎となっています。
JとKは、それぞれ以下の期間を指します。
- J = フォーメーション期間(Formation Period):銘柄の過去リターンを測定し、ランキング付けするための期間。ルックバック期間とも呼ばれます。
- K = 保有期間(Holding Period):ランク付けに基づいて組成したポートフォリオを保有する期間。
具体的な戦略構築のプロセスは、以下のステップで構成されます。
- ユニバースの定義:まず、分析対象となる銘柄群(例:米国の上場普通株)を決定します。
- フォーメーション期間Jでのランク付け:ユニバース内の全銘柄について、過去Jヶ月間のリターンを計算します。ジェガディッシュとティットマンは、Jとして3, 6, 9, 12ヶ月の期間をテストしました。
- ポートフォリオの組成:計算したリターンに基づき、全銘柄を高い順から低い順へと並べ替え、10等分のグループ(デシル)に分類します。リターンが最も高かった上位10%のグループを「勝者ポートフォリオ」、最も低かった下位10%を「敗者ポートフォリオ」とします。
- 保有期間Kでのポジション保有:勝者ポートフォリオをロング(買い)、敗者ポートフォリオをショート(空売り)します。このポジションをKヶ月間保有します。彼らは、Kとして3, 6, 9, 12ヶ月の期間をテストしました。
- リバランス:Kヶ月が経過したらポートフォリオを解消し、再びステップ2に戻って新しいポートフォリオを組成します。保有期間が例えば6ヶ月の場合、毎月新しいポートフォリオを組成するため、常に6つの異なるポートフォリオが並行して運用されることになります。
この研究で最も高いリターンを示したのは、J=12ヶ月、K=3ヶ月といった、比較的長い期間で勝者/敗者を判断し、比較的短い期間で手仕舞う組み合わせでした。
第4のファクターへ:Carhart (1997)による標準化
ジェガディッシュとティットマンの発見後も、モメンタムは長らく「説明のつかないアノマリー」として扱われていました。当時、資産価格を説明する標準モデルであったファーマ=フレンチの3ファクターモデル(市場リスク、サイズ、バリュー)をもってしても、モメンタム効果がもたらす超過リターンを説明することはできなかったのです。
この状況を変えたのが、マーク・カーハートが1997年に発表した論文「On persistence in mutual fund performance」です。彼は、投資信託のパフォーマンスを分析する中で、3ファクターモデルを補完する「第4のファクター」として、モメンタムファクター(MOM)を導入しました。
このMOMファクターは、過去12ヶ月のリターンに基づき、上位30%の銘柄群のリターンから下位30%の銘柄群のリターンを差し引くことで算出されます。このカーハートの4ファクターモデルの登場により、モメンタムは単なるアノマリーから、サイズやバリューと並ぶ市場の体系的なリスクファクターの一つとして、広く学術界と実務界に認知されるようになりました。
モメンタムの「アキレス腱」:Daniel and Moskowitz (2016)が暴いたクラッシュ・リスク
モメンタム戦略は、長期間にわたって安定したリターンを生み出す一方で、深刻なリスクを伴ってきました。それは突然発生し、数年分の利益をわずか数ヶ月で吹き飛ばすほど壊滅的な損失です。これを「モメンタム・クラッシュ」と呼びます。
この現象に学術的な光を当て、その発生メカニズムを詳細に解明したのが、ケント・ダニエルとトビアス・モスコウィッツによる2016年の決定的な論文「Momentum crashes」です。
彼らは80年以上にわたるデータを分析し、モメンタム・クラッシュが発生しやすい市場環境を特定しました。その条件とは「パニック的な弱気相場の後、市場が急反発する局面」です。
このメカニズムはモメンタム戦略が保有する銘柄の特性に起因します。
- 弱気相場: 市場がパニックに陥ると、財務的に脆弱でベータが高い「ジャンク株」は徹底的に売られ「敗者ポートフォリオ」の常連となります。一方で、財務が健全でベータが低い「優良株」は相対的に底堅く、「勝者ポートフォリオ」を構成します。
- 急反発局面: パニックが収まって市場が急激にリスクオンに転じると、それまで最も売られていた敗者ポートフォリオ(ジャンク株)が、その高いベータのために爆発的なリバウンドを見せます。逆に、勝者ポートフォリオ(優良株)は、そのディフェンシブな性質から、市場全体の反発に乗り遅れます。
この「勝者の敗北」と「敗者の逆襲」が同時に発生することで、モメンタム戦略は短期間に凄まじい損失を被るのです。2009年初頭の金融危機からの反発局面や、2020年のコロナショック後の反発局面は、まさにこのモメンタム・クラッシュが観測された典型的な例です。
結論:古典的モメンタムの功罪と次なる課題
古典的なモメンタム戦略の具体的な構築方法と、それが標準的なファクターとして確立された経緯、そしてその最大の弱点であるクラッシュ・リスクについて解説してきました。
古典的モメンタム戦略は、市場の根深い非効率性を捉える強力なエッジである一方、そのリターンには致命的なテールリスクが内包されています。これはこの戦略を実運用する上で、無視できない「アキレス腱」です。ノイズというには頻度が低く、しかし、あまりにも1回の影響・被害が大きすぎるのです。
この事実は、トレーダーに新たな問いを突きつけます。「モメンタムの強力なリターンを享受しつつ、この壊滅的なクラッシュのリスクをいかにして軽減、あるいは回避すればよいのか?」
次回の記事では、この困難な課題に対し、現代の学術研究が提示するモメンタムの「進化形」による洗練されたアプローチについて、紹介・解説します。
用語集・補足
モメンタム・ファクター(Momentum Factor, MOM)
過去のリターンが高かった資産が将来も高いリターンを得やすく、過去のリターンが低かった資産が将来も低いリターンを得やすいという傾向を数値化した指標。ファーマ=フレンチ3ファクターモデルにカーハート(1997)が追加した「第4のファクター」として広く知られ、過去12か月のリターン上位銘柄と下位銘柄のリターン差として測定されることが多い。学術研究や実務で、株式や通貨、コモディティなど幅広い資産クラスに適用される。
ファーマ=フレンチ3ファクターモデル(Fama-French 3-Factor Model)
株式のリターンを説明するために、ユージン・ファーマとケネス・フレンチが提案したモデル。従来の資本資産評価モデル(CAPM)の「市場リスク(Market)」に加え、以下の2つのファクターを追加する。
- サイズ(SMB: Small Minus Big):小型株と大型株のリターン差
- バリュー(HML: High Minus Low):株式の割安度を示す概念または投資スタイルの総称。一般的には簿価純資産倍率(P/B)や利益倍率(P/E)が低い銘柄を割安株(バリュー株)とみなし、長期的には市場平均を上回るリターンを得られる傾向があるとされる。
ファーマ=フレンチモデルでは、割安株(High Book-to-Market)と割高株(Low Book-to-Market)のリターン差を「HML(High Minus Low)」として計測する。バリュー投資はウォーレン・バフェットやベンジャミン・グレアムの投資哲学とも関係している。
テールリスク(Tail Risk)
確率分布の「端(テール)」に存在する、発生確率は極めて低いが、発生すると非常に大きな損失や利益をもたらすリスク。金融市場では、通常のボラティリティでは説明できない極端な値動き(暴落や暴騰)を指すことが多い。モメンタム戦略における「モメンタム・クラッシュ」は、このテールリスクの典型例で、数年分の利益を数日~数週間で失うことがある。
ベータ(β, Beta)
市場全体の値動きに対する感応度を示す指標。CAPM(資本資産評価モデル)では、資産のリスクを市場との共変動で測定する。β=1なら市場と同じ割合で動き、β>1なら市場より値動きが大きく、β<1なら市場より値動きが小さい。高ベータ株は上昇局面では大きく上がるが、下落局面では大きく下がる傾向があるため、モメンタム戦略のリスク要因として重要視される。
デシル(Decile)
データを10等分したグループのこと。モメンタム戦略の検証では、過去リターンに基づき全銘柄を並べ替え、上位10%(第10デシル)を勝者ポートフォリオ、下位10%(第1デシル)を敗者ポートフォリオとする方法が一般的。この分割により、リターン特性の違いを明確にし、統計的検証を容易にする。
参考文献
- Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of Finance, 52(1), 57–82.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x - Daniel, K., & Moskowitz, T. J. (2016). Momentum crashes. Journal of Financial Economics, 122(2), 221–247.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.12.002 - Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65–91.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x

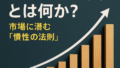
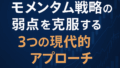
コメント