概論:モメンタム効果の新たな地平
「上がっている株は上がり続け、下がっている株は下がり続ける」――この、市場の「勢い」に着目したモメンタム効果は、投資の世界で最も広く知られ、かつ頑健なアノマリー(経験則)の一つです。この現象は、ジェガディッシュとティットマンによる1993年の画期的な論文によって、学術的に確立されました [1]。
しかし、その後の研究は、この「勢い」が単に個別銘柄のレベルだけで発生している現象ではないことを突き止めました。モメンタムは、より大きな単位、すなわち産業(インダストリー)レベルでも、強力に存在していたのです。
産業モメンタムとは、過去に高いリターンを記録した産業に属する株式ポートフォリオが、将来にわたって、過去に低いリターンしか記録できなかった産業のポートフォリオをアウトパフォームする傾向がある、というアノマリーです。
この現象を学術的に初めて体系的に示したのが、トビアス・モスコウィッツとマーク・グリンブラットによる1999年の論文「Do Industries Matter?」です [2]。彼らは、米国市場のデータを分析し、個別銘柄のモメンタム効果のかなりの部分が、実はこの産業モメンタムによって説明できることを発見しました。つまり、ある株が上がっているのは、その株自体が優れているからというだけでなく、単にその株が「勢いのある産業」に属しているから、という側面が強かったのです。
彼らが構築した、過去のパフォーマンスが良かった産業を買い、悪かった産業を売るというシンプルな戦略は、個別銘柄のモメンタム戦略に匹敵する、強力なリターンを生み出しました。この発見は、投資家がリターンの源泉を探る上で、個別企業だけでなく、よりマクロな産業レベルのダイナミクスにも注目すべきであることを示唆したのです。
長短の解説と損益の事例紹介
産業モメンタムは、伝統的な個別株モメンタムと比較して、いくつかのユニークな長所を持つ一方で、モメンタム戦略に共通する深刻なリスクも内包しています。
長所、強み、有用な点について
1.取引コストの低減と戦略の安定性
個別株のモメンタム戦略は、勝者と敗者が目まぐるしく入れ替わるため、非常に高い売買回転率(ターンオーバー)を要求され、その結果として多額の取引コストが発生するという大きな欠点を抱えています。
一方、産業レベルでの「勝ち組」「負け組」は、個別株レベルよりも緩やかに変化する傾向があります。そのため、産業モメンタム戦略は、個別株モメンタム戦略よりも低い売買回転率で実行可能であり、リターンを蝕む取引コストを抑制できるという、実践的な強みを持っています [2]。
2.より根源的なトレンドの反映
産業のパフォーマンスは、その産業に共通する技術革新、規制の変更、需要の構造的変化、あるいはマクロ経済的な要因といった、より長期的で根源的なトレンドを反映していると考えられます。
ホンとスタインによる1999年の理論研究は、このようなファンダメンタルな情報が、市場参加者の間でゆっくりと伝播していく過程で、モメンタムが生まれるメカニズムを説明しています [3]。産業モメンタムは、個別企業の一時的なニュースに左右されるノイズの多いシグナルではなく、このような情報の緩やかな拡散という、より本質的な市場の非効率性を捉えている可能性があります。
収益事例:歴史的に確認された強力なリターン
産業モメンタムの有効性は、その発見当初から、非常に強力なものでした。モスコウィッツとグリンブラットの研究によれば、1963年から1995年の期間において、上位の産業を買い、下位の産業を売る戦略は、月平均で約1%の有意なリターンを生み出しました [2]。
また、アスネス、モスコウィッツ、ペデルセンによる2013年の包括的な研究は、モメンタムという現象が、国や資産クラスを超えて普遍的に存在することを示しており、産業モメンタムの背後にある原理の頑健性を補強しています [4]。
短所、弱み、リスクについて
損失事例:モメンタム・クラッシュの宿命
産業モメンタムは、他のすべてのモメンタム戦略と同様に、「モメンタム・クラッシュ」と呼ばれる、突発的で壊滅的な損失に見舞われるリスクを常に内包しています。
ダニエルとモスコウィッツによる2016年の研究は、この現象を詳細に分析しました [5]。モメンタム・クラッシュは、金融危機後のような、市場がパニック的な売りを経験した後の急反発局面で発生しやすくなります。このような局面では、それまで最も売り込まれていた「負け組」の産業(モメンタム戦略が空売りしている対象)が、最も激しく買い戻されるため、戦略は短期間で極めて大きな損失を被るのです。このリスクは予測が困難であり、モメンタム戦略の最大の弱点とされています。
リスクの源泉としての側面
モメンタム戦略が生み出すリターンは、単なるフリーランチ(リスクのない利益)ではない可能性も指摘されています。グリフィン、ジー、マーティンによる2003年の国際市場を対象とした研究は、モメンタムの収益が景気サイクルと関連しており、マクロ経済的なリスクを引き受けたことへの対価である可能性を示唆しています [6]。つまり、モメンタム戦略は、特定の経済状況下で大きな損失を被るリスクを内包しているからこそ、平均的に高いリターンを生む、というわけです。
非対称性と摩擦の視点
なぜ、産業レベルでの「勢い」は、市場で簡単には修正されずに、超過リターンの源泉となり得るのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:情報の伝達速度の非対称性
産業モメンタムが生まれる根源には、情報の伝達と浸透における「速度の非対称性」が存在します。
ある産業に影響を与える重要なファンダメンタル情報(例えば、画期的な技術革新や、有利な規制変更など)が発生したとしても、その情報が市場参加者全員に瞬時に、かつ均等に理解されるわけではありません。
ホンとスタインが提唱した理論モデルが示すように、情報はまず一部の専門家や注意深い「ニュースウォッチャー」に届き、彼らの取引によって価格に反映され始めます [3]。その後、その初期の価格変動を見た他の投資家(トレンドを追う「モメンタムトレーダー」)が追随することで、価格のトレンドは時間をかけて形成されていきます。
この情報の拡散プロセスの「遅さ」という非対称性こそが、モメンタムという現象の本質です。産業レベルの情報は、個別企業の情報よりも複雑でマクロ的なため、市場全体に浸透するのにより長い時間を要する可能性があります。この非対称性、すなわち情報の価値が価格に完全に織り込まれるまでのタイムラグを利用することが、産業モメンタム戦略における収益機会の源泉なのです。
Friction:「ストーリー」への固執と空売り制約という摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、産業モメンタムの存続を許している、より強力で根深い摩擦が存在します。
1.「ストーリー」への固執という認知的摩擦
産業には、しばしば強力で持続的な「ストーリー(物語)」が付随します。「AI革命」や「再生可能エネルギーへの移行」といったポジティブなストーリーは、多くの投資家を惹きつけ、長期的な買い需要を生み出します。逆に、「斜陽産業」や「構造不況」といったネガティブなストーリーは、投資家を遠ざけ、長期的な売り圧力となります。
この「ストーリーへの固執」という認知的な摩擦は、投資家が企業のファンダメンタルズやバリュエーションを冷静に分析することを妨げ、トレンドを過度に長引かせる原因となります。たとえ割高になってもポジティブなストーリーを持つ産業は買われ続け、割安になってもネガティブなストーリーを持つ産業は売られ続けるのです。この非合理的な行動が、モメンタム・アノマリーが簡単には消滅しない土壌を提供しています。
2.空売り制約という物理的な摩擦
モメンタム戦略からリターンを得るためには、勝ち組を「買う」だけでなく、負け組を「空売りする」ことが極めて重要です。しかし、パフォーマンスが悪い産業には、しばしば財務的に苦境に陥っている、流動性の低い小型株が多く含まれています。
これらの銘柄は、空売りのための株式を借りることが困難であったり、非常に高いコスト(貸株料)がかかったりします。この「空売り制約」という物理的な摩擦は、負け組産業の株価が適正な水準以上に割高なままで放置される原因となり、裁定取引を不完全にします。この摩擦があるからこそ、負け組を空売りすることで得られるリターンが市場に残り続けるのです。
総括
・産業モメンタムとは、過去にパフォーマンスが良かった産業が、将来も勝ち続ける傾向があるというアノマリーです [2]。
・その収益性は、個別銘柄のモメンタムに匹敵するほど強力でありながら、売買回転率が低く、取引コストを抑制しやすいという長所を持ちます。
・アノマリーの背景には、産業レベルの情報が市場にゆっくりと浸透していく「情報の非対称性」や、投資家が特定の「ストーリー」に固執する「認知的摩擦」が存在すると考えられています [3]。
・一方で、全てのモメンタム戦略と同様に、市場の急な反転局面で壊滅的な損失を被る「モメンタム・クラッシュ」のリスクを常に内包しており、そのリターンは景気サイクルリスクの対価である可能性も指摘されています [5, 6]。
用語集
産業モメンタム (Industry Momentum) 過去のリターンが高かった産業が、将来も高いリターンを生む傾向があるというアノマリー。
モメンタム効果 (Momentum Effect) 過去の価格トレンドが継続する傾向。一般的には、過去の勝者(Winners)が勝ち続け、過去の敗者(Losers)が負け続ける現象を指す。
アノマリー (Anomaly) 現代ファイナンス理論の常識では説明できないが、市場で経験的に観測されるリターンの規則性。
ロング・ショート戦略 割安と判断した資産を買い持ち(ロング)し、同時に割高と判断した資産を空売り(ショート)する投資戦略。
売買回転率 (Turnover) 一定期間内に、ポートフォリオ内の資産がどの程度の割合で入れ替えられたかを示す指標。高いほど取引が頻繁であることを意味する。
モメンタム・クラッシュ (Momentum Crash) 市場が急落し、その後急反発する特定の局面で、モメンタム戦略が突如として大きな損失を出す現象。
裁定取引 (Arbitrage) 同一の価値を持つ資産間で価格差が生じた際に、割安な方を買い、割高な方を売ることで、リスクなく利益を得ようとする取引。
景気サイクル 好況、後退、不況、回復というように、経済活動が周期的に拡大と縮小を繰り返す循環のこと。
ドローダウン (Drawdown) ポートフォリオの資産価値が、過去の最高値から下落した際の、その下落率のこと。
シャープレシオ (Sharpe Ratio) リターンを、そのリターンを得るために取ったリスクの大きさで割った値。リスク調整後のパフォーマンスを測る指標。
参考文献一覧
[1] Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65-91.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x
[2] Moskowitz, T. J., & Grinblatt, M. (1999). Do industries matter?. The Journal of Finance, 54(5), 1607-1640.
https://doi.org/10.1111/0022-1082.00146
[3] Hong, H., & Stein, J. C. (1999). A unified theory of underreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets. The Journal of Finance, 54(6), 2143-2184.
https://doi.org/10.1111/0022-1082.00184
[4] Asness, C. S., Moskowitz, T. J., & Pedersen, L. H. (2013). Value and Momentum Everywhere. The Journal of Finance, 68(3), 929-985.
https://doi.org/10.1111/jofi.12021
[5] Daniel, K., & Moskowitz, T. J. (2016). Momentum crashes. Journal of Financial Economics, 122(2), 221-247.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.12.002
[6] Griffin, J. M., Ji, X., & Martin, J. S. (2003). Momentum investing and business cycle risk: Evidence from international stock markets. The Journal of Finance, 58(6), 2515-2547.
https://doi.org/10.1046/j.1540-6261.2003.00614.x

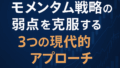
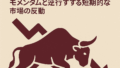
コメント