物理学には「慣性の法則」という基本原理があります。運動している物体は、外部から力が加わらない限り、その運動を続けようとする、というものです。興味深いことに、金融市場にもこれとよく似た現象が存在することが、多くの学術研究によって示されています。それが「モメンタム効果」です。
モメンタム効果とは、過去数ヶ月から1年程度の期間において、良好なパフォーマンスを上げた資産(勝者)は、その後の数ヶ月間も良好なパフォーマンスを続ける傾向があり、逆に、不振だった資産(敗者)は、その後も不振が続く傾向がある、というアノマリーを指します。
これは、効率的市場仮説(EMH)が想定するランダムウォークの世界とは相容れない、市場の非効率性を示唆する強力なエッジの一つです。本稿では、このモメンタム効果がどのように発見され、どのように測定され、また、なぜこのような現象が発生するのかについて、その強力な根拠となる学術論文を基に解説します。
モメンタム効果の発見:Jegadeesh & Titman (1993)の衝撃
モメンタム効果に関する議論は、すべてこの論文から始まったと言っても過言ではありません。1993年に発表されたジェガディッシュとティットマン(Jegadeesh & Titman)による論文「Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency」は、金融学界に大きな衝撃を与えました。
彼らは、1965年から1989年までの米国株式市場のデータを使い、シンプルなテストを行いました。まず、全銘柄を過去3ヶ月から12ヶ月のリターンに基づいて10個のグループ(デシル)に分類します。そして、最もリターンが高かった上位10%の「勝者ポートフォリオ」を買い、最もリターンが低かった下位10%の「敗者ポートフォリオ」を売る、という戦略を構築しました。
その結果は驚くべきものでした。この勝者買い・敗者売り戦略は、市場リスク(ベータ)を考慮してもなお、月平均で約1%の統計的に有意な超過リターンを生み出したのです。これは年率に換算すれば12%を超えるリターンであり、当時の金融理論では説明のつかない、明らかな異常(アノマリー)でした。この発見は、市場が必ずしも効率的ではないという強力な証拠となり、その後の行動ファイナンス研究の爆発的な発展を促すきっかけとなりました。
モメンタムの算出と可視化:テクニカル指標としてのアプローチ
では、この「勢い」は具体的にどのように測定されるのでしょうか。今では多くのトレーディングプラットフォームで、「モメンタム」という名のテクニカル指標が標準で搭載されています。これは通常、以下のいずれかの計算式に基づいています。
計算式1:Rate of Change (ROC) モメンタム = (現在の価格 / N期間前の価格) × 100
この計算式では、結果が100を上回っていれば価格はN期間前より上昇(プラスのモメンタム)、100を下回っていれば下落(マイナスのモメンタム)していることを示します。100からの乖離が大きいほど、勢いが強いと解釈できます。
計算式2:価格差 モメンタム = 現在の価格 – N期間前の価格
こちらは単純な価格差で勢いを測定します。結果が0より大きければプラスのモメンタム、0より小さければマイナスのモメンタムとなります。
これらの指標をチャートに表示すると、価格の勢いを視覚的に捉えることができます。 指標が基準線(100または0)を上抜く/下抜くタイミングや、指標の傾きの変化から、トレンドの加速・減速を読み取ることが可能です。
本来のモメンタム測定法:クロスセクションでのアプローチ
ここで一つ、とても重要な注意点があります。前項で紹介したテクニカル指標としてのモメンタムと、ジェガディッシュとティットマンの論文で用いられたモメンタムの測定法は、似て非なるものです。
- テクニカル指標: ある一つの銘柄の価格の勢いを、時間軸に沿って時系列で測定する「絶対的」な勢いの指標です。
- 論文の測定法: ある特定の時点において、市場に存在する多数の銘柄の勢いを比較し、ランキング付けする「相対的」な勢いの指標です。
学術研究でモメンタム効果を検証する際のプロセスは、以下のようになります。
- ユニバースの定義: まず、分析対象となる銘柄群(例:米国市場の全普通株)を決定します。
- ルックバック期間リターンの計算: 各銘柄について、過去Nヶ月間(例:過去12ヶ月)のリターンを計算します。(多くの場合、直近1ヶ月は短期的なリバーサル効果を避けるために除外されます)
- ランキング付け: 計算したリターンに基づき、ユニバース内の全銘柄を高い順から低い順へと並べ替えます。
- ポートフォリオの組成: ランキング上位10%を「勝者ポートフォリオ」、下位10%を「敗者ポートフォリオ」としてグループ分けします。
このように、学術的なモメンタム戦略の核心は、個別銘柄の絶対的な勢いではなく、市場全体における「相対的な勝ち組と負け組」を特定する、クロスセクショナルなアプローチにあるのです。
なぜモメンタムは存在するのか?:2つの行動ファイナンス理論
ジェガディッシュとティットマンが現象を発見して以来、多くの研究者が「なぜモメンタムは存在するのか?」という謎の解明に挑んできました。現在、その説明として特に有力視されているのが、投資家の心理的なバイアスや、市場の情報伝達の構造に着目した、以下の2つの行動ファイナンス理論です。
理論1:投資家心理による過剰/過小反応(Daniel, et al., 1998)
ケント・ダニエル、デビッド・ハーシュライファー、アヴニドラ・サブラマニヤムによるこの理論は、モメンタムの源泉を投資家の非合理的な心理に求めます。彼らは、投資家が持つ2つの主要なバイアスを指摘しました。
一つは、自身の情報や分析能力に対する「自信過剰」です。もう一つは、成功は自分の手柄、失敗は不運(他人)のせいだと考える「自己帰属バイアス」です。これらのバイアスにより、投資家は良いニュース(例:好決算)が出た際に、その情報を過小評価してしまいがちです(初期の過小反応)。株価はすぐには全ての情報を織り込まず、時間をかけてゆっくりと上昇していきます。これがモメンタムの前半部分を形成します。そして、株価が上昇し続けると、自己帰属バイアスによって投資家は自身の判断が正しかったと確信を深め、さらなる買いを呼び込み、最終的にはバブルのような過剰反応を引き起こす、と説明されています。
理論2:情報の拡散速度の遅れ(Hong and Stein, 1999)
ハリソン・ホンとジェレミー・スタインは、異なるタイプの投資家間の相互作用からモメンタムが発生するという、精緻なモデルを提唱しました。彼らは市場参加者を2種類に分類します。
- ニュースウォッチャー: 企業のファンダメンタルズに関する私的な情報を分析するが、過去の価格トレンドには注意を払わない投資家。
- モメンタムトレーダー: ファンダメンタルズは分析せず、過去の価格トレンドのみを追いかける投資家。
このモデルでは、まずニュースウォッチャーが新しい情報に反応しますが、その情報は市場全体にゆっくりとしか広がりません。これにより、株価の初期の緩やかなドリフト(価格変動)が生まれます。次に、モメンタムトレーダーがこの初期ドリフトを「トレンドの始まり」として検知し、追随買いを入れます。この行動がトレンドをさらに増幅させ、価格を一定方向に押し進める力となるのです。つまり、異なる情報を持つ投資家グループ間の「情報の伝達の遅れ」そのものが、モメンタム効果を生み出すと説明されています。
結論:モメンタム効果の含意
モメンタム効果は、単なるチャート上のパターンではなく、学術的にその存在が繰り返し確認されてきた、市場における強力なアノマリーです。その源泉は、人間の認知バイアスや、市場の構造的な情報伝達の非効率性といった、根深い要因にあると考えられています。
もちろん、これは決して「聖杯」ではありません。モメンタム効果を利用した戦略には、特有のリスクや弱点が存在します。
次回の記事では、このモメンタム効果を、どのようにして具体的なトレーディング戦略へと落とし込むのか、その古典的なアプローチを解説しつつ、その戦略が抱える致命的な「アキレス腱」についても、深く掘り下げていきます。
用語集と補足
クロスセクション vs タイムシリーズ・モメンタム
タイムシリーズ(時系列)モメンタム:「その銘柄自身の過去と現在を比べる」ことで勢いを測ります。例えば、ある銘柄の現在の価格が過去200日間の平均価格より上にあれば、それはプラスのタイムシリーズ・モメンタムがある、と判断します。一般的なテクニカル指標(移動平均やROCなど)が測っているのは、主にこちらのモメンタムです。
クロスセクション(横断的)モメンタム:「ある同じ時点において、市場にいる多数の銘柄どうしを比較し、順位付けする」ことで勢いを測ります。言わば、「クラス全員のテストの点数を並べて、誰が1位で誰が最下位かを見る」ようなアプローチです。
注意点: 本稿で扱った学術的な「モメンタム効果」は、基本的に後者のクロスセクション・モメンタムを指します。この区別は、モメンタム戦略を正しく理解する上で重要です。
アノマリー (Anomaly)
既存の金融理論(特に効率的市場仮説)では説明することが難しい、市場で一貫して観測されるリターンの偏りや規則性のことです。いわば、金融理論という「常識」に対する「例外」や「異常」と言えます。モメンタム効果は、数あるアノマリーの中でも非常に強力なもので、研究が盛んに行われているものの一つです。
効率的市場仮説 (EMH) / ランダムウォーク
「市場の価格は、利用可能な全ての情報を即座にかつ完全に織り込んでいるため、将来の価格変動を予測して利益を上げ続けることは不可能である」という考え方です。この仮説が正しければ、株価の動きは過去の動きとは無関係な「ランダムウォーク(酔歩)」となり、エッジは存在しません。モメンタム効果の発見は、この仮説に対する最も強力な反証の一つとされています。
デシル (Decile)
ある指標(例えば、過去12ヶ月のリターン)でソート(ランキング付け)した銘柄群を、均等に10個のグループに分けたものです。例えば、1000銘柄をリターンの高い順に並べた場合、上位100銘柄が「第10デシル(最上位デシル)」、次の100銘柄が「第9デシル」となります。学術研究では、この最上位デシルを「勝者ポートフォリオ」、最下位の「第1デシル」を「敗者ポートフォリオ」として、その後のパフォーマンスを比較することが一般的です。
市場リスク(β)と超過リターン(α)
β(ベータ):市場全体(例:TOPIX)の動きに対して、ある銘柄がどれだけ敏感に反応するかを示す感応度です。βが1.5なら、市場が1%上昇した際に、その銘柄は平均して1.5%上昇する傾向があることを意味します。いわば「市場の潮の流れにどれだけ乗っているか」を示す指標です。
α(アルファ):そのβで説明される市場全体の動きでは説明できない、銘柄固有の超過リターンを指します。論文で「市場リスクを考慮してもなお、月次1%のリターンが観測された」と記述されている場合、それはβの影響を差し引いた後でも、純粋なαが月次1%残った、という意味です。真のエッジとは、このαを生み出す能力に他なりません。
統計的有意性 (Significance)
観測されたリターン(例:月次+1%)が、単なる偶然のブレ(誤差)ではなく、統計的に意味のある結果である可能性がどの程度高いかを示す指標です。論文では、t値(t-statistic)やp値(p-value)で示されます。直感的には、t値が概ね2以上(p値が5%以下)であれば、「偶然とは考えにくく、統計的に意味のある結果だ」と判断されるのが一般的です。
ルックバック期間とスキップ月 (Skip-month)
ルックバック期間は、モメンタムを測定するために遡る過去の期間を指します(例:過去12ヶ月)。 スキップ月は、そのルックバック期間の計算から、直近の1ヶ月を除外する学術的な慣習のことです。例えば、過去12ヶ月のリターンでランキングを作る際、実際には「12ヶ月前から1ヶ月前まで」の11ヶ月間のリターンを使います。これは、次項の「短期リバーサル効果」というノイズを避けるための、実務的な工夫です。
ユニバース (Universe)
戦略の構築や検証の対象となる銘柄の全集合のことです。例えば、「米国の上場普通株」「日本の時価総額上位500銘柄」のように定義されます。ユニバースの定義が変われば、当然、戦略のパフォーマンスも変わるため、論文を読む際はどのようなユニバースで検証されたのかを確認することが重要です。
短期リバーサル効果 (Short-term Reversal)
1週間から1ヶ月といったごく短い期間においては、価格の動きが反転しやすい、つまり「直近の勝者が反落し、敗者が反発しやすい」というアノマリーです。これはモメンタム効果とは逆の現象であり、多くの場合は市場参加者の過剰反応とその修正によって生じると考えられています。モメンタム戦略で「スキップ月」を設けるのは、この短期的な逆張りの動きを避けるためです。
ROC/価格差モメンタム(テクニカル指標)
Rate of Change(ROC):「現在の価格 ÷ N期間前の価格」、価格差モメンタムは「現在の価格 – N期間前の価格」で計算される、個別銘柄の絶対的な勢いを測る指標です。 注意: これらは単一銘柄の「今の勢い」を時系列で見るためのツールであり、多数の銘柄を「相対的に順位付け」する学術的なクロスセクション・モメンタムとは、目的も性質も異なります。
ドリフト (Price Drift)
新しい情報(例:好決算)が発表された後、価格が一度に全ての情報を織り込むのではなく、時間をかけて同じ方向にじわじわと動き続ける現象です。モメンタム効果の持続性を説明する際の、直感的なイメージとなります。
投資家の行動バイアス(自信過剰・自己帰属)
モメンタム効果を心理学的に説明する根拠です。自信過剰は、自分の分析や判断を過大評価してしまう傾向。自己帰属バイアスは、成功を自分の手柄、失敗を外部要因(運など)のせいにしてしまう傾向です。これらのバイアスが、良いニュースへの初期の過小反応と、その後のトレンド追随(モメンタム)を生み出すと考えられています。
情報拡散の遅れモデル(ニュースウォッチャー/モメンタムトレーダー)
モメンタム効果を市場の構造から説明する理論です。まず、ファンダメンタルズを分析する「ニュースウォッチャー」が新しい情報にゆっくりと反応し、初期の価格ドリフトが生まれます。次に、価格トレンドだけを見ている「モメンタムトレーダー」がその動きを察知して追随することで、トレンドが増幅され、持続的なモメンタムが形成される、というモデルです。
参考文献
- Daniel, K., Hirshleifer, D., & Subrahmanyam, A. (1998). Investor psychology and security market under- and overreactions. The Journal of Finance, 53(6), 1839–1885.
https://doi.org/10.1111/0022-1082.00077 - Hong, H., & Stein, J. C. (1999). A unified theory of underreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets. The Journal of Finance, 54(6), 2143–2184.
https://doi.org/10.1111/0022-1082.00184 - Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65–91.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x
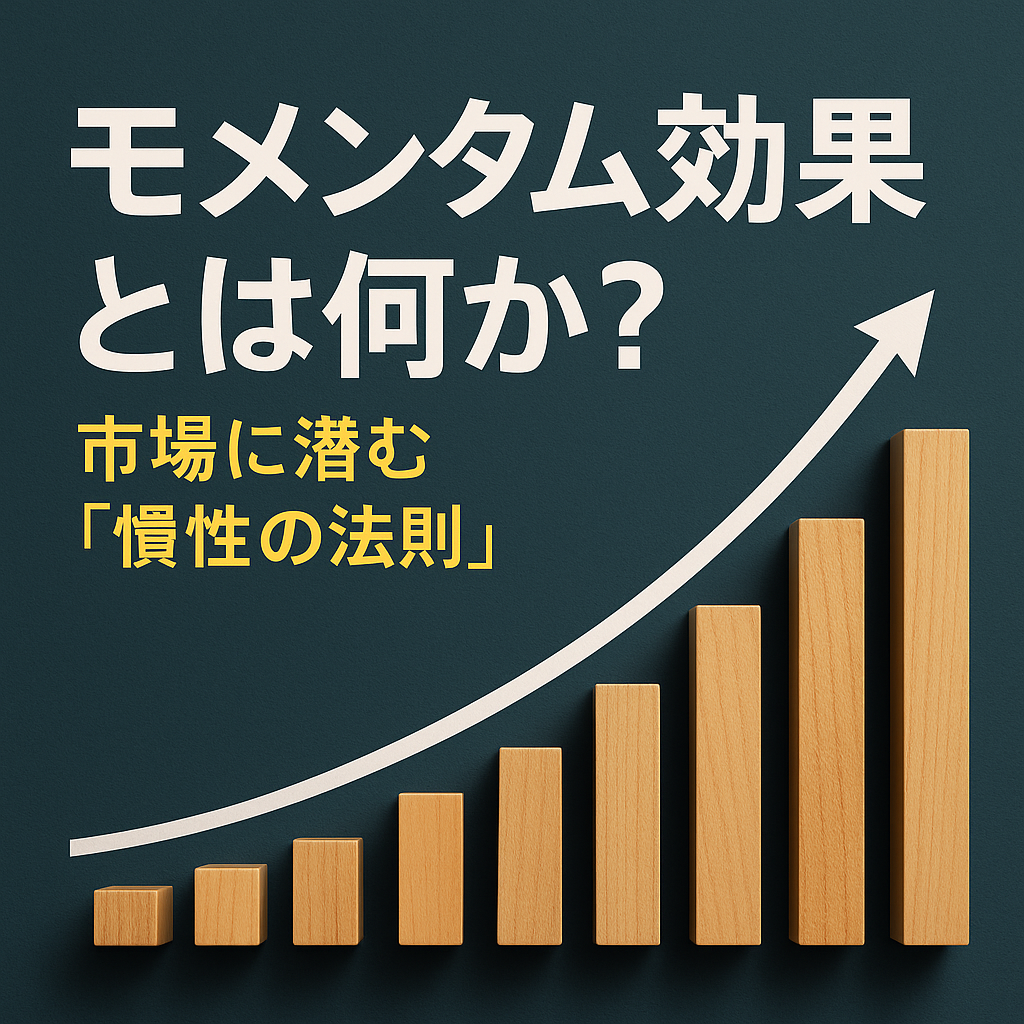
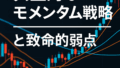
コメント