概論:市場の記憶は驚くほど短い?
「トレンドは友(Your trend is your friend)」という相場の格言があります。これは、中期的な(3ヶ月〜12ヶ月)時間軸においては、過去の勝者が勝ち続け、敗者が負け続けるというモメンタム効果が市場に存在することを示唆しています。しかし、時間軸をより短く、数週間から1ヶ月程度にまで縮めてみると、市場は全く逆の顔を見せ始めます。
それが短期リバーサル効果です。これは、ごく短期的に見て、過去の敗者(Losers)が勝者(Winners)となり、過去の勝者が敗者となる、すなわち株価が平均へと回帰(ミーン・リバージョン)する傾向があるというアノマリー(経験則)を指します。
この現象を学術的に初めて体系的に示したのが、ナラシムハン・ジェガディッシュによる1990年の論文「Evidence of predictable behavior of security returns」です [1]。彼は、1929年から1982年までの米国市場のデータを分析し、過去1ヶ月のリターンに基づいて株式をランク付けした場合、過去1ヶ月の敗者ポートフォリオが、勝者ポートフォリオを翌月に有意にアウトパフォームすることを発見しました。
これは、市場が非常に短い時間軸においては「行き過ぎる」傾向があり、その行き過ぎが翌月には修正される、ということを意味します。中期的なモメンタムとは正反対のこの短期的な反動は、市場の効率性に対する新たな問いを投げかけ、その後の金融研究に大きな影響を与えました。なぜ市場は、これほど短期的に記憶を失い、逆の動きを見せるのでしょうか。
長短の解説と損益の事例紹介
短期リバーサル効果は、高頻度で取引を行うトレーダーにとって常に魅力的なエッジの候補であり続けてきました。しかし、その輝かしいバックテストの裏には、極めて深刻な実践上の課題が潜んでいます。
長所、強み、有用な点について:市場の短期的な「行き過ぎ」を捉える
収益事例:歴史的に確認されたリターン
短期リバーサル戦略が示す理論上のリターンは、非常に強力です。ジェガディッシュの1990年の研究では、過去1ヶ月の敗者(下位10%)を買い、勝者(上位10%)を売る戦略は、1929年から1940年の期間において、年率換算で20%を超える驚異的なリターンを生み出したと報告されています [1]。この効果は、その後の様々な研究でも、時代や市場を超えて確認されています [5]。
考えられる源泉1:投資家の過剰反応バイアス
なぜこのような「行き過ぎ」と「揺り戻し」が起こるのでしょうか。その背景の一つとして、投資家の過剰反応(Overreaction)という行動バイアスが指摘されています。
デボンとセイラーによる1985年の研究は、投資家が予期せぬ、あるいは劇的なニュースに対して、その重要性を過大評価し、過剰に反応する傾向があることを示しました [2]。悪いニュースが出た銘柄は必要以上に売り叩かれ、良いニュースが出た銘柄は熱狂的に買われすぎる。短期リバーサル効果とは、この短期的な熱狂や悲観が冷め、株価がより冷静な水準へと「修正」される過程を捉えたものである、という説明です。
考えられる源泉2:流動性と価格圧力
もう一つの有力な説明は、市場のミクロ構造、特に流動性に起因するものです。
ジェガディッシュとティットマンによる1995年の研究などでは、大口の投資家が特定の銘柄を売買する際に発生する、一時的な価格圧力(Price Pressure)がリバーサルの原因である可能性が議論されています [3]。例えば、ある投資信託が大量の売り注文を出すと、その圧力によって、その銘柄の株価は本来の価値以上に下落します。そして、その売り圧力がなくなった後、株価は元の水準へと自然に反発するのです。アブラモフらの2006年の研究は、機関投資家による大口の売りが、その翌日の高いリターン(リバーサル)を予測することを実証しており、この価格圧力説を強く裏付けています [4]。
短所、弱み、リスクについて:幻のアルファ?
最大の弱点:取引コストの壁
短期リバーサル戦略が直面する、最も深刻かつ致命的な問題が取引コストです。
この戦略は、毎週末や毎月末にポートフォリオのほぼ全てを入れ替えるという、極めて高い売買回転率(ハイ・ターンオーバー)を要求します。レスモンド、シル、ゾウによる2004年の研究は、このような高頻度取引戦略の「幻想」を明らかにしました [6]。彼らの推計によれば、短期リバーサル戦略が理論上生み出すリターンの大部分は、現実の取引で発生する売買スプレッドによって完全に相殺されてしまう可能性が高いのです。
つまり、バックテスト上は大きな利益を生むように見えても、一度現実の市場で取引しようとすると、その利益は取引コストとして市場に吸い上げられてしまう、「幻のアルファ」である危険性が極めて高いのです。
非対称性と摩擦の視点
なぜ、市場は短期的に「行き過ぎ」、そしてそれがすぐに修正されるのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:取引動機の非対称性と「ノイズ」
短期リバーサル効果の根源には、市場参加者の「取引動機の非対称性」が存在します。
市場で行われる全ての取引が、企業の将来性に関する新しい情報に基づいているわけではありません。一部の取引は、投資信託の解約に伴う換金売りや、マージンコールによる強制決済といった、ファンダメンタルズとは無関係な「流動性需要」によって引き起こされます。また、一部の取引は、ニュースに過剰に反応した感情的な「パニック売り」や「熱狂買い」によってもたらされます。
これらの流動性需要や感情に基づく取引は、市場に「ノイズ(雑音)」を生み出し、株価を一時的に本来の価値から乖離させます。一方で、市場には、このノイズを見抜き、価格の歪みから利益を得ようとする、より情報に基づいた取引を行う投資家も存在します。
この、ファンダメンタルズに基づかない「ノイズ取引」と、情報に基づく「インフォームド取引」との間の非対称性こそが、リバーサル現象の本質です。ノイズ取引が引き起こした価格の「行き過ぎ」を、インフォームド取引が「修正」する。短期リバーサル戦略とは、この市場の自浄作用の過程を捉え、ノイズトレーダーに流動性を提供する対価として、リターンを得ようとする試みと言えるのです [3, 4]。
Friction:取引コストという「絶対的な壁」
短期リバーサル効果は、理論上は非常に強力なエッジに見えます。ではなぜ、このアノマリーは裁定取引によって完全に消滅しないのでしょうか。その答えは、この戦略が直面する、他のファクターとは比較にならないほど巨大な「摩擦(Friction)」にあります。
この戦略においては、一般的な手数料やスプレッドといった取引コストそのものが、議論の中心となるべき本質的な摩擦です。
1.売買スプレッドという摩擦
短期リバーサル戦略は、その性質上、「スプレッドを横断する」取引を、極めて高い頻度で繰り返すことになります。つまり、常に市場の提示する買値(ビッド)と売値(アスク)の差額であるスプレッドを、コストとして支払い続けなければならないのです。特に、リバーサル効果が大きいとされる敗者ポートフォリオに含まれる銘柄は、しばしば流動性が低く、スプレッドが非常に広い傾向があります。レスモンドらの研究が示すように、このスプレッドという摩擦コストが、理論上の超過リターンの大部分を食い潰してしまう可能性が極めて高いのです [6]。
2.マーケットインパクトという摩擦
さらに、スプレッドに加えて、自らの取引が株価を不利な方向に動かしてしまう「マーケットインパクト」という、より見えにくい摩擦も存在します。敗者銘柄を買おうとすれば株価は上がり、勝者銘柄を売ろうとすれば株価は下がる。この自らの行動が引き起こす価格変動が、実現リターンをさらに悪化させます。
結論として、短期リバーサル効果とは、取引コストという絶対的な壁によって守られた、実行不可能なアノマリーである可能性が否定できません。この巨大な摩擦があるからこそ、バックテスト上はアノマリーが存在し続け、しかし現実の市場では、誰もが簡単に利益を上げることはできないのです。
総括
・短期リバーサル効果とは、過去1ヶ月程度の短期間における敗者株が、翌月に勝者株をアウトパフォームするという、中期的なモメンタムとは逆行する現象です [1]。
・その源泉は、投資家のニュースに対する「過剰反応」 [2]や、大口取引による一時的な「価格圧力」 [3, 4]にあると考えられています。
・このアノマリーは、理論上のリターンが非常に高い一方で、戦略の性質上、極めて高い頻度の取引(ハイ・ターンオーバー)を要求されます。
・売買スプレッドやマーケットインパクトといった取引コストが、この戦略における最大の「摩擦」であり、理論上のリターンの大部分を相殺してしまうため、現実世界で利益を上げることは極めて困難であると指摘されています [6]。
用語集
短期リバーサル効果 過去のごく短期間(1週間〜1ヶ月程度)において、株価パフォーマンスが悪かった銘柄群が、その後の短期間で、パフォーマンスが良かった銘柄群を上回るリターンを上げる傾向。
モメンタム効果 過去の中期間(3ヶ月〜12ヶ月程度)において、株価パフォーマンスが良かった銘柄群が、その後も勝ち続ける傾向。短期リバーサルとは逆の現象。
アノマリー 現代ファイナンス理論の常識では説明できないが、市場で経験的に観測されるリターンの規則性。
平均回帰 (Mean Reversion) ある変数が、長期的にはその平均値に戻っていくとする統計的な性質。短期リバーサルは、株価の短期的な平均回帰現象と見なせる。
過剰反応 (Overreaction) 投資家が、特定のニュースに対して、その情報が持つ本来の価値以上に、感情的に大きく反応してしまう行動バイアス。
流動性 (Liquidity) 資産を、市場価格に大きな影響を与えることなく、どれだけ迅速に、大量に売買できるかの度合い。
価格圧力 (Price Pressure) 大口の売買注文など、ファンダメンタルズとは無関係な要因によって、株価が一時的に押し上げられたり、押し下げられたりする力。
取引コスト 金融商品を売買する際に発生する費用の総称。売買手数料、スプレッド、マーケットインパクトなどが含まれる。
売買スプレッド (Bid-Ask Spread) 金融商品の買値(ビッド)と売値(アスク)の差額。市場参加者が支払う実質的な取引コストの一つ。
売買回転率 (Turnover) 一定期間内に、ポートフォリオ内の資産がどの程度の割合で入れ替えられたかを示す指標。高いほど取引が頻繁であることを意味する。
参考文献一覧
[1] Jegadeesh, N. (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. The Journal of Finance, 45(3), 881-898.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb05110.x
[2] De Bondt, W. F., & Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact?. The Journal of Finance, 40(3), 793-805.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x
[3] Jegadeesh, N., & Titman, S. (1995). Overreaction, delayed reaction, and contrarian profits. The Review of Financial Studies, 8(4), 973-993.
https://doi.org/10.1093/rfs/8.4.973
[4] Avramov, D., Chordia, T., & Goyal, A. (2006). The Impact of Trades on Daily Volatility. The Review of Financial Studies, 19(4), 1241–1277.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhj027
[5] Subrahmanyam, A. (2018). Short-horizon overreaction and return predictability. In G. M. Constantinides, M. Harris, & R. M. Stulz (Eds.), Handbook of the Economics of Finance (Vol. 6, pp. 313-353). Elsevier.
[6] Lesmond, D. A., Schill, M. J., & Zhou, C. (2004). The illusory nature of momentum profits. Journal of Financial Economics, 71(2), 349-380.
https://doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00206-X

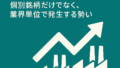

コメント