概論
伝統的な経済学は、「ホモ・エコノミカス(経済人)」という、常に合理的な意思決定を行う人間像を前提としてきました。この理想的な人間は、期待される価値や満足度(効用)を最大化するように、冷静に計算して行動すると考えられていました [1]。しかし、現実の私たちは、本当にそれほど合理的でしょうか。
含み損の株を「いつか戻るはずだ」と塩漬けにし、少し利益が出た株は慌てて利益確定してしまう。宝くじが期待値的には損だと分かっていても、一攫千金の夢を見て買ってしまう。このような、理論的には「非合理的」な行動を、なぜ私たちは取ってしまうのでしょうか。
この問いに、心理学的なアプローチから光を当て、現代の経済学とファイナンスに革命をもたらしたのが、ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーが1979年に発表したプロスペクト理論です [2]。この理論は、「人間はどのように意思決定すべきか(規範理論)」ではなく、「人間は現実にどのように意思決定しているか(記述理論)」を、実験心理学に基づいてモデル化したものです。この業績により、心理学者であったカーネマンは、後にノーベル経済学賞を受賞しました。
プロスペクト理論の核心は、主に以下の3つの人間の心理的特性に集約されます。
- 参照点依存性 (Reference Dependence): 人々は、資産の絶対額ではなく、ある「参照点(通常は取得価格など)」からの利得(gain)か損失(loss)かによって、その価値を主観的に評価する。
- 損失回避 (Loss Aversion): 人々は、利益を得る喜びよりも、同額の損失を被る苦痛を、精神的により重く(約2〜2.5倍)感じる。
- 確率加重関数 (Probability Weighting Function): 人々は、客観的な確率をそのまま評価するのではなく、主観的に歪めて認識する。特に、発生確率が非常に低い事象(大当たりの可能性や、大暴落の可能性)を、実際よりも過大に評価する傾向がある。
これらの発見は、投資家が市場で見せる様々な「非合理」な行動の背後にある、体系的な心理メカニズムを解き明かすための、強力な鍵となったのです。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について:市場の「非合理性」を解き明かす鍵
プロスペクト理論の最大の強みは、伝統的な金融理論では説明できなかった、数多くの市場アノマリーの謎を、人間の心理に基づいて見事に説明できる点にあります。
エクイティ・プレミアム・パズルの説明
その代表例が、エクイティ・プレミアム・パズルです。これは、株式の歴史的なリターンが、債券のリターンを、経済学的なリスクの観点からは説明できないほど、異常に高くあり続けてきたという謎です。
ベナーツィとセイラーによる1995年の研究は、プロスペクト理論の「損失回避」を用いることで、このパズルを説明しました [3]。彼らの主張によれば、投資家は、頻繁に株価をチェックするため、短期的な株価の下落(損失)の苦痛を何度も経験します。この強い損失回避の感情があるために、投資家は株式という資産を保有することに対して、非常に高いリターン(プレミアム)を要求する。その結果として、歴史的に高いエクイティ・プレミアムが生まれてきた、というのです。
行動ファイナンスの基礎理論として
プロスペクト理論は、その後の行動ファイナンス研究の爆発的な発展の基礎となりました。バーバリスによる2013年のレビュー論文が示すように、プロスペクト理論は、この記事のテーマであるディスポジション効果をはじめ、数多くの金融市場のパズルを解明するための、統一的な理論的枠組みを提供しています [4]。
短所、弱み、リスクについて:プロスペクト理論が予測する「負ける投資行動」
プロスペクト理論は、市場の謎を解き明かす強力なツールであると同時に、多くの投資家がなぜ損失を出すのか、その行動パターンを冷徹に予測します。
損失事例:ディスポジション効果
プロスペクト理論が予測する最も代表的で、かつ多くのトレーダーにとって耳の痛い投資行動がディスポジション効果です。
これは、利益が出ている資産(winners)は早すぎる段階で売却して利益を確定し、損失が出ている資産(losers)は売却を先延ばしにして保有し続けるという、体系的なバイアスを指します。シェフリンとスタットマンによる1985年の論文で、この現象は名付けられ、プロスペクト理論によって説明されました [5]。
なぜ、このような「損大利小」ならぬ「利小損大」の行動を取ってしまうのでしょうか。プロスペクト理論の価値関数によれば、人々は「利得」の領域ではリスク回避的になり(確実な利益を早く手に入れたい)、逆に「損失」の領域ではリスク愛好的になる(損失を取り戻すためのギャンブルに出やすい)からです。この非合理的な行動パターンこそが、多くの投資家が市場で損失を被る、主要な原因の一つなのです。
理論の限界と発展
プロスペクト理論は画期的でしたが、その最初のバージョン(1979年版)には、いくつかの理論的な問題点も指摘されていました。この点を克服するために、トベルスキーとカーネマンは1992年に、確率加重関数などをより精緻化した累積プロスペクト理論を発表し、理論を発展させました [6]。このことは、この強力な理論でさえ、現実の複雑な意思決定を完全に記述するための、発展途上のモデルであることを示しています。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、プロスペクト理論が描き出す人間の意思決定は、これほどまでに「非合理」で、かつ「非対称」なのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:価値観の「S字カーブ」という非対称性
プロスペクト理論の核心は、人間の価値判断がいかに「非対称」であるかを、数学的なモデルで示した点にあります。
価値関数の非対称性
プロスペクト理論が提示する価値関数は、参照点を中心とした美しい「S字カーブ」を描きます [2]。このカーブは、二つの重要な非対称性を持っています。
- 利得と損失の非対称性:損失領域におけるカーブの傾きは、利得領域における傾きよりも遥かに急です。これが、利益を得る喜びよりも損失の苦痛を重く感じる「損失回避」の正体であり、人間の感情が本質的に非対称であることを示しています。
- リスク態度の非対称性:利得領域では、カーブは上に凸(コンケーブ)であり、これは人々が「リスク回避的」になることを意味します(確実な利益を好む)。一方で、損失領域では、カーブは下に凸(コンベックス)であり、これは人々が「リスク愛好的」になることを意味します(損失を取り戻すためのギャンブルを好む)。
確率認識の非対称性
同様に、確率加重関数も、客観的な確率(45度線)に対して、非対称に歪んでいます。私たちは、低い確率を過大評価し、中程度から高い確率を過小評価するのです。
この二重の非対称性こそが、ディスポジション効果 [5]のような、一見すると不可解な投資行動の源泉です。この非対称な心理的OSの存在を理解し、自らの意思決定を客観視すること、そして市場の他の参加者がこのバイアスに支配されていることを見抜くことが、エッジの源泉となり得るのです。
Friction:「参照点」への固執という認知的摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、プロスペクト理論が明らかにするのは、私たちの意思決定プロセスそのものに内在する、より根深い「摩擦」です。
「参照点」への固執という認知的摩擦
プロスペクト理論によれば、私たちのあらゆる判断は、ある「参照点」を基準に行われます。トレーディングにおいては、多くの場合、その銘柄の「取得価格」が、この強力な参照点として機能します。
合理的な投資家であれば、ある株式を保有し続けるべきかどうかの判断は、その株式の将来性のみに基づいて行われるべきであり、自分がいくらで買ったか(取得価格)は、本来は何の関係もないはずの「埋没費用(サンクコスト)」です。
しかし、プロスペクト理論が示すように、私たちの心は、この「参照点」という過去の情報に強く縛り付けられてしまいます。これが、合理的な判断を妨げる、極めて強力な「認知的な摩擦」として機能するのです。含み損の銘柄を損切りできないのは、「損失を確定させたくない」という感情が、将来性の分析という合理的な思考を上回ってしまうからです。この摩擦が、ディスポジション効果 [5]を生み出し、多くの投資家を損失へと導くのです。
総括
・プロスペクト理論は、伝統的な経済学が前提とした「合理的な人間像」を覆し、人々が実際に行う意思決定を記述した、行動経済学の基礎理論です [2]。
・その核心は、人々が「参照点」からの利得と損失で価値を判断し、利益の喜びより損失の苦痛を重く感じる「損失回避」という非対称な心理を持つ点にあります。
・この理論は、なぜ株式のリターンが歴史的に高かったのか(エクイティ・プレミアム・パズル)[3]や、なぜ投資家が利益の出た株を早く売り、損失の出た株を持ち続けるのか(ディスポジション効果)[5]といった、市場の大きな謎を説明することができます。
・プロスペクト理論が示す認知バイアスは、多くの投資家が市場で損失を被る原因であると同時に、そのメカニズムを理解し、自らの行動を律する者にとっては、エッジの源泉となり得るのです。
用語集
プロスペクト理論 (Prospect Theory) 不確実性のある状況下での人間の意思決定を、心理学的な実験に基づいてモデル化した理論。「プロスペクト」とは「くじ」や「見込み」を意味する。
期待効用理論 (Expected Utility Theory) 人々は金額の期待値を最大化するのではなく、その金額から得られる「効用(満足度)」の期待値を最大化するように行動するという、合理的な意思決定モデル。
価値関数 (Value Function) プロスペクト理論の中核をなす、参照点からの利得と損失に対する、主観的な価値(満足度)の変化を示すS字型の関数。
確率加重関数 (Probability Weighting Function) 人々が客観的な確率を、主観的にどのように歪めて認識するかを示す関数。低い確率を過大評価し、中〜高確率を過小評価する傾向を示す。
参照点 (Reference Point) 利得と損失を判断するための基準となる点。トレーディングにおいては、しばしば株式の取得価格がこれにあたる。
損失回避 (Loss Aversion) 同じ金額であれば、利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛の方を精神的に2倍以上重く受け止めてしまうという、人間の非対称な心理的傾向。
ディスポジション効果 (Disposition Effect) 投資家が、利益の出ている資産は早すぎる段階で売却し、損失の出ている資産は売却を先延ばしにして保有し続けるという、体系的な行動バイアス。
エクイティ・プレミアム・パズル 株式の歴史的なリターンが、債券のリターンを、伝統的な経済学のリスク理論では説明できないほど、異常に高くあり続けてきたという金融市場の謎。
行動ファイナンス 心理学の知見を用いて、金融市場における人々の非合理的な意思決定や、それに起因する市場の非効率性を分析する学問分野。
ヒューリスティック (Heuristic) 人々が複雑な問題に対して、経験則などに基づき、直感的に素早く答えを導き出す思考のショートカットのこと。しばしば体系的なバイアスの原因となる。
参考文献一覧
[1] von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press.
https://doi.org/10.1515/9781400829460
[2] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
https://doi.org/10.2307/1914185
[3] Benartzi, S., & Thaler, R. H. (1995). Myopic loss aversion and the equity premium puzzle. The Quarterly Journal of Economics, 110(1), 73-92.
https://doi.org/10.2307/2118511
[4] Barberis, N. (2013). Thirty years of prospect theory in economics: A review and assessment. Journal of Economic Perspectives, 27(1), 173-96.
https://doi.org/10.1257/jep.27.1.173
[5] Shefrin, H., & Statman, M. (1985). The disposition to sell winners too early and ride losers too long: Theory and evidence. The Journal of Finance, 40(3), 777-790.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb05002.x
[6] Tversky, A., & Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), 297-323.
https://doi.org/10.1007/BF00122574
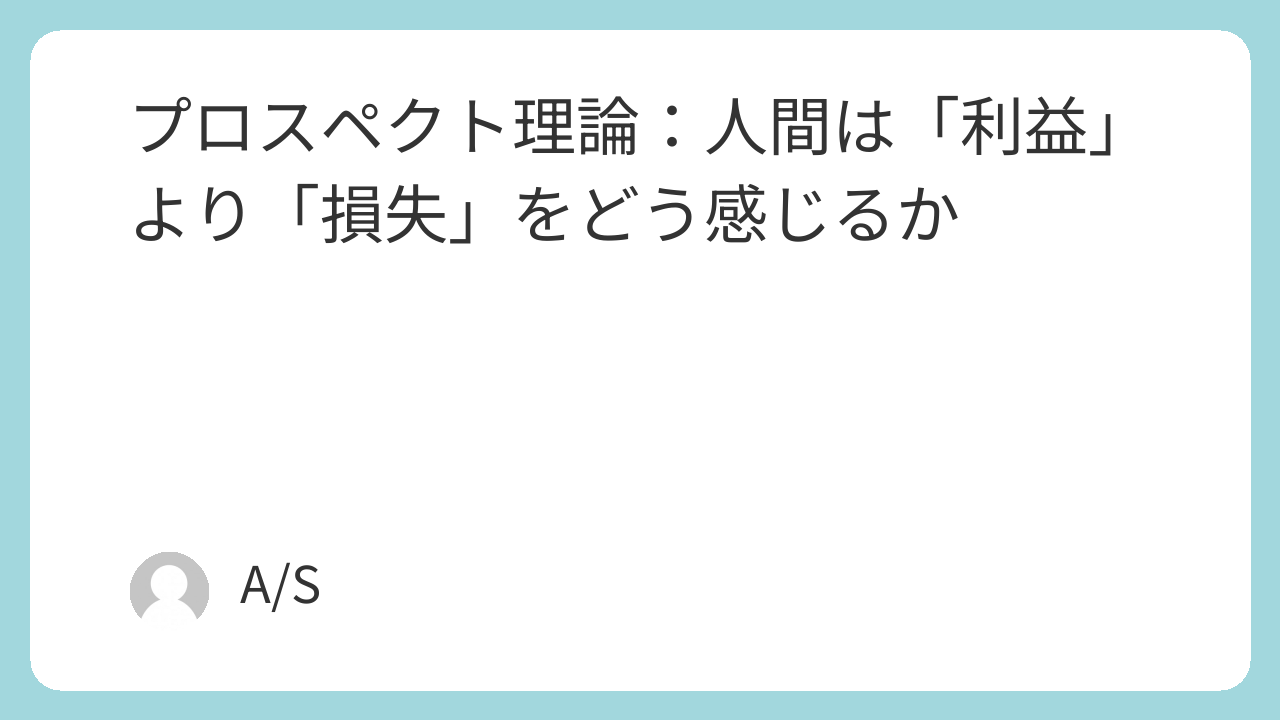
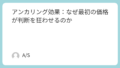
コメント