概論
「自分は、平均的なドライバーよりも運転がうまい」。多くの人が、そう信じています。統計的にはありえないにも関わらず、私たちは自分の能力や知識を、客観的な事実以上に高く評価してしまう傾向があります。この、人間の心に深く根ざした認知バイアスこそが、自信過剰バイアス(Overconfidence Bias)です。
トレーディングの世界において、このバイアスは、数ある認知バイアスの中でも最も致命的なものの一つとされています。自信過剰バイアスとは、トレーダーが、自らの知識の正確さ、情報の質、そして将来を予測する能力を、体系的に過大評価してしまう傾向を指します。
このバイアスは、単なる気の持ちようの問題ではありません。リキテンシュタイン、フィッシュホフ、フィリップスによる1982年の包括的なレビュー研究をはじめ、心理学の分野では、人間が自らの知識の精度を評価する際に、いかに体系的に「較正(キャリブレーション)がずれているか」が、数多くの実験によって示されてきました [1]。
金融の世界では、自信過剰バイアスは主に二つの形で現れます。
- 過信(Miscalibration):自分の知識や予測の精度を過大評価すること。「この株が上がる確率は90%だ」と、その確率の範囲を不当に狭く見積もってしまう。
- 優越感(Better-than-Average Effect):自分の能力が、他者(平均的な投資家)よりも優れていると信じ込むこと。
テランス・オディーンによる1998年の理論研究は、このような自信過剰な投資家が市場に存在すると、彼らは過度に取引を行い、その結果として市場のボラティリティを高め、自らの期待リターンを押し下げるだろうと予測しました [2]。自信過剰は、トレーダーを大胆にさせますが、その大胆さが、しばしば破滅的な結果を招くのです。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
短所、弱み、リスクについて:自信過剰がもたらす「負ける取引」(損失事例)
自信過剰バイアスがトレーディングのパフォーマンスに与える影響は、数多くの実証研究によって、ほぼ例外なく「破壊的」であることが示されています。
過剰な取引とリターンの悪化
自信過剰がもたらす最も直接的で、かつ致命的な結果が「過剰な取引(Excessive Trading)」です。
ブラッド・バーバーとテランス・オディーンによる2000年の金字塔的な研究は、この関係を明確に実証しました [3]。彼らは、数万口座に及ぶ個人投資家の取引データを分析し、取引頻度が最も高い投資家グループほど、その投資パフォーマンスが最も悪かったことを発見したのです。そのリターン悪化の主な原因は、頻繁な売買によって発生する取引コスト(手数料やスプレッド)でした。自信過剰な投資家は、自分の情報やスキルが優れていると信じ込んでいるため、本来なら必要のない取引を繰り返し、自らのリターンを食い潰してしまうのです。
性別と自信過剰
さらに、バーバーとオディーンは2001年の研究で、この自信過剰バイアスに性別による差があることを示し、大きな注目を集めました [4]。彼らの分析によれば、男性投資家は、女性投資家よりも約45%も高い頻度で取引を行っており、その結果として、女性投資家よりも低いリターンに甘んじていました。彼らは、この取引頻度の差が、心理学的な研究で示されている、男性の方が女性よりも自信過剰である傾向が強いことに起因すると結論付けています。
自己帰属バイアスによる悪循環
一度、自信過剰の罠に陥ると、そこから抜け出すのは容易ではありません。その背景には、自己帰属バイアス(Self-Attribution Bias)という、もう一つの認知バイアスが存在します。
ダニエル、ハーシュライファー、サブラマニヤムによる1998年の理論モデルでも論じられているように、投資家は、取引が成功した際には「自分のスキルのおかげだ」と考え、失敗した際には「運が悪かっただけだ」と、外部の要因に責任を転嫁する傾向があります [5]。この心理的なメカニズムが、自らの能力を客観的に評価することを妨げ、自信過剰をさらに強化するという、負のループを生み出してしまうのです。
長所、強み、有用な点について:自信は悪か?
これまでの議論は、自信過剰が百害あって一利なしであることを示唆します。しかし、ある程度の自信がなければ、そもそも投資家はリスクを取って市場に参加することさえできません。
グレイザーとウェーバーによる2007年の研究は、オンライン証券の顧客へのアンケート調査を通じて、投資家の自信過剰の度合い(特に過信)を直接的に測定し、それが取引量と正の相関があることを実証的に確認しました [6]。
この過剰な取引は、取引を行う本人にとってはリターンを悪化させる要因となりますが、市場全体にとっては「流動性」を供給するという、意図せざる「貢献」をしている側面もあります。しかし、それはあくまで市場システム全体から見た話であり、個々のトレーダーにとって、自信過剰が利益に繋がるという学術的な証拠は、ほとんど見当たりません。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、自信過剰はこれほどまでに人間の心に深く根付き、多くのトレーダーを破滅へと導くのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:自己評価の「非対称性」
自信過剰バイアスの根源には、自己評価における、成功と失敗の「非対称な」捉え方が存在します。
ダニエルらの研究が示したように、人間は、成功した時にはその原因を自らの「スキル」や「才能」に帰属させ、失敗した時にはその原因を「運」や「外部環境」のせいにするという、強い傾向(自己帰属バイアス)を持っています [5]。
この成功と失敗の原因分析における非対称性が、極めて危険なフィードバック・ループを生み出します。
- 取引で利益が出た場合:「やはり、私の分析は正しかった。私はトレードの才能がある」と、自信を過度に強化する。
- 取引で損失が出た場合:「今回は運が悪かっただけだ。市場が非合理だった」と、自らのスキルに対する評価を下方修正することなく、失敗の事実から目をそむける。
この非対称な学習プロセスが、トレーダーが自らの能力を客観的に評価することを妨げ、経験を積めば積むほど、その自信が実態とかけ離れていくという、悲劇的な状況を生み出すのです。このアノマリーにおける収益機会とは、まず何よりも、自らがこの非対称なバイアスに囚われていることを認識し、全ての取引結果を対称的、かつ客観的に分析する規律を持つことにあるのです。
Friction:「フィードバック」の欠如という情報の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、自信過剰というバイアスには、市場そのものの性質に起因する、極めて根深い「摩擦」が存在します。
市場からのフィードバックという情報の摩擦
ある人物がチェスの名手であるかどうかは、何局か対戦すればすぐに分かります。チェスでは、良い手は勝ちに、悪い手は負けに、明確なフィードバックとして返ってくるからです。
しかし、金融市場はそうではありません。市場から得られるフィードバックは、本質的に「ノイズ」が非常に多く、極めて曖昧です。ある取引が成功したとしても、それが本当にスキルによるものなのか、それとも単なる幸運(市場全体の上げ相場など)によるものなのかを、一回の取引結果から完璧に見分けることは不可能です。
この「市場からのフィードバックの曖昧さ」という情報の摩擦が、自信過剰バイアスが温存され、是正されにくい最大の原因です。自己帰属バイアスと相まって、トレーダーは、曖昧なフィードバックの中から、自分に都合の良い部分(成功体験)だけを拾い上げ、都合の悪い部分(失敗体験)をノイズのせいにして無視することができてしまうのです。
総括
・自信過剰バイアスとは、投資家が自らのスキルや知識の正確さを体系的に過大評価してしまう、強力な認知バイアスです [1, 2]。
・このバイアスがもたらす最も直接的な帰結は「過剰な取引」であり、それは取引コストの増大を通じて、投資家のリターンを確実に悪化させます [3]。
・実証研究によれば、より自信過剰であるとされる男性投資家は、女性投資家よりも取引頻度が高く、その結果として低いパフォーマンスに甘んじる傾向があります [4]。
・このバイアスは、成功を自分の手柄とし、失敗を運のせいにする「自己帰属バイアス」によって、経験を積んでも是正されにくいという悪循環に陥りがちです [5]。
用語集
自信過剰バイアス (Overconfidence Bias) 自らの知識、能力、判断の正確性を、客観的な事実以上に高く評価してしまう認知バイアス。
認知バイアス (Cognitive Bias) 人間の思考の癖や、思い込みによって、非合理的な判断を下してしまう心理的な傾向のこと。
ヒューリスティック (Heuristic) 人々が複雑な問題に対して、経験則などに基づき、直感的に素早く答えを導き出す思考のショートカットのこと。
過信 (Miscalibration) 自信過剰の一形態で、自らの知識や予測の「精度」を過大評価してしまうこと。「99%の確率で正しい」といった、過度に狭い信頼区間を設定する傾向。
優越感効果 (Better-than-Average Effect) 自信過剰の一形態で、自らの「能力」が、他者(平均)よりも優れていると信じ込む傾向。「自分は平均以上のドライバーだ」と多くの人が考えるのが典型例。
自己帰属バイアス (Self-Attribution Bias) 成功した場合はその原因を自分自身の内的要因(能力、努力)に求め、失敗した場合はその原因を外部の環境要因(不運、他者)に求める心理的傾向。
過剰な取引 (Excessive Trading) 合理的な水準を超えて、過度に高い頻度で金融商品を売買すること。自信過剰がその主な原因とされる。
流動性 (Liquidity) 資産を、市場価格に大きな影響を与えることなく、どれだけ迅速に、大量に売買できるかの度合い。自信過剰なトレーダーによる過剰な取引は、市場に流動性を供給する側面もある。
バックテスト (Backtest) ある投資戦略が、過去の市場データを用いてシミュレーションした場合に、どのようなパフォーマンスを示したかを検証すること。
アルファ (Alpha) 市場や他のファクターの動きでは説明できない、その資産固有の超過リターン。運用者のスキルやエッジの指標とされる。
参考文献一覧
[1] Lichtenstein, S., Fischhoff, B., & Phillips, L. D. (1982). Calibration of probabilities: The state of the art to 1980. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases (pp. 306-334). Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511809477.023
[2] Odean, T. (1998). Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average. The Journal of Finance, 53(6), 1887-1934.
https://www.jstor.org/stable/117456
[3] Barber, B. M., & Odean, T. (2000). Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors. The Journal of Finance, 55(2), 773-806.
https://doi.org/10.1111/0022-1082.00226
[4] Barber, B. M., & Odean, T. (2001). Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. The Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261-292.
https://www.jstor.org/stable/2696449
[5] Daniel, K., Hirshleifer, D., & Subrahmanyam, A. (1998). Investor psychology and security market under-and overreactions. The Journal of Finance, 53(6), 1839-1885.
https://doi.org/10.1111/0022-1082.00077
[6] Glaser, M., & Weber, M. (2007). Overconfidence and trading volume. The Geneva Risk and Insurance Review, 32(1), 1-36.
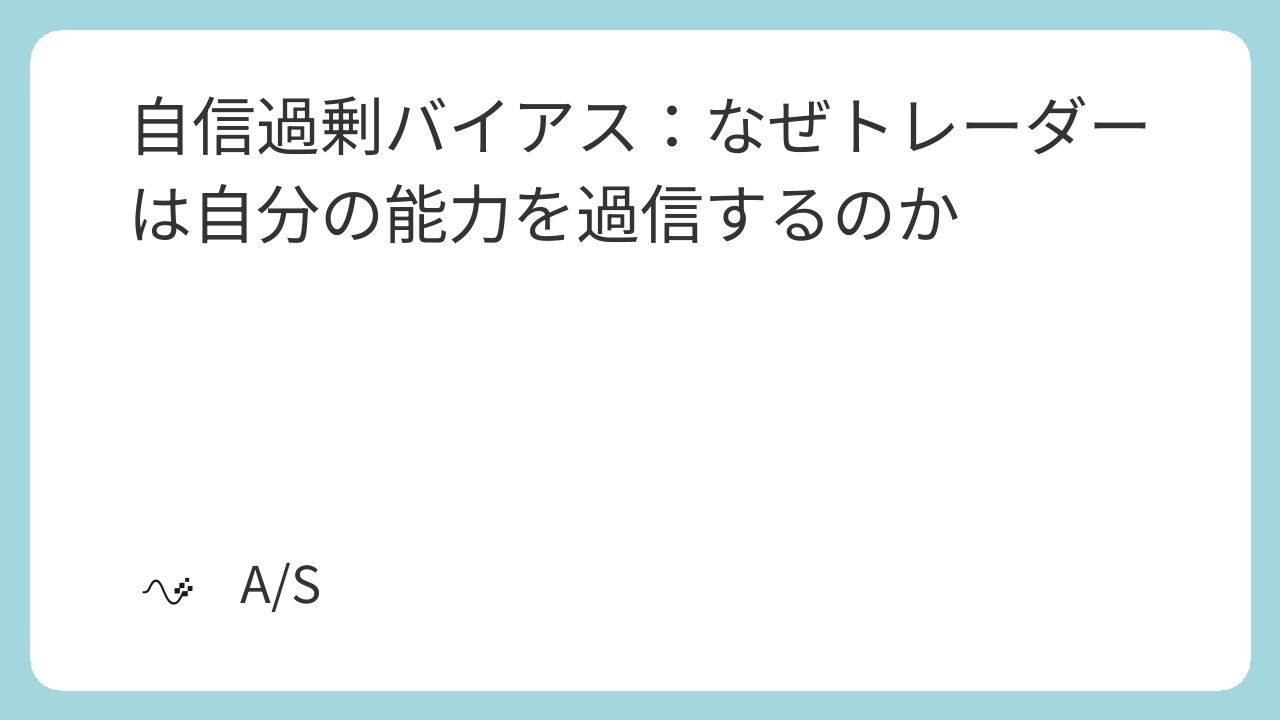
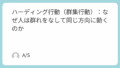
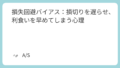
コメント