概論
道で1万円を拾う喜びと、財布から1万円を失くす悲しみ。金額は同じはずなのに、なぜ私たちは、失うことの痛みを、得ることの喜びよりも遥かに強く感じてしまうのでしょうか。この、人間の心に深く刻まれた非対称な感情反応こそが、損失回避(Loss Aversion)バイアスです。
損失回避とは、同じ金額であれば、利益を得ることから得られる心理的な満足度よりも、損失を被ることから生じる心理的な苦痛の方が、より大きく感じられるという認知バイアスを指します。
この概念は、行動経済学の金字塔である、ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによる1979年のプロスペクト理論の中核をなす発見です [1]。彼らが提示したS字型の「価値関数」は、利得と損失に対する人間の価値判断が、参照点(通常は現状)を境に非対称であることを示しました。
さらに、トベルスキーとカーネマンは1991年の研究で、この損失回避の度合いを定量化し、損失の心理的なインパクトは、同額の利益の約2倍から2.5倍にも達すると結論付けました [2]。つまり、1万円の損失の痛みは、2万円の利益の喜びに匹敵するほどの力を持っているのです。
この強力なバイアスは、「リスク回避(risk aversion)」とは区別されるべき概念です。リスク回避が、不確実な結果よりも確実な結果を好むという一般的な性質を指すのに対し、損失回避は、結果が「利益」か「損失」かによって、私たちの感情と、それに続く意思決定がいかに劇的に変化するかを説明します。
トレーディングの世界において、この損失から逃れたいという根源的な欲求は、多くの投資家を「損大利小」という最悪の行動パターンへと駆り立てる、最も危険な心理的罠の一つなのです。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
短所、弱み、リスクについて:損失回避が引き起こす不合理な行動(損失事例)
損失回避バイアスは、トレーダーに、長期的には資産を確実に蝕む、体系的に誤った行動を取らせます。
ディスポジション効果:「利小損大」のメカニズム
損失回避が引き起こす最も有名で、かつ破壊的な行動パターンがディスポジション効果です。これは、利益が出ている銘柄(Winners)は早すぎる段階で売却して利益を確定し、損失が出ている銘柄(Losers)は、損失の確定を避けるために売却を先延ばしにして保有し続けるという、体系的なバイアスを指します。
シェフリンとスタットマンによる1985年の論文は、この現象を名付け、プロスペクト理論によってそのメカニズムを説明しました [3]。
- 利益が出ている局面:投資家は「利得」の領域におり、プロスペクト理論によれば、この領域ではリスク回避的になります。目の前の確実な利益を失うことを恐れるあまり、将来さらに大きな利益になる可能性を捨てて、早すぎる「利食い」に走るのです。
- 損失が出ている局面:投資家は「損失」の領域におり、この領域ではリスク愛好的になります。「損切り」をして損失を確定させるという耐え難い苦痛を避けるため、「いつか買値に戻るはずだ」という希望的観測にすがり、さらにリスクを取り続ける(塩漬けにする)ことを選択するのです。
テランス・オディーンによる1998年の、数万口座の取引データを分析した大規模な実証研究は、このディスポジション効果が現実の市場で強力に存在することを裏付けました [4]。彼の分析によれば、投資家は、含み益のある銘柄を、含み損のある銘柄よりも、遥かに高い確率で売却していたのです。
近視眼的な損失回避と資産配分
このバイアスは、個々の取引だけでなく、ポートフォリオ全体のアセットアロケーション(資産配分)さえも歪ませます。
ベナーツィとセイラーによる1995年の研究は、「近視眼的な損失回避(Myopic Loss Aversion)」という概念を提唱しました [5]。これは、投資家が、長期的な視点ではなく、短期的な価格変動に過度に注目してしまう(近視眼的)ために、株式のようなボラティリティの高い資産の短期的な下落(損失)の苦痛を、必要以上に感じてしまうというものです。この短期的な損失への恐怖が、投資家を、長期的に見ればより高いリターンが期待できる株式への配分を過度に少なくし、より安全な債券へと資金を偏らせる原因となっている、と彼らは主張しました。
長所、強み、有用な点について:バイアスの認識という最大の防御
損失回避は、それ自体が利益を生むものではありません。しかし、この抗いがたい心理的な力の存在を深く理解することは、他の投資家が陥る罠を避け、自らの規律を守る上での決定的な「強み」となります。
自己分析のためのフレームワーク
損失回避という概念は、自らの取引行動を客観的に分析するための、強力なフレームワークを提供します。ある含み損のポジションを保有し続けているのは、その銘柄の将来性に対する合理的な分析に基づいているのか、それとも単に「損失を確定させたくない」という心理的な苦痛から逃げているだけなのか。この問いを自らに投げかけることが、不合理な塩漬けを防ぐ第一歩となります。
リスク管理ルールの理論的根拠
「損切り(ストップロス)」は、トレーディングにおける最も重要なリスク管理の原則です。損失回避バイアスは、なぜこの損切りが、これほどまでに重要で、かつ実行が困難なのかを、理論的に説明してくれます。損失の苦痛から逃れたいという強力な本能に逆らい、規律を維持するためには、事前に厳格な損切りルールを定め、それを機械的に実行する以外の方法はないのです。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、損失回避はこれほどまでに強力で、私たちの合理的な判断をいとも簡単に狂わせてしまうのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:利得と損失の「価値」の非対称性
損失回避バイアスは、その定義そのものが「非対称性」です。
プロスペクト理論が提示する価値関数は、参照点を境にして、利得と損失に対する人間の価値判断が、全く異なる、非対称な形をとることを示しています [1]。
- 価値判断の非対称性:損失領域におけるカーブの傾きは、利得領域における傾きよりも遥かに急です。これは、1万円の利益から得られる満足度と、1万円の損失から得る苦痛の大きさが、全く異なる(非対称である)ことを意味します [2]。
- リスク態度の非対称性:さらに、利得の領域では、人々は確実性を好む「リスク回避的」な行動を取るのに対し、損失の領域では、一発逆転を狙う「リスク愛好的」な行動を取りやすくなります。
この、利得と損失という二つの世界で、私たちの価値観やリスクへの態度が豹変してしまうという、根本的な心理の非対称性こそが、ディスポジション効果 [3, 4]のような、一見すると不可解な行動の源泉なのです。収益機会とは、この非対称な心理の働きを客観的に理解し、市場の他の参加者がこのバイアスに支配されていることによって生じる価格の歪みを見つけ出すことにあります。
Friction:「参照点」への固執という認知的摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、損失回避バイアスは、私たちの意思決定プロセスそのものに内在する、より根深い「摩擦」によって強化されます。
「参照点」への固執という認知的摩擦
プロスペクト理論によれば、私たちのあらゆる判断は、ある「参照点」を基準に行われます。トレーディングにおいては、多くの場合、その銘柄の「取得価格」が、この強力な参照点として機能します。
合理的な投資家であれば、ある株式を保有し続けるべきかどうかの判断は、その株式の将来性のみに基づいて行われるべきであり、自分がいくらで買ったか(取得価格)は、本来は何の関係もないはずの「埋没費用(サンクコスト)」です。
しかし、私たちの心は、この「参照点」という過去の情報に強く縛り付けられてしまいます。これが、合理的な判断を妨げる、極めて強力な「認知的な摩擦」として機能するのです。含み損の銘柄を損切りできないのは、「損失を確定させたくない」という損失回避の感情が、将来性の分析という合理的な思考を上回ってしまうからです。この摩擦が、ディスポジション効果 [3]を生み出し、多くの投資家を損失へと導くのです。
総括
・損失回避バイアスとは、プロスペクト理論の中核をなす概念であり、人間が利益の喜びよりも、同額の損失の苦痛を2倍以上強く感じるという、非対称な心理的傾向を指します [1, 2]。
・このバイアスは、トレーダーに、利益が出ている銘柄は早く売り(利小)、損失が出ている銘柄は長く保有し続ける(損大)という、ディスポジション効果と呼ばれる破壊的な行動を取らせる主要な原因です [3, 4]。
・また、より広範な資産配分においても、短期的な損失への恐怖から、長期的に期待リターンの高い株式への投資を過度に抑制させてしまう「近視眼的な損失回避」の原因となります [5]。
・損失回避は、人間の本能的な感情であり、完全に克服することは困難です。そのため、このバイアスの存在を自覚し、あらかじめ損切りなどの厳格なルールを定めて、機械的に実行することが、自らを守るための最も有効な手段となります。
用語集
損失回避 (Loss Aversion) 同じ金額であれば、利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛の方を精神的に2倍以上重く受け止めてしまうという人間の非対称な心理的傾向。
プロスペクト理論 (Prospect Theory) 不確実性のある状況下での人間の意思決定を、心理学的な実験に基づいてモデル化した理論。損失回避はその中核をなす。
期待効用理論 (Expected Utility Theory) 人々は金額の期待値を最大化するのではなく、その金額から得られる「効用(満足度)」の期待値を最大化するように行動するという、合理的な意思決定モデル。
価値関数 (Value Function) プロスペクト理論の中核をなす、参照点からの利得と損失に対する、主観的な価値(満足度)の変化を示すS字型の関数。
参照点 (Reference Point) 利得と損失を判断するための基準となる点。トレーディングにおいては、しばしば株式の取得価格がこれにあたる。
ディスポジション効果 (Disposition Effect) 投資家が、利益の出ている資産は早すぎる段階で売却し、損失の出ている資産は売却を先延ばしにして保有し続けるという、体系的な行動バイアス。
損切り (Stop-Loss) 損失が一定の水準に達した場合に、ポジションを決済して損失を確定させること。
利食い (Profit Taking) 利益が出ているポジションを決済して、利益を確定させること。
認知バイアス (Cognitive Bias) 人間の思考の癖や、思い込みによって、非合理的な判断を下してしまう心理的な傾向のこと。
エクイティ・プレミアム (Equity Premium) 株式に投資することで期待されるリターンが、債券などの安全資産のリターンをどれだけ上回っているかを示す差。
参考文献一覧
[1] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
https://doi.org/10.2307/1914185
[2] Tversky, A., & Kahneman, D. (1991). Loss aversion in riskless choice: A reference-dependent model. The Quarterly Journal of Economics, 106(4), 1039-1061.
https://doi.org/10.2307/2937956
[3] Shefrin, H., & Statman, M. (1985). The disposition to sell winners too early and ride losers too long: Theory and evidence. The Journal of Finance, 40(3), 777-790.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb05002.x
[4] Odean, T. (1998). Are investors reluctant to realize their losses?. The Journal of Finance, 53(5), 1775-1798.
https://doi.org/10.1111/0022-1082.00072
[5] Benartzi, S., & Thaler, R. H. (1995). Myopic loss aversion and the equity premium puzzle. The Quarterly Journal of Economics, 110(1), 73-92.
https://doi.org/10.2307/2118511
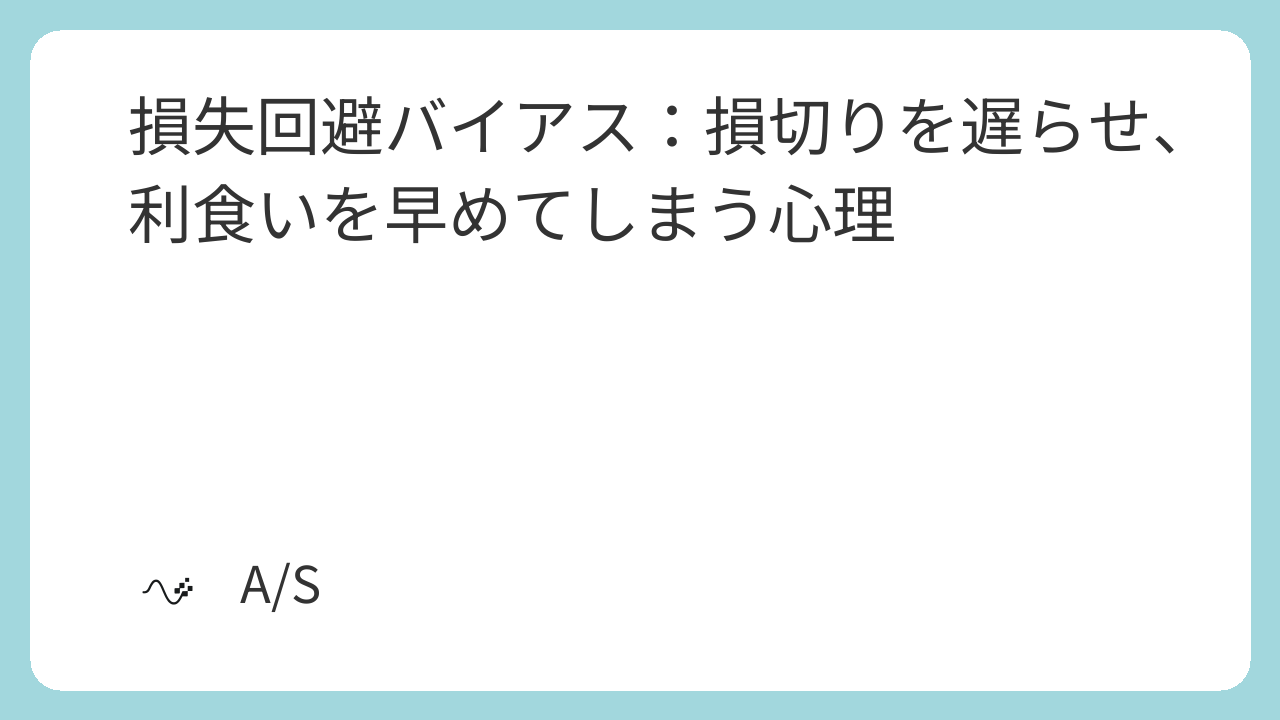
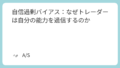
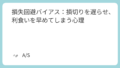
コメント