概論
「あの会社は革新的な製品を次々と生み出し、売上も急成長している。だから、この会社の株は『買い』だ」――多くの投資家が、このような直感的な判断を下した経験があるのではないでしょうか。しかし、この一見すると正しく思える判断には、人間の思考に深く根ざした、巧妙な心理的な罠が潜んでいます。
それが、代表性ヒューリスティック(Representativeness Heuristic)です。
代表性ヒューリスティックとは、ある事象の確率を、それが典型的なイメージ(ステレオタイプ)にどれだけ似ているか(代表しているか)に基づいて、直感的に判断してしまうという、思考のショートカット(ヒューリスティック)のことです。この概念は、行動経済学の父であるダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって、1974年の論文で初めて提示されました [1]。
彼らの古典的な実験に、「リンダ問題」として知られるものがあります。被験者に「リンダは31歳独身、非常に知的で、哲学を専攻していた。学生時代は差別問題や社会正義に強い関心があった」という人物像を提示します。その上で、「リンダは銀行員である」という選択肢と、「リンダは銀行員であり、かつフェミニスト活動家である」という二つの選択肢のうち、どちらの確率が高いかを尋ねます。
論理的に考えれば、後者は前者の部分集合であるため、確率が上回ることはありえません。しかし、多くの被験者は、リンダの人物像が「フェミニスト活動家」というステレオタイプを強く代表しているため、後者の方が確率が高いと直感的に判断してしまうのです。
この思考の癖が、金融市場に持ち込まれるとどうなるでしょうか。投資家は、「良い会社(高い成長率、革新的な製品、優れた経営陣)」という典型的なイメージに当てはまる企業を見つけると、それが「良い株(将来的に高いリターンを生む投資対象)」というカテゴリーを代表していると、自動的に結論付けてしまうのです。
しかし、この思考プロセスからは、投資判断において最も重要な要素である「価格(バリュエーション)」が、完全に抜け落ちています。「良い会社」であっても、その価値が既に株価に織り込まれ、あるいは過大評価されているならば、それは「悪い株」となり得るのです。
長短の解説、利益例・損失例の紹介
短所、弱み、リスクについて:「良い会社」への過剰な期待(損失事例)
代表性ヒューリスティックは、投資家を体系的に「人気の成長株を高値で買い、不人気の割安株を安値で売る」という、パフォーマンスを悪化させる行動へと駆り立てます。
「魅力的な株(Glamour Stocks)」の罠
このバイアスがもたらす最も典型的な損失事例が、「魅力的な株(グラマー・ストック)」への過剰投資です。
ラコニショック、シュライファー、ヴィシュニーによる1994年の影響力の大きい研究は、この問題を実証的に明らかにしました [2]。彼らの分析によれば、多くの投資家は、過去の高い成長率や華やかな事業内容といった特徴が、「将来も成長し続ける良い株」を代表していると信じ込み、これらのグラマー・ストックに高いプレミアムを支払います。しかし、現実はその期待を裏切ることが多く、これらのグラマー・ストックのポートフォリオは、長期的には、人気のない「バリュー株(割安株)」のポートフォリオに、体系的に劣後することが示されました。
長期リバーサル効果
代表性ヒューリスティックは、市場における長期リバーサル効果、すなわち「過去の勝者が敗者となり、敗者が勝者となる」現象の主要な説明要因と考えられています。
デボンとセイラーによる1985年の研究が示したように、過去3〜5年間にわたって素晴らしいパフォーマンスを記録した「勝者」銘柄(多くの投資家にとって「良い会社」を代表する)は、その後の3〜5年間で、市場平均を大きくアンダーパフォームする傾向があります [3]。これは、投資家が過去の成功を過度に将来に投影(外挿)した結果、株価が過大評価され、その後の長い時間をかけて、その過剰な期待が剥落していく過程であると解釈できます。
アナリスト予想の罠
この「良い会社」への過剰な期待は、専門家であるはずの証券アナリストの予想においてさえも見られます。ラポルタによる1996年の研究は、アナリストによる長期の利益成長率予想が最も楽観的な銘柄群ほど、その後の株価リターンが最も低くなるという、皮肉な結果を報告しています [4]。市場は、アナリストが描くバラ色の未来像を信じて株価を買い上げますが、その高すぎる期待に、現実の企業業績が追いつけないのです。
長所、強み、有用な点について:逆張り戦略の論理的根拠
代表性ヒューリスティックは、それに囚われる投資家にとっては罠ですが、その存在を理解する投資家にとっては、収益機会の源泉となります。
逆張り・バリュー投資戦略への応用
このバイアスを逆手に取る最も直接的な戦略が、逆張り投資、特にバリュー投資です。バリュー投資とは、本質的に、市場が代表性ヒューリスティックによって見過ごし、あるいは過度に悲観視している「良くない会社(に見える)が、実は良い株かもしれない」という非効率性を利用する戦略です [2]。
ファーマとフレンチによる2007年の研究は、一部の投資家が、成長株のような特定の特性を持つ株式に対して、合理的な理由なく、特別な「好み(tastes)」を持っている可能性を示唆しています [5]。このような非合理的な選好が、市場に価格の歪みを生み出し、それを是正しようとする合理的な投資家(アービトラージャー)に、リターンの機会を提供しているのです。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、これほどまでに単純な思考のショートカットが、市場に大きな価格の歪みを生み出し続けるのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:ステレオタイプ思考の非対称性
代表性ヒューリスティックの根源には、「ステレオタイプ(典型)」と「統計的な現実(基準率)」との間の、情報の重み付けにおける非対称性が存在します。
カーネマンとトベルスキーの研究が示したように、私たちの脳は、物事を判断する際に、地味で退屈な統計データ(基準率)よりも、鮮やかで分かりやすいステレオタイプの方に、非対称に大きな重みを置いてしまいます [1]。
金融市場においては、「急成長している革新的な企業(ステレオタイプ)」という物語は、その企業の株が、歴史的に見て、長期的には市場平均に劣後する傾向があるという「統計的な現実(基準率)」よりも、遥かに魅力的に響きます。この「物語の魅力」と「統計の退屈さ」との間の非対称性が、投資家の判断を体系的に歪ませるのです。
このアノマリーにおける収益機会とは、市場の大多数がこのステレオタイプ思考に囚われ、企業の「物語」に過剰な価格を支払っている中で、その熱狂から距離を置き、統計的な現実に立脚して、不人気で退屈に見えるが故に割安に放置されている資産を見つけ出すことにあります。
Friction:「物語」への固執という認知的摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、代表性ヒューリスティックは、人間の認知プロセスそのものに深く根差した、抗いがたい「摩擦」によって強化されます。
「物語」への固執という認知的摩擦
「良い会社」という評価は、単なるデータ分析の結果ではなく、しばしば強力な「物語(ナラティブ)」を伴います。革新的な創業者、世界を変える技術、熱狂的な顧客――これらの物語は、人間の感情に強く訴えかけ、一度信じてしまうと、それを覆すことは非常に困難です。
この「心地よい物語に固執したい」という欲求は、合理的な判断を妨げる、強力な認知的な摩擦として機能します。たとえ株価が割高な水準にあることを示すデータがあったとしても、投資家は、そのデータを無視したり、軽視したりして、自らが信じる物語を維持しようとするのです。この摩擦が、グラマー・ストックの過大評価が長期間にわたって是正されない原因となります [2]。
「価格」を無視させる情報の摩擦
代表性ヒューリスティックは、投資家の注意を、企業の「質的な側面(良い会社かどうか)」に集中させ、最も重要な定量的要素である「価格」への注意を削いでしまうという、情報の摩擦を生み出します。
投資家は、「この会社は、業界のリーダーか?」「製品は革新的か?」といった問いに夢中になるあまり、「しかし、その素晴らしい未来に対して、自分はいくら支払っているのか?」という、最も基本的な問いを忘れてしまうのです。この思考の焦点の偏りが、どんなに良い会社であっても、高値で買ってしまえば「悪い投資」になる、という単純な事実を見過ごさせてしまうのです。
総括
・代表性ヒューリスティックとは、物事の確率を、それが典型的なイメージ(ステレオタイプ)にどれだけ似ているかに基づいて直感的に判断してしまう、人間の思考のショートカットです [1]。
・金融市場では、このバイアスが「良い会社は、良い株であるに違いない」という誤った判断を誘発し、投資家を過去の成長率が高い「魅力的な株(グラマー・ストック)」への過剰投資へと駆り立てます [2]。
・この過剰な期待は、長期的には裏切られることが多く、過去の勝者銘柄が、その後に市場平均をアンダーパフォームする「長期リバーサル効果」の主要な原因であると考えられています [3]。
・このバイアスは、専門家である証券アナリストの業績予想さえも歪ませるほど強力であり [4]、その逆を行くバリュー投資戦略の有効性の根拠となっています。
用語集
代表性ヒューリスティック (Representativeness Heuristic) 物事の確率を、それが典型的なイメージ(ステレオタイプ)にどれだけ似ているかに基づいて判断してしまう認知バイアス。
ヒューリスティック (Heuristic) 人々が複雑な問題に対して、経験則などに基づき、直感的に素早く答えを導き出す思考のショートカットのこと。
認知バイアス (Cognitive Bias) 人間の思考の癖や、思い込みによって、非合理的な判断を下してしまう心理的な傾向のこと。
ステレオタイプ (Stereotype) 多くの人に共有されている、特定のグループやカテゴリーに対する、単純化され、固定化されたイメージや信念。
基準率 (Base Rate) ある事象が発生する、統計的な事前確率や基本的な頻度のこと。代表性ヒューリスティックは、この基準率を無視させる傾向がある。
過剰反応 (Overreaction) 投資家が、特定のニュースや過去のトレンドに対して、その情報が持つ本来の価値以上に、感情的に大きく、そして持続的に反応してしまうこと。
長期リバーサル効果 過去3〜5年といった長期間の株価パフォーマンスが最も悪かった銘柄群が、その後の同程度の期間で、最も良かった銘柄群を上回るリターンを上げる傾向。
バリュー株 (Value Stock) 企業のファンダメンタルズに対して、株価が割安に評価されている株式。
グロース株 (Growth Stock) 売上や利益が高い成長率を示している企業の株式。「魅力的な株(グラマー・ストック)」と重なることが多い。
ファンダメンタルズ (Fundamentals) 企業の収益力や財務状況、資産価値といった、その企業の本質的な価値を決定する基礎的条件。
参考文献一覧
[1] Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124-1131.
https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124
[2] Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. The Journal of Finance, 49(5), 1541-1578.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb04772.x
[3] De Bondt, W. F., & Thaler, R. H. (1985). Does the stock market overreact?. The Journal of Finance, 40(3), 793-805.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x
[4] La Porta, R. (1996). Expectations and the cross-section of stock returns. The Journal of Finance, 51(5), 1715-1742.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05223.x
[5] Fama, E. F., & French, K. R. (2007). Disagreement, tastes, and asset prices. Journal of Financial Economics, 83(3), 667-689.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.01.003
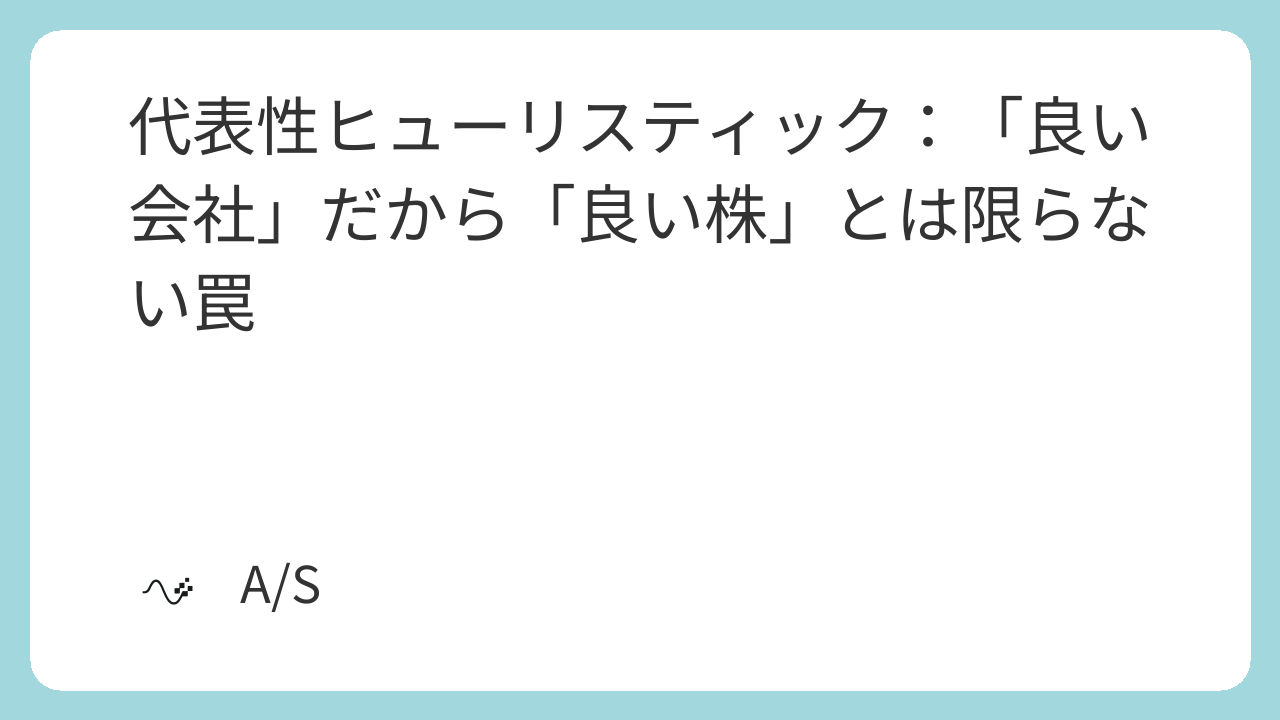
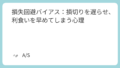
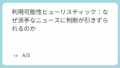
コメント