概論
「サメによる襲撃」と「飛行機事故で落下した部品による死亡」。どちらの確率が高いと思いますか。多くの人は、映画やニュースで繰り返し報じられる「サメの襲撃」の方が、遥かに起こりやすいと感じるでしょう。しかし、統計的な事実は、後者の方が確率が高いことを示しています。
なぜ、私たちの直感は、これほどまでに現実と食い違うのでしょうか。その背景にあるのが、利用可能性ヒューリスティック(Availability Heuristic)です。
利用可能性ヒューリスティックとは、ある事象の頻度や確率を判断する際に、その事例をどれだけ「思い出しやすいか(利用可能性が高いか)」に頼ってしまうという、思考のショートカット(ヒューリスティック)のことです。この概念は、行動経済学の父、エイモス・トベルスキーとダニエル・カーネマンが1973年に発表した論文によって、初めて世に知られるようになりました [1]。
彼らの古典的な実験に、次のようなものがあります。被験者に対して、「rで始まる英単語」と「3番目の文字がrである英単語」では、どちらが多いかを尋ねます。ほとんどの人は、”road”や”river”のように、rで始まる単語の方が遥かに思い出しやすいため、「rで始まる単語の方が多い」と答えます。しかし、実際には、3番目の文字がrである単語(”car”や”park”など)の方が、遥かに多いのです。
この実験が示すのは、私たちの脳が、統計的な頻度を正確に計算する代わりに、「記憶からの検索のしやすさ」という、より簡単な手がかりで確率を代用してしまう、という事実です。
この思考の癖は、金融市場において、投資家の判断を体系的に歪ませる強力なバイアスとして機能します。メディアで大々的に報じられるニュース、最近の株価の急騰や急落、あるいは友人から聞いた景気の良い話――これらの「派手で」「新しく」「感情を揺さぶる」情報は、私たちの記憶に強く残り、利用可能性が非常に高くなります。そして、私たちは、これらの目立つ情報に基づいて、市場全体のトレンドや、個別銘柄の将来性を、過大あるいは過小に評価してしまうのです。
長短の解説、利益例・損失例の紹介
短所、弱み、リスクについて:派手な情報がもたらす投資の歪み(損失事例)
利用可能性ヒューリスティックは、投資家を、統計的な根拠ではなく、その時々の「話題性」や「親近感」に基づいて、衝動的な取引へと駆り立てます。
「注目の的」銘柄への過剰投資
このバイアスが引き起こす最も典型的な損失事例が、「注目の的となっている(attention-grabbing)」銘柄への過剰投資です。
ブラッド・バーバーとテランス・オディーンによる2008年の影響力の大きい研究は、この問題を実証的に明らかにしました [2]。彼らの分析によれば、特に個人投資家は、ニュースで頻繁に取り上げられたり、取引量が急増したり、あるいは前日に異常な高騰を見せたりした、注意を引きやすい銘柄を、純粋な買い越し(net buying)する傾向が強いことを発見しました。しかし、皮肉なことに、このようにして買われた「注目の的」銘柄は、その後の株価パフォーマンスが、市場平均を有意に下回っていたのです。
「地元びいき」による分散不足
利用可能性は、情報の地理的な近さにも影響されます。私たちは、自分が住んでいる地域や国の企業に関する情報の方を、遠い国の企業の情報よりも、遥かに簡単に入手できます。
ガーマン・ヒューバーマンによる2001年の研究は、この「情報の利用可能性」が、投資家のポートフォリオを歪ませることを示しました [3]。彼は、米国の投資家が、地理的に近い企業の株式を、合理的な水準を超えて過剰に保有する「ローカル・バイアス」が存在することを発見しました。この「知っている」という安心感に基づく投資行動は、国際分散投資によるリスク低減の恩恵を放棄する、非効率なポートフォリオを生み出してしまいます。
メディア・センチメントへの過剰反応
利用可能性を操作する上で、メディアは絶大な力を持っています。ポール・テトロックによる2007年の独創的な研究は、ウォール・ストリート・ジャーナルの特定のコラムの論調(センチメント)をテキスト分析し、その影響を定量化しました [4]。その結果、コラムの論調が悲観的である日には、市場全体に下落圧力がかかり、その後の数日間で価格が反転(リバーサル)する傾向があることが示されました。これは、メディアによって増幅されたネガティブな情報が、市場に短期的な過剰反応を引き起こしていることを示唆しています。
長所、強み、有用な点について:他者の「注意力」の限界を利用する
このバイアスは、それに囚われる投資家にとっては罠ですが、その存在を理解する投資家にとっては、収益機会のシグナルとなり得ます。
逆張り戦略への応用
バーバーとオディーンの研究[2]が示した結果は、裏を返せば、「市場の注目を集めている派手な銘柄を避け、誰も話題にしていない地味で退屈な銘柄に投資する」という逆張り戦略が、有効である可能性を示唆しています。市場の大多数の参加者が、利用可能性の高い情報に飛びついている時こそ、利用可能性の低い、見過ごされた情報の中に、価値が眠っているのかもしれません。
バーバリスとセイラーによる2003年の行動ファイナンスに関するレビュー論文でも論じられているように、利用可能性ヒューリスティックは、代表性ヒューリスティックやアンカリングといった他のバイアスと相互に作用し、市場に複雑な非効率性を生み出します [5]。これらのバイアスの存在を理解し、市場のセンチメントを客観的に分析する能力こそが、群集の熱狂から距離を置き、長期的なリターンを追求するための強みとなるのです。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、私たちの判断は、これほどまでに「思い出しやすさ」に支配されてしまうのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:情報の「顕著性」の非対称性
利用可能性ヒューリスティックの根源には、情報が持つ「顕著性(Salience)」の非対称性が存在します。
私たちの周りにある全ての情報が、同じ重みで私たちの心に届くわけではありません。飛行機が墜落したというニュースは、その衝撃的な映像と共に、私たちの記憶に強烈な印象を残します。一方で、統計データが示す退屈な数字は、ほとんど記憶に残りません。この「鮮やかで感情的な情報」と「退屈で統計的な情報」との間の、心理的インパクトにおける極端な非対称性が、私たちの確率判断を歪ませるのです。
金融市場においても同様です。あるハイテク企業が画期的な新製品を発表したというニュースは、その企業の地味な財務データよりも、遥かに顕著性の高い情報です。バーバーとオディーンの研究が示すように、投資家の注意と資金は、このような顕著性の高い情報を持つ、ごく一部の銘柄に非対称に集中します [2]。
このアノマリーにおける収益機会とは、市場の大多数の参加者が、この顕著性の高い情報に注意を奪われている中で、あえて顕著性の低い、見過ごされた情報(例えば、地味な優良企業の財務諸表)の中に価値を見出す、という逆張りの思考法にあるのです。
Friction:メディアという「増幅器」の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、利用可能性ヒューリスティックは、現代の情報環境そのものに根差した、強力な「摩擦」によって増幅されます。
メディアという構造的摩擦
現代の投資家が情報に接する主要な経路は、ニュースサイトやSNSといったメディアです。しかし、メディアのビジネスモデルは、本質的に「読者の注意を引くこと」を目的としています。そのため、地味で退屈な情報よりも、派手で、衝撃的で、感情を揺さぶる情報を優先的に報道するインセンティブが常に働きます。
テトロックの研究が示すように、メディアは単に事実を報じるだけでなく、市場のセンチメントそのものを形成する力を持っています [4]。この「メディアという情報の増幅器」は、利用可能性ヒューリスティックを強化する、強力な構造的摩擦として機能します。投資家は、自らが中立的な情報を得ていると信じていても、実はメディアによってフィルタリングされ、増幅された、極めて偏った情報環境の中に置かれているのです。
探索コストという認知的摩擦
私たちの脳は、エネルギーを節約するため、常に思考のショートカットを探しています。記憶の中から簡単に思い出せる情報に基づいて判断を下すことは、認知的に見て、非常に「楽」なプロセスです。
一方で、利用可能性の低い情報、例えば、注目されていない企業の財務諸表を一から読み解いたり、メディアの論調とは逆の証拠を探したりする行為は、多大な時間と精神的なエネルギー(探索コスト)を要求します。この「探索コスト」という認知的な摩擦が、多くの投資家を、安易で手軽な、しかし偏った情報に基づく意思決定へと導いてしまうのです。
総括
・利用可能性ヒューリスティックとは、ある事象の確率を、その事例の「思い出しやすさ」に基づいて直感的に判断してしまう、人間の思考のショートカットです [1]。
・金融市場では、このバイアスが、投資家を、ニュースなどで頻繁に取り上げられる「注目の的」銘柄へと過剰に投資させる原因となり、その後の低いパフォーマンスに繋がることが示されています [2]。
・また、地理的に近いなど、情報が入手しやすいという理由だけで特定の資産に投資してしまう「ローカル・バイアス」も、このヒューリスティックの一例です [3]。
・メディアは、特定の情報の利用可能性を高める「増幅器」として機能し、市場のセンチメントに大きな影響を与えます [4]。このバイアスを乗り越えるためには、情報の顕著性に惑わされず、客観的なデータに基づいて判断する規律が求められます。
用語集
利用可能性ヒューリスティック (Availability Heuristic) ある事象の頻度や確率を、その事例の「思い出しやすさ」に基づいて判断してしまう認知バイアス。
ヒューリスティック (Heuristic) 人々が複雑な問題に対して、経験則などに基づき、直感的に素早く答えを導き出す思考のショートカットのこと。
認知バイアス (Cognitive Bias) 人間の思考の癖や、思い込みによって、非合理的な判断を下してしまう心理的な傾向のこと。
ローカル・バイアス (Local Bias) 投資家が、地理的に近い、あるいは自国籍の企業など、よく知っている(情報が利用可能な)企業の株式を、ポートフォリオの中で過剰に保有してしまう傾向。
センチメント (Sentiment) 市場参加者の総意として形成される、楽観や悲観といった市場全体の心理状態や雰囲気のこと。
分散投資 (Diversification) 異なる値動きをする複数の資産に資金を分散させることで、ポートフォリオ全体のリスクを低減させる投資手法。ローカル・バイアスは、この原則に反する。
逆張り戦略 (Contrarian Strategy) 市場の大多数の投資家の意見や行動(コンセンサス)とは逆のポジションを取る投資戦略。
ファンダメンタルズ (Fundamentals) 企業の収益力や財務状況、資産価値といった、その企業の本質的な価値を決定する基礎的条件。
アノマリー (Anomaly) 現代ファイナンス理論の常識では説明できないが、市場で経験的に観測されるリターンの規則性。
効率的市場仮説 (Efficient Market Hypothesis) 市場価格は利用可能な全ての情報を即座に織り込んでいるため、継続的に市場を上回ることはできないとする理論。
参考文献一覧
[1] Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. Cognitive Psychology, 5(2), 207-232.
https://doi.org/10.1016/0010-0285(73)90033-9
[2] Barber, B. M., & Odean, T. (2008). All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. The Review of Financial Studies, 21(2), 785-818.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhm079
[3] Huberman, G. (2001). Familiarity breeds investment. The Review of Financial Studies, 14(3), 659-680.
https://doi.org/10.1093/rfs/14.3.659
[4] Tetlock, P. C. (2007). Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market. The Journal of Finance, 62(3), 1139-1168.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01232.x
[5] Barberis, N., & Thaler, R. H. (2003). A survey of behavioral finance. In G. M. Constantinides, M. Harris, & R. M. Stulz (Eds.), Handbook of the Economics of Finance (Vol. 1, pp. 1053-1128). Elsevier.
https://doi.org/10.1016/S1574-0102(03)01027-6
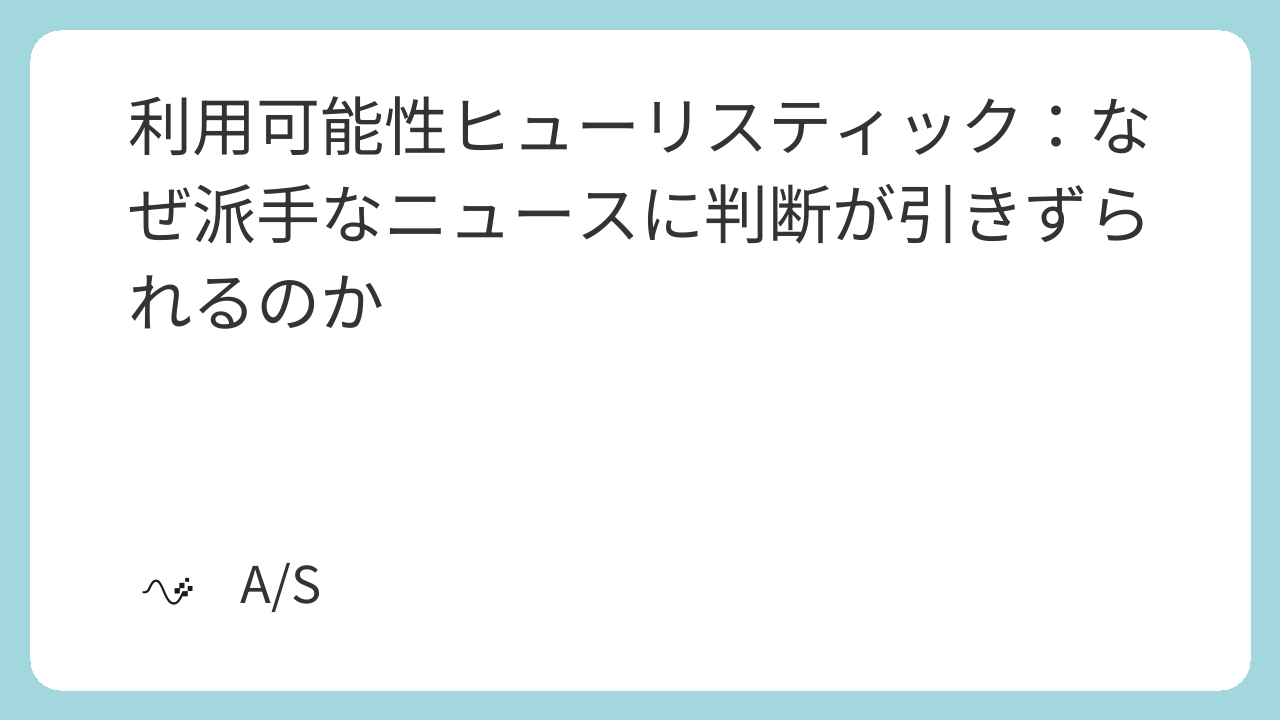
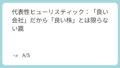
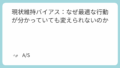
コメント