概論
伝統的な金融理論では、リスクは二つの種類に分解されます。一つは、市場全体と共に動くことで避けられないシステマティック・リスク(市場リスク)。もう一つは、その企業固有の要因(新製品の成功、不祥事など)によって生じるイディオシンクラティック・リスク(個別銘柄リスク)です。
理論上、効率的なポートフォリオを組むことで、個別銘柄リスクは分散・消去が可能であるため、投資家がそのリスクを取ることに対して追加的なリターンを得ることはないとされてきました。むしろ、ロバート・マートンによる1987年の理論モデルは、もし投資家が十分に分散投資を行っていない場合、彼らは個別銘柄リスクを引き受けることへの対価として、より高いリターンを要求するはずだと予測しました [1]。
しかし、現実の市場は、この理論的予測とは全く逆の動きを見せます。すなわち、個別銘柄リスク(イディオシンクラティック・ボラティリティ)が高い株式ほど、将来の平均リターンが体系的に低くなるという、極めて不可解な現象が観測されているのです。これがイディオシンクラティック・ボラティリティ・パズルとして知られる、金融市場における最も頑健なアノマリー(経験則)の一つです。
このパズルを現代の金融学における一大テーマとして確立したのが、アンドリュー・アン、ロバート・ホドリック、イェーユン・シン、シャオヤン・チャンによる2006年の論文です [2]。彼らは、米国市場において、個別銘柄リスクの高さと将来リターンの間に、強力で頑健な「負の相関関係」が存在することを実証しました。
なぜ、分散可能なはずのリスクが、罰せられるかのように低いリターンと結びついてしまうのか。この謎は、市場の効率性や、投資家の合理性そのものに対する、根源的な問いを投げかけています。
長短の解説と損益の事例紹介
短所、弱み、リスクについて:高リスク・低リターンの現実
イディオシンクラティック・ボラティリティ・パズルは、高いリスクを取れば高いリターンが得られるという投資の常識を覆します。個別銘柄リスクの高い株式に投資することは、このパズルが示す体系的なアンダーパフォームのリスクを直接的に引き受けることを意味します。
損失事例:驚異的なアンダーパフォーマンス
アンらの2006年の研究が示した結果は、衝撃的です。1963年から2000年までの米国市場において、個別銘柄リスク(イディオシンクラティック・ボラティリティ)の高さで株式を5つのグループに分けた場合、リスクが最も高いグループのリターンは、リスクが最も低いグループのリターンを、月平均で1.06%も下回りました [2]。これは、統計的に極めて有意な差であり、単なる偶然では説明できません。
国際市場での再現性
この現象は、米国市場だけの特殊なものではありません。アンらが2009年に行った追試研究では、フランス、ドイツ、イタリア、日本、イギリスといったG7諸国を含む、23の先進国市場でも同様のパズルが観測されることが確認されました [3]。この国際的な頑健性は、このパズルが、市場の根源的な何らかの構造的歪み、あるいは投資家に共通する心理的バイアスに根差していることを強く示唆しています。
長所、強み、有用な点について:パズルの謎を解く(収益機会)
このパズルは、高リスク株を保有する投資家にとっては「損失の源泉」ですが、そのメカニズムを理解する投資家にとっては、「収益機会」のヒントとなり得ます。なぜ、このような非合理的な値付けが起こるのでしょうか。
考えられる源泉1:宝くじ銘柄への選好
最も有力な説明の一つが、投資家の行動バイアスです。個別銘柄リスクが高い株式は、しばしば投機的で、株価が短期間で何倍にもなる可能性を秘めた、「宝くじ」のような性質を持っています。
バーバリスとホアンによる2008年の研究が示すように、多くの投資家は、期待値がマイナスであっても、ごく稀に起こる「一攫千金」の可能性に強く惹きつけられます [4]。この宝くじへの選好という非合理的な需要が、個別銘柄リスクの高い株式に集中し、その価格を本来の価値以上に吊り上げてしまうのです。過大評価された価格で買う以上、その後の平均リターンが低くなるのは必然的な結果と言えます。
考えられる源泉2:裁定取引の非対称性
高リスク株の過大評価がなぜ是正されないのか。その答えは、裁定取引の難しさにあります。スタンバー、ユー、ユアンによる2015年の研究は、このパズルが、空売りが困難な銘柄で特に強く現れることを示しました [5]。
楽観的な投資家が、宝くじのような高リスク株を買い上げるのは簡単です。しかし、それが割高だと判断した合理的な投資家(裁定取引者)が、それを空売りして価格を押し下げようとしても、貸株料が高かったり、そもそも株を借りられなかったりと、多くの制約(摩擦)に直面します。この「買いは易しく、売りは難しい」という裁定取引の非対称性が、過大評価の是正を妨げ、パズルが市場に存続する原因となっているのです。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、これほどまでに明確で、かつ国際的に観測されるアノマリーが、市場から簡単には消え去らないのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:リターン分布の非対称性と裁定取引の非対称性
イディオシンクラティック・ボラティリティ・パズルの根源には、二種類の深刻な「非対称性」が存在します。
リターン分布の非対称性(歪度)
個別銘柄リスクが高い株式は、そのリターン分布が、宝くじのように極めて非対称な形、すなわち「正の歪度(スキューネス)が大きい」という特徴をしばしば持っています。これは、「ほとんどの場合は小さな損失を出すが、ごく稀に、驚異的な利益をもたらす」というリターンの構造を意味します。バーバリスとホアンの研究が示すように、人間の脳は、このような非対称なペイオフを持つ対象を合理的に評価できず、稀に起こる「大当たり」の可能性を過大評価してしまう傾向があります [4]。このリターン分布の非対称性が、投資家を惹きつけ、過大評価を生み出す最初の原因となります。
裁定取引の非対称性
この過大評価を、なぜプロの投資家が是正できないのでしょうか。その答えが、「裁定取引の非対称性」です。スタンバーらの研究が明らかにしたように、市場において、価格を押し上げる力(買い)と、押し下げる力(空売り)は、対称ではありません [5]。
楽観的な投資家が、夢のある高リスク株を買い上げるのは簡単です。しかし、それが割高だと判断した合理的な投資家(裁定取引者)が、それを空売りして価格を押し下げようとする際には、多くの制約に直面します。この「買いは易しく、売りは難しい」という構造的な非対称性が、過大評価の是正を妨げ、パズルが存続する決定的な要因となっているのです。
Friction:空売り制約と「希望」という二重の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、このパズルを支えているのは、より本質的で克服困難な、物理的・認知的な二重の「摩擦」です。
空売り制約という物理的な摩擦
裁定取引の非対称性を生み出す具体的な原因が、「空売り制約」という物理的な摩擦です。個別銘柄リスクが高い株式は、しばしば時価総額が小さく、流動性が低い、あるいはボラティリティが極端に高いといった特徴を持つため、空売りのための株式を借りることが困難であったり、非常に高いコスト(貸株料)がかかったりします。この物理的な摩擦が、割高な株価を押し下げようとする裁定取引者の行動を直接的に妨害し、過大評価された状態を長期間にわたって放置させるのです [5]。
「希望」という抗いがたい認知的摩擦
個別銘柄リスクが高い株式は、しばしば「次世代の巨大企業になるかもしれない」という、強力な「ストーリー」や「希望」を伴っています。この「希望」という感情的な価値は、投資家が合理的な判断を下すことを妨げる、極めて強力な「認知的な摩擦」として機能します。
多くの投資家は、低い確率のデータや、割高なバリュエーションを無視して、その輝かしい物語に賭けてしまいます。この根源的な人間の欲求は、たとえ過去のデータがその戦略の不利を示していても、常に新たな買い手を市場に呼び込みます。この尽きることのない需要が、アノマリーが簡単には消滅しない、最も手強い理由の一つなのです。
総括
・イディオシンクラティック・ボラティリティ・パズルとは、個別銘柄リスクが高い株式ほど、将来の平均リターンが体系的に低くなるという、伝統的金融理論の予測に反する現象です [2, 3]。
・その主な原因は、投資家が「宝くじ」のような一攫千金の可能性を持つ高リスク株を好み、過大評価してしまうという行動バイアスにあると考えられています [4]。
・この過大評価は、「買いは易しく、売りは難しい」という裁定取引の非対称性のために、市場で簡単には是正されません。特に、空売り制約がこのパズルの存続に大きく寄与しています [5]。
・したがって、高い個別銘柄リスクは、それ自体が将来の低リターンを示唆する危険なシグナルであると同時に、その背景にある市場の構造的な歪みと摩擦を理解することで、投資家はより賢明な判断を下すことが可能になります。
用語集
イディオシンクラティック・リスク 市場全体の値動きでは説明できない、その個別銘柄固有の要因(新技術の開発、経営判断の失敗、不祥事など)によって生じるリスク。ポートフォリオを組むことで分散可能とされる。idiosyncratic risk。
システマティック・リスク 市場全体に関わる要因(景気変動、金利変動、地政学的リスクなど)によって生じるリスク。分散投資を行っても避けることができない。systematic risk。
CAPM (資本資産評価モデル) 資産のリターンが、その資産が持つシステマティック・リスク(ベータ)の大きさに比例して決まるという理論。
アノマリー 現代ファイナンス理論の常識では説明できないが、市場で経験的に観測されるリターンの規則性。
ボラティリティ 資産価格の変動の激しさを示す指標。リターンの標準偏差で測定されることが多い。
裁定取引 (Arbitrage) 価格の歪みを利用して、リスクなく利益を得ようとする取引。価格を適正な水準に戻す力となる。
空売り 所有していない株式を証券会社などから借りて市場で売却し、将来価格が下落した時点で買い戻して返済し、その差額を利益とする取引。
歪度 (スキューネス) 確率分布が、その平均値に対してどれだけ非対称であるかを示す統計的な指標。「正の歪度」が大きいとは、分布の裾が右側に長く伸びている(稀に大きなプラスの値を取る)ことを意味する。
プロスペクト理論 不確実性のある状況下での人間の意思決定を説明する理論。人々が低い確率を過大評価する傾向などをモデル化している。
ポートフォリオ 投資家が保有する、株式、債券、不動産などの金融資産の組み合わせ、またその一覧。
参考文献一覧
[1] Merton, R. C. (1987). A simple model of capital market equilibrium with incomplete information. The Journal of Finance, 42(3), 483-510.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1987.tb04565.x
[2] Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The cross‐section of volatility and expected returns. The Journal of Finance, 61(1), 259-299.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00836.x
[3] Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2009). High idiosyncratic volatility and low returns: International and further U.S. evidence. Journal of Financial Economics, 91(1), 1-23.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.12.005
[4] Barberis, N., & Huang, M. (2008). Stocks as lotteries: The implications of probability weighting for security prices. American Economic Review, 98(5), 2066-2100.
https://doi.org/10.1257/aer.98.5.2066
[5] Stambaugh, R. F., Yu, J., & Yuan, Y. (2015). Arbitrage asymmetry and the idiosyncratic volatility puzzle. The Journal of Finance, 70(5), 1903-1941.
https://doi.org/10.1111/jofi.12286
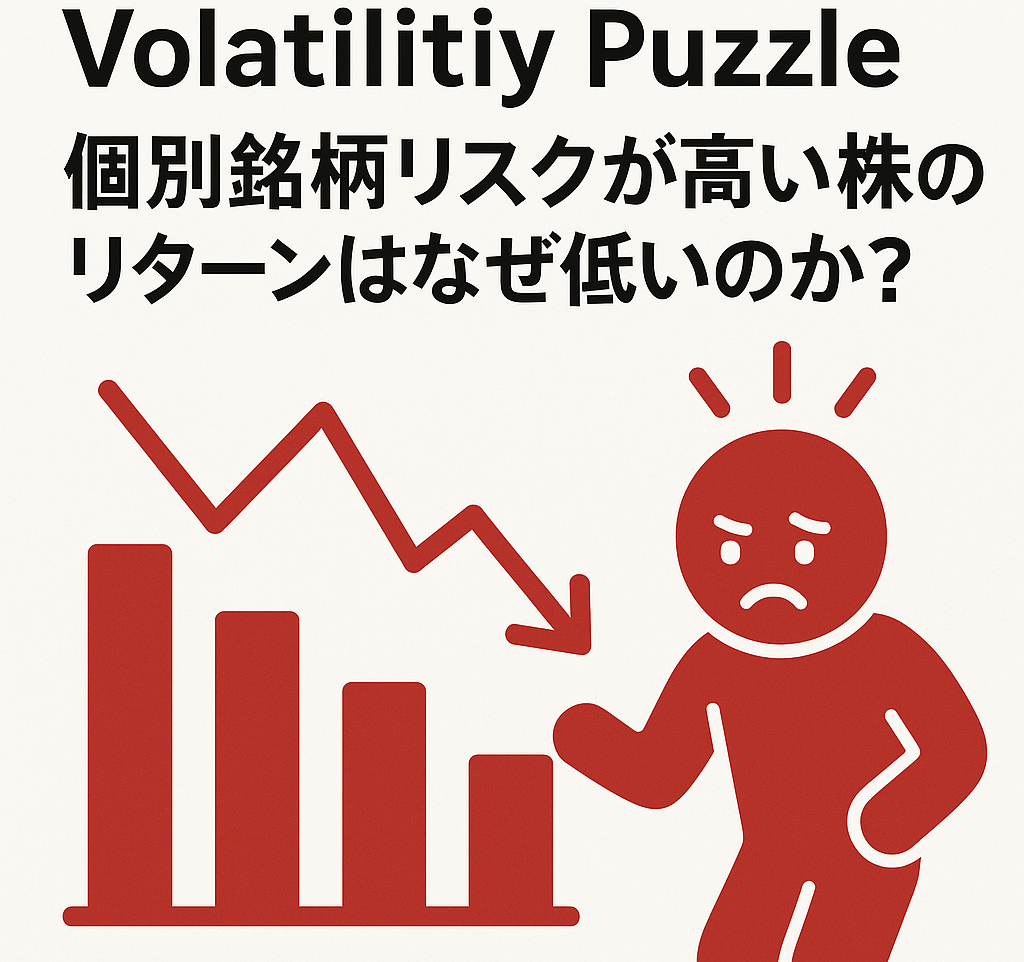
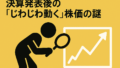
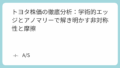
コメント