概論:聖杯の賞味期限
投資の世界では、市場を出し抜くことができる「聖杯」の探求が絶えず行われています。学術研究の世界でも、市場平均を上回るリターンを生み出すアノマリー(経験則)、すなわちファクターが数多く発見されてきました。しかし、これらの輝かしい発見には、ある残酷な宿命が伴います。それは、発見されたアノマリーの多くが、その存在が広く知られるようになった後、パフォーマンスが低下、あるいは消滅してしまうという現象です。
これが「ファクターの減衰(Factor Decay)」あるいは「アノマリーの減衰(Anomaly Decay)」と呼ばれるものです。
この現象を学術的に広く知らしめたのが、ウィリアム・シュワートによる2003年の包括的なレビュー研究です [1]。彼は、過去に報告された様々な市場アノマリーを検証し、その多くが論文として出版された後に、超過リターンが著しく減少する傾向にあることを突き止めました。つまり、投資家が「勝てる戦略」の存在を知ったまさにその時には、もはやその戦略は以前ほど有効ではなくなっている、という皮肉な現実をデータで示したのです。
では、なぜこのような減衰が起こるのでしょうか。その背景には、主に二つの対立する、しかし両立しうる仮説が存在します。
- 裁定取引仮説:アノマリーは本物の市場の非効率性であり、その存在が公になることで、洗練された投資家たちが利益を得ようと殺到(裁定取引)した結果、価格の歪みが是正され、超過リターンが消滅するという考え方。
- データマイニング仮説:そもそも発見されたアノマリーの多くは、本物の非効率性などではなく、研究者が過去のデータを過剰に分析(データマイニング)した結果、偶然見つけ出した統計上の幻に過ぎない、という考え方。
この記事では、これらの仮説を裏付ける学術研究を紐解きながら、ファクター減衰のメカニズムとその現実を深掘りしていきます。
長短の解説と損益の事例紹介
ファクターの減衰は、市場のダイナミズムを象徴する現象です。その原因を理解することは、過去の成功に固執するリスクと、一方で今なお有効性を保つファクターを見極めるヒントを与えてくれます。
ファクターが減衰する主な理由(損失事例)
学術研究によって発見されたエッジが、なぜ時間とともにその輝きを失っていくのか。その背景には、少なくとも3つの強力なメカニズムが存在します。
1.公表と裁定取引によるリターンの消滅
市場の非効率性を利用した儲け話は、秘密であるからこそ価値があります。学術論文によるアノマリーの発見は、いわば「儲けの秘密」を全世界に公開するようなものです。
マクリーンとポンティフによる2016年の大規模な研究は、このプロセスを克明に描き出しました [2]。彼らは97種類のアノマリーを調査し、論文として公表された後、その超過リターンが平均で58%も減少することを発見しました。さらに重要なのは、このリターンの低下が、取引コストが低い(裁定取引が行いやすい)銘柄群でより顕著であったことです。これは、論文の発表をきっかけに、ヘッジファンドなどのプロの投資家が即座に裁定取引を行い、利益の源泉を食い潰してしまったことを強く示唆しています。
2.そもそも「幻」だった可能性:データマイニング
発見されたファクターの多くが、そもそも本物のエッジではなかった、という厳しい指摘も存在します。キャンベル・ハーヴェイらの2016年の研究は、金融研究の世界で数百もの「ファクター」が”発見”された状況を「ファクター動物園」と揶揄しました [3]。
彼らの分析によれば、統計的に有意とされる発見の基準が甘すぎたため、本来は単なる偶然のノイズであるにもかかわらず、意味のあるファクターとして報告されてしまったものが大量に紛れ込んでいると結論付けています。このような「偽りのファクター」のパフォーマンスが、発見後に平均へと回帰していくのは当然であり、それは「減衰」というよりも、単に「化けの皮が剥がれた」だけなのです。
3.乗り越えられない摩擦:取引コストの壁
たとえアノマリーが本物で、裁定取引でも完全には消滅しなかったとしても、現実の投資家がその利益を手にできるとは限りません。ノヴィーマークスとヴェリコフによる2016年の研究は、様々なアノマリー戦略を実行するために必要な現実的な取引コストを推計しました [4]。
その結果、特に短期モメンタム戦略のような、売買回転率が非常に高い戦略においては、理論上の超過リターン(アルファ)の大部分、あるいは全てが、スプレッドやマーケットインパクトといった取引コストによって消し飛んでしまうことが示されました。つまり、一部のアノマリーは、減衰したのではなく、最初から「絵に描いた餅」であった可能性が高いのです。
一方、なぜ全てのアノマリーが消滅しないのか?
ジェイコブスとミュラーによる2020年の、世界49カ国、240種類以上のアノマリーを検証した大規模な研究は、この問題に光を当てています [5]。彼らの研究によれば、論文として公表された後、アノマリーの平均的なリターンは確かに大幅に低下し、特に米国市場ではその多くが統計的に有意でなくなりました。
しかし、その減衰効果は一様ではなく、バリューやモメンタムといった、より経済的な根拠を持つ主要なファクターは、特に国際市場において、依然としてその存在感を示していることも明らかにしています。
これは、ファクターの減衰が全てのファクターに等しく起こるわけではないことを意味します。データマイNINGの産物や、裁定取引が容易な単純な戦略は淘汰される一方で、根深い行動バイアスや、裁定取引を困難にするリスクや摩擦に根差した、より本質的なファクターは、形を変えながらも存続し続けているのです。
非対称性と摩擦の視点
なぜ、一部のファクターは急速にリターンを失い、また一部はしぶとく存続するのでしょうか。その鍵は、市場に存在する「非対称性」と、裁定取引を阻む「摩擦」にあります。
Asymmetry:情報の伝達速度という非対称性
ファクター減衰のプロセスそのものが、市場における情報の非対称性を浮き彫りにします。学術論文という形でアノマリーの存在が公になると、その情報は理論上は誰でもアクセス可能になります。しかし、その情報を入手し、理解し、そして取引に結びつけるまでの速度と能力は、投資家によって全く異なります。
ヘッジファンドやクオンツ・ファンドのような洗練された機関投資家は、学術界の最新の研究を常に監視し、論文が公開されると同時にその内容を解析し、取引アルゴリズムを開発・実行する能力を持っています。一方で、個人投資家や伝統的な資産運用会社がその情報を知るのは、専門メディアで解説されたり、金融商品としてパッケージ化されたりした後、つまり数ヶ月から数年後になることも珍しくありません。
この情報の伝達と実行における速度の非対称性こそが、ファクター減衰の本質です。超過リターンは、ごく一部の「情報強者」が最初に参入する段階で最も大きく、情報が広く一般に普及するにつれて、彼らの裁定取引によって食い潰されていくのです [2]。つまり、私たちがアノマリーの存在を知った時には、その収益機会(エッジ)の最も美味しい部分は、すでに刈り取られた後である可能性が高いのです。
Friction:「裁定取引の限界」こそがアノマリー存続の土壌
では、なぜ全てのファクターが完全に消滅しないのでしょうか。それは、現実の市場が、裁定取引を困難にする様々な「摩擦(Friction)」に満ちているからです。手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、より根源的な摩擦がアノマリーの存続を許しています。
1.取引コストという摩擦
理論上の超過リターンと、現実に得られるリターンとの間には、取引コストという巨大な溝が存在します。特に、売買回転率が高い戦略は、この摩擦の影響を強く受けます。例えば、短期モメンタム戦略のバックテストでは高いリターンが示されても、現実の取引で発生するコストを考慮すると、利益がほとんど残らない、あるいはマイナスになることさえあります [4]。この摩擦が、理論上のアノマリーが市場に残り続ける一因となります。誰も儲からないので、誰も本気で裁定取引を行わないのです。
2.裁定取引のリスクという摩擦
教科書的な裁定取引はリスクフリーですが、現実のアノマリー取引は様々なリスクを伴います。価格の歪みがいつ是正されるか分からず、短期的にはむしろ拡大して損失を被る可能性もあります。また、多くのプロ投資家は、短期的な損失が顧客資金の流出に繋がるという「キャリアリスク」を抱えているため、長期的に有効な戦略であっても、短期的なドローダウンを恐れて実行できないことがあります。これらの裁定取引に伴うリスクが、価格の歪みを完全に解消しようとする力を弱める摩擦として機能します。
結果として、論文公表後に多くのアノマリーが統計的に有意でなくなる中でも [5]、取引コストや裁定リスクといった根強い摩擦が存在するため、データマイニングの産物ではない、本質的なファクターはその減衰効果を完全に受けることなく市場に残り続けるのです。
用語集
ファクターの減衰 (Factor Decay) 学術論文などで発見された、市場の非効率性(アノマリー)がもたらす超過リターンが、その発見が公になった後に低下、または消滅する現象。
アノマリー (Anomaly) 現代ファイナンス理論の常識では説明できないが、市場で経験的に観測されるリターンの規則性。
裁定取引 (Arbitrage) 同一の価値を持つ資産間で価格差が生じた際に、割安な方を買い、割高な方を売ることで、リスクなく利益を得ようとする取引。価格の歪みを是正する力となる。
データマイニング (Data Mining) 大量のデータを分析し、本来は意味のない偶然の相関関係を、意味のある規則性であるかのように見つけ出してしまうこと。
pハッキング (p-hacking) 統計的な分析において、研究者が自分に都合の良い結果(統計的に有意な結果)が得られるまで、データの分析方法を様々に試行錯誤すること。データマイニングの一種。
取引コスト (Transaction Costs) 金融商品を売買する際に発生する費用の総称。売買手数料やスプレッド、マーケットインパクトなどが含まれる。
マーケットインパクト (Market Impact) 自らの取引が、市場価格を不利な方向に動かしてしまうことによる、目に見えないコスト。大口の取引ほど大きくなる。
5ファクターモデル 株式リターンを市場リスク、サイズ、バリュー、プロフィタビリティ、インベストメントの5つの因子で説明する、ファーマ=フレンチが提唱したモデル。
バックテスト (Backtest) ある投資戦略が、過去の市場データを用いてシミュレーションした場合に、どのようなパフォーマンスを示したかを検証すること。
シャープレシオ (Sharpe Ratio) リターンを、そのリターンを得るために取ったリスクの大きさで割った値。リスク調整後のパフォーマンスを測る指標。
参考文献一覧
[1] Schwert, G. W. (2003). Anomalies and market efficiency. In G. M. Constantinides, M. Harris, & R. M. Stulz (Eds.), Handbook of the Economics of Finance (Vol. 1, Part B, pp. 939-974). Elsevier.
https://doi.org/10.1016/S1574-0102(03)01024-0
[2] McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability?. The Journal of Finance, 71(1), 5-48.
https://doi.org/10.1111/jofi.12365
[3] Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). …and the Cross-Section of Expected Returns. The Review of Financial Studies, 29(1), 5-68.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhv059
[4] Novy-Marx, R., & Velikov, M. (2016). A taxonomy of anomalies and their trading costs. The Review of Financial Studies, 29(1), 104-147.
https://doi.org/10.3386/w20721
[5] Jacobs, H., & Müller, S. (2020). Anomalies across the globe: Once public, no longer existent?. Journal of Financial Economics, 135(1), 261-289.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.06.004
ファクター投資の知識をさらに深めるための全記事リスト
この記事をお読みいただきありがとうございます。ファクター投資という奥深いテーマを、より体系的に理解していただくために、当メディア「Asymmetry Signal」が提供する関連する全記事をまとめました。
ご自身の興味やレベルに合わせて、ぜひ次のステップにお進みください。
- ファクター投資とは何か?市場を超えるリターンの源泉
ファクター投資の基本概念と、その歴史的背景を網羅的に解説しています。ファクター投資への第一歩に最適な記事です。 - バリューファクター:なぜ「割安」な株は報われるのか?
「安く買って高く売る」という投資の原則を科学したバリュー投資の核心を、学術的知見から解き明かします。 - サイズファクター:小型株効果(SMB)の理論と現実
時価総額が小さい企業が長期的にアウトパフォームする傾向、小型株効果の理論と、その有効性の変化について解説します。 - クオリティファクター:財務健全性が生み出す超過リターン
ウォーレン・バフェットも重視する「質の高い企業」に焦点を当て、その防御的特性とリターンの源泉を分析します。 - 収益性ファクター:なぜ「儲かっている」企業は強いのか?
企業の「儲ける力」が、いかにして長期的な超過リターンにつながるかを、売上総利益という指標から深掘りします。 - インベストメントファクター:なぜ「投資をしない」企業がアウトパフォームするのか?
投資の世界の常識に逆らう、総資産成長率が低い企業が優位性を持つという逆説的なファクターを解説します。 - マルチファクターモデルの構築:複数のエッジを組み合わせる技術
複数のファクターを組み合わせることで、より安定したリターンを目指す高度な戦略と、その実践における課題を論じます。 - ファクターのシクリカリティ:市場サイクルとファクターパフォーマンスの関係
ファクターの有効性が景気や市場のサイクルによって変動する、動的な性質とその応用、そしてリスクについて考察します。 - ファクターの減衰:なぜ発見されたアノマリーは消えていくのか?
論文として公表されたアノマリーの超過リターンが失われる現象と、その背後にあるメカニズムを深く掘り下げます。 - 「ファクター動物園」問題:数百のアノマリーから本物を見分ける方法
学術研究で発見された数百ものファクターの中から、データマイニングの産物ではない「本物」を見分けるための基準を解説します。
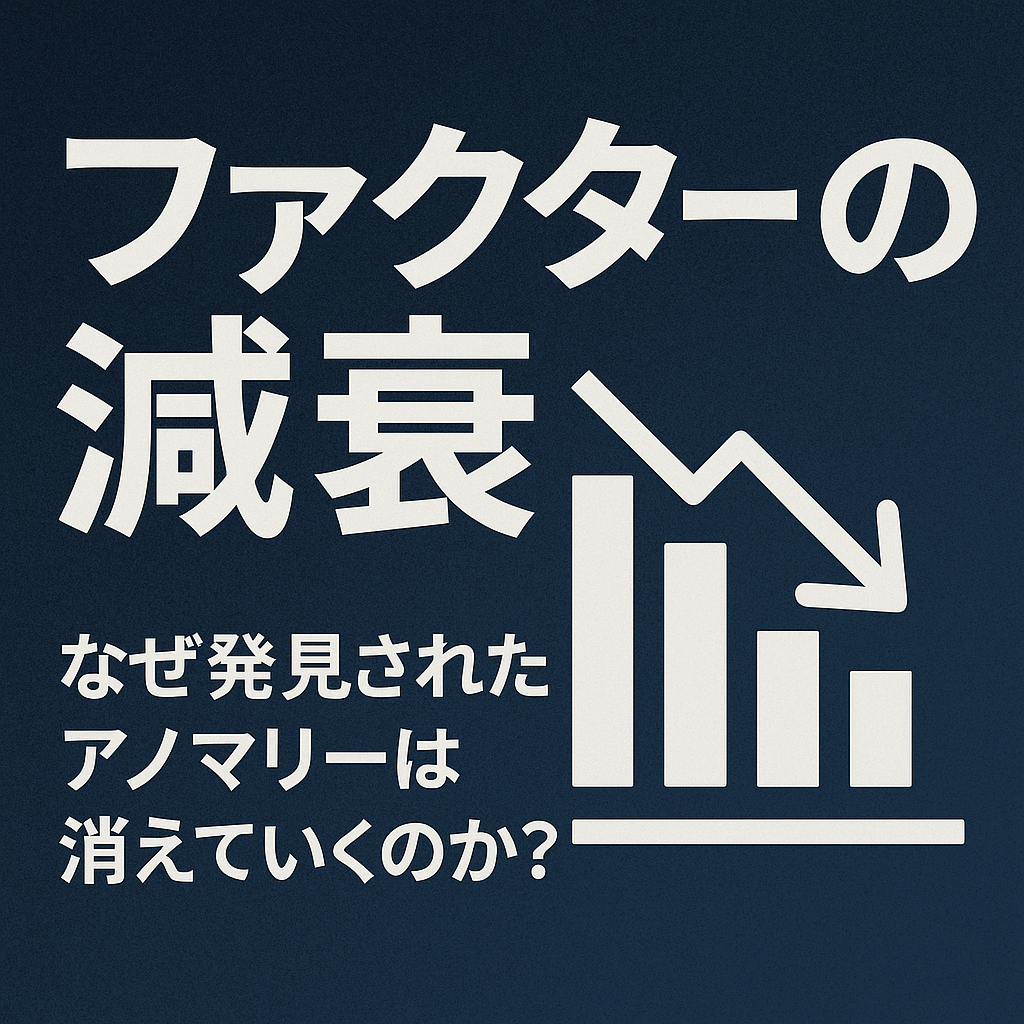
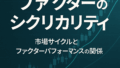
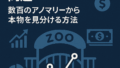
コメント