投資の世界には、市場の平均リターンを上回ることを目指すための様々な「ファクター」が存在します。中でも、最も直感的で理解しやすいものの一つが「プロフィタビリティ(収益性)ファクター」でしょう。「どうせ投資するなら、しっかりと利益を上げている優良企業が良い」――この、誰もが抱くであろう健全な感覚を、学術的な rigor(厳密さ)をもって体系化したのがこのファクターです。
プロフィタビリティ・ファクターは、収益性の高い企業群の株式が、収益性の低い企業群の株式を長期的にアウトパフォームするというアノマリー(経験則)に基づいています。
この記事では、なぜこの単純明快な戦略が有効なエッジとなり得るのか、その根拠を査読付き学術論文のみをソースとして徹底的に解説します。
単に「儲かっている企業が良い」という直感的な説明に留まらず、プロフィタビリティ・ファクターの提唱者であるロバート・ノヴィーマークスの研究に基づき、なぜ「売上総利益」という一見シンプルな指標が強力なのか、その理論的背景を深掘りします。
ファーマ=フレンチの5ファクターモデルに組み込まれた経緯や、国際的な市場での有効性を示し、このファクターの普遍性と重要性を立体的に解説しています。さらに、当メディア「Asymmetry Signal」独自の視点から、リターンの源泉となる「非対称性」と、アノマリーの存続を許す市場の「摩擦」についても深く掘り下げていきます。
プロフィタビリティ・ファクターの概論
長らく金融資産の価格形成は、市場リスク、サイズ(小型株効果)、バリュー(割安株効果)を基にしたファーマ=フレンチの3ファクターモデルで説明されてきました。しかし、このモデルでも説明しきれないリターンが存在することが知られていました。
「第4のファクター」としての登場
この状況に大きな進展をもたらしたのが、ロバート・ノヴィーマークスが2013年に発表した画期的な論文「The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium」です¹。彼はこの研究で、売上総利益(Gross Profit)を総資産(Total Assets)で割った「グロス・プロフィタビリティ(Gross Profitability)」という指標が、将来の株式リターンを強力に予測することを発見しました。
驚くべきことに、このシンプルな指標で測定したプロフィタビリティ・ファクターのパフォーマンスは、伝統的なバリューファクターに匹敵するほど強力でした。さらに、プロフィタビリティとバリューの間には負の相関関係が見られ、両者を組み合わせることでポートフォリオのリスク分散に大きく貢献することも示されたのです。
ノヴィーマークスは、なぜ純利益や営業利益ではなく「売上総利益」を用いたのでしょうか。彼は、売上総利益が企業の核となる事業の「儲ける力」を最もクリーンに反映していると主張します。研究開発費や広告宣伝費、金利、税金といった要素は、会計方針や経営判断によって変動しやすく、ノイズとなり得ます。それらを差し引く前の売上総利益こそが、企業の真の収益力を示す最も直接的な指標である、というわけです。
5ファクターモデルへの採用
このプロフィタビリティ・ファクターの重要性は、現代ファイナンス理論の権威であるユージン・ファーマとケネス・フレンチ自身によっても認められました。彼らは2015年、自らの3ファクターモデルを拡張し、プロフィタビリティとインベストメント(投資姿勢)を加えた「ファーマ=フレンチの5ファクターモデル」を発表しました²。これにより、プロフィタビリティは、サイズやバリューと並ぶ、株式リターンを説明する上で欠かせない基本的なファクターとして、学術的に確固たる地位を築いたのです。
長所と短所、そして損益の実例
プロフィタビリティ戦略は強力な理論的背景を持ちますが、実践においてはその長所と短所を冷静に評価する必要があります。
長所と強み:頑健で普遍的なパフォーマンス
プロフィタビリティ・ファクターの最大の強みは、その頑健性(Robustness)と普遍性にあります。
- 長期的な有効性: ノヴィーマークスの研究では、1963年から2010年までの米国市場において、グロス・プロフィタビリティの高い企業のポートフォリオが、低い企業のポートフォリオを月平均で0.31%上回るリターンを生み出したことが示されています¹。これは、単なる偶然では説明が難しい、統計的に有意な差です。
- 国際市場でのパフォーマンス: プロフィタビリティ・プレミアムは、米国市場だけの現象ではありません。ファーマとフレンチが2017年に行った国際市場でのテストでは、北米、欧州、日本、アジア太平洋の4地域すべてにおいて、収益性の高い企業が低い企業をアウトパフォームする傾向が確認されました³。これは、このファクターが特定の国の経済や市場構造に依存するものではなく、より根源的な原理に基づいていることを示唆しています。
- クオリティ戦略の核として: プロフィタビリティは、より広範な「クオリティ・ファクター」の中核をなす要素でもあります。Ballらによる2016年の研究では、会計上の発生高で調整した営業利益を用いたプロフィタビリティ指標もまた、将来のリターンを強く予測することが示されています⁴。測定方法に多少の違いはあれど、「儲ける力」がリターンの源泉であるという事実は、多くの研究によって裏付けられているのです。
短所とリスク:手放しでは称賛できない現実
直感的で強力なプロフィタビリティ戦略にも、注意すべき欠点やリスクが存在します。
- 「プロフィタビリティ・トラップ」のリスク: 現在非常に収益性が高い企業は、すでにその成長がピークに達している可能性があります。経済学の原則として、超過利益は競争を呼び込みます。高い利益率を誇る市場にはいずれ競合他社が参入し、価格競争などによって利益率が平均へと回帰していく圧力がかかります。つまり、今日の高い収益性が明日も続くとは限らないのです。
- 指標の定義による差異: 前述の通り、プロフィタビリティを測る指標には、ノヴィーマークスが提唱する「グロス・プロフィタビリティ」¹や、Ballらが用いる「オペレーティング・プロフィタビリティ」⁴など、複数の定義が存在します。どの指標を用いるかによって、選択される銘柄やパフォーマンスが異なる可能性があり、絶対的な「正解」が存在しない点はリスクと言えます。
- グロース相場での相対的な劣後: 市場全体が将来の夢や期待に沸くような、いわゆる「グロース相場」においては、現在の利益よりも将来の成長可能性が重視されます。このような局面では、赤字であっても高い成長期待を持つハイテク企業などが、地味で着実に利益を上げている高収益性企業をアウトパフォームする可能性があります。
非対称性と摩擦の視点
プロフィタビリティ・ファクターがなぜ有効なエッジとして存続するのか。その本質を、当メディアの思想である「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かします。
非対称性(Asymmetry):情報の質が生むリターンの源泉
プロフィタビリティ・プレミアムは、市場参加者の間に存在する「情報の非対称性」、特に「情報の質」に対する評価の非対称性に根差しています。
- シグナルの質の非対称性: 多くの投資家やアナリストは、決算発表で最も注目される「EPS(一株当たり利益)」といった純利益ベースの指標に注目しがちです。しかし、これらの指標は会計上の見積もりや裁量の余地が大きく、ノイズを含んでいる場合があります。一方で、ノヴィーマークスが指摘するように、「売上総利益」は事業の根源的な収益力を示す、よりクリーンで質の高いシグナルです¹。市場参加者の多くが、この「シグナルの質」の非対称性を十分に認識せず、ノイズの多い情報に過剰反応し、質の高い情報を見過ごすことが、価格の非効率性を生み出します。プロフィタビリティ戦略は、この質の高い情報に注目することで、市場の集合知の一歩先を行く試みと言えます。
- 持続性の評価の非対称性: 市場は、企業の高い収益性がやがて平均に回帰すると予測する傾向があります。しかし、強力なブランド、特許、効率的な生産プロセスなど、真に持続可能な競争優位性を持つ企業の収益性は、市場の平均的な想定よりも長く持続することがあります。この「収益性の持続性」に対する期待の非対称性が、優れた企業が過小評価され続ける原因となり、リターンの源泉となるのです。
摩擦(Friction):なぜアノマリーは完全には消滅しないのか?
もし市場が完全に効率的なら、質の高い情報は即座に価格に織り込まれるはずです。しかし、現実の市場には様々な「摩擦」が存在し、アノマリーの存続を許しています。
- 限定された注意力(Limited Attention)という認知的摩擦: 現代の投資家は、膨大な情報に常に晒されています。企業の財務諸表を深く読み込み、売上総利益のような「地味だが重要な」指標の価値を評価するには、時間と専門知識が必要です。多くの投資家は、より分かりやすく、メディアで大きく取り上げられるニュースや指標に注意を奪われがちです。この「限定された注意力」という認知的な摩擦が、プロフィタビリティという強力なシグナルが完全には価格に織り込まれない状況を生み出しています。
- 分析コストという摩擦: 質の高い企業を見つけるためには、単に指標でスクリーニングするだけでなく、その収益性がなぜ高いのか、そしてそれは持続可能なのかを定性的に分析する必要があります。これには多大な分析コスト(時間、労力、専門性)がかかります。このコストが、多くの投資家にとって参入障壁となり、完全な裁定取引を妨げる摩擦として機能します。結果として、分析コストをかけてでも優位性を追求する投資家のために、超過リターンが残り続けるのです。
用語集
- プロフィタビリティ・ファクター: 収益性の高い企業群の株式が、低い企業群の株式を長期的にアウトパフォームする傾向。
- 売上総利益 (Gross Profit): 売上高から売上原価を差し引いた利益。企業の基本的な「儲ける力」を示す。
- 総資産 (Total Assets): 企業が保有する資産の合計額。
- ファーマ=フレンチの5ファクターモデル: 株式リターンを市場リスク、サイズ、バリュー、プロフィタビリティ、インベストメントの5つの因子で説明するモデル。
- クオリティ・ファクター: 収益性、財務健全性、成長の安定性など、企業の「質」の高さを示す銘柄群が持つリターン特性。プロフィタビリティはその中核要素。
- 頑健性 (Robustness): ある現象が、異なる期間、異なる市場、異なる定義を用いても、同様に観測される性質。統計的な信頼性が高いことを示す。
- リスク調整後リターン: リターンの大きさを、そのリターンを得るために取ったリスクの大きさで調整した指標。シャープレシオが代表的。
- シャープレシオ (Sharpe Ratio): リスク1単位あたりで得られた超過リターンを示す、投資効率の指標。
- アノマリー (Anomaly): 効率的市場仮説では説明できないが、市場で経験的に観測される株価の規則的なパターン。
- 平均回帰 (Mean Reversion): ある変数が、長期的にはその平均値に戻っていくとする統計的な性質。企業の超過利益は平均に回帰する傾向がある。
参考文献一覧
Novy-Marx, R. (2013). The other side of value: The gross profitability premium. Journal of Financial Economics, 108(1), 1-28.
Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1-22.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010
Fama, E. F., & French, K. R. (2017). International tests of a five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 123(3), 441-463.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.11.004
Ball, R., Gerakos, J., Linnainmaa, J. T., & Nikolaev, V. V. (2016). Accruals, cash flows, and operating profitability in the cross-section of stock returns. Journal of Financial Economics, 121(3), 545–565.
ファクター投資の知識をさらに深めるための全記事リスト
この記事をお読みいただきありがとうございます。ファクター投資という奥深いテーマを、より体系的に理解していただくために、当メディア「Asymmetry Signal」が提供する関連する全記事をまとめました。
ご自身の興味やレベルに合わせて、ぜひ次のステップにお進みください。
- ファクター投資とは何か?市場を超えるリターンの源泉
ファクター投資の基本概念と、その歴史的背景を網羅的に解説しています。ファクター投資への第一歩に最適な記事です。 - バリューファクター:なぜ「割安」な株は報われるのか?
「安く買って高く売る」という投資の原則を科学したバリュー投資の核心を、学術的知見から解き明かします。 - サイズファクター:小型株効果(SMB)の理論と現実
時価総額が小さい企業が長期的にアウトパフォームする傾向、小型株効果の理論と、その有効性の変化について解説します。 - クオリティファクター:財務健全性が生み出す超過リターン
ウォーレン・バフェットも重視する「質の高い企業」に焦点を当て、その防御的特性とリターンの源泉を分析します。 - 収益性ファクター:なぜ「儲かっている」企業は強いのか?
企業の「儲ける力」が、いかにして長期的な超過リターンにつながるかを、売上総利益という指標から深掘りします。 - インベストメントファクター:なぜ「投資をしない」企業がアウトパフォームするのか?
投資の世界の常識に逆らう、総資産成長率が低い企業が優位性を持つという逆説的なファクターを解説します。 - マルチファクターモデルの構築:複数のエッジを組み合わせる技術
複数のファクターを組み合わせることで、より安定したリターンを目指す高度な戦略と、その実践における課題を論じます。 - ファクターのシクリカリティ:市場サイクルとファクターパフォーマンスの関係
ファクターの有効性が景気や市場のサイクルによって変動する、動的な性質とその応用、そしてリスクについて考察します。 - ファクターの減衰:なぜ発見されたアノマリーは消えていくのか?
論文として公表されたアノマリーの超過リターンが失われる現象と、その背後にあるメカニズムを深く掘り下げます。 - 「ファクター動物園」問題:数百のアノマリーから本物を見分ける方法
学術研究で発見された数百ものファクターの中から、データマイニングの産物ではない「本物」を見分けるための基準を解説します。
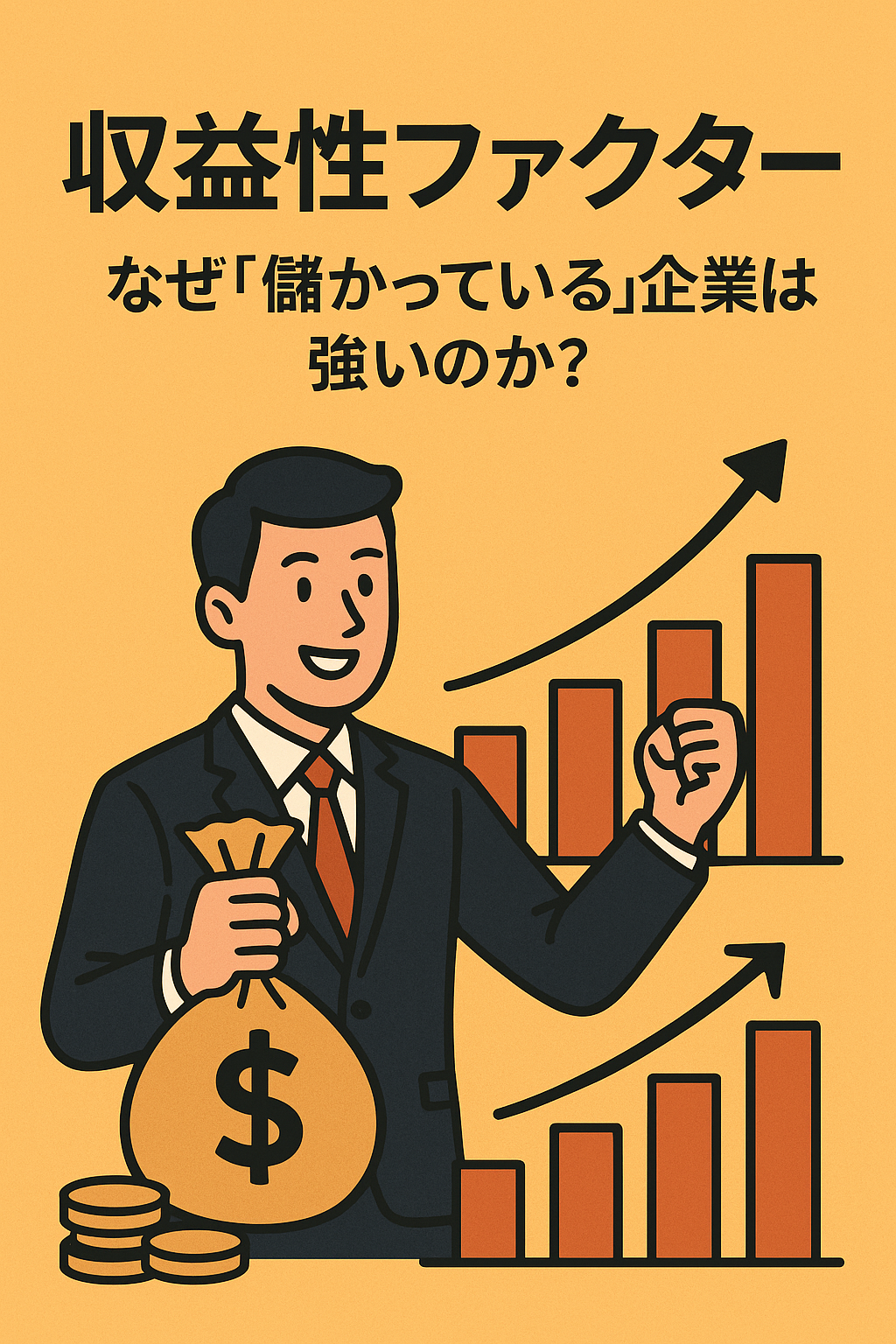
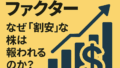
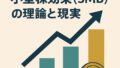
コメント