概論:静的ではないファクターリターン
これまでの記事で解説してきたバリュー、モメンタム、クオリティといったファクターは、長期的に見れば市場平均を上回るリターンを提供してきました。しかし、そのリターンは決して一直線に得られるものではありません。ファクターのパフォーマンスは、経済や市場の状況によって周期的に変動する、すなわち「シクリカリティ(Cyclicality)」を持つことが知られています。
ある年には市場を大きくアウトパフォームしたファクターが、次の年には一転して市場に劣後する。このような現象はなぜ起こるのでしょうか。それは、ファクターリターンが経済のファンダメンタルズと無関係な統計上の偶然ではなく、現実の景気サイクルや市場参加者の心理サイクル(センチメント)と深く結びついているためです。
この関係性を学術的に示した初期の研究の一つが、リューとヴァッサロウによる2000年の論文です。彼らは、バリューファクター(HML)とモメンタムファクター(UMD)が、将来のGDP成長率を予測する上で有意な情報を含んでいることを発見しました [1]。これは、ファクターのパフォーマンスが、将来の経済が好転するか悪化するかというマクロ経済環境の変化を先取りして動く傾向があることを示唆しています。
ファクターのシクリカリティを理解することは、自らのポートフォリオがなぜ好調なのか、あるいは不調なのかを理解するための鍵となります。そして、それは「ファクタータイミング」という、より高度な戦略の可能性と、その大きなリスクの両方を私たちに教えてくれるのです。
長短の解説と損益の事例紹介
ファクターのシクリカリティを理解すれば、それを戦略的な強みとして活かせる可能性があります。しかし、その一方で、サイクルを読み違えることは深刻な損失に繋がる危険もはらんでいます。
長所、強み、いい点について
景気サイクルに応じた強み(収益事例)
各ファクターは、特定の経済局面で強みを発揮する「個性」を持っています。イルマネン、イスラエル、モスコウィッツによる、約100年間のデータを分析した2019年の包括的な研究は、この個性を明確に示しています [2]。
- 景気後退期(Recession):経済の先行きが不透明になり、投資家がリスク回避的になる局面では、クオリティや低ボラティリティといったディフェンシブなファクターが強みを発揮します。財務が健全で、事業が安定している「質の高い」企業は、不況下でもキャッシュフローを稼ぎ出すため、市場全体が下落する中でも相対的に株価が底堅く推移する傾向があります。
- 景気回復期(Recovery):経済が底を打ち、回復へと向かう局面では、バリューやサイズといった景気敏感なファクターが力強いパフォーマンスを見せます。景気後退期に売り込まれ、極端に割安になった景気敏感株や小型株は、経済活動の正常化と共に、その価値が見直される過程で大きく上昇するのです。この現象は、景気が悪い時期にこそ、投資家がこれらの銘柄を保有するために要求するリスクプレミアムが最大化し、その後の景気回復と共にそのプレミアムが実現されるためであると説明されています [3]。
短所、欠点、リスクについて
ファクタータイミングの罠(損失事例)
景気サイクルとパフォーマンスの関係が分かっているなら、サイクルを予測してファクターを乗り換える「ファクタータイミング」を行えば、さらに高いリターンが得られるように思えます。しかし、これは理論通りにはいかない、極めて困難な挑戦です。
- モメンタム・クラッシュ:ファクターのシクリカリティがもたらす最も劇的な損失事例が「モメンタム・クラッシュ」です。ダニエルとモスコウィッツによる2016年の研究は、この現象を詳細に分析しました [4]。モメンタム戦略は、通常は安定したリターンを生み出しますが、金融危機の後のような、市場が急落し、その後急反発する特定の局面で、突如として壊滅的な損失を出すことがあります。これは、市場の底で最も売り込まれていた銘柄(モメンタム戦略が空売りしている対象)が、急反発局面で最も大きく上昇するためです。サイクルが転換するまさにその瞬間に、戦略が裏目に出てしまうのです。
- センチメント・サイクルの罠:市場のパフォーマンスは、実体経済だけでなく、投資家の過熱した心理、すなわちセンチメントのサイクルにも大きく影響されます。スタンバー、ユー、ユアンによる2012年の研究は、多くのアノマリー(ファクターリターン)が、投資家センチメントが高い(市場が楽観に沸いている)時期の後に、最もパフォーマンスが悪化することを示しました [5]。楽観的な時期に形成された価格の歪みが、センチメントが反転する過程で一気に修正され、大きな損失に繋がるのです。
これらの事例は、ファクターのシクリカリティが、収益機会であると同時に、予測困難で深刻なリスクの源泉でもあることを示しています。そのため、多くの学術研究や実践家は、安易なファクタータイミングに警鐘を鳴らしているのです [2, 6]。
非対称性と摩擦の視点
なぜ、景気や市場のサイクルによってファクターのパフォーマンスはこれほどまでに変化するのでしょうか。そして、なぜその関係性を利用して、誰もが簡単に利益を上げることができないのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かします。
Asymmetry:マクロ経済と市場心理の「非対称な」影響
ファクターのシクリカリティの根源には、経済や市場の状態変化が、各ファクターのリターンに対して「非対称な」影響を与えるという事実が存在します。
景気が良い時期には、多くの企業が恩恵を受け、投資家のリスク許容度も高まるため、様々なファクター間のパフォーマンスの差は比較的小さくなるかもしれません。しかし、ひとたび景気後退期に突入すると、状況は一変します。投資家のリスク回避姿勢は、好況期の楽観姿勢よりも遥かに強く、急激に高まります。この市場心理の非対称性が、ファクターのパフォーマンスに劇的な差をもたらすのです。
例えば、投資家は企業の倒産リスクに極めて敏感になり、財務的に脆弱な企業(低クオリティ株、一部のバリュー株)を投げ売りする一方で、財務が健全な企業(高クオリティ株)へと資金を逃避させます。また、市場がパニックから急反発する局面では、それまで最も売り込まれていた銘柄群が最も激しく買い戻されるという、極端なリターンの反転が起こります。これが「モメンタム・クラッシュ」の引き金となります [4]。
このように、市場のサイクルは、すべてのファクターに均一な影響を与えるのではなく、その時々の投資家の心理状態を反映して、特定のファクターを極端に有利にしたり、不利にしたりするという非対称な性質を持っているのです。
Friction:タイミングを阻害する「予測」という究極の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、ファクターのシクリカリティを利用した戦略の前に立ちはだかる、より本質的で克服困難な摩擦が存在します。
1.経済予測の不確実性という摩擦
ファクターのパフォーマンスが景気サイクルと連動していることは、過去のデータを振り返れば明らかです [2, 3]。しかし、最も重要な問題は、「今がサイクルのどの地点にいるのか」そして「サイクルがいつ転換するのか」を、事前に正確に予測することが極めて困難であるという点です。
経済指標は遅行したり、ノイズが多かったりするため、景気後退が公式に認定される頃には、市場はすでにその大部分を織り込み済みであることも少なくありません。この「予測の不確実性」という究極の摩擦が、安易なファクタータイミングを機能不全に陥らせる最大の原因です。サイクルを読み間違えれば、本来なら強みを発揮するはずのファクターが最もパフォーマンスの悪い時期に投資してしまうという、最悪の結果を招きかねません。
2.レジーム・チェンジという摩擦
過去のサイクルで有効だったパターンが、未来も同じように繰り返されるとは限りません。金融政策、技術革新、地政学的リスクなどによって、市場の構造そのものが変化(レジーム・チェンジ)することがあります。例えば、過去のデータではインフレ局面で価値株が有利だったとしても、未来のインフレが全く異なる原因で引き起こされた場合、同じ結果になるとは断定できません。この「市場構造の変化(レジーム・チェンジ)」という摩擦は、過去のデータに依存するタイミング戦略の有効性を根本から揺るがすリスクとなります。
用語集
ファクターのシクリカリティ バリューやモメンタムといったファクターのパフォーマンスが、景気や市場のサイクルに応じて周期的に変動する性質。
景気サイクル 好況、後退、不況、回復というように、経済活動が周期的に拡大と縮小を繰り返す循環のこと。
センチメント 市場参加者の総意として形成される、楽観や悲観といった市場全体の心理状態や雰囲気のこと。
バリューファクター 企業のファンダメンタルズに対して株価が割安な銘柄群が、長期的にアウトパフォームする傾向。
モメンタムファクター 過去に価格が上昇した銘柄群が、その後もアウトパフォームする傾向。
クオリティファクター 財務的に健全で収益性の高い「質の高い」企業群が、長期的にアウトパフォームする傾向。
モメンタム・クラッシュ 市場が急落し、その後急反発する特定の局面で、モメンタム戦略が突如として大きな損失を出す現象。
ファクタータイミング 景気や市場のサイクルを予測し、その局面で最もパフォーマンスが良いと期待されるファクターに投資対象を切り替えるアクティブな戦略。
ディフェンシブ 景気後退期や市場の混乱時にも、比較的価格が安定し、下落しにくいとされる性質。クオリティや低ボラティリティファクターがこれに該当する。
リスクプレミアム ある資産を保有する際に、その資産が持つリスクを引き受けることへの対価として、無リスク資産のリターンを上回って期待される追加的なリターンのこと。
参考文献一覧
[1] Liew, J., & Vassalou, M. (2000). Can book-to-market, size and momentum be risk factors that predict economic growth?. Journal of Financial Economics, 57(2), 221-245.
https://doi.org/10.2139/SSRN.159293
[2] Ilmanen, A., Israel, R., & Moskowitz, T. J. (2019). Factor premia and factor timing: A century of evidence. Journal of Investment Management, 17(3), 1-36.
[3] Henkel, S. J., Martin, J. S., & Nardari, F. (2011). Time-varying short-horizon predictability. Journal of Financial Economics
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.09.008
[4] Daniel, K., & Moskowitz, T. J. (2016). Momentum crashes. Journal of Financial Economics, 122(2), 221-247.
https://doi.org/10.3386/w20439
[5] Stambaugh, R. F., Yu, J., & Yuan, Y. (2012). The short of it: Investor sentiment and anomalies. Journal of Financial Economics, 104(2), 288-302.
https://doi.org/10.3386/w16898
[6] Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5
ファクター投資の知識をさらに深めるための全記事リスト
この記事をお読みいただきありがとうございます。ファクター投資という奥深いテーマを、より体系的に理解していただくために、当メディア「Asymmetry Signal」が提供する関連する全記事をまとめました。
ご自身の興味やレベルに合わせて、ぜひ次のステップにお進みください。
- ファクター投資とは何か?市場を超えるリターンの源泉
ファクター投資の基本概念と、その歴史的背景を網羅的に解説しています。ファクター投資への第一歩に最適な記事です。 - バリューファクター:なぜ「割安」な株は報われるのか?
「安く買って高く売る」という投資の原則を科学したバリュー投資の核心を、学術的知見から解き明かします。 - サイズファクター:小型株効果(SMB)の理論と現実
時価総額が小さい企業が長期的にアウトパフォームする傾向、小型株効果の理論と、その有効性の変化について解説します。 - クオリティファクター:財務健全性が生み出す超過リターン
ウォーレン・バフェットも重視する「質の高い企業」に焦点を当て、その防御的特性とリターンの源泉を分析します。 - 収益性ファクター:なぜ「儲かっている」企業は強いのか?
企業の「儲ける力」が、いかにして長期的な超過リターンにつながるかを、売上総利益という指標から深掘りします。 - インベストメントファクター:なぜ「投資をしない」企業がアウトパフォームするのか?
投資の世界の常識に逆らう、総資産成長率が低い企業が優位性を持つという逆説的なファクターを解説します。 - マルチファクターモデルの構築:複数のエッジを組み合わせる技術
複数のファクターを組み合わせることで、より安定したリターンを目指す高度な戦略と、その実践における課題を論じます。 - ファクターのシクリカリティ:市場サイクルとファクターパフォーマンスの関係
ファクターの有効性が景気や市場のサイクルによって変動する、動的な性質とその応用、そしてリスクについて考察します。 - ファクターの減衰:なぜ発見されたアノマリーは消えていくのか?
論文として公表されたアノマリーの超過リターンが失われる現象と、その背後にあるメカニズムを深く掘り下げます。 - 「ファクター動物園」問題:数百のアノマリーから本物を見分ける方法
学術研究で発見された数百ものファクターの中から、データマイニングの産物ではない「本物」を見分けるための基準を解説します。

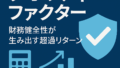
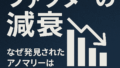
コメント