概論:市場に潜むリターンの源泉を探る
なぜ、一部の投資家は長期的に市場の平均利益を上回り続けることができるのでしょうか。運や勘といった曖昧な要素を除外し、その問いに学術的な厳密さで迫るアプローチが「ファクター投資」です。これは、株式など個別の資産価格を動かす、背景に存在する共通の要因(ファクター)を特定し、その要因に投資することで、市場平均を超えるリターンの獲得を目指す体系的な戦略を指します。
この概念は、現代ファイナンス理論の根幹であった資本資産評価モデル(CAPM)への挑戦から始まりました。CAPMは、資産のリターンは市場全体のリスク(ベータ)をどれだけ取るかだけで決まる、という考え方でした。しかし、研究が進むにつれ、この理論だけでは説明できない、市場に存在する数々の「アノマリー(経験則)」が発見されていきました [1]。
この流れを決定づけたのが、経済学者ユージン・ファーマとケネス・フレンチによる1993年の研究です。彼らは、株式のリターンをより精緻に説明するためには、従来の市場リスクに加えて、以下の二つの要因が重要であることを発見しました [2]。
- サイズファクター:企業の時価総額が小さい(小型株)ほど、リターンが高くなる傾向。
※サイズファクター:小型株効果(SMB)の理論と現実(https://www.asymmetrysignal.com/finance/archives/340)で詳細に解説しています。 - バリューファクター:企業の純資産に対して株価が割安(高ブックマーケット比率)なほど、リターンが高くなる傾向。
※バリューファクター:なぜ「割安」な株は報われるのか?(https://www.asymmetrysignal.com/finance/archives/314)で詳細に解説しています。
この「ファーマ=フレンチの3ファクターモデル」の登場により、リターンは単一の要因ではなく、複数のファクターによって駆動されているという考え方が学術的に確立されました。その後、研究はさらに進展し、マーク・カーハートは1997年に、過去の価格トレンドが継続する傾向を示す「モメンタム」を第4のファクターとして追加し、モデルの予測力を高めました [3]。
※モメンタムファクターは、ファクターのシクリカリティ:市場サイクルとファクターパフォーマンスの関係(https://www.asymmetrysignal.com/finance/archives/363)で言及されているように、景気サイクルと深く関連しています。
そして2015年、ファーマとフレンチ自身が、企業の「収益性(プロフィタビリティ)」と「投資姿勢(インベストメント)」という新たなファクターを加え、現代のファクター投資の基礎となる5ファクターモデルを提唱するに至ります [4]。
※収益性ファクター:なぜ「儲かっている」企業は強いのか?(https://www.asymmetrysignal.com/finance/archives/318)で詳細に解説しています。
※インベストメントファクター:なぜ「投資をしない」企業がアウトパフォームするのか?(https://www.asymmetrysignal.com/finance/archives/346)で詳細に解説しています。
※複数のファクターを組み合わせるメリットについては、マルチファクターモデルの構築:複数のエッジを組み合わせる技術(https://www.asymmetrysignal.com/finance/archives/398)で詳細に解説しています。
ファクター投資とは、このように学術研究によって特定された、統計的に頑健で、経済的な合理性を持つリターンの源泉に、規律をもって投資するアプローチなのです。
長所の解説と収益事例
ファクター投資の最大の強みは、その背後に数十年間にわたる膨大なデータによる裏付けがあることです。これは単なる一時的な流行や特定の市場だけで通用する戦術ではなく、より普遍的な現象である可能性が多くの研究によって示されています。
強み1:理論的背景と再現性
ファクター投資は、感情や相場観といった属人的なスキルへの依存を減らし、ルールに基づいた規律ある投資を可能にします。各ファクターには、「なぜそれがリターンを生むのか」について、リスクプレミアム(割安株は倒産リスクが高い分、リターンも高い)や、行動ファイナンス(投資家の非合理的な行動が価格の歪みを生む)といった理論的な説明が試みられており、その有効性は長期間のデータで検証されています [2, 7]。
強み2:グローバル市場で確認された有効性(収益事例)
ファクターの有効性は、米国市場だけでなく、国境や資産クラスを超えて普遍的に観測されることが、この戦略の信頼性を大きく高めています。
クリフ・アスネス、トビアス・モスコウィッツ、ラッセ・ペデルセンによる2013年の影響力のある研究「Value and Momentum Everywhere」は、その強力な証拠を提示しました。彼らは、1972年から2011年までのデータを使い、個別の株式(米国、英国、欧州、日本)、国の株価指数、為替、債券、コモディティという、全く異なる24の市場と資産クラスでテストを行いました。
その結果は驚くべきものでした。バリュー(安いものは高いものよりリターンが高い)とモメンタム(上がっているものは上がり続け、下がっているものは下がり続ける)という二つのファクターが、調査したほぼすべての市場で、統計的に有意なプラスのリターンを生み出していたのです [5]。この結果は、ファクターが単なる米国の株式市場における偶然の産物ではなく、市場を動かす根源的な力であることを強く示唆しています。
強み3:ポートフォリオの分散効果
各ファクターは、それぞれ異なる経済環境や市場心理の局面で強みを発揮する傾向があります。例えば、バリューファクターとモメンタムファクターは、歴史的に負の相関関係に近い動きを示すことが知られています [5]。つまり、バリューが好調な時期にはモメンタムが不調になりやすく、その逆もまた然り、ということです。
これは、単一のファクターに依存するのではなく、複数のファクター(マルチファクター)を組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリターンをより安定させ、リスクを分散させる効果が期待できることを意味します。あるファクターが不調な時期の落ち込みを、別のファクターが補うことで、長期的に、より滑らかなリターンを目指すことが可能になるのです。
短所とリスク:手放しでは称賛できない現実
ファクター投資は強力な枠組みですが、決して「必ず儲かる魔法」ではありません。その有効性が広く知られるにつれ、いくつかの深刻な問題点やリスクが学術研究によって指摘されています。
短所1:アノマリーの減衰と陳腐化
市場の非効率性(アノマリー)は、発見され、多くの投資家に知れ渡ると、その優位性が失われていく傾向があります。ウィリアム・シュワートによる2003年の包括的なレビューによれば、学術論文で報告されたアノマリーの多くは、その論文が出版された後にパフォーマンスが低下するか、場合によっては消滅することが示されています [1]。
これは、多くの投資家が同じ「エッジ」を利用しようと殺到することで、価格の歪みが修正され、裁定機会が失われてしまうためです。つまり、過去に有効だったファクターが、未来永劫有効である保証はどこにもないのです。
※この現象については、ファクターの減衰:なぜ発見されたアノマリーは消えていくのか?(https://www.asymmetrysignal.com/finance/archives/377)で詳しく掘り下げています。
短所2:「ファクター動物園」とデータマイニングの問題
近年、リターンを予測するとされる「ファクター」が爆発的に発見され、その数は数百にも上ります。キャンベル・ハーヴェイらの2016年の研究は、この乱立状況を痛烈に「ファクター動物園 (Factor Zoo)」と揶揄しました [6]。
彼らの分析によれば、発見されたファクターの多くは、研究者が意図的、あるいは無意識的に過去のデータに過剰に適合させてしまった「データマイニング(データ snooping)」の産物である可能性が高いと結論付けています。統計学的な偶然によって過去のデータ上では有効に見えただけで、再現性がなく、将来のリターン予測には全く役立たない「偽りのファクター」が動物園には多数紛れ込んでいる、という厳しい指摘です。
※「ファクター動物園」問題:数百のアノマリーから本物を見分ける方法(https://www.asymmetrysignal.com/finance/archives/382)で詳細に論じています。
非対称性と摩擦の視点
では、なぜ本当に有効なファクターは、減衰しつつも完全には消滅しないのでしょうか。その本質を、当メディア「Asymmetry Signal」の根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かします。
Asymmetry:収益機会の源泉としての「期待の非対称性」
ファクターが超過リターンを生む根源には、市場参加者の「期待の非対称性」が存在します。これは、投資家が必ずしも教科書通りに合理的に行動しないことから生じます。
例えば、バリューファクターがなぜ機能するのか。ラコニショック、シュライファー、ヴィシュニーによる1994年の研究は、多くの投資家が過去の業績を将来に過度に当てはめてしまう傾向(外挿バイアス)を指摘しています [7]。
具体的には、過去に高い成長を遂げた華やかな「グロース株」の未来を過度に楽観視し、その成長が永遠に続くかのように期待を織り込んで高値で買ってしまいます。一方で、業績が一時的に低迷している地味な「バリュー株」の未来を過度に悲観視し、まるで倒産するかのように売り叩いてしまうのです。
この、楽観と悲観の「期待の非対称性」こそが、市場に価格の歪みを生み出します。ファクター投資とは、この非対称性を客観的に検出し、市場の行き過ぎた期待が現実へと修正される過程を利用することで、収益機会に変える試みと言えるのです。
Friction:収益を阻害する「諸悪の根源」
もし市場が完全に滑らか(frictionless)な理想的環境であれば、上記のような価格の歪みは、瞬時にプロの投資家の裁定取引によって解消されるはずです。しかし、現実の市場は、リターンの獲得を妨げ、コストとして収益を蝕む様々な「摩擦(Friction)」に満ちています。これらは、常に検出し、破壊・除去を試みるべき対象です。
1.取引コストという摩擦
スプレッド、手数料、そして大口注文が価格を不利な方向に動かしてしまうマーケットインパクトといった直接的なコストは、最も分かりやすい摩擦です。特に、銘柄の入れ替えが頻繁に必要なモメンタム戦略や、流動性の低い小型株を対象とする戦略では、この摩擦がリターンを大きく蝕む主要な原因となります。
2.制度的摩擦という摩擦
ファンドマネージャーの多くは、四半期や年次といった短い期間のパフォーマンスで評価されます。バリュー戦略のように、効果が出るまでに数年かかることもある戦略は、短期的な不振期に顧客からの資金流出や解雇といった「キャリアリスク」をもたらします。このため、長期的に有効だと頭では理解していても、実行をためらわせる強い圧力、すなわち摩擦として機能します。
アンドレ・シュライファーとロバート・ヴィシュニーが1997年に発表した論文「裁定取引の限界」は、このような現実世界の摩擦が、なぜ市場の非効率性を存続させるのかを理論的に説明しています [8]。裁定取引は、理論上はリスクフリーであっても、現実には様々なコストとリスク(摩擦)を伴うため、価格の歪みは完全には解消されないのです。
用語集
- ファクター 株式などのリターンを長期的に説明するとされる、共通の性質や特徴のこと。
- アルファ 市場全体の動き(ベータ)や、既知のファクターでは説明できない、純粋な超過リターン。
- ベータ 個別の株式が、市場全体の動きに対してどれくらい敏感に反応するかを示す指標。
- 効率的市場仮説 市場価格は利用可能な全ての情報を即座に織り込んでいるため、継続的に市場を上回ることはできないとする理論。
- バリュー 企業のファンダメンタルズ(純資産や利益)に対して、株価が割安であるという性質。
- モメンタム 過去の価格トレンドが継続しやすいという性質。過去に上昇した銘柄は上昇しやすく、下落した銘柄は下落しやすい傾向。
- クオリティ 企業の財務的な健全性、収益性、成長の安定性といった「質」の高さを示す性質。
- シャープ・レシオ リターンを、そのリターンを得るために取ったリスクの大きさで割った値。リスク調整後のパフォーマンスを測る指標。
- 裁定取引 同一の価値を持つ資産間で価格差が生じた際に、割安な方を買い、割高な方を売ることで、リスクなく利益を得ようとする取引。
- リスク調整後リターン リターンの絶対額だけでなく、そのリターンを得るためにどれだけのリスクを取ったかを考慮に入れたリターンのこと。
参考文献一覧
[1] Schwert, G. W. (2003). Anomalies and market efficiency. In G. M. Constantinides, M. Harris, & R. M. Stulz (Eds.), Handbook of the Economics of Finance (Vol. 1, Part B, pp. 939-974). Elsevier.
[2] Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
[3] Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance, 52(1), 57-82.
[4] Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1-22.
[5] Asness, C. S., Moskowitz, T. J., & Pedersen, L. H. (2013). Value and Momentum Everywhere. The Journal of Finance, 68(3), 929-985.
[6] Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). …and the Cross-Section of Expected Returns. The Review of Financial Studies, 29(1), 5-68.
[7] Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk. The Journal of Finance, 49(5), 1541-1578.
[8] Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). The Limits of Arbitrage. The Journal of Finance, 52(1), 35-55.

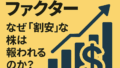
コメント