第1章 1ファクターの世界:資本資産価格モデル(CAPM)の優雅さと支配
今回は当サイトで最も引用回数の多いファーマ&フレンチの研究について徹底的に解説します。日本語圏で、オンラインで無料で全文閲覧可能な記事で、ファーマ&フレンチの研究について、この記事よりも詳しく説明した記事はおそらく、2025年9月現在、存在しないのではないかと思われます。もしこれよりも詳しい記事があったら是非教えて下さい。記事内にリンクを貼ってご紹介します。
ファーマ&フレンチの一連の研究は本当にとんでもない研究で、ブラック&ショールズと並ぶ、人類がもたらした偉大な2大経済研究です。
現代ファイナンスの中心的な問いは、ある投資のリスクとその期待リターン(将来得られると見込まれる収益)との関係をいかにして定量化するか、という点にあります 。この根源的な問いに対し、1960年代にウィリアム・シャープ、ジョン・リントナー、ヤン・モッシンがそれぞれ独立して構築した「資本資産価格モデル(Capital Asset Pricing Model、CAPM)」は、初めて首尾一貫した理論的枠組みを提供しました 。
CAPMが登場する以前、資産の期待リターンを評価する手法は体系的ではありませんでした。多くの場合、企業の財務構造(負債と自己資本の比率など)に焦点が当てられていましたが、リスクを普遍的に測定する尺度は存在しませんでした 。CAPMの革命的な点は、リスクを二つの種類に明確に分類したことにあります。一つは「アンシステマティック・リスク(非システマティック・リスク)」で、これは個別企業に特有のリスク(例:工場の火災、新製品の失敗など)を指します。この種のリスクは、多数の銘柄に分散投資することで、理論上はほぼ完全に消去することが可能です。もう一つは「システマティック・リスク」で、これは市場全体に影響を及ぼすリスク(例:金利変動、インフレ、景気後退など)を指します。このリスクは分散投資によっても消去することができません 。CAPMが提示した極めて重要な洞察は、「投資家は、自らが回避できないリスク、すなわちシステマティック・リスクを引き受けることに対してのみ、対価(より高い期待リターン)を要求すべきである」というものでした 。
この理論に基づき、CAPMはシステマティック・リスクを測定するための単一の指標として「ベータ(β)」を導入しました 。ベータとは、ある資産のリターンが市場全体のリターンの動きに対してどれほど敏感に反応するかを示す尺度です。市場全体のベータを1.0とした場合、ベータが1.0より大きい株式は市場よりも値動きが激しく(ハイリスク・ハイリターン)、1.0より小さい株式は市場よりも値動きが穏やかである(ローリスク・ローリターン)とされます。CAPMの核心的な予測は、ある資産の期待リターンは、その資産のベータとの間に正の線形関係によって「のみ」決定される、というものでした 。
この関係は、「証券市場線(Security Market Line、SML)」と呼ばれるグラフで視覚的に表現されます。SMLは、横軸にベータ(リスク)、縦軸に期待リターンをとり、リスクが高い(ベータが大きい)資産ほど、より高い期待リターンが要求されることを示す右上がりの直線となります。理論上、すべての資産の期待リターンはこの直線上にプロットされるはずであり、SMLより上に位置する資産は割安、下に位置する資産は割高と判断されました 。
CAPMの真のインパクトは、その数式の精緻さだけではなく、複雑怪奇なリスクの世界を「ベータ」というたった一つの数字に集約した、そのラディカルな単純さにありました。この優雅さと簡潔さゆえに、CAPMは学術界のみならず、企業の設備投資の意思決定からポートフォリオ管理に至るまで、金融実務のあらゆる場面で広く採用される標準的なツールとなりました 。
さらに、CAPMは科学的なモデルとして極めて重要な性質を持っていました。それは、「資産の期待リターンの断面的な差異を説明する変数はベータだけである」という、明確で検証可能な(反証可能な)予測を提示したことです 。この厳密な予測があったからこそ、研究者たちはCAPMが現実の市場をどれだけ正確に説明できるかを実証的にテストすることができました。結果として、この反証可能性こそが、後に続く研究の道を切り開き、最終的にはCAPM自体の限界を明らかにし、新たなモデルの誕生を促す土壌となったのです。CAPMの支配は、研究者たちに明確な一つの的を提供し、それを検証し、そして最終的にそれに挑戦する動機を与えたのです。
第2章 迫りくる嵐:CAPMでは説明できないアノマリー
CAPMの理論的優雅さとは裏腹に、1970年代から80年代にかけて、その予測と現実の株式リターンとの間に体系的な乖離が存在することが、実証研究によって次々と明らかになっていきました。これらの乖離は「市場のアノマリー」と呼ばれます。アノマリーとは、CAPMのような支配的な資産価格理論とは整合しない、予測可能なリターンのパターンのことを指します 。アノマリーの存在が示唆するのは、次の二つのうちのいずれかです。すなわち、市場が非効率であり、裁定機会(リスクなしで利益を得る機会)が存在するのか、あるいは、リスクを測定するモデル自体が不完全であるのか、という問題です 。
バリュー効果(Basu, 1977)
CAPMへの最初の重大な挑戦の一つは、サンジョイ・バスーによる1977年の論文「Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis」によって提示されました 。この論文のアブストラクトは、株価収益率(PER)が低い銘柄は高い銘柄をアウトパフォームする傾向があるという「プライス・レシオ仮説」を検証することを目的としていました 。バスーの研究は、PERが低い(一般に「バリュー株」や「割安株」と見なされる)銘柄で構成されたポートフォリオが、PERが高い(「グロース株」や「成長株」と見なされる)銘柄のポートフォリオよりも、リスク調整後リターンにおいても絶対リターンにおいても、体系的に高い収益を上げていたことを明らかにしました 。これはCAPMの予測とは相容れない結果でした。CAPMによれば、リターンの差はベータの差によってのみ説明されるはずであり、PERのような変数がリターンと体系的な関係を持つべきではなかったからです。これは後に「バリュー効果」として知られるアノマリーの初期の発見でした。
サイズ効果(Banz, 1981)
もう一つの決定的なアノマリーは、ロルフ・バンツが1981年に発表した論文「The relationship between return and the total market value of NYSE common stocks」で示されました 。この論文のアブストラクトは、「平均して、小規模な企業(時価総額が小さい企業)は、大規模な企業よりも高いリスク調整後リターンを上げてきた」と明確に結論付けています 。この「サイズ効果」は、少なくとも40年間にわたって存在しており、バンツはこれを「資本資産価格モデルが誤って特定されている(misspecified)証拠である」と断じました 。この効果は線形ではなく、特に最も時価総額の小さい企業群において顕著に見られました 。
これらの発見は、単なる統計上の奇妙な現象として片付けられるものではありませんでした。特にバンツは、自身の発見をCAPM理論そのものの根本的な欠陥として位置づけました。彼の論文のアブストラクトで使われた「misspecified」という言葉は、CAPMが現実のリスクとリターンの関係を捉えきれていないという、金融界のパラダイムに対する直接的な挑戦状でした。
これらのアノマリーの発見は、金融学の研究者たちを重大な岐路に立たせました。この「超過リターン」は、投資家が特定の種類の株式を非合理的に誤って価格付けしている「市場の非効率性」の現れなのでしょうか(これは後の行動ファイナンス理論につながる考え方です)。それとも、CAPMが定義するリスク(ベータのみ)が不完全であり、「サイズ」や「バリュー」といった企業特性は、CAPMでは測定されていない別のシステマティック・リスクの代理変数(プロキシ)であり、合理的な投資家がそのリスクを引き受ける対価として正当な報酬を得ているのでしょうか。この「市場の非効率性か、不完全なモデルか」という知的対立こそが、その後30年以上にわたる資産価格研究の舞台を設定し、ユージン・ファーマとケネス・フレンチの研究が登場する背景となったのです。
第3章 革命の始まり:ファーマ=フレンチの3ファクターモデル
CAPM理論を揺るがしたアノマリーという知的パズルに対し、シカゴ大学のユージン・ファーマとケネス・フレンチは、1990年代に一連の画期的な論文を発表し、資産価格理論に革命をもたらしました。彼らは、アノマリーを「市場の非効率性」の証拠と見なすのではなく、「リスク・モデルの不完全性」の現れと捉え、CAPMに代わる新たな枠組みを実証的に構築しました。
3.1. 実証的破壊(1992年):”The Cross-Section of Expected Stock Returns”
ファーマとフレンチの革命は、CAPMの牙城を実証的に突き崩すことから始まりました。この1992年の論文のアブストラクトは、金融界に衝撃を与える結論を簡潔に述べています。それは、測定が容易な二つの変数、すなわちサイズ(企業の時価総額、ME)と簿価時価比率(Book-to-Market Equity、BE/ME、バリュー度を測る指標)が、「株式の平均リターンの断面的なばらつきを捉える」というものでした 。さらに決定的だったのは、CAPMの根幹をなすベータに関する次の発見です。「市場ベータと平均リターンの関係は、ベータが唯一の説明変数である場合でさえ、フラット(無関係)である」 。これは、企業のサイズとバリュー特性を考慮に入れると、ベータには株式リターンを説明する力がほとんど残っていないことを意味していました。長年にわたりリスクの唯一の尺度とされてきたベータが、その役割を果たしていないことを実証的に示したのです。
3.2. 新たな枠組み(1993年):”Common risk factors in the returns on stocks and bonds”
1992年の論文で「何が」リターンを説明するかを示したファーマとフレンチは、翌1993年のこの論文で「なぜ」そうなるのかを説明する理論的枠組みを提示しました。アブストラクトは、「株式と債券のリターンにおける5つの共通リスクファクター」を特定したと述べています 。特に株式については、以下の3つのファクターを特定しました。
- 市場ファクター全体:CAPMの市場リスクと同様のもの。
- サイズファクター(SMB – Small Minus Big):小型株ポートフォリオのリターンから大型株ポートフォリオのリターンを差し引いたもの。これは「サイズプレミアム」(小型株が大型株を上回るリターンを上げる傾向)を捉えることを目的としています。
- バリューファクター(HML – High Minus Low):簿価時価比率が高い(バリュー)株ポートフォリオのリターンから、簿価時価比率が低い(グロース)株ポートフォリオのリターンを差し引いたもの。これは「バリュープレミアム」(バリュー株がグロース株を上回るリターンを上げる傾向)を捉えることを目的としています。
この「ファーマ=フレンチの3ファクターモデル」の核心的な主張は、小型株やバリュー株が示す高いリターンはアノマリーではなく、投資家がSMBファクターやHMLファクターに関連するシステマティック・リスクを引き受けることに対する合理的な対価である、というものでした。
3.3. アノマリーの動物園の平定(1996年):”Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies”
3ファクターモデルの真価は、この1996年の論文で示されました。アブストラクトは、それまでの研究で発見された多数の企業特性(サイズ、PER、簿価時価比率など)とリターンの関係、すなわちCAPMでは説明できない「アノマリー」に言及した上で、決定的な結論を提示します。「短期的なリターンの継続性を除き、これらのアノマリーは3ファクターモデルの中でほぼ消失する」 。
これは、PER効果のような多くのアノマリーが、それぞれ独立した現象なのではなく、根底にあるサイズとバリューという二つのリスクファクターが、異なる形で表面化したものに過ぎないことを示唆していました。3ファクターモデルは、これらのアノマリーを体系的に説明することに成功したのです。
1992年の論文と1993年の論文の間には、微妙かつ深遠な知的飛躍が存在します。1992年の論文は、企業の「特性(characteristics)」(サイズや簿価時価比率)がリターンを予測することを示しました。しかし1993年の論文では、これらの特性をシステマティックな「リスクファクター(risk factors)」(SMBやHML)の代理変数として再定義しました。これは彼らの「市場は合理的である」という議論の核心部分です。彼らは「小型株は小さいから買え」と言っているのではなく、「小型株は『小型であること』に付随する共通のリスクに晒されており、投資家はそのリスクを引き受ける対価としてプレミアムを要求する」と主張したのです。この再定義により、アノマリーは合理的なリスクプレミアムとしてファイナンス理論の枠組みに再び取り込まれました。
そして1996年の論文は、この議論の集大成と言えます。それまで無秩序に存在していた「アノマリーの動物園」に秩序をもたらし、多数の現象をたった3つのファクターで説明する、簡潔かつ強力な新しい枠組みを提供しました。これは、実証ファイナンスにおける大きな知的整理であり、理論の統一でした。
第4章 知的論争と第4のファクターの台頭
ファーマとフレンチの3ファクターモデルは、資産価格理論に新たな標準を打ち立てましたが、その解釈が普遍的に受け入れられたわけではありませんでした。また、モデル自体にも説明できない現象が残されていました。このセクションでは、3ファクターモデルに対する主要な反論と、モデルを補完する最も重要な追加要素について概説します。
4.1. 競合する見解:特性か、リスクか(Daniel and Titman, 1997)
ファーマとフレンチの「リスクファクター」という解釈に真っ向から異議を唱えたのが、ケント・ダニエルとシェリダン・ティットマンによる1997年の論文「Evidence on the Characteristics of Cross-Sectional Variation in Stock Returns」でした 。
この論文のアブストラクトは、ファーマとフレンチの主張に対する直接的な反論を展開しています。彼らは、小型株や高簿価時価比率株が示すリターンプレミアムは、「これらの株式が広範なファクターと共変動(comovements)することによって生じるのではない」と主張しました 。そして、「株式リターンの断面的なばらつきを説明しているのは、リターンの共分散構造ではなく、企業特性そのものであるように見える」と結論づけています 。
要するに、ダニエルとティットマンの主張はこうです。市場は、企業が共通のリスクを負っているからではなく、単にその企業が「小さい」から、あるいは「バリュー株である」という「特性」そのものに対して、高いリターンを与えているのだ、と。これは、投資家の認知バイアスや、リスク以外の要因(例えば流動性の低さなど)が価格形成に影響を与えている可能性を示唆しており、ファーマとフレンチの合理的なリスク・ストーリーとは根本的に異なる解釈です。この論文は、アノマリーを巡る「合理的なリスクか、非合理的な価格付けか」という根源的な論争が、3ファクターモデルの登場後も決して終わっていなかったことを明確に示しています。科学の進歩とは、一つの理論がすべてを完全に説明して終わるのではなく、説得力のある対立仮説との絶え間ない緊張関係の中で進んでいくものなのです。
4.2. モメンタム・ファクター(Carhart, 1997)
ファーマとフレンチ自身も、1996年の論文で自らのモデルの限界を認めていました。アブストラクトには、「短期的なリターンの継続性を除き」という留保が付けられており、これは過去に好調だった銘柄がその後もしばらく好調を維持し、不調だった銘柄が不調を続けるという「モメンタム効果」を3ファクターモデルでは説明できないことを示唆していました 。
このパズルの欠けていたピースを提供したのが、マーク・カーハートの1997年の論文「On Persistence in Mutual Fund Performance」です 。カーハートは、投資信託(ミューチュアル・ファンド)のパフォーマンスの持続性を研究する中で、その大部分が「1年間のモメンタム効果」によって説明できることを発見しました 。彼の研究のアブストラクトは、「株式リターンにおける共通ファクターと投資信託の経費が、パフォーマンスの持続性のほぼすべてを説明する」と述べています 。
この分析を行うために、カーハートはファーマ=フレンチの3ファクターモデルに第4のファクターとしてモメンタムを加えました。このファクターは、一般にWML(Winners Minus Losers)やUMD(Up Minus Down)と呼ばれ、過去1年間のリターンが高かった銘柄群を買い、リターンが低かった銘柄群を売るポートフォリオを模倣します。この「カーハートの4ファクターモデル」は、実証研究において極めて高い説明力を持つことが示され、学術研究における標準的なベンチマークモデルとして広く利用されるようになりました 。
モメンタム・ファクターの採用は、金融学のプラグマティズム(実用主義)を示す好例です。サイズやバリューは、企業の財務的困難といった合理的なリスク・ストーリーと結びつけやすいのに対し、モメンタムが存在する理論的根拠はより曖昧で、投資家の過剰反応や過小反応といった行動バイアスに起因すると考えられることが多いです。しかし、その理論的背景の解釈が定まっていなくても、モメンタム効果の経験的な頑健性は否定しがたく、資産価格を分析する上で不可欠なツールとして学術界に受け入れられたのです。
表1:資産価格モデルの進化
| モデル名 | 提唱者 | 年代 | 含まれるファクター |
| 資本資産価格モデル(CAPM) | Sharpe, Lintner, Mossin | 1960年代 | 1. 市場リスク (Mkt-Rf) |
| ファーマ=フレンチの3ファクターモデル | Fama, French | 1993年 | 1. 市場リスク (Mkt-Rf) 2. サイズ (SMB) 3. バリュー (HML) |
| カーハートの4ファクターモデル | Carhart | 1997年 | 1. 市場リスク (Mkt-Rf) 2. サイズ (SMB) 3. バリュー (HML) 4. モメンタム (WML/UMD) |
第5章 モデルの進化とグローバルな展開
ファーマとフレンチの研究は、1993年の3ファクターモデルの発表で終わりませんでした。彼らはその後も自らのモデルを検証し、改良し続けました。その過程で、モデルの頑健性を国際市場で確認し、さらには新たな証拠に基づいてモデル自体を進化させました。これは、彼らのアプローチがデータに基づき、ドグマにとらわれない科学的なものであったことを示しています。
5.1. 国際的な妥当性の検証(1998年):”Value versus Growth: The International Evidence”
3ファクターモデル、特にバリュープレミアムに対して投げかけられた批判の一つに、それが米国市場のデータマイニング(データの中から偶然見つかっただけの見せかけの規則性)の結果に過ぎないのではないか、というものがありました。この批判に対する強力な反証となったのが、1998年のこの論文です。
アブストラクトは、「バリュー株は、世界中の市場でグロース株よりも高いリターンを持つ」と断定しています 。具体的には、1975年から1995年の期間において、調査対象となった主要13市場のうち12市場でバリュー株がグロース株をアウトパフォームし、グローバルなバリュープレミアムは年率7.68%に達したと報告しています 。この結果は、バリュー効果が米国特有の現象ではなく、世界的に見られる普遍的な現象であることを示しました。
異なる市場構造、規制、文化を持つ多数の国々で同じパターンが確認されたという事実は、それが単なる統計上の偶然である可能性を著しく低下させます。むしろ、投資家の行動バイアスが国境を越えて全く同じ形で現れると考えるよりも、バリュー特性に連動する何らかの根源的な経済リスクが存在し、そのリスクに対する対価としてプレミアムが支払われている、という「合理的なリスク」仮説を強く支持する証拠となりました。この国際的な検証は、ファーマとフレンチの議論の信頼性を大幅に高めました。
5.2. 新世代モデルの登場(2015年):”A Five-Factor Asset Pricing Model”
最初の3ファクターモデルの発表から20年以上が経過した2015年、ファーマとフレンチは自らモデルのアップデート版を発表しました。この論文のアブストラクトは、新たな5ファクターモデルが「平均株式リターンにおけるサイズ、バリュー、収益性、投資のパターンを捉えることを目的としている」と述べています 。この新モデルは、従来の市場ファクターとサイズファクター(SMB)は維持しつつ、新たに2つのファクターを加え、バリューファクター(HML)の役割を再検討しました。
- 収益性ファクター(RMW – Robust Minus Weak):営業収益性が高い(Robust)企業の株式リターンから、収益性が低い(Weak)企業の株式リターンを差し引いたもの。これは、収益性の高い企業がより高いリターンを上げる傾向を捉えます。
- 投資ファクター(CMA – Conservative Minus Aggressive):投資姿勢が保守的(Conservative、資産の伸びが低い)な企業のリターンから、投資姿勢が積極的(Aggressive、資産の伸びが高い)な企業のリターンを差し引いたもの。これは、保守的な投資を行う企業がより高いリターンを上げる傾向を捉えます。
そして、この論文のアブストラクトは、驚くべき発見を報告しています。「収益性ファクターと投資ファクターを加えると、FF3ファクターモデルのバリューファクター(HML)は、平均リターンを説明する上で冗長(redundant)になる」 。
これは、ファーマとフレンチが自らの最も有名で影響力のある発見の一つであるHMLファクターを、事実上、時代遅れのものとしたことを意味します。この知的誠実さは、彼らが特定のモデルに固執するのではなく、あくまで経験的証拠を重視する姿勢の現れです。この発見はまた、より深い経済的な洞察をもたらしました。「バリュー」(高い簿価時価比率)という特性自体がリスクの源泉なのではなく、むしろ根底にあるビジネスのファンダメンタルズの「症状」である可能性が示唆されたのです。株価が簿価に対して低い企業(バリュー株)とは、多くの場合、収益性が低かったり、過剰で非効率な投資を行っていたりする企業です。5ファクターモデルは、リターンを駆動するより根源的な要因が、企業の収益性と投資方針にあることを示唆しています。これにより、説明のレベルが統計的な観察(高い簿価時価比率)から、より具体的で触知可能な企業活動(収益を上げ、投資を行う能力)へと深化しました。
第6章 遺産:ファクターの「動物園」と新産業の誕生
ファーマとフレンチの研究がもたらした影響は、学術界の理論的変革にとどまりませんでした。彼らの発見は、新たな研究分野の爆発的な拡大を促し、さらには数兆ドル規模の巨大な金融産業を生み出す直接的な引き金となったのです。
6.1. 警鐘:”…and the Cross-Section of Expected Returns” (Harvey, Liu, and Zhu, 2016)
ファーマとフレンチの成功がもたらした意図せざる結果の一つが、いわゆる「ファクターの動物園(factor zoo)」問題です。彼らがマルチファクター・モデルへの扉を開いたことで、研究者たちは強力なコンピュータと膨大なデータセットを駆使し、リターンを予測しうる新たな「ファクター」を探す競争に乗り出しました。
この状況に警鐘を鳴らしたのが、キャンベル・ハーヴェイ、ヤン・リウ、ヘチン・ジューによる2016年の論文です。彼らのアブストラクトは、「何百もの論文と何百ものファクターが、期待リターンの断面を説明しようと試みている」と指摘し、このような「広範なデータマイニング」を考慮すると、従来用いられてきた統計的有意性の基準(例えばt値が2.0以上)はもはや適切ではないと主張しました 。彼らは、新たに発見されたファクターが本物であると認められるためには、t値が3.0以上という、はるかに高いハードルを越える必要があると提言し、「金融経済学で主張されている研究結果のほとんどは、おそらく誤りである可能性が高い」という衝撃的な結論を述べました 。
これは、ファーマとフレンチの研究の成功が、皮肉にも新たな科学的問題を生み出したことを示しています。つまり、無数の候補の中から、真のリスクファクターと単なるデータマイニングの産物とをいかにして見分けるか、という課題です。ハーヴェイらの研究は、ファーマとフレンチが切り開いた分野に、統計的な規律を取り戻そうとする試みだったのです。
6.2. 理論から実践へ:ファクター投資とスマートベータETF
ファーマとフレンチの研究が残した最も具体的で巨大な遺産は、彼らの学術的発見が直接的に商業化され、「ファクター投資」あるいは「スマートベータ」と呼ばれる新しい投資手法を生み出したことです。
スマートベータとは、従来の時価総額加重型のインデックス投資から脱却し、特定のルールに基づいて、リターンを駆動するとされるファクターに意図的にエクスポージャー(投資配分)を持つようにインデックスを構築する戦略です 。これらの戦略でターゲットとされるファクターは、まさにファーマ、フレンチ、カーハートらが学術的に特定したものであり、最も一般的なものとして、バリュー、サイズ、モメンタム、クオリティ(収益性の代理変数)、低ボラティリティなどが挙げられます 。
金融業界は、これらのファクタープレミアムに、低コストで容易にアクセスできる金融商品として、数多くのETF(上場投資信託)を開発しました 。例えば、「iシェアーズ MSCI 米国バリュー・ファクター ETF (VLUE)」や「バンガード・米国バリュー・ファクターETF (VFVA)」といった商品は、投資家がファーマとフレンチのHMLファクター(あるいはそれに類するバリューファクター)に投資することを可能にします 。今日、この分野は数兆ドル規模の資産を運用する巨大産業へと成長しており、その知的基盤はファーマとフレンチの研究に深く根差しています 。
この現象は、かつて「アルファ(α)」、すなわちアクティブ運用マネージャーの独自のスキルや情報によって生み出されると信じられていた超過リターンが、「ベータ(β)」、すなわち体系的で誰もがアクセス可能なファクターへのエクスポージャーへと姿を変えたことを意味します。ファーマとフレンチの研究以前は、もしあるファンドマネージャーが継続的に割安な小型株に投資して市場を上回る成績を上げていれば、それは彼の卓越した銘柄選択眼の賜物だと考えられていました。しかし、彼らの研究以降、その超過リターンの大部分は、単にサイズとバリューというリスクプレミアムを獲得した結果として説明できるようになりました。スマートベータETFは、このプロセスを「コモディティ化」し、一般の投資家がアクティブマネージャーに高い手数料を支払うことなく、これらのリターンの源泉に体系的に投資することを可能にしたのです 。これこそが、彼らの研究が現実世界に与えた最も大きなインパクトと言えるでしょう。
第7章 結論:実証的革命が残した永続的インパクト
本稿で概観してきたように、ユージン・ファーマとケネス・フレンチの研究は、現代ファイナンスの理論と実践を根底から覆す、まさに革命的なものでした。その影響は、単一の優れた論文にとどまらず、数十年にわたる一貫した実証的探求の積み重ねによって築かれました。
その旅は、CAPMという、理論的には優雅であるものの現実を説明するには不完全であった1ファクターの世界から始まりました。CAPMが予測できないサイズ効果やバリュー効果といった「アノマリー」が次々と発見され、資産価格理論は大きな壁に突き当たります。この混乱に対し、ファーマとフレンチは厳密な実証分析を通じて、これらのアノマリーが市場の非効率性の現れではなく、CAPMが見逃していたシステマティックなリスクファクター(サイズとバリュー)に対する合理的な対価であるという、新たなパラダイムを提示しました。彼らの3ファクターモデルは、それまで無秩序に存在していた多くのアノマリーを統一的に説明し、学術界に新たな標準を打ち立てました。
しかし、彼らの探求はそこで止まりませんでした。自らのモデルが国際的にも通用することを証明し、データマイニングであるとの批判を退けました。さらに、20年以上の時を経て、収益性と投資という、より根源的なファクターを導入した5ファクターモデルを自ら提唱し、かつての3ファクターモデルの象徴であったバリューファクターが冗長であることを示しました。これは、彼らが特定の理論に固執するのではなく、あくまでデータと証拠に基づいて思考を進化させ続ける、真の科学者であったことを物語っています。
ファーマとフレンチが残した最終的な遺産は、学術理論の書き換えだけではありません。彼らの研究は、かつては一部の優れたアクティブマネージャーの「アルファ(腕前)」とされていた超過リターンの源泉を、誰もがアクセス可能な体系的な「ファクター(代替ベータ)」へと変えました。この知的変革は、ファクター投資やスマートベータETFという巨大な金融産業の礎となり、世界中の何百万人もの投資家が資産を運用する方法を根本的に変えたのです。
彼らの業績は、厳密な実証研究が、いかにして学術理論を再構築し、さらには現実世界の産業構造そのものを変革しうるかを示す、不朽の証として輝き続けています。ファーマとフレンチは、ファイナンスの世界におけるリスクとリターンの理解を、不可逆的に、そして決定的に深化させたのです。
ファクター投資についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ。
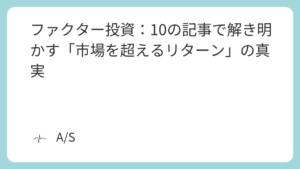
参考文献一覧
Asness, C. S., Moskowitz, T. J., & Pedersen, L. H. (2013). Value and momentum everywhere. The Journal of Finance, 68(3), 929–985.
https://doi.org/10.1111/jofi.12021
Barillas, F., & Shanken, J. (2018). Comparing asset pricing models. The Journal of Finance, 73(2), 715–754.
https://doi.org/10.1111/jofi.12607
Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of Finance, 52(1), 57–82.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x
Daniel, K., & Titman, S. (1997). Evidence on the characteristics of cross-sectional variation in stock returns. The Journal of Finance, 52(1), 1–33.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03806.x
Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. The Journal of Finance, 47(2), 427–465.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x
Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5
Fama, E. F., & French, K. R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. The Journal of Finance, 51(1), 55–84.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05202.x
Fama, E. F., & French, K. R. (1998). Value versus growth: The international evidence. The Journal of Finance, 53(6), 1975–1999.
https://doi.org/10.1111/0022-1082.00080
Fama, E. F., & French, K. R. (2010). Luck versus skill in the cross-section of mutual fund returns. The Journal of Finance, 65(5), 1915–1947.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01598.x
Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1–22.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010
Fama, E. F., & French, K. R. (2016). Dissecting anomalies with a five-factor model. The Review of Financial Studies, 29(1), 69–103.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhv043
Fama, E. F., & French, K. R. (2017). International tests of a five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 123(3), 441–463. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.11.004
Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). … and the cross-section of expected returns. The Review of Financial Studies, 29(1), 5–68.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhv059
Hou, K., Xue, C., & Zhang, L. (2015). Digesting anomalies: An investment approach. The Review of Financial Studies, 28(3), 650–705.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhu068
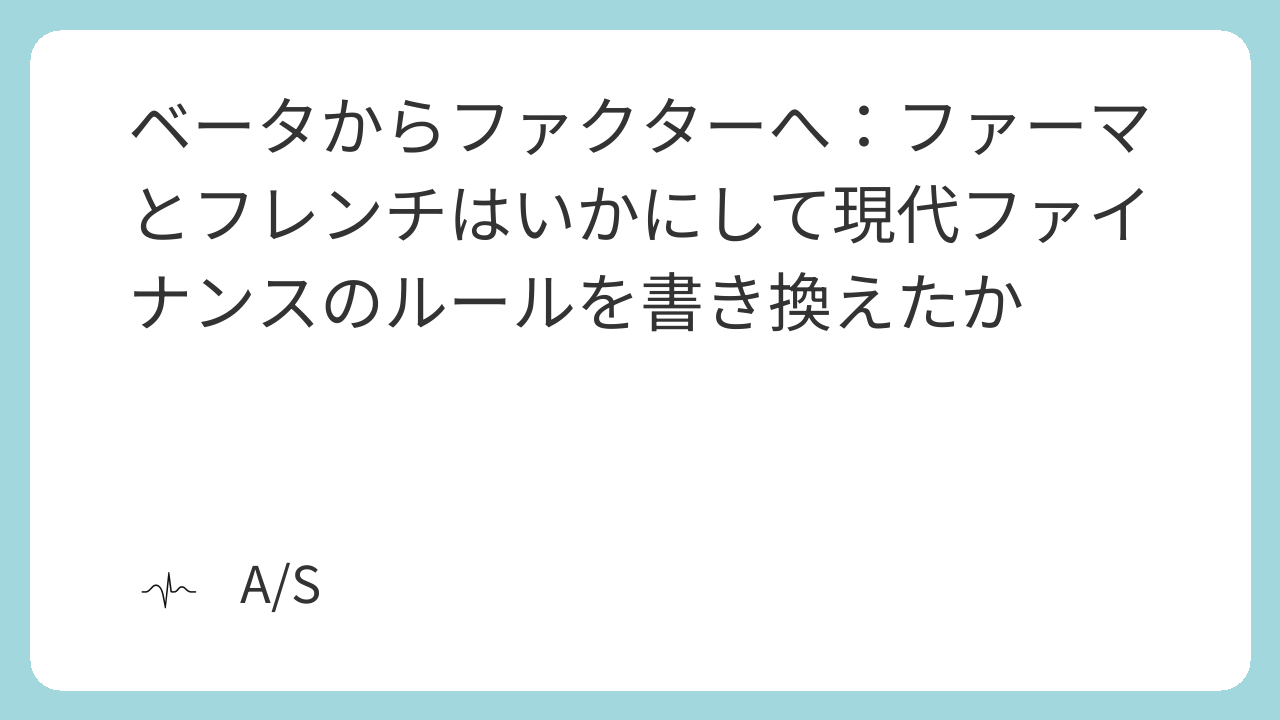
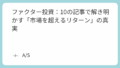
コメント