概論:インデックス運用の進化形
投資の世界において、TOPIXやS&P500といった株価指数に連動することを目指す「インデックス運用」は、低コストで市場全体の平均的なリターンを得るための王道とされてきました。これらの伝統的なインデックスのほとんどは、時価総額加重平均という方法で算出されています。これは、企業の時価総額(株価 × 発行済株式数)が大きいほど、その企業の株式をインデックスに組み入れる比率も高くなるという、シンプルで分かりやすい仕組みです。
しかし、この時価総額加重平均には、構造的な欠陥があるのではないか、という批判が長年なされてきました。それは、市場で人気化して株価が過大評価されている銘柄を自動的に買い増し、逆に見過ごされて割安になっている銘柄の比率を下げてしまうという性質です。つまり、高値掴みと安値売りを助長するメカニズムが内包されている、というわけです。
この伝統的なインデックスの欠点を克服し、より「賢く(スマートに)」市場を上回るリターン(ベータ)を獲得しようという思想から生まれたのが、スマートベータです。
スマートベータとは、時価総額以外の、客観的なルールや指標に基づいてポートフォリオを構築するインデックス戦略の総称です。その先駆けとなったのが、ロバート・アーノット、ジェイソン・シュー、フィリップ・モアによる2005年の画期的な研究「ファンダメンタル・インデックス」です [1]。彼らは、企業の時価総額ではなく、売上高、利益、配当、純資産といった、より本質的な企業価値(ファンダメンタルズ)に基づいてインデックスを構築することで、時価総額加重インデックスを長期的に上回ることを実証しました。
現在では、この考え方がさらに発展し、スマートベータは、学術研究によって発見された様々な「ファクター」へのエクスポージャーを獲得するための手段として広く認識されています。バリュー(割安株)、サイズ(小型株)、モメンタム、クオリティといった、リターンの源泉となることが示されている特定の要因(ファクター)に意図的にポートフォリオを傾けるのです [2]。つまり、スマートベータとは、伝統的なパッシブ運用(インデックス運用)と、銘柄選択を行うアクティブ運用の中間に位置する、第三の運用手法と言えるでしょう。
長短の解説と損益の事例紹介
長所、強み、有用な点について
体系的なファクターへのエクスポージャー
スマートベータの最大の長所は、これまでアクティブファンドマネージャーの専門領域であったファクター(リターンの源泉)への投資を、低コストで、透明性の高い、ルールに基づいた形で実現した点にあります。
どのファクターに、どのようなルールで投資するかが事前に明確に定義されているため、投資家は自分がどのようなリスクを取り、どのようなリターンの源泉に賭けているのかを正確に理解することができます。これは、高コストで、かつ戦略が不透明になりがちな多くの伝統的なアクティブ運用に対する、明確な優位点です [3]。
時価総額加重の罠からの脱却(収益事例)
スマートベータは、時価総額の大きさに連動して投資比率を決めるという「呪縛」からポートフォリオを解放します。アーノットらの研究によれば、彼らが提唱したファンダメンタル・インデックスは、1962年から2004年までの米国市場において、時価総額加重インデックス(S&P500)を年率平均で約2%アウトパフォームしたと報告されています [1]。これは、時価総額加重平均が抱える「割高な銘柄を買いすぎる」というバイアスを避けることで、リターンが改善された結果であると彼らは主張しています。
短所、弱み、リスクについて
スマートベータという言葉は魅力的ですが、その背景にあるリスクや批判を理解することが極めて重要です。
それは本当に「スマート」なのか?
著名な経済学者であるバートン・マルキールは、2014年の論文で「スマートベータは本当に賢いのか?」と題し、その呼称自体に疑問を呈しました [4]。彼によれば、スマートベータ戦略の多くは、単にバリューファクターやサイズファクターといった、古くから知られているリスクファクターへのエクスポージャーを高めているに過ぎない、と指摘します。つまり、スマートベータが得る超過リターンは、何か特別な「アルファ(運用者のスキル)」ではなく、単に異なる種類のリスク(ベータ)を取ったことへの対価であり、「スマート」という言葉は誤解を招くマーケティング用語である、という批判です。
人気化による過大評価とクラッシュのリスク(失敗事例)
スマートベータ戦略が直面する最大のリスクは、その人気化そのものです。あるスマートベータ戦略(例えば、低ボラティリティ戦略)が成功を収めて人気化すると、多くの資金がその戦略に該当する銘柄に殺到します。その結果、それらの銘柄の株価は本来の価値以上に吊り上がり、ファクターの源泉であったはずの「割安さ」が失われてしまいます。
スマートベータの提唱者の一人であるロブ・アーノット自身も、2016年の論文「スマートベータは、いかにして悲惨な結果を招きうるか?」の中で、この危険性に警鐘を鳴らしました [5]。彼は、人気化して割高になったファクターは、将来的に長期的な低迷、あるいは急落(クラッシュ)に見舞われる危険があると警告しています。
根拠となるアノマリーの減衰リスク
スマートベータ戦略の根拠となっているファクター(アノマリー)は、学術論文によって広く知れ渡っています。マクリーンとポンティフによる2016年の研究が示すように、学術論文として公表されたアノマリーは、その後、裁定取引によって超過リターンが大幅に減少(減衰)する傾向にあります [6]。つまり、スマートベータETFなどの商品として一般の投資家が手軽に投資できるようになった時点では、そのエッジの多くは既に失われている可能性があるのです。
非対称性と摩擦の視点
なぜ、時価総額加重平均から脱却することが、超過リターンの源泉となり得るのでしょうか。そして、スマートベータという戦略には、どのような見えざるリスクが潜んでいるのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かします。
Asymmetry:時価総額加重の「構造的」非対称性
スマートベータが利用しようとしているエッジの根源には、伝統的な時価総額加重インデックスそのものが内包する「構造的な非対称性」が存在します。
時価総額加重インデックスは、その定義上、株価が上昇した銘柄のウェイトを自動的に引き上げ、株価が下落した銘柄のウェイトを引き下げます。これは、意図せずしてモメンタム戦略に近い性質を持つことを意味します。市場がバブルの様相を呈し、特定の銘柄が過大評価されていく局面では、インデックスはその過大評価された銘柄をどんどん買い増していくのです。
この構造は、非対称なリスクプロファイルを生み出します。つまり、株価上昇の恩恵は受けられますが、ひとたびバブルが崩壊した際には、最もウェイトが高まった過大評価銘柄の暴落によるダメージを最大級に受けてしまうのです。
スマートベータ、特にアーノットらが提唱したファンダメンタル・インデックスは、この非対称性に対して、逆の非対称性、すなわちリバランスを通じた逆張り戦略を導入します [1]。株価が上昇してファンダメンタル価値に対して割高になった銘柄のウェイトを機械的に引き下げ(売り)、株価が下落して割安になった銘柄のウェイトを引き上げる(買い)。この「高く売って、安く買う」という非対称なリバランス行動こそが、時価総額加重の罠を回避し、超過リターンを生み出す源泉であると考えられています。
Friction:マーケティングと現実の乖離という摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、スマートベータという戦略には、その商業的な成功と普及に起因する、より本質的な摩擦が存在します。
1.「スマート」という呼称がもたらす認知的摩擦
「スマートベータ」という言葉は、非常に優れたマーケティング用語ですが、それ自体が投資家の誤解を招く「認知的な摩擦」として機能します。マルキールが指摘するように、この言葉は、まるでリスクなしに得られる賢いリターン(アルファ)が存在するかのような幻想を与えます [4]。
しかし、その実態は、単に伝統的な市場リスク(ベータ)とは異なる種類のリスク(ファクター・ベータ)を取っているに過ぎません。このマーケティングと現実の乖離という摩擦は、投資家が自らのポートフォリオのリスクの本質を理解することを妨げ、想定外の損失に繋がる危険性をはらんでいます。
2.バックテストの美しさと現実の乖離という摩擦
スマートベータ商品は、その多くが、過去のデータで驚異的なパフォーマンスを示した「バックテスト」を掲げて宣伝されます。しかし、この美しいバックテスト結果そのものが、投資家を惑わす摩擦となります。
アーノットらが警告するように、過去に成功した戦略は、人気化による資金流入で過大評価を招き、将来のリターンを著しく悪化させる可能性があります [5]。また、マクリーンとポンティフが示したように、根拠となるファクターの有効性自体が、公になることで減衰していきます [6]。投資家は、摩擦のない理想的な過去(バックテスト)を提示されますが、実際に直面するのは、過密化(クラウディング)とファクター減衰という、厳しい摩擦に満ちた未来なのです。
総括
・スマートベータとは、伝統的な時価総額加重インデックスの「割高な銘柄を買いすぎる」という欠点を克服するため、時価総額以外のルールに基づいて構築されるインデックス戦略です。
・その主な長所は、バリューやクオリティといった、リターンの源泉となる「ファクター」へのエクスポージャーを、低コストかつ透明性の高い形で獲得できる点にあります [1, 3]。
・一方で、その超過リターンは賢さ(アルファ)の対価ではなく、単に異なる種類のリスクを取った結果であるという批判があります [4]。
・また、戦略の人気化による過大評価や、根拠となるアノマリーの減衰によって、過去のバックテスト通りのリターンが将来も続くとは限らない、という重大なリスクを抱えています [5, 6]。
用語集
スマートベータ 時価総額加重平均以外の、客観的なルールに基づいて構築されるインデックス戦略の総称。
時価総額加重平均 企業の時価総額が大きいほど、インデックスに占める比率が高くなる、伝統的な株価指数の算出方法。
ファンダメンタル・インデックス 企業の売上高や利益といった、ファンダメンタルズ(企業価値の基礎的条件)に基づいて構成比率を決めるインデックス。スマートベータの代表例。
ファクター 株式などのリターンを長期的に説明するとされる、共通の性質や特徴のこと。スマートベータが獲得を目指すリターンの源泉。
パッシブ運用 特定の株価指数(インデックス)に連動することを目指す運用手法。インデックス運用とも言う。
アクティブ運用 ファンドマネージャーが独自の調査や判断に基づき、インデックスを上回るリターンを目指す運用手法。
リスクプレミアム ある資産を保有する際に、その資産が持つリスクを引き受けることへの対価として、無リスク資産のリターンを上回って期待される追加的なリターンのこと。
シャープレシオ リターンを、そのリターンを得るために取ったリスクの大きさで割った値。リスク調整後のパフォーマンスを測る指標。
バックテスト ある投資戦略が、過去の市場データを用いてシミュレーションした場合に、どのようなパフォーマンスを示したかを検証すること。
ファクターの減衰 (Factor Decay) 発見されたアノマリーがもたらす超過リターンが、その発見が公になった後に低下、または消滅する現象。
参考文献一覧
[1] Arnott, R. D., Hsu, J., & Moore, P. (2005). Fundamental indexation. Financial Analysts Journal, 61(2), 83-99.
https://doi.org/10.2469/faj.v61.n2.2718
[2] Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5
[3] Bender, J., Briand, R., Melas, D., & Subramanian, R. A. (2013). Foundations of factor investing. The Journal of Portfolio Management, 40(1), 1-17.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2543990
[4] Malkiel, B. G. (2014). Is smart beta really smart?. The Journal of Portfolio Management, 40(5), 137-143.
https://doi.org/10.3905/jpm.2014.40.5.127
[5] Arnott, R. D., Beck, N., & Kalesnik, V. (2016). How can “smart beta” go horribly wrong?. Financial Analysts Journal, 72(2), 6-16.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3040949
[6] McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability?. The Journal of Finance, 71(1), 5-48.
https://doi.org/10.1111/jofi.12365


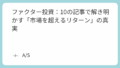
コメント