概論
経済の動向を予測する際、伝統的な経済学は、金利、インフレ率、失業率といった定量的なデータと、人々が常に自己の利益を最大化するように合理的に行動するという「ホモ・エコノミカス(経済人)」の仮定を基盤としてきました。この考え方の究極形が、ジョン・マスによって提唱された合理的期待形成仮説です [1]。これは、人々が利用可能な全ての情報を駆使して、将来を体系的な間違いなく予測すると仮定する、非常に強力な理論でした。
しかし、この合理的な人間像を前提としたモデルは、現実の経済が時折見せる、熱狂的なバブルや、パニック的な暴落といった、極端で非合理的な動きをうまく説明することができませんでした。なぜ人々は、明らかに割高な資産をこぞって買い上げたり、一斉に恐怖に駆られて売り浴びせたりするのでしょうか。
この問いに、古くから多くの経済学者が気づいていました。ジョン・メイナード・ケインズは、1936年の主著「雇用・利子および貨幣の一般理論」の中で、経済活動がしばしば計算や合理性だけでは説明できない、楽観や悲観といった「アニマルスピリッツ」によって突き動かされることを指摘しています [2]。
この「人間の心理」を、現代的なアプローチで経済学に再導入したのが、行動経済学です。ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによるプロスペクト理論は、人々が体系的に非合理な判断を下すことを実験で示し、伝統的な経済学の前提を根本から揺るがしました [3]。
そして、この流れをさらに一歩進め、人々の意思決定に影響を与える、より大きな社会的現象として「物語」の力に着目したのが、ノーベル経済学賞受賞者であるロバート・シラーが提唱するナラティブ経済学(Narrative Economics)です。
シラーは2017年の論文で、人々の間で口コミやメディアを通じて伝染し、経済行動に影響を与える「物語(ナラティブ)」こそが、これまで説明が困難だった経済変動を理解するための鍵であると主張しました [4]。ナラティブ経済学とは、このような物語が、まるでウイルスのように社会に広まり、流行し、やがては忘れ去られていく過程を、疫学などの手法を用いて分析する、新しい経済学のアプローチなのです。
長短の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について:物語の伝染力
ナラティブ経済学の最大の強みは、伝統的なモデルが見過ごしてきた、経済的なアイデアや信念が、どのようにして社会全体に広まっていくのか、そのダイナミックなプロセスを説明できる点にあります。
経済変動の伝播メカニズムの解明
なぜ、特定の投資アイデアや、経済に対する楽観論・悲観論が、突如として社会全体を覆うほどの流行となるのでしょうか。ナラティブ経済学は、この現象を説明するために、感染症の流行をモデル化する疫学の知見を取り入れます。
アビジット・バナジーによる1992年の「情報カスケード」に関する理論モデルは、そのメカニズムの一端を説明しています [5]。人々は、他者の行動を見て、「何か自分が知らない情報があるのだろう」と推論し、自らの情報を捨てて群集に追随する。このような情報の連鎖が、ナラティブをウイルスのように伝播させるのです。シラーは、この考え方をさらに発展させ、ナラティブの「感染率」や「回復率」といった要素が、経済的な流行の規模や期間を決定すると論じています [4]。
短所、弱み、リスクについて:「ニューエコノミー」という幻想(損失事例)
人々の心を捉えるナラティブは、経済を活性化させる力を持つ一方で、時として人々を熱狂的なバブルへと導き、その崩壊と共に深刻なダメージをもたらす、極めて危険な存在でもあります。
損失事例:ITバブルと「ニューエコノミー」の物語
その最も象徴的な例が、1990年代後半のITバブル(ドットコム・バブル)です。
ロバート・シラーが2000年に出版した著書「根拠なき熱狂」は、このバブルの渦中で、その熱狂の正体を分析しました [6]。当時、市場を支配していたのは、「インターネットが世界を変え、古い経済の法則はもはや通用しない『ニューエコノミー』が到来した」という、極めて強力で魅力的なナラティブでした。
この物語に熱狂した投資家たちは、「今は利益よりも成長が重要だ」と信じ込み、伝統的な企業価値評価の指標を無視して、赤字のIT関連企業の株を競って買い上げました。このナラティブが、株価を本来の価値から天文学的なレベルまで乖離させ、史上最大級のバブルを形成したのです。
しかし、2000年になると、このナラティブは急速にその力を失い、バブルは崩壊。多くの投資家が巨額の損失を被るという悲劇的な結末を迎えました。これは、いかに強力なナラティブであっても、最終的には経済のファンダメンタルズから乖離し続けることはできないという、歴史の教訓を示しています。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、非合理的に見える「物語」が、合理的なはずの市場参加者の行動を、これほどまでに支配できるのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:物語の「伝染力」の非対称性
ナラティブ経済学の核心には、物語が持つ「伝染力」そのものの非対称性が存在します。
全ての物語が、同じように人々の心に響き、社会に広まっていくわけではありません。ロバート・シラーが指摘するように、人間の感情に強く訴えかけ、シンプルで分かりやすく、そして興味深い人間的要素を持つ物語は、退屈で、複雑で、データに基づいた客観的な事実よりも、非対称に強い伝染力(ヴァイラリティ)を持つのです [4]。
「AIが人類の仕事を奪う」という物語は、「労働市場の構造変化に関する多変量分析」という報告書よりも、遥かに速く、そして広く伝播します。この「物語の魅力」と「事実の退屈さ」との間の非対称性こそが、時に市場全体を、ファンダメンタルズからかけ離れた熱狂や悲観へと導く力の源泉です。
このアノマリーにおける収益機会とは、市場がどのようなナラティブに「感染」しているかを客観的に観測し、そのナラティブがもたらす価格の歪みを利用することにあります。しかしそれは同時に、自らがその強力なナラティブに感染してしまうリスクと、常に隣り合わせでもあるのです。
Friction:「合理性」への固執という知的摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、ナラティブという概念が経済学の世界で正当な評価を得るまでには、より根深い、知的な「摩擦」が存在しました。
伝統的経済学の「慣性」という摩擦
伝統的な経済学は、その誕生以来、「人間は合理的である」という強力なパラダイム(思考の枠組み)の上に成り立ってきました。合理的期待形成仮説 [1]に代表されるように、全ての経済主体が、数学的に最適化された行動を取るという前提は、美しく、かつ強力なモデルの構築を可能にしました。
この「合理性」というパラダイムへの固執が、ナラティブのような、定性的で、測定が困難で、一見すると「非科学的」に見える要素を、経済分析の対象から長年にわたって排除してきた、巨大な知的摩擦として機能してきたのです。ケインズの「アニマルスピリッツ」[2]のような先駆的な洞察がありながらも、それが主流派のモデルに本格的に組み込まれることがなかったのは、この摩擦が原因です。
測定の困難性という技術的摩擦
ナラティブ経済学が直面するもう一つの大きな摩擦が、「物語をどうやって定量的に測定するか」という技術的な問題です。金利やGDPと異なり、社会に流布する物語を客観的なデータとして捉え、その影響を統計的に分析することは、極めて困難な作業です。
近年、テキストマイニングなどの技術発展により、この摩擦は克服されつつありますが、それでもなお、物語の微妙なニュアンスや、人々の解釈の多様性を完全にデータ化することはできません。この測定の困難性という技術的な摩擦が、ナラティブ経済学を、いまだ発展途上の、挑戦的な分野にしているのです。
総括
・伝統的な経済学は、人々が常に合理的に行動すると仮定するため、バブルや暴落といった、市場の非合理な動きを説明することが困難でした [1]。
・ロバート・シラーが提唱したナラティブ経済学は、人々の経済行動が、社会で伝染する「物語(ナラティブ)」によって、いかに大きく影響されるかを分析する新しいアプローチです [4]。
・ケインズの「アニマルスピリッツ」[2]や、行動経済学の知見 [3]をさらに発展させ、物語がウイルスのように広まるプロセスを、疫学のモデルなどを用いて説明しようと試みます。
・ITバブルにおける「ニューエコノミー」の物語のように、強力なナラティブは、時に投資家を熱狂させ、株価を本質的価値から大きく乖離させ、最終的に深刻な損失をもたらす危険性をはらんでいます [6]。
用語集
ナラティブ経済学 (Narrative Economics) ノーベル経済学賞受賞者のロバート・シラーが提唱した、人々の間で伝播する「物語(ナラティブ)」が、経済全体の変動にいかに影響を与えるかを分析する経済学のアプローチ。
ナラティブ (Narrative) 人々の感情や動機に訴えかけ、口コミやメディアを通じて伝染していく、特定の出来事に関する「物語」や「説明」のこと。
伝統的経済学 人々が常に合理的に自己の利益を最大化するように行動する「ホモ・エコノミカス(経済人)」を前提とする、新古典派などの経済学の主流派。
合理的期待形成仮説 人々は、利用可能な全ての情報を合理的に利用して将来を予測するため、体系的な(何度も同じ方向の)予測誤差を犯さないとする仮説。
アニマルスピリッツ (Animal Spirits) ジョン・メイナード・ケインズが用いた言葉で、経済活動を左右する、合理的な計算だけでは説明できない、人々の楽観や悲観といった衝動的な感情や心理のこと。
行動経済学 心理学の知見を用いて、人々が時に見せる非合理的な意思決定のパターンを分析し、それが経済に与える影響を研究する学問分野。
情報カスケード (Informational Cascade) 人々が、自らの私的な情報よりも、先行する他者の行動をより重要な情報源と見なし、次々と行動を模倣していく連鎖的なプロセス。
バブル (Bubble) 資産の価格が、その本質的な価値から大きくかけ離れて、熱狂的に高騰する状態。
ファンダメンタルズ (Fundamentals) 企業の収益力や財務状況、資産価値といった、その企業の本質的な価値を決定する基礎的条件。
センチメント (Sentiment) 市場参加者の総意として形成される、楽観や悲観といった市場全体の心理状態や雰囲気のこと。
参考文献一覧
[1] Muth, J. F. (1961). Rational expectations and the theory of price movements. Econometrica, 29(3), 315-335.
https://doi.org/10.2307/1909635
[2] Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan.
※書籍です。
[3] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
https://doi.org/10.2307/1914185
[4] Shiller, R. J. (2017). Narrative economics. American Economic Review, 107(4), 967-1004.
https://doi.org/10.1257/aer.107.4.967
[5] Banerjee, A. V. (1992). A simple model of herd behavior. The Quarterly Journal of Economics, 107(3), 797-817.
https://doi.org/10.2307/2118364
[6] Shiller, R. J. (2000). Irrational Exuberance. Princeton University Press.
※書籍です。
【免責事項】
本サイト/本記事は、著者個人の見解、経験、学習・研究内容に基づいた情報提供を目的としています。特定の銘柄や投資手法の推奨を目的としたものではなく、また、金融商品取引法に基づく投資助言サービスではありません。
投資には元本割れを含む様々なリスクがあります。価格変動、金利変動、為替変動、発行者の信用状況などにより、損失が生じる可能性があります。
本サイト/本記事で提供される情報を利用した投資判断や取引によって生じたいかなる損害についても、筆者および運営者は一切の責任を負いません。
投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行って(あるいは行わないで)ください。
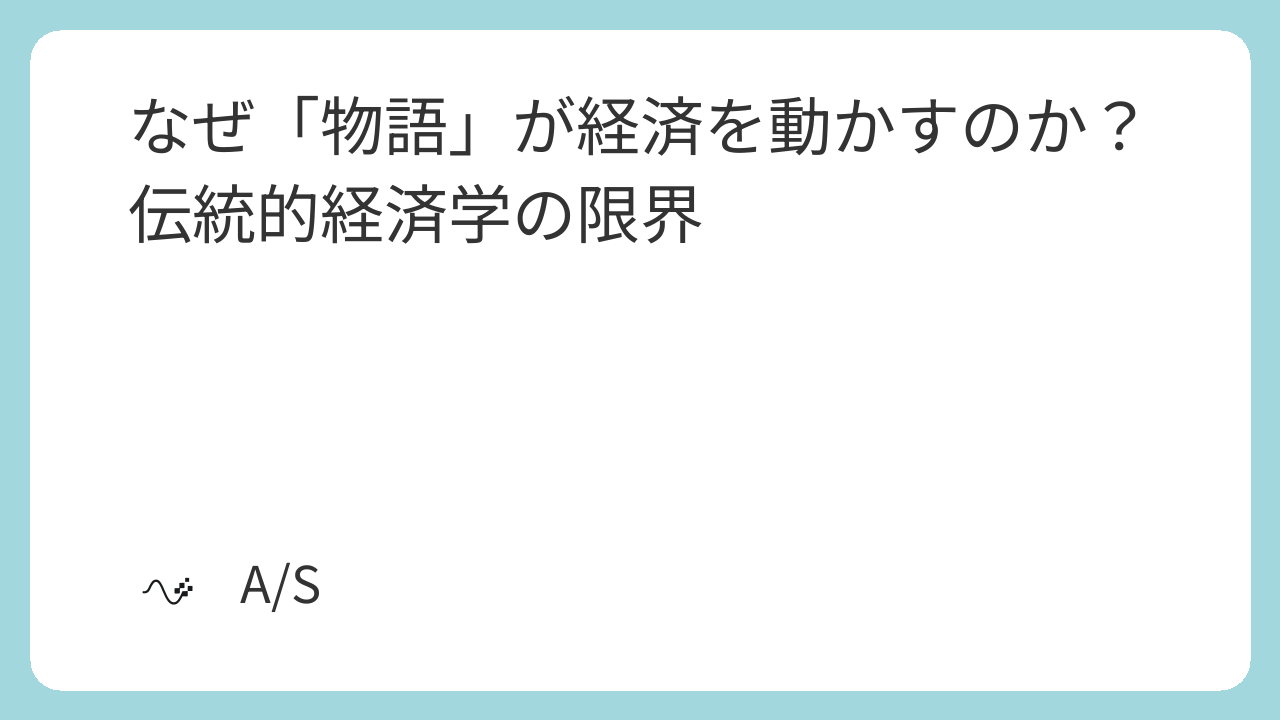
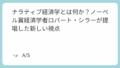
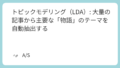
コメント