概論
なぜ、市場は時に熱狂的なバブルに浮かされ、またある時はパニック的な暴落に見舞われるのでしょうか。伝統的な経済学は、金利や失業率といった定量的なデータと、人々が合理的に行動するという仮定に基づいて、これらの現象を説明しようと試みてきました。しかし、その説明には限界があることを、私たちは歴史から学んでいます。この問いに、全く新しい角度から光を当てたのが、ノーベル経済学賞受賞者であるロバート・シラーが提唱した「ナラティブ経済学」です。
ナラティブ経済学とは、経済的な事象を理解するためには、人々の間で語られ、ウイルスのように広まっていく「物語(ナラティブ)」の研究が不可欠である、という考え方です [1]。シラーによれば、人々の経済的な意思決定(何に投資し、何を買い、あるいはいつ仕事を探すか)は、単なるデータ分析だけでなく、その時々に流行している印象的な物語に大きく影響されます。「不動産価格は決して下がらない」「IT革命が新しい経済(ニューエコノミー)を生み出す」といった物語が、人々の信念を形成し、集団的な行動を引き起こし、そして経済全体を動かしていくのです。
この思想の根底には、シラーがジョージ・アカーロフと共に探求してきた、人間の心理が経済を動かすという「アニマルスピリッツ」の概念があります [2]。ナラティブ経済学は、この心理的な要因を、より具体的に「物語の伝染」という形でモデル化しようとする試みです。そのためにシラーが着目したのが、疫学の世界です。彼は、経済的な物語が人々の間で広まっていくプロセスが、感染症の流行と驚くほど似ていると指摘し、その流行を分析するために疫学で用いられる数学モデル(SIRモデルなど)の応用を提案しています [1]。このモデルの起源は古く、20世紀初頭にはその基礎が築かれていました [3]。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所と収益事例
ナラティブ経済学がもたらす最大の長所は、伝統的な経済モデルでは捉えきれなかった、歴史的な経済変動の背後にある「動機」を解き明かす、強力な説明能力にあります。
このアプローチの「収益事例」とは、特定の取引戦略のリターンというよりは、経済現象そのものへの理解が深まるという、知的な収益です。その代表例が、2000年代の米国住宅バブルの分析です。当時、「住宅価格は長期的に見て、決して下落しない安全な投資である」という極めて強力なナラティブが、社会に広く浸透していました。実際、住宅ブームの最中に行われた購入者への調査によれば、多くの人々が、過去の価格上昇を根拠に、将来も同様の上昇が続くと強く信じていたことが確認されています [4]。ナラティブ経済学は、この広く共有された信念(物語)こそが、人々を高リスクな住宅ローンへと駆り立て、バブルを膨張させた根源的な要因であったと説明するのです。
また、この一見すると曖昧な「物語」を、客観的に測定し、その影響を定量化しようとする試みも進んでいます。これは、ナラティブ経済学のもう一つの強みです。例えば、中央銀行の金融政策決定会合後の記者会見における議長の発言を、自然言語処理(NLP)を用いて分析した研究があります。この研究は、発言内容をトピックごとに分類し、どの「物語」が語られたかを定量化することで、特定の発言(ナラティブ)が、その後の金融市場や実体経済に、実際にどのような影響を与えたかを特定することに成功しました [5]。これは、ナラティブが単なる雑談ではなく、測定可能な経済的インパクトを持つことを示す重要な証拠です。
短所と弱み、リスク
ナラティブ経済学は、経済学に新たな地平を開く可能性を秘めていますが、その実践には、いくつかの深刻な課題と方法論的な困難が伴います。
最大の弱みは、ナラティブと経済事象との間の「因果関係の特定」が極めて難しい点です。例えば、景気後退期には、悲観的なナラティブが流行します。しかし、そのナラティブが景気後退を「引き起こした」のでしょうか、それとも、景気後退という現実が、悲観的なナラティブを「生み出した」のでしょうか。この「鶏が先か、卵が先か」という因果の方向性を、データから厳密に識別することは、非常に困難な課題です。
第二に、「ナラティブの測定」そのものの難しさです。中央銀行の声明のような整理されたテキストとは異なり、ソーシャルメディアなどに溢れる人々の日常的な会話から、意味のある経済ナラティブを抽出し、その影響力を客観的に測定することは容易ではありません。例えば、ツイッターの投稿データを用いて株式市場のセンチメントを分析したある研究では、人々の「気分」と株価の間に相関が見られるものの、その関係は複雑で、予測モデルの構築は単純ではないことが示されています [6]。膨大なテキストデータは、シグナルだけでなく、大量のノイズを含んでおり、その中から本物のナラティブを識別するには、高度な技術と慎重な解釈が求められます。
最後に、このアプローチは、歴史の解釈において、「後付けの物語」を作り出してしまうリスクを常に内包しています。ある経済変動が起こった後で、その原因に合致するような物語を過去の言説の中から見つけ出すことは、比較的簡単です。しかし、それが本当に当時、経済を動かすほど影響力を持った「支配的なナラティブ」であったのかを証明することは、別の問題です。この解釈の恣意性が、ナラティブ経済学が科学的な厳密性を確立する上での、大きなハードルとなっています。
非対称性と摩擦の視点から
ポジティブファクター:Asymmetry
ナラティブ経済学が明らかにするのは、市場における「信念の非対称性」が、いかにして経済的な変動の源泉となるか、という点です。
伝統的な経済学が、全ての市場参加者が同じ情報を持ち、合理的に行動すると仮定するのとは対照的に、ナラティブ経済学は、人々が異なる物語を、異なるタイミングで、異なる強さで信じるという現実から出発します。ある強力な物語(例えば「今回は違う」というバブル期の楽観論)が伝染し始めると、その物語を信じる「感染者」と、まだ信じていない「未感染者」との間に、世界認識の大きな非対称性が生まれます。この信念の乖離こそが、市場にトレンドとモメンタumを生み出すエンジンです。物語を早期に信じた人々が資産を購入することで価格が上昇し、その価格上昇が物語の説得力をさらに高め、新たな信者を引き寄せるのです。
このプロセスは、トレーダーにとって非対称な機会を生み出します。市場を支配する支配的なナラティブの発生、ピーク、そして崩壊のパターンを特定できれば、極めて有利なリスク・リターン特性を持つ取引が可能になります。物語がまだ黎明期にある時にそれに乗り、熱狂がピークに達した時に降りる、あるいはその逆張りを行う。これは、市場の集合的な信念の非対称なライフサイクルを利用して、アルファ(超過リターン)を追求する試みと言えます。
ネガティブファクター:Friction
ではなぜ、明らかに非合理的な物語が、プロの投資家による裁定取引によって、即座に修正されることなく、市場に蔓延し、大きな影響を及ぼすことができるのでしょうか。その背景には、人間の認知能力や社会構造に根差した、強力な「摩擦」が存在します。
最大の摩擦は、認知的な摩擦です。人間の脳は、複雑で無味乾燥な統計データを処理するよりも、シンプルで感情に訴えかける物語を理解し、記憶し、他者に伝えることに、遥かに適しています。この「物語への選好」という認知的な摩擦が、たとえデータが警鐘を鳴らしていても、人々を魅力的な物語に固執させます。合理的な分析が、物語の持つ強い感染力の前に無力化されてしまうのです。
第二に、社会的な摩擦です。一度あるナラティブが支配的になると、それに異を唱えることは、社会的な同調圧力に逆らうことを意味します。バブルの最中に「これは行き過ぎだ」と警告する専門家は、「時代の変化が分からない古い人間だ」と嘲笑されがちです。この、コンセンサスから外れることへの恐怖という社会的な摩擦が、健全な懐疑主義を麻痺させ、ナラティブの自己強化的なスパイラルを加速させます。
最後に、メディアという摩擦(あるいは増幅器)です。現代のメディア、特にソーシャルメディアは、新奇で感情的な物語を、瞬時に、そして大規模に拡散させる能力を持っています。メディアのビジネスモデルは、しばしば人々の注意を引くことに最適化されており、そのプロセスで、複雑な現実は単純化され、物語はよりドラマチックに脚色されます。このメディアという強力な伝達経路が、ナラティブの流行を抑制しようとする合理的な声に対する、大きな摩擦として機能するのです。
総括
この記事では、ノーベル経済学賞受賞者ロバート・シラーが提唱した「ナラティブ経済学」の基本的な概念と、その可能性、そして課題について解説しました。
- ナラティブ経済学とは、経済的な変動を理解するためには、人々の間でウイルスのように伝染する「物語(ナラティブ)」の研究が不可欠である、という新しいアプローチです [1]。
- この理論は、人間の心理が経済を動かすという「アニマルスピリッツ」の考え方を拡張し、物語の流行を分析するために疫学の数学モデルなどを応用します [2, 3]。
- 長所として、伝統的なモデルでは説明が困難な、住宅バブルのような歴史的な経済事象の動機を解き明かす強力な説明能力を持ちます [4]。また、テキスト分析などの手法により、ナラティブを定量化する試みも進んでいます [5]。
- 短所として、物語と経済事象の間の因果関係の特定が難しいことや、SNSなどに溢れる膨大なノイズの中から意味のあるナラティブを客観的に測定することの困難さが挙げられます [6]。
- 非対称性の観点からは、市場における「信念の非対称性」がトレンドを生み出し、トレーダーに非対称な収益機会を提供します。
- 摩擦の観点からは、人間の「物語への選好」という認知摩擦や、同調圧力という社会的摩擦が、非合理的なナラティブが市場で生き残り、影響を及ぼすことを許しています。
用語集
ナラティブ経済学 ノーベル経済学賞受賞者のロバート・シラーによって提唱された経済学のアプローチ。人々の間で語られ、ウイルスのように広まる「物語(ナラティブ)」が、いかにしてバブルや不況といった大きな経済変動を引き起こすかを研究する。
ロバート・シラー 米国の経済学者。2013年にノーベル経済学賞を受賞。「行動ファイナンス」の第一人者であり、市場の「アニマルスピリッツ」や、本書のテーマである「ナラティブ経済学」を提唱した。
ナラティブ 単なる事実の羅列ではなく、因果関係や感情的な意味合いを持つ、人々によって語られる「物語」のこと。経済学の文脈では、経済的な意思決定に影響を与える信念や世界観を形成する。
アニマルスピリッツ 経済学者ジョン・メイナード・ケインズが用いた言葉で、経済活動を促進する、人々の漠然とした楽観や自信といった、数値化できない衝動や感情のこと。
行動経済学 人間の心理的なバイアスやヒューリスティックが、経済的な意思決定にどのような影響を与えるかを研究する学問分野。
伝染モデル(疫学モデル) 感染症が人口の中でどのように広まるかを記述するための数学モデル。ナラティブ経済学では、経済的な物語が人々の間で広まるプロセスを分析するために、このモデルの応用が提案されている。
フィードバック・ループ あるシステムの出力が、入力としてそのシステム自身にフィードバックされ、その後のシステムの振る舞いを増幅または抑制する循環的なプロセスのこと。バブルの形成は、正のフィードバック・ループの典型例。
ヒューリスティック 複雑な問題に対して、必ずしも最適ではないが、ある程度のレベルで正解に近い解を、より少ない労力で見つけ出すための、経験則に基づいた簡便な解法や思考プロセスのこと。
自然言語処理(NLP) 人間が日常的に使っている言葉(自然言語)を、コンピューターが処理・分析するための技術。ナラティブ経済学では、ニュース記事やSNSの投稿から、経済ナラティブを定量的に抽出するために用いられる。
因果関係 二つの事象の間に存在する、原因と結果の関係。ナラティブ経済学における大きな課題は、物語と経済事象の間の相関関係と因果関係を区別することである。
参考文献一覧
[1] Shiller, R. J. (2017). Narrative economics. American Economic Review, 107(4), 967-1004.
https://doi.org/10.1257/aer.107.4.967
[2] Akerlof, G. A., & Shiller, R. J. (2009). Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism. Princeton University Press.
※書籍です。
[3] Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 115(772), 700-721.
https://www.jstor.org/stable/94815
[4] Case, K. E., Shiller, R. J., & Thompson, A. (2012). What have they been thinking? Home buyer behavior in hot and cold markets. Brookings Papers on Economic Activity, Fall, 265-315.
https://doi.org/10.3386/w18400
[5] Hansen, S., McMahon, M., & Prat, A. (2018). Transparency and deliberation within the FOMC: A computational linguistics approach. The Quarterly Journal of Economics, 133(2), 801-870.
https://doi.org/10.1093/qje/qjx045
[6] Bollen, J., Mao, H., & Zeng, X. (2011). Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Science, 2(1), 1-8.
https://doi.org/10.1016/j.jocs.2010.12.007
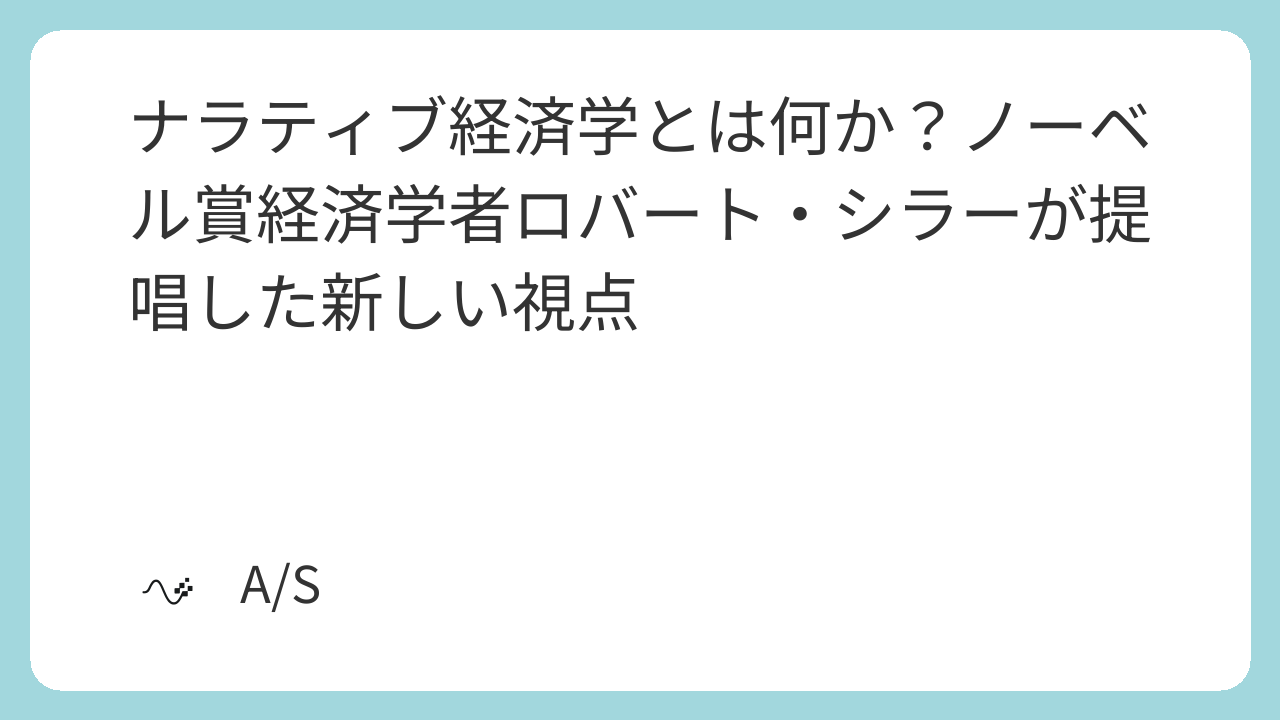
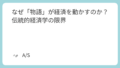
コメント