概論
1990年代後半、世界はインターネットという革命的な技術の登場に沸き立っていました。ドットコム(.com)企業が次々と生まれ、株価は熱狂的に上昇し、多くの「IT長者」が誕生した時代です。この熱狂の背景には、単なる技術革新への期待を超えた、一つの強力な物語(ナラティブ)が存在しました。
それが、「ニューエコノミー(New Economy)」というナラティブです。
この物語の骨子は、「インターネットと情報技術が経済の構造を根本的に変革し、もはや古い時代の経済法則や企業評価尺度は通用しない。今は利益よりも、ウェブサイトの訪問者数や市場シェアの獲得こそが重要である」というものでした。このナラティブは、輝かしい未来への希望と結びつき、驚異的なスピードで社会に伝播していきました。
ノーベル経済学賞受賞者であるロバート・シラーは、この現象をナラティブ経済学の観点から分析しています [1]。彼によれば、ITバブルは、この「ニューエコノミー」というナラティブが、まるでウイルスのように人々の心に「感染」し、その思考や行動を支配した結果として生じた、典型的な事例なのです。
シラーは、まさにバブルの最中にあった2000年に出版した著書「根拠なき熱狂」の中で、この熱狂をリアルタイムで分析しました [2]。彼は、メディアが連日報じるIT企業の成功物語、アナリストたちの楽観的な見通し、そして急騰する株価そのものが相互に作用し合い、ナラティブをさらに強化していくフィードバック・ループの存在を指摘しました。このループの中で、投資家の判断は、客観的な事実よりも、支配的な物語によって大きく左右されていったのです。
長短の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について:物語が現実を創造した時代
「ニューエコノミー」というナラティブは、なぜあれほどまでに多くの人々を惹きつけ、巨大なバブルを形成するに至ったのでしょうか。その力は、時に現実の企業価値さえも創造してしまうほど強力でした。
「.com」の名前が持つ魔力(収益事例)
このナラティブの純粋な力を、見事に実証した研究が存在します。クーパー、ディミトロフ、ラウによる2001年の論文は、「.com」という名前が持つ魔術的な効果を明らかにしました [3]。
彼らの分析によれば、ITバブルの最盛期に、社名をインターネット関連(「.com」など)に変更することを発表した企業は、その企業の事業内容に実質的な変化がほとんどないにも関わらず、発表を挟んだ10日間で平均74%もの異常な株価上昇を記録しました。これは、投資家が企業のファンダメンタルズではなく、単に「.com」という記号が持つ「ニューエコノミー」という物語性(ナラティブ)だけに反応していたことを示す、強力な証拠です。
市場の不合理性という現実
ナラティブの力は、市場に、基本的な算数さえも成り立たないほどの、極端な価格の歪みをもたらしました。
ラモントとセイラーによる2003年の研究は、その決定的証拠を提示しています [4]。彼らは、親会社がハイテク子会社の一部をスピンオフ(カーブアウト)した事例を分析しました。その中で最も有名な3Com社とPalm社の事例では、市場が評価した子会社(Palm)の時価総額だけで、親会社(3Com)全体の時価総額を上回るという、ありえない事態が発生しました。これは、市場が親会社の残りの事業(子会社以外の全事業)の価値を「マイナス」と評価していたことを意味し、市場がいかに不合理な熱狂に支配されていたかを物語っています。
短所、弱み、リスクについて:物語の限界と崩壊(損失事例)
しかし、ファンダメンタルズから乖離したナラティブは、永遠には続きません。その崩壊は、物語を信じた多くの投資家に深刻な損失をもたらしました。
スマートマネーの不在
このような明らかなバブルに対して、なぜプロの投資家(スマートマネー)は、空売りを仕掛けて価格を是正しなかったのでしょうか。ブルナーマイヤーとナーゲルによる2004年の研究は、ヘッジファンドの行動を分析し、その謎に迫りました [5]。
驚くべきことに、彼らの分析によれば、ヘッジファンドはバブルを是正するどころか、むしろ積極的にハイテク株へのエクスポージャーを高め、バブルの波に乗っていたことが示されています。彼らがバブルから本格的に撤退し始めたのは、ピークを迎えるごく直前でした。これは、バブルの勢いの前では裁定取引が極めて困難であること、そして、群集に逆らうことの「キャリアリスク」がいかに大きいかを示唆しています。
根拠なき熱狂の終焉
「ニューエコノミー」の物語が約束した未来(永続的な高成長と高い収益性)は、現実のものとはなりませんでした。多くのドットコム企業は、利益を上げることなく倒産し、生き残った企業も、その後の成長が市場の熱狂的な期待には到底及ばないことが明らかになりました。
物語の根拠が失われた時、熱狂はパニックへと変わり、株価は暴落。2000年から2002年にかけて、ハイテク株を中心に構成されるナスダック総合指数は、その価値の8割近くを失いました。これは、いかに強力なナラティブであっても、最終的には経済のファンダメンタルズという重力から逃れることはできないという、歴史の教訓です [2]。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、「ニューエコノミー」という物語は、あれほどまでに多くの、時には合理的なはずの投資家までもを巻き込む、巨大な熱狂へと発展したのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:物語の「伝染力」の非対称性
ITバブルの根源には、物語が持つ「伝染力」そのものの非対称性が存在します。
ロバート・シラーが指摘するように、人間の感情に強く訴えかけ、シンプルで分かりやすい物語は、退屈で、複雑で、データに基づいた客観的な事実よりも、非対称に強い伝染力を持ちます [1]。
「インターネットが世界を変える」という「ニューエコノミー」の物語は、未来への希望、若き起業家の成功譚、そして一攫千金の可能性といった、極めて魅力的で、感情に訴えかける要素に満ちていました。
一方で、PERやPBRといった伝統的な評価指標が示す「割高感」というデータは、この輝かしい物語の前では、古臭く、退屈な「旧時代の遺物」として退けられました。この「物語の魅力」と「データの退屈さ」との間の非対称性が、市場の熱狂を増幅させ、多くの投資家を非合理的な判断へと導いたのです。
Friction:「空売り」の難しさという物理的摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、ITバブルがこれほどまでに巨大化し、長期間にわたって持続した背景には、市場の価格是正メカニズムを機能不全に陥らせる、より深刻な「摩擦」が存在しました。
空売り制約という物理的摩擦
市場の過熱を是正する最も直接的な力は、割高な銘柄を「空売り」する裁定取引です。しかし、ITバブルの渦中にあったドットコム企業の多くは、その空売りが極めて困難でした。
ラモントとセイラーの研究が示すように、これらの銘柄の多くは、貸株市場で株を借りるためのコスト(貸株料)が異常に高騰しており、物理的に空売りが不可能な銘柄も少なくありませんでした [4]。この「空売り制約」という強力な物理的摩擦が、価格を押し下げようとする合理的な投資家の力を奪い、バブルが何の障害もなく膨らみ続けることを許してしまったのです。
キャリアリスクという制度的摩擦
もう一つの摩擦は、プロの投資家であるファンドマネージャーが直面する「キャリアリスク」です。
ブルナーマイヤーとナーゲルの研究が示唆するように、バブルの最盛期において、もしファンドマネージャーが「ニューエコノミー」の物語を信じず、ハイテク株への投資を避けていたとしたら、彼のファンドのパフォーマンスは、熱狂する市場全体のパフォーマンスに大きく劣後したでしょう [5]。その結果、彼は顧客から資金を引き揚げられ、キャリアを失っていたかもしれません。
この「群集に従わないことのリスク」という制度的な摩擦が、たとえ内心では割高だと分かっていたとしても、多くのプロの投資家に、バブルに乗り続けざるを得ないという選択を強いたのです。
総括
・1990年代後半のITバブルは、インターネットが経済のルールを根本的に変えたという「ニューエコノミー」という強力な物語(ナラティブ)によって引き起こされました。
・ロバート・シラーの研究は、この現象をナラティブ経済学の観点から分析し、物語がメディアや口コミを通じてウイルスのように伝染し、市場に「根拠なき熱狂」を生み出す過程を明らかにしました [1, 2]。
・ナラティブの純粋な力は、「.com」と社名変更するだけで株価が異常に高騰した事実 [3]や、市場が基本的な算数さえできなくなるほどの価格の歪みを生んだ事実 [4]からも確認できます。
・このバブルは、「空売り制約」という物理的な摩擦や、プロの投資家でさえバブルに追随せざるを得なかった「キャリアリスク」という制度的な摩擦によって増幅され、最終的に崩壊しました [4, 5]。
用語集
ナラティブ経済学 (Narrative Economics) ロバート・シラーが提唱した、人々の間で伝播する「物語(ナラティブ)」が、経済全体の変動にいかに影響を与えるかを分析する経済学のアプローチ。
ナラティブ (Narrative) 人々の感情や動機に訴えかけ、口コミやメディアを通じて伝染していく、特定の出来事に関する「物語」や「説明」のこと。
ITバブル (Dot-com Bubble) 1990年代後半に、インターネット関連企業の株価が、実態価値からかけ離れて熱狂的に高騰した経済バブル。
ニューエコノミー (New Economy) ITバブル期に広く信じられた、インターネットと情報技術が経済の構造を根本的に変え、古い経済法則はもはや通用しない、という物語。
根拠なき熱狂 (Irrational Exuberance) ロバート・シラーの著書のタイトルであり、資産価格がファンダメンタルズから説明できないほどに高騰する、市場の心理的な熱狂状態を指す言葉。
フィードバック・ループ (Feedback Loop) ある事象の結果が、その原因にさらに影響を与え、プロセス全体を増幅または抑制する循環的な関係。ITバブルでは、株価上昇がさらなる楽観を生み、それがさらなる株価上昇を呼ぶ、という正のフィードバック・ループが発生した。
ファンダメンタルズ (Fundamentals) 企業の収益力や財務状況、資産価値といった、その企業の本質的な価値を決定する基礎的条件。
裁定取引 (Arbitrage) 価格の歪みを利用して、リスクなく利益を得ようとする取引。価格を適正な水準に戻す力となる。
空売り (Short Selling) 所有していない株式を証券会社などから借りて市場で売却し、将来価格が下落した時点で買い戻して返済し、その差額を利益とする取引。
カーブアウト (Carve-out) 親会社が、その子会社や特定事業の一部を、戦略的に分離・独立させて、新会社の株式を市場に上場させること。
参考文献一覧
[1] Shiller, R. J. (2017). Narrative economics. American Economic Review, 107(4), 967-1004.
https://doi.org/10.1257/aer.107.4.967?utm_source=chatgpt.com
[2] Shiller, R. J. (2000). Irrational Exuberance. Princeton University Press.
※書籍です。
[3] Cooper, M. J., Dimitrov, O., & Rau, P. R. (2001). A rose.com by any other name. The Journal of Finance, 56(6), 2371-2388.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.242376
[4] Lamont, O. A., & Thaler, R. H. (2003). Can the market add and subtract? Mispricing in tech stock carve-outs. Journal of Political Economy, 111(2), 227-268.
https://doi.org/10.1086/367683
[5] Brunnermeier, M. K., & Nagel, S. (2004). Hedge funds and the technology bubble. The Journal of Finance, 59(5), 2013-2040.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00690.x
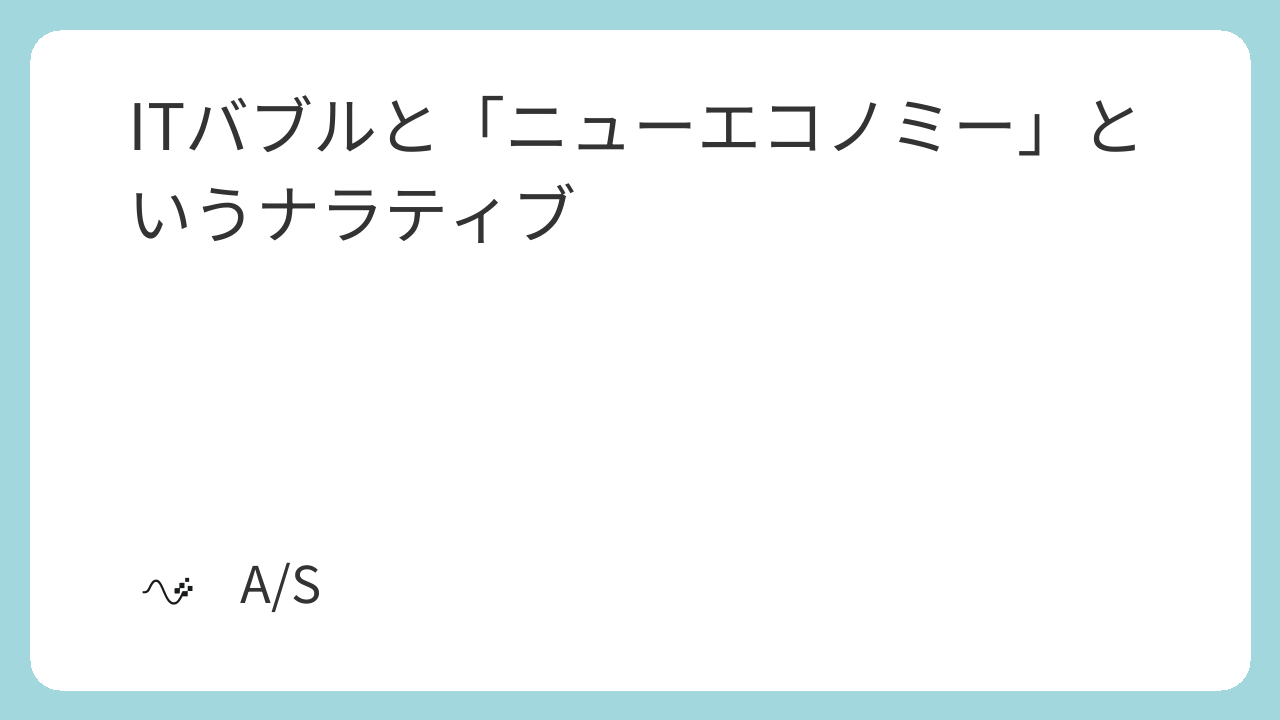
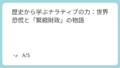
コメント