概論
先日の記事では、ノーベル経済学賞受賞者ロバート・シラーが提唱した「ナラティブ経済学」が、人々の間でウイルスのように広まる「物語」が経済を動かすという、新しい視点を提供することを解説しました。しかし、ここで一つの重要な問いが浮かび上がります。情報が溢れる現代において、その「ナラティブ」とは、私たちが日々触れている無数のニュースや、時折耳にする噂と、一体何が違うのでしょうか。
この区別は、市場の情報を分析する上で極めて重要です。なぜなら、情報の種類によって、その伝播の仕方も、経済に与える影響の規模や持続性も、全く異なるからです。シラーによれば、経済的ナラティブとは、単なる情報の断片ではなく、人々の感情や道徳観に訴えかけ、人間的な魅力を伴って伝染していく物語です [1]。
この記事では、この「経済的ナラティブ」という概念の輪郭を、関連する情報形態である「ニュース」と「噂」との比較を通じて、学術的な知見に基づきながら明確に定義していきます。それぞれの本質的な違いを理解することは、市場の背後にある、より深く、そして強力な動機を読み解くための第一歩となるでしょう。
ナラティブ、ニュース、噂の境界線
経済的ナラティブの本質を理解するためには、まず、私たちが日常的に接する他の情報形態との比較が有効です。ここでは、学術的な研究に基づき、「ニュース」と「噂」がそれぞれどのような役割と性質を持つのかを整理し、ナラティブとの違いを浮き彫りにします。
ニュースの役割:アジェンダ(議題)の設定
ニュースメディアが社会に与える最も強力な影響の一つは、「アジェンダ設定機能」として知られています。これは、メディアが、何が重要で、何について考えるべきかという「議題(アジェンダ)」を人々に提示する力を持つ、という理論です [2]。例えば、メディアが繰り返しインフレについて報道すれば、人々はインフレを重要な問題として認識するようになります。
このように、ニュースの主な役割は、経済的な議論の「素材」や「土台」を提供することにあります。ニュースは「今月の失業率は3.5%だった」というような客観的な事実を伝えますが、それ自体が「なぜそうなったのか」「これからどうすべきか」という解釈や因果関係の物語を必ずしも提供するわけではありません。ニュースが設定した議題の上で、その意味を説明し、人々の感情や行動を方向づける物語、それこそがナラティブなのです。
噂の性質:曖昧さの解消と情報の歪み
噂は、ナラティブと同様に人から人へと伝染する性質を持ちますが、その発生メカニズムと機能は異なります。心理学の古典的な研究によれば、噂とは、人々が重要かつ曖昧な状況に直面した際に、その状況を理解し、意味づけしようとする集団的な問題解決の試みとして生まれます [3]。
噂は、伝播の過程で特徴的な変化を遂げることが知られています。物語は次第に単純化・簡潔化され(平準化)、特定のディテールが誇張され(強調化)、そして聞き手の既存の信念や期待に沿うように、内容が歪められていくのです(同化)[3]。一方で、経済的ナラティブは、より長期間にわたって存続し、社会の価値観や世界観を反映する、より複雑で構造化された物語であることが多い点で、一時的で断片的な噂とは区別されます。
ナラティブの本質:因果関係と人間的魅力
ニュースが「何が起きたか」を伝え、噂が「何が起きているらしいか」という不確かな情報を拡散させるのに対し、ナラティブは「なぜそれが起きたのか」という因果関係の説明と、人々の感情に訴えかける人間的な魅力を提供します [1]。例えば、「テクノロジー株が上昇している」というニュースに対し、「AI革命によって、世界は新しい時代に突入したのだ」というナラティブは、その現象に壮大な意味と未来への期待感を与え、人々の投資行動を強く動機付けます。
この「物語の層」が持つ力は、金融市場の分析においても確認されています。ある研究は、金融ニュース記事で使われる言葉の「悲観度」を分析し、単なる客観的な事実だけでなく、その伝え方、すなわちナラティブの持つ感情的なトーンが、将来の企業収益や株価リターンを予測する力を持つことを示しました [4]。
なぜこの区別が重要なのか?
この三つの情報形態を区別することが重要なのは、それぞれが経済に与える影響のスケールと持続性が全く異なるからです。
噂や誤情報は、時に特定の銘柄の株価を一時的に動かすことはあっても、その影響は比較的限定的です。たとえ虚偽の情報であっても、その拡散力には限界があることが研究で示唆されています [5]。
しかし、一度社会に広く浸透した強力な経済ナラティブは、人々の行動様式を根本から変え、数年、あるいは数十年単位の長期的な経済トレンドを生み出す力を持っています。例えば、財政政策に関するナラティブが、一国の経済政策の方向性を長期間にわたって規定することがあります。ある研究では、ドイツとフランスにおける相異なる政策ディスコースが、欧州通貨同盟改革に関する合意形成をどのように方向づけてきたかが分析されており、物語が現実の経済構造を形成する力を持つことが示されています [6]。単なるニュースや噂を超え、人々の世界観そのものを形作る力、それこそが経済的ナラティブを特異な存在たらしめているのです。
非対称性と摩擦の視点から
ポジティブファクター:Asymmetry
ナラティブ、ニュース、噂の決定的な違いは、その情報が持つ「伝染力の非対称性」にあります。すべての情報が、平等な力で人々の心に広まっていくわけではありません。
客観的な事実を伝えるニュースや、検証不可能な噂に比べ、優れた物語、すなわちナラティブは、伝染において本質的に非対称な優位性を持っています。なぜなら、ナラティブは単なる情報ではなく、人間の感情や記憶に深く刻み込まれるように設計された「パッケージ」だからです。因果関係が明確で、人間的な魅力があり、感情に訴えかける物語は、無味乾燥なデータよりも遥かに伝染力が高いのです。この伝染力の非対称性は、近年の研究でも示唆されています。例えば、ソーシャルメディア上では、感情的な要素を伴う虚偽のニュースが、客観的な真実のニュースよりも、遥かに速く、広く、そして深く拡散することが示されています [5]。
トレーダーや投資家にとって、この情報の伝染における非対称性は、収益機会の源泉となり得ます。ある経済事象に対して、どのようなナラティブが形成され、支配的になっていくかを早期に察知できれば、大多数の人々がその物語に「感染」し、行動を起こす前に、有利なポジションを構築することが可能になります。市場のコンセンサスを形成するのが、客観的なニュースそのものではなく、そのニュースをどう解釈するかという、伝染力の高いナラティブであると理解すること。それ自体が、他の市場参加者に対する、非対称な情報的優位性となるのです。
ネガティブファクター:Friction
ある情報が、単なるニュースや噂に留まるか、それとも社会を動かすほどの強力なナラティブへと進化するか。その運命を分けるのが、情報の伝達経路に存在する様々な「摩擦」です。
最大の摩擦は、認知的な摩擦です。人間の脳は、情報を処理する上で、できるだけエネルギーを節約しようとします。複雑で、多角的で、 nuanceに富んだ情報は、理解するのに多大な認知的な負荷を要求するため、伝達の過程で高い摩擦に直面します。一方で、シンプルで、白黒がはっきりしており、既存の信念体系に合致する物語は、この認知的な摩擦が極めて低く、容易に人々の心に浸透します。古典的な噂の研究が示したように、情報は伝わるにつれて、よりシンプルで、覚えやすく、語りやすい形へと変容していくのです [3]。この摩擦こそが、質の低い情報から成るナラティブが、質の高い複雑な分析を駆逐してしまう現象の背景にあります。
第二に、社会的な摩擦です。新しい情報や物語は、既存の社会規範や信頼できる情報源(権威あるメディアや専門家など)による検証という摩擦に晒されます。多くの噂は、この検証のプロセスで「事実ではない」と否定され、その伝播が食い止められます。しかし、強力なナラティブは、時にこの社会的な摩擦を乗り越え、あるいは迂回します。特に、物語が特定の集団のアイデンティティや価値観と強く結びついた場合、人々は事実関係の検証よりも、その物語を信じることによる連帯感を優先するようになります。
最後に、メディアという摩擦(あるいは増幅器)です。メディアは、どの情報を議題として取り上げるかを選択する「ゲートキーパー」として機能します [2]。メディアの注目というゲートを通過できなかった情報は、社会に広まる上で大きな摩擦に直面します。逆に、一度メディアに取り上げられ、繰り返し報道された物語は、その伝達における摩擦が劇的に低下し、爆発的な伝染を引き起こす可能性があるのです。
総括
この記事では、「経済的ナラティブ」が、私たちが日常的に接する「ニュース」や「噂」と、本質的に何が違うのかを、学術的な知見に基づいて定義し、比較しました。
- 経済的ナラティブとは、ロバート・シラーが提唱した概念で、単なる情報ではなく、人々の感情や道徳観に訴えかけ、ウイルスのように伝染していく「物語」のことです [1]。
- ニュースは、社会が何について考えるべきかという「議題」を提供する役割を持ちますが [2]、ナラティブは、その議題に対して「なぜそうなったのか」という因果関係と解釈を与えます。
- 噂は、曖昧な状況を理解しようとする集団心理から生まれ、伝播の過程で内容が単純化・歪曲していく特徴があります [3]。一方、ナラティブはより構造化され、長期間持続する世界観を提示します。
- この区別が重要なのは、影響力のスケールと持続性が異なるためです。強力なナラティブは、短期的な株価の変動に留まらず、数十年単位の経済政策や投資トレンドを形成する力を持っています [5]。
- 非対称性の観点からは、物語は客観的な事実よりも「伝染力」において非対称な優位性を持ちます [5]。
- 摩擦の観点からは、人間の「認知的な限界」や、メディアによる情報の選別が、特定のナラティブが流行し、他の情報が無視される原因となっています。
用語集
経済的ナラティブ 経済的な意思決定に影響を与える、人々の間でウイルスのように広まる「物語」のこと。ロバート・シラーによって提唱された [1]。
ロバート・シラー 米国の経済学者。2013年にノーベル経済学賞を受賞。「行動ファイナンス」の第一人者であり、「ナラティブ経済学」の提唱者。
ニュース 社会で起きた出来事に関する、客観的な事実に基づくとされる情報。メディアによって選別され、報道される。
噂(Rumor) 真偽が不確かなまま、人々によって口伝えで広まっていく情報。曖昧な状況を理解しようとする集団心理から生まれるとされる [3]。
アジェンダ設定機能 マスメディアが、特定の争点を選択的に報道することで、公衆が重要と見なす議題(アジェンダ)を形成する力を持つ、という理論 [2]。
伝染(Contagion) この文脈では、情報や物語が、感染症のように人から人へと広まっていくプロセスを指す。
平準化・強調化・同化 噂が伝播する過程で、内容が変化していく3つの心理的プロセス [3]。「平準化」は物語が単純になること、「強調化」は特定の点が誇張されること、「同化」は聞き手の信念に合わせて内容が歪められること。
因果関係 二つの事象の間に存在する、原因と結果の関係。ナラティブは、単なる事象の発生だけでなく、その背後にある因果関係を説明しようとする。
自然言語処理(NLP) 人間が日常的に使っている言葉(自然言語)を、コンピューターが処理・分析するための技術。ナラティブ経済学では、ニュース記事などからナラティブを定量的に抽出するために用いられる [5]。
ソーシャルメディア 個人が情報を発信し、社会的なネットワークを形成するためのオンラインプラットフォーム。情報の伝達速度を劇的に高め、ナラティブの拡散に大きな影響を与える [5]。
参考文献一覧
[1] Shiller, R. J. (2017). Narrative economics. American Economic Review, 107(4), 967-1004.
https://doi.org/10.1257/aer.107.4.967?utm_source=chatgpt.com
[2] McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176-187.
https://doi.org/10.1086/267990?utm_source=chatgpt.com
[3] Allport, G. W., & Postman, L. (1947). The Psychology of Rumor. Henry Holt and Company.
※書籍です。
[4] Tetlock, P. C., Saar-Tsechansky, M., & Macskassy, S. (2008). More than words: Quantifying language to measure firms’ fundamentals. The Journal of Finance, 63(3), 1437-1467.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01362.x?utm_source=chatgpt.com
[5] Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146-1151.
https://doi.org/10.1126/science.aap9559?utm_source=chatgpt.com
[6] Crespy, A., & Schmidt, V. A. (2014). The clash of Titans: France, Germany and the discursive double game of EMU reform. Journal of European Public Policy, 21(8), 1085–1101.
https://doi.org/10.1080/13501763.2014.914629
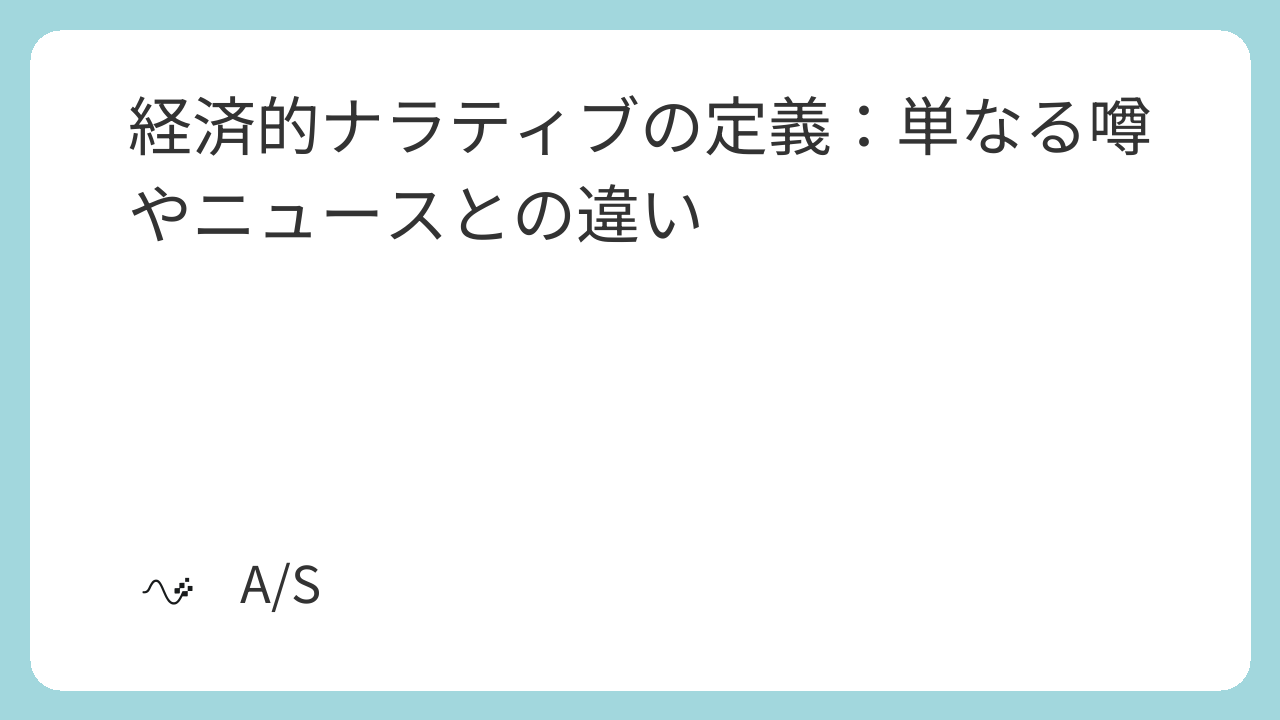
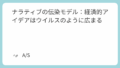
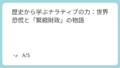
コメント