概論
経済的な意思決定に影響を与える、人々の間で伝染する「物語」を研究するナラティブ経済学 [1]にとって、1929年に始まった世界恐慌ほど、その力を雄弁に物語る歴史的事件はありません。株価は暴落し、銀行は次々と倒産、失業率は壊滅的な水準に達しました。この未曾有の経済危機に対し、なぜ当時の為政者や大衆は、状況をさらに悪化させかねない政策を選択してしまったのでしょうか。
その答えの鍵を握るのが、当時、社会を支配していた極めて強力な経済ナラティブ、すなわち「緊縮財政」の物語です。これは、政府の財政を個人の家計になぞらえ、「収入が減ったのだから、支出を切り詰めて、借金を減らすべきだ」という、一見すると道徳的で、直感的に理解しやすい物語でした。
この記事では、世界恐慌という極限状況において、この「緊縮財政」というナラティブが、いかにして人々の心を掴み、金融政策や通商政策にまで影響を及ぼし、そして最終的にどのような結末を招いたのかを、学術的な知見に基づいて分析します。物語が、時に経済合理性をも凌駕する力を持つことを、歴史は教えてくれます。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
この文脈における「長所」とは、特定のナラティブがいかにして人々の心を掴み、社会的なコンセンサスを形成する力を持っていたか、という「説得力」を指します。一方で「短所」とは、そのナラティブに基づいて下された意思決定が、いかにして経済に深刻なダメージを与えたか、という「負の帰結」を意味します。
「緊縮財政」ナラティブの強み:その道徳的な説得力
世界恐慌の最中にあって、緊縮財政という物語がこれほどまでに強力な支持を得た理由は、そのシンプルさと道徳的な魅力にありました。このナラティブは、複雑なマクロ経済の問題を、「勤勉に働き、収入の範囲内で暮らし、借金を返済する」という、誰もが理解できる個人の家計の倫理へと置き換えてみせました [1]。
この考え方は、経済的な苦境を、過去の過剰な消費や投機に対する「当然の報い」と見なし、痛みを伴う緊縮こそが、経済の健全性を回復させるための唯一の道である、という道徳的な正当性を人々に与えました。このような「危険な思想の歴史」を分析した研究によれば、緊縮財 政は、単なる経済政策の選択肢ではなく、しばしば道徳的な十字軍として語られてきたのです [2]。
この強力な物語に後押しされ、当時のフーヴァー政権は、歳入を増やして財政均衡を目指すために、歴史的な増税(1932年歳入法)を断行しました。さらに、金融政策においても、「健全な通貨」を維持し、金本位制を守るというナラティブが支配的でした。その結果、連邦準備制度(FRB)は、経済が深刻なデフレに陥っているにもかかわらず、金融緩和に踏み切ることができませんでした。ある画期的な金融史研究が明らかにしたように、この金融引き締めが、本来であればただの景気後退で終わったかもしれない事象を、大恐慌へと悪化させた主要な原因でした [3]。
また、これと並行して、「国内の雇用を外国製品から守る」という保護主義のナラティブも広まりました。この物語は、1930年のスムート・ホーリー法の成立へと繋がり、結果として世界的な報復関税の連鎖、すなわち貿易戦争を引き起こし、世界経済のブロック化と恐慌の深化を招いたことが、その後の研究で示されています [4]。
対抗ナラティブの登場と、緊縮財政の短所
この支配的な緊縮ナラティブに対して、全く新しい物語を提示したのが、経済学者ジョン・メイナード・ケインズです。彼は、経済全体の需要が不足している時には、個人や企業が節約すればするほど、経済はさらに悪化するという「節約のパラドックス」を指摘しました。そして、この悪循環を断ち切るためには、政府が借金をしてでも支出を増やし、需要を創出するしかない、という対抗ナラティブを提唱したのです [5]。
ケインズの理論は、すぐには受け入れられませんでしたが、その後の経済政策に絶大な影響を与えました。そして、この「緊縮か、刺激か」というナラティブの対立は、一世紀近く経った現代でも繰り返されています。2008年の金融危機後、多くの国で緊縮財政が採用されましたが、その後の研究では、政府支出の削減が経済成長を大きく抑制し、結果としてかえって政府の債務残高対GDP比を悪化させるという、自己破壊的な効果を持つ可能性が示唆されています [6]。これは、世界恐慌の時代に支配的だった緊縮ナラティブが、現代においてもなお、その危険な魅力を失っていないことを物語っています。
非対称性と摩擦の視点から
ポジティブファクター:Asymmetry
世界恐慌期における「緊縮財政」の物語は、アイデアの競争における「非対称性」の力を鮮明に示しています。
第一に、物語の「単純さ」と「複雑さ」の間の非対称性です。緊縮財政の物語、すなわち「政府の財政は家計と同じであり、苦しい時こそ支出を切り詰めるべきだ」というアナロジーは、非常にシンプルで、直感的、かつ道徳的にも分かりやすいものでした [1, 2]。一方、ジョン・メイナード・ケインズが提唱した対抗ナラティブ、すなわち「皆が節約すると経済全体が縮小する(節約のパラドックス)」という考え方は、複雑で、直感に反するものでした [5]。危機的状況において、人々の心に響き、伝染していく力は、この二つの物語の間で著しく非対称でした。単純な物語は、複雑な真実に対して、伝播力という非対称な優位性を持つのです。
第二に、政策がもたらす結果の非対称性です。緊縮財政や金融引き締め政策は、しばしば「信認の回復」や「健全な通貨の維持」といった目的を掲げ、長期的には経済に良い影響をもたらすと語られます。しかし、その短期的な影響は、社会に対して極めて非対称に作用します。失業の増大や社会保障の削減といったコストは、主に社会的弱者層に集中します。一方で、デフレによる通貨価値の維持は、債権を保有する富裕層にとっては有利に働く場合があります。このように、一見すると中立的に見える経済ナラティブが、実際にはその利益と損害を、社会の異なる階層に対して非対称に分配する機能を持っているのです。
ネガティブファクター:Friction
ではなぜ、多くの経済学者があの時点でその危険性を指摘していたにもかかわらず、緊縮財政という、経済を悪化させる可能性のあるナラティブが、これほどまでに支配的になったのでしょうか。その背景には、合理的な政策決定を阻む、強力な「摩擦」が存在しました。
最大の摩擦は、認知的な摩擦です。先述の通り、「政府の家計アナロジー」は、人々の認知にとって、最も抵抗の少ない、滑らかな道筋を提供します。この強力な認知のショートカットが、より複雑で、しかしより現実に即した経済モデルの理解を妨げる、強力な摩擦として機能しました。人々は、理解しやすい物語に固執し、それに反する証拠から目を背けてしまうのです。
第二に、制度的な摩擦としての「金本位制」の存在です。当時、多くの国が採用していた金本位制は、各国の通貨価値を金に固定する、極めて硬直的な制度でした。この制度の下では、通貨価値を守ることが金融政策の最優先課題とされ、国内経済が深刻なデフレに陥っていても、FRBは大胆な金融緩和に踏み切ることができませんでした [3]。この金本位制という制度的な枠組みが、より柔軟な政策対応を妨げ、緊縮的な思考を正当化する、抗いがたい摩擦として作用したのです。
最後に、政治的な摩擦です。経済危機において、有権者に対して「痛みを伴う改革」や「規律」を説くことは、道徳的に正しく、責任あるリーダーシップの証であるかのように語られます。一方で、大規模な財政出動や赤字国債の発行を主張することは、「無責任なバラマキ」として政治的な攻撃を受けやすい、という非対称性があります。この政治的な力学が、たとえ経済的には不合理であっても、為政者を緊縮財政という物語へと誘導する、強力な摩擦となったのです。
総括
この記事では、世界恐慌という歴史的な出来事を題材に、社会を支配する「物語(ナラティブ)」が、いかにして経済政策を方向づけ、危機を深刻化させたかを分析しました。
- 世界恐慌期において、多くの国で採用された緊縮財政や金融引き締め政策の背景には、「政府の財政は家計と同じである」という、シンプルで道徳的に魅力的なナラティブが存在しました [1, 2]。
- このナラティブは、フーヴァー政権の増税や、FRBによる金融緩和の遅れを正当化し、大恐慌を深刻化させる一因となりました [3]。また、「国内雇用の保護」というナラティブは、世界的な貿易戦争を引き起こしました [4]。
- これに対し、ケインズは「需要創出のための政府支出」という対抗ナラティブを提示し、その後の経済政策に大きな影響を与えました [5]。
- この「緊縮か、刺激か」というナラティブの対立は、2008年の金融危機後にも繰り返され、緊縮財政が経済成長を阻害し、かえって債務問題を悪化させる可能性が指摘されています [6]。
- 非対称性の観点からは、単純な物語は複雑な真実に対して非対称な伝播力を持ち、緊縮政策は社会の異なる階層に非対称な影響を与えます。
- 摩擦の観点からは、「政府の家計アナロジー」という認知摩擦や、「金本位制」という制度的摩擦が、より合理的な政策決定を妨げ、破壊的なナラティブの支配を許しました。
用語集
ナラティブ経済学 ノーベル経済学賞受賞者のロバート・シラーによって提唱された経済学のアプローチ。人々の間で語られ、ウイルスのように広まる「物語(ナラティブ)」が、いかにして大きな経済変動を引き起こすかを研究する [1]。
世界恐慌 1929年のウォール街における株価大暴落に端を発し、1930年代を通じて世界中を巻き込んだ深刻な経済危機。大量の失業と生産の激減を特徴とする。
緊縮財政(Austerity) 政府の財政赤字を削減するために、政府支出の削減や増税を行う経済政策。財政規律を重視する物語に支えられることが多い [2]。
ジョン・メイナード・ケインズ 20世紀を代表する英国の経済学者。大恐慌の分析を通じて、政府が積極的に市場に介入し、需要を創出することの重要性を説き、現代マクロ経済学の基礎を築いた [5]。
節約のパラドックス 個人にとっては合理的な節約行動も、社会全体で行われると、総需要を減少させて経済を縮小させ、結果として社会全体の貯蓄も減少してしまう、というケインズが指摘した概念。
金本位制 一国の通貨価値を、一定量の金(ゴールド)と等価であると定義し、その兌換を保証する通貨制度。世界恐慌期には、この制度が金融政策の柔軟性を奪う「足枷」となった [3]。
スムート・ホーリー法 1930年に米国で制定された関税法。2万品目以上の輸入品に高関税を課し、各国の報復関税を招いて世界貿易を著しく縮小させ、大恐慌を悪化させる一因となった [4]。
保護主義 高い関税や輸入制限などを通じて、国内産業を海外との競争から保護しようとする貿易政策。
財政政策 政府支出や税制を通じて、経済全体の需要をコントロールし、景気の安定や成長を目指す経済政策。
金融政策 中央銀行が、金利や通貨供給量を調整することを通じて、物価の安定や経済の健全な発展を目指す経済政策 [3]。
参考文献一覧
[1] Shiller, R. J. (2019). Narrative economics: How stories go viral and drive major economic events. Princeton University Press.
https://doi.org/10.2307/j.ctvdf0jm5
[2] Blyth, M. (2013). Austerity: The history of a dangerous idea. Oxford University Press.
https://www.jstor.org/stable/intesociscierevi.91.1.07
[3] Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1963). A monetary history of the United States, 1867-1960. Princeton University Press.
https://www.jstor.org/stable/j.ctt7s1vp
[4] Irwin, D. A. (1998). The Smoot-Hawley Tariff: A quantitative assessment. The Review of Economics and Statistics, 80(2), 326-334.
https://www.jstor.org/stable/2646642
[5] Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan.
https://doi.org/10.2307/1882087
[6] Fatás, A., & Summers, L. H. (2018). The permanent effects of fiscal consolidations. Journal of International Economics, 112, 238-250.
https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2018.02.005
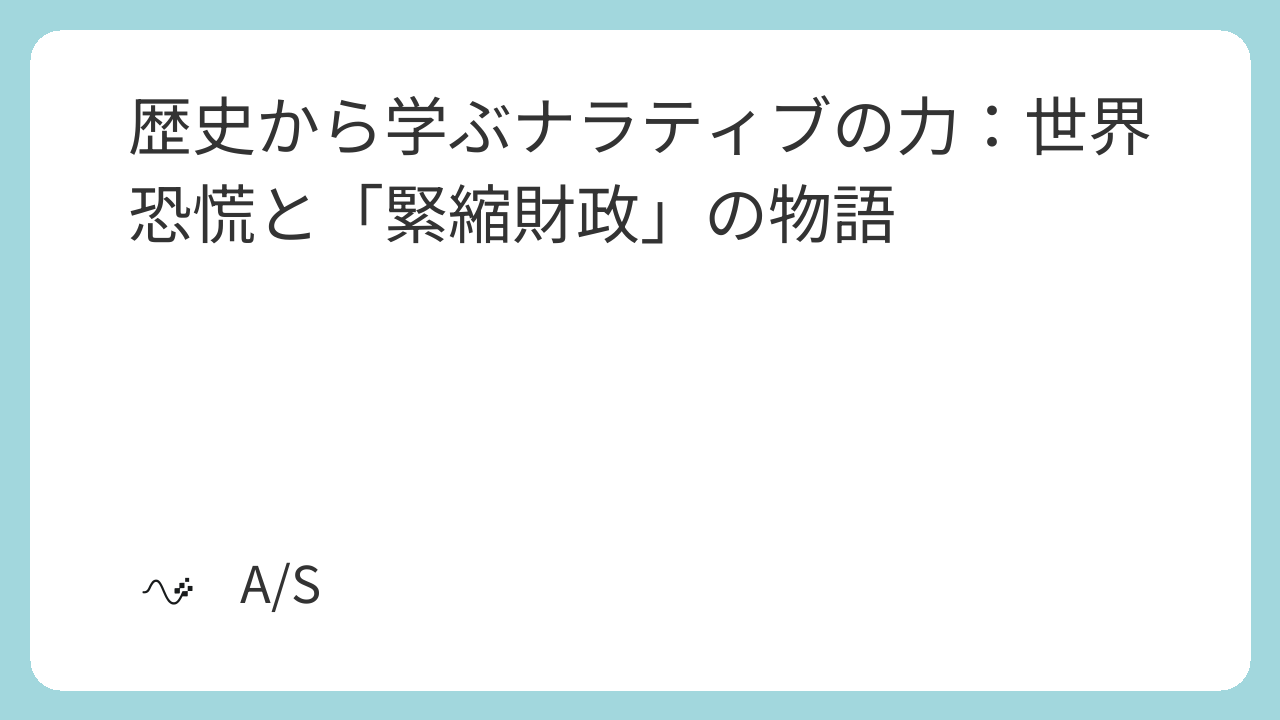
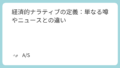
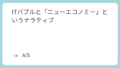
コメント