概論:現代ファイナンス理論の根幹を揺るがす逆説
「ハイリスク・ハイリターン」――これは、投資の世界における大原則だと考えられています。この思想を理論的に体系化したのが、ウィリアム・シャープらによって構築された資本資産評価モデル(CAPM)です [1]。CAPMによれば、個別株式のリターンは、その株式が市場全体の値動きに対してどれだけ敏感に反応するかを示す指標、ベータ(β)の大きさに比例して決まります。つまり、ベータが高い(市場全体よりも値動きが激しい)株式ほど、そのリスクを引き受ける対価として、高いリターンが期待されるはずでした。
しかし、その後の実証研究は、この美しい理論が現実の市場では必ずしも成り立たないことを示しました。むしろ、「高ベータの株式のリターンは理論的に予測されるよりも低く、逆に低ベータの株式のリターンは予測されるよりも高い」という、CAPMの予測とは正反対の現象が観測されたのです。これがベータ・アノマリー、あるいは低ボラティリティ・アノマリーとして知られる、現代ファイナンスにおける最も根源的で、不可解な謎の一つです。
このアノマリーの存在を最初に大規模なデータで示したのが、フィッシャー・ブラック、マイケル・ジェンセン、マイロン・ショールズによる1972年の有名な実証研究です [2]。彼らは、米国株式市場の長期データを用いてCAPMを検証し、ベータとリターンの関係が、理論が予測するよりも遥かに「フラット」であることを発見しました。高リスク(高ベータ)を取っても、それに見合うリターンは得られていなかったのです。
この発見は、半世紀以上経った今なお、活発な学術的議論の対象となっています。なぜ、リスクを取ることが必ずしも報われないのか?この記事では、ベータ・アノマリーの正体と、その背景にあるメカニズムを、学術研究を基に深掘りしていきます。
長短の解説と損益の事例紹介
ベータ・アノマリーは、伝統的なリスクの概念に疑問を投げかけると同時に、新たな投資機会の可能性を示唆します。ここでは、このアノマリーがもたらす影響を、具体的な研究成果と共に解説します。
長所、強み、有用な点について:低ベータ株の驚くべき実績
ベータ・アノマリーの発見は、「高リスク資産を避ける」という一見すると退屈な戦略が、実は優れたリスク調整後リターンを生み出す可能性を示しました。
収益事例1:高ボラティリティ株の長期的な低迷
近年の研究は、このアノマリーをさらに強力に裏付けています。アンドリュー・アンらの2006年の研究は、株式の idiosyncratic volatility(個別銘柄固有のボラティリティ)と将来のリターンの関係を調査しました [3]。その結果は衝撃的で、ボラティリティが最も高いポートフォリオのリターンは、最も低いポートフォリオのリターンを大幅に下回り、その差は月次で1%以上にも達しました。これは、「ハイリスク・ローリターン」という、CAPMの予測とは真逆の現実を示しています。
収益事例2:「ベータに賭ける」戦略の有効性
このアノマリーを体系的に利用する戦略として最も有名なのが、アンドレア・フラッツィーニとラッセ・ペデルセンが2014年の論文で提唱した「ベッティング・アゲンスト・ベータ(Betting Against Beta, BAB)」ファクターです [4]。
この戦略は、低ベータの銘柄(安全資産)をレバレッジをかけて買い持ちし、同時に高ベータの銘柄(リスク資産)を空売りすることで、市場全体の動きに対して中立なポートフォリオを構築します。彼らの分析によれば、1926年から2012年までの米国市場において、このBABファクターは極めて高いシャープレシオ(0.77)を記録しました。さらに、この戦略は20の国際市場でも同様に有効であり、ベータ・アノマリーがグローバルな現象であることが示されています。
短所、弱み、リスクについて:高ベータ株が報われない理由
なぜ、リスクが高いはずの高ベータ株は、期待されるリターンを生み出さないのでしょうか。その背景には、市場参加者の構造的な制約や、非合理的な行動があると考えられています。
1.レバレッジ制約という構造的問題
ベータ・アノマリーを説明する最も有力な仮説が「レバレッジ制約」です。フラッツィーニとペデルセンが指摘するように、多くの投資家、特にミューチュアル・ファンドのような機関投資家は、規約などによってレバレッジ(借入)の利用を制限されています [4]。
高いリターンを目指す彼らが、レバレッジを使えない状況で唯一取れる手段は、ポートフォリオ全体のベータを高めること、すなわち高ベータ株をオーバーウェイトすることです。その結果、多くの投資家がこぞって高ベータ株を買おうとするため、これらの銘柄の価格は需要によって押し上げられ、将来の期待リターンが低下してしまうのです。逆に、魅力の乏しい低ベータ株は人気がなく、割安な価格で放置されるため、結果的に高いリターンを生む、というメカニズムです。
2.ベンチマークと代理人問題
ベイカー、ブラッドリー、ワーグラーによる2011年の研究は、レバレッジ制約の問題を「代理人問題(エージェンシー問題)」の観点から補強しました [5]。多くのファンドマネージャーは、そのパフォーマンスをS&P500のようなベンチマークと比較して評価されます。
彼らの目的が、顧客の資産を最大化することではなく、「ベンチマークに負けないこと」あるいは「少しだけ勝つこと」である場合、最も合理的な行動は、ベンチマークから大きく乖離しないようにしつつ、高ベータ株を少しだけ多く組み入れてリターンの上乗せを狙うことになります。この行動が、高ベータ株への歪んだ需要を生み出し、アノマリーの存続に繋がっているのです。
3.宝くじへの選好という行動バイアス
高ベータ株は、しばしば「宝くじ」のような性質を持つと指摘されます。つまり、ほとんどの場合は低いリターンに終わるものの、ごく稀に驚異的なリターンを生み出す可能性を秘めている、ということです。多くの個人投資家は、このような一攫千金の可能性を持つ投機的な銘柄を、その期待値以上に好むという行動バイアスを持っています。この非合理的な需要が、高ベータ株を恒常的に過大評価させ、その平均的なリターンを押し下げる一因となっているのです。
非対称性と摩擦の視点
なぜ、CAPMという合理的で美しい理論が、現実の市場では機能しないのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:レバレッジへのアクセスの非対称性
ベータ・アノマリーを生み出す根源には、市場参加者の間にある「レバレッジへのアクセスの非対称性」が存在します。
ヘッジファンドのような洗練された、制約の少ない投資家は、必要であればレバレッジ(借入)を利用して、リターンを高めることができます。彼らは、安全な低ベータ資産を買い、それにレバレッジをかけることで、市場平均と同等のベータ(リスク)を取りながら、より高いリターンを狙うことが可能です。これが「ベッティング・アゲンスト・ベータ」戦略の核心です [4]。
一方で、ミューチュアル・ファンドや年金基金、多くの個人投資家は、規約や心理的な抵抗から、レバレッジの利用を厳しく制限されています。彼らがリターンを高めようとする場合、取れる手段は限られており、その結果、ポートフォリオ全体のベータを高める、すなわち高ベータ株を買い増すという安易な選択に走りがちです。
この「レバレッジを使える者」と「使えない者」との間の構造的な非対称性が、市場に歪みを生み出します。レバレッジを使えない多数派が高ベータ株に殺到することで、その価格は過大評価され、将来のリターンは低下します。一方で、レバレッジを使える少数派は、その歪みを利用して利益を得る機会を手にするのです。
Friction:ベンチマークという「見えざる鎖」の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、ベータ・アノマリーの存続を許している、より強力で根深い摩擦が存在します。
1.ベンチマークという制度的摩擦
多くの機関投資家(ファンドマネージャー)は、その運用成績をTOPIXやS&P500といったベンチマークと比較して評価されます。この「ベンチマーク」という制度そのものが、アノマリーの是正を妨げる巨大な摩擦として機能します。
低ベータ戦略は、長期的には高いリスク調整後リターンをもたらすかもしれませんが、市場全体が強気相場にある局面では、必然的にベンチマークに劣後します。ベンチマークに負け続けるファンドマネージャーは、たとえその戦略が合理的であったとしても、顧客から資金を引き揚げられ、キャリアを失うリスクに直面します [5]。このため、多くのマネージャーは、たとえ高ベータ株が割高だと分かっていても、ベンチマークから大きく乖離することを恐れ、それをポートフォリオに組み入れざるを得ないのです。この「見えざる鎖」が、アノマリーの存続を許しています。
2.レバレッジへの嫌悪という認知的摩擦
多くの投資家にとって、レバレッジは「危険」「破産」といったネガティブなイメージと強く結びついています。この「レバレッジへの嫌悪」という認知的な摩擦は、投資家が低ベータ戦略のポテンシャルを最大限に引き出すことを妨げます。低ベータ資産から高いリターンを得るためには、レバレッジの活用が不可欠ですが、多くの投資家はこの選択肢を自ら封じてしまいます。その結果、彼らは再び「より高いリターンを得るためには、より高いベータの資産を買うしかない」という、歪んだ市場へと押し戻されてしまうのです。
総括
・ベータ・アノマリーとは、CAPMの予測に反し、高ベータ(高リスク)株のリターンが期待ほど高くなく、低ベータ(低リスク)株のリターンが期待以上に高いという、市場で観測される逆説的な現象です [2]。
・低ベータ株に投資し、高ベータ株を空売りする「ベッティング・アゲンスト・ベータ」のような戦略は、歴史的に優れたリスク調整後リターンを生み出してきました [4]。
・このアノマリーの主な原因は、レバレッジを利用できない投資家が高ベータ株を過大評価してしまう「レバレッジ制約」であると考えられています [4]。
・また、ベンチマークを意識せざるを得ないファンドマネージャーの行動 [5]や、投機的な銘柄を好む投資家の「宝くじ選好」といった要因も、アノマリーの存続に寄与しています。
用語集
ベータ (Beta) 個別の株式が、市場全体の動きに対してどれくらい敏感に反応するかを示す指標。1より大きいと市場より値動きが激しく、1より小さいと穏やかとされる。
CAPM (資本資産評価モデル) 資産のリターンが、その資産が持つ市場全体に対するリスク(ベータ)の大きさに比例して決まるという、伝統的な金融理論の根幹。
ベータ・アノマリー (Beta Anomaly) CAPMの予測に反して、ベータとリターンの間に明確な正の相関が見られない、あるいは負の相関さえ見られるという市場の経験則。
リスク調整後リターン リターンの絶対額だけでなく、そのリターンを得るためにどれだけのリスクを取ったかを考慮に入れたリターンのこと。シャープレシオが代表的。
シャープレシオ (Sharpe Ratio) リターンを、そのリターンを得るために取ったリスクの大きさで割った値。数値が高いほど、効率的にリターンを上げたことを示す。
BABファクター (Betting Against Beta Factor) 低ベータ株をレバレッジをかけて買い、高ベータ株を空売りすることで組成されるポートフォリオ。ベータ・アノマリーを利用する代表的な戦略。
レバレッジ (Leverage) 借入を利用して、自己資金だけの場合よりも大きな投資を行うこと。「てこ」の原理に由来する。
ベンチマーク (Benchmark) ファンドなどの運用成績を評価するために比較対象となる、TOPIXやS&P500といった市場の平均を示す指数のこと。
代理人問題 (Agency Problem) 企業の経営者やファンドマネージャー(代理人)が、株主や顧客(本人)の利益ではなく、自己の利益を優先して行動してしまう問題。
宝くじ銘柄 (Lottery-Ticket Stock) リターンの期待値は低いものの、ごく稀に非常に大きなリターンを生む可能性のある、投機的な性質が強い株式のこと。
参考文献一覧
[1] Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425-442.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x
[2] Black, F., Jensen, M. C., & Scholes, M. (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests. In M. C. Jensen (Ed.), Studies in the Theory of Capital Markets (pp. 79-121). Praeger Publishers.
https://ssrn.com/abstract=908569
[3] Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The cross‐section of volatility and expected returns. The Journal of Finance, 61(1), 259-299.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00836.x
[4] Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2014). Betting against beta. Journal of Financial Economics, 111(1), 1-25.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.10.005
[5] Baker, M., Bradley, B., & Wurgler, J. (2011). Benchmarks as limits to arbitrage: Understanding the low-volatility anomaly. Financial Analysts Journal, 67(1), 40-54.
https://doi.org/10.2469/faj.v67.n1.4
本サイト/本記事は、著者個人の見解、経験、学習・研究内容に基づいた情報提供を目的としています。特定の銘柄や投資手法の推奨を目的としたものではなく、また、金融商品取引法に基づく投資助言サービスではありません。
投資には元本割れを含む様々なリスクがあります。価格変動、金利変動、為替変動、発行者の信用状況などにより、損失が生じる可能性があります。
本サイト/本記事で提供される情報を利用した投資判断や取引によって生じたいかなる損害についても、筆者および運営者は一切の責任を負いません。
投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行って(あるいは行わないで)ください。
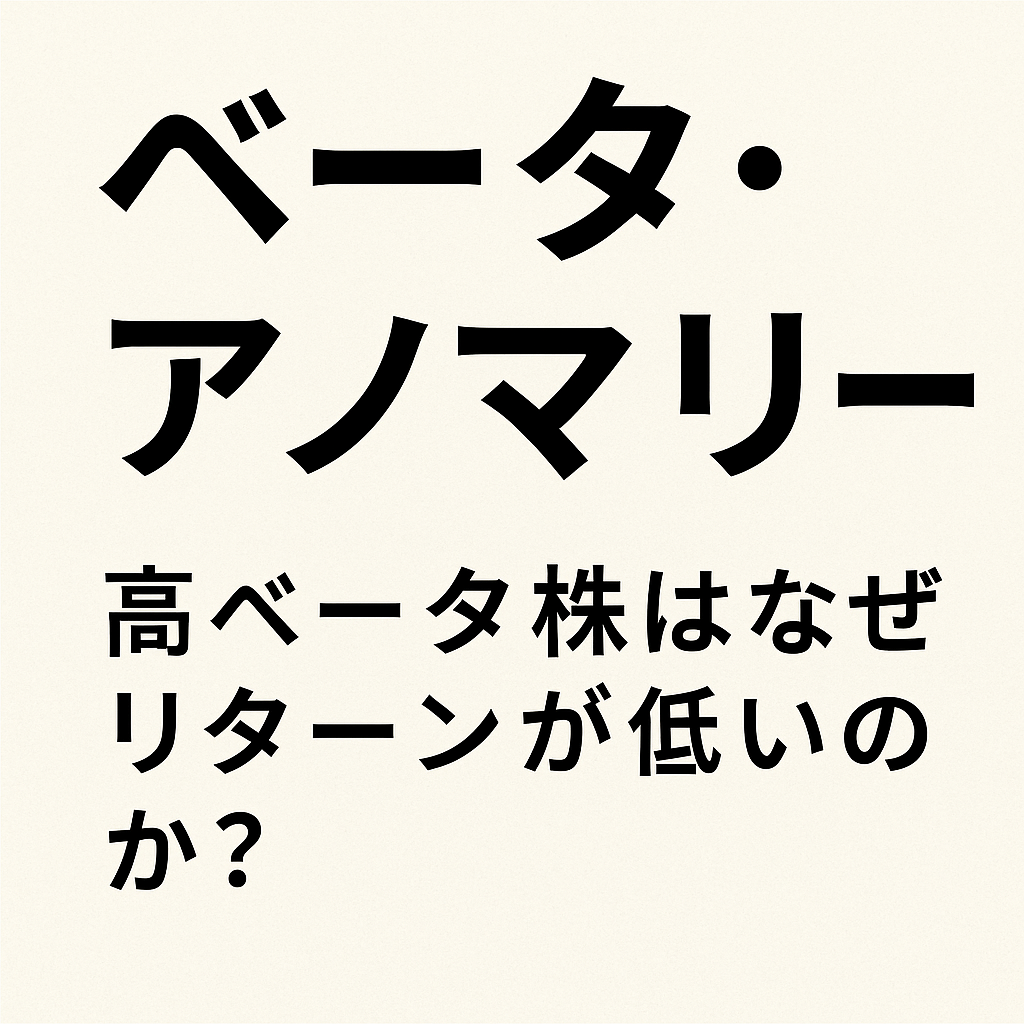
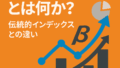
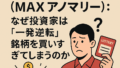
コメント