概論:一攫千金の夢と、その代償
「もしこの株が10倍になったら…」――多くの投資家が一度は抱く、一発逆転の夢。この心理は、高額当選を夢見て宝くじを買う心理と驚くほどよく似ています。そして、この根深い人間心理こそが、株式市場に存在する不可解なアノマリー(経験則)の一つ、「宝くじ効果」を生み出す源泉です。
宝くじ効果とは、ごく低い確率で極めて大きなリターンを生む可能性のある、ギャンブル的な性質を持つ株式(宝くじ銘柄)を、投資家が過度に選好し、その結果として、それらの銘柄の平均リターンが長期的に低迷するという現象を指します。
この非合理的な行動の理論的背景は、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによる1979年の「プロスペクト理論」によって説明できます [1]。彼らは、人間が確率を評価する際、非常に低い確率を、実際よりも過大に評価してしまう「確率加重関数」という認知バイアスを持つことを示しました。当選確率100万分の1を、人々はゼロとは見なさず、それに「夢」という過大な価値を与えてしまうのです。
この理論を株式市場に適用し、実証的なアノマリーとして確立したのが、トゥーラン・バリ、ヌスレット・ジャキジ、ロバート・ホワイトローによる2011年の画期的な研究です [2]。彼らは、企業のファンダメンタルズではなく、株価の極端な値動きそのものに着目しました。具体的には、「過去1ヶ月間の日次リターンの最大値(MAX)」を測定し、このMAXが高い銘柄、すなわち「過去に一度でも驚異的な急騰を見せた銘柄」が、その後どのようなパフォーマンスを示すかを検証したのです。
その結果は明確でした。MAXが高い、すなわち宝くじ的な性質が最も強い株式ポートフォリオは、将来の平均リターンが著しく低いという、明確な負の関係が発見されました。これが「MAXアノマリー」です。
長短の解説と損益の事例紹介
宝くじ効果は、人間の非合理的な夢が、いかに市場で手痛い「罰金」を科されるかを示しています。ここでは、このアノマリーがもたらす損失と、それを逆手に取ることで得られるかもしれない収益機会を解説します。
短所、弱み、リスクについて:宝くじ銘柄がもたらす低リターン(損失事例)
宝くじ銘柄に投資することの最大の欠点は、その長期的なパフォーマンスの低さです。
バリらの研究によれば、1926年から2005年までの米国市場において、MAXが最も高い上位10%の銘柄で構成されるポートフォリオは、市場平均を月次で1.31%もアンダーパフォームしました [2]。これは、一発逆転の夢を追いかける投資家が、平均的に見て、極めて高い代償を支払わされていることを意味します。
なぜ、このような現象が起こるのでしょうか。ニコラス・バーバリスとミン・ホアンによる2008年の理論研究は、プロスペクト理論に基づき、そのメカニズムを説明しています [3]。彼らのモデルによれば、投資家は、ポートフォリオ全体のリスク・リターンではなく、個々の銘柄が持つ「歪度(スキューネス)」、すなわち稀に起こる大きな当たり(正の歪み)を強く好みます。この選好のために、多くの投資家が宝くじ銘柄に殺到し、その価格が本来の価値以上に吊り上げられてしまうのです。過大評価された価格で買う以上、その後の平均リターンが低くなるのは必然的な結果です。
この現象は、アンドリュー・アンらによる2006年の、高ボラティリティ株に関する研究によっても補強されています [4]。宝くじ銘柄は、その性質上、必然的にボラティリティ(価格変動)が非常に高くなります。そして、彼らの研究は、そのような高ボラティリティ株のポートフォリオが、驚くほど低いリターンしか生まないことを示しています。
長所、強み、有用な点について:アノマリーを利用した戦略(収益事例)
このアノマリーは、宝くじ銘柄を買う投資家にとっては罠ですが、市場の非効率性を利用しようとする投資家にとっては、収益機会のシグナルとなり得ます。
その最も直接的な戦略は、宝くじ銘柄を避ける、あるいは積極的に空売りすることです。バリらの研究では、MAXが最も低い銘柄群を買い、最も高い銘柄群を売るロング・ショート戦略を構築した場合、月次で1.48%という、統計的に極めて有意なリターンが生まれることが示されています [2]。これは、市場の他の参加者が犯す体系的なミスを逆手に取ることで、超過リターンが生まれることを意味します。
この宝くじ効果は、米国市場だけの特殊な現象ではありません。クリスチャン・ウォークショイスルによる2014年の研究は、欧州の16カ国の市場においても、MAXアノマリーが存在することを確認しました [5]。この国際的な頑健性は、宝くじ的な資産を好むという人間の心理的バイアスが、文化を超えて普遍的に存在することを示唆しており、このアノマリーが根深い現象であることを裏付けています。
非対称性と摩擦の視点
なぜ、これほどまでに明確なアノマリーが、市場から簡単には消え去らないのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:リターン分布の「歪み」という非対称性
宝くじ効果の根源には、リターンの分布そのものが持つ「非対称性」が存在します。
一般的な株式のリターン分布は、ある程度正規分布に近い、左右対称な形をしています。しかし、宝くじ銘柄のリターン分布は、極めて非対称な形、すなわち「正の歪度(スキューネス)が大きい」という特徴を持っています。これは、「ほとんどの場合は小さな損失を出すが、ごく稀に、想像を絶するほど大きな利益をもたらす」というリターンの構造を意味します。
プロスペクト理論が示すように、人間の脳は、このような非対称なリターン分布を合理的に評価することができません [1]。我々は、確率的にはほとんどゼロに近い「巨大な当たり」の可能性を過大評価し、そのために、期待値がマイナスであるにも関わらず、その資産を喜んで購入してしまうのです。
このリターン分布の非対称性と、それを評価する人間の認知の非対称性の二重の歪みこそが、宝くじ銘柄が過大評価される根本的な原因です。このアノマリーを利用した収益機会は、この歪みの存在を客観的に認識し、市場の多くの参加者が抱く非合理的な期待の逆を行くことで生まれるのです [3]。
Friction:空売り制約と「希望」という認知的摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、宝くじ効果の存続を許している、より強力で根深い摩擦が存在します。
1.空売り制約という物理的な摩擦
このアノマリーから利益を得る最も直接的な方法は、過大評価されている宝くじ銘柄を空売りすることです。しかし、これらの銘柄は、しばしば時価総額が小さく、流動性が低い、あるいはボラティリティが極端に高いといった特徴を持つため、空売りのための株式を借りることが困難であったり、非常に高いコスト(貸株料)がかかったりします。
この「空売り制約」という物理的な摩擦は、価格の歪みを是正しようとする裁定取引の力を大きく削いでしまいます。たとえ割高だと分かっていても、誰もそれを効率的に空売りできないため、過大評価された状態が長期間にわたって放置されるのです。
2.「希望」という抗いがたい認知的摩擦
宝くじ銘柄は、単なる投機の対象であるだけでなく、投資家に「希望」という強力な感情的価値を提供します。「もし成功すれば、人生が変わるかもしれない」という物語は、冷徹な確率計算を麻痺させる力を持っています。
この「希望」や「夢」といった、数値化できない感情的な魅力は、投資家が合理的な判断を下すことを妨げる、極めて強力な「認知的な摩擦」として機能します。多くの人々が抱くこの根源的な欲求は、たとえ過去のデータが宝くじ銘柄の不利を示していても、常に新たな買い手を市場に呼び込みます。この尽きることのない需要が、アノマリーが簡単には消滅しない、最も手強い理由の一つなのです。
総括
・宝くじ効果(MAXアノマリー)とは、投資家が「一発逆転」の可能性を秘めたギャンブル的な銘柄を過度に好み、その結果として、それらの銘柄が長期的に見て低いリターンに甘んじるという現象です。
・その背景には、人間が低い確率を過大評価してしまうという、プロスペクト理論によって説明される根深い認知バイアスが存在します [1]。
・過去に一度でも急騰した実績(高いMAX値)を持つ銘柄は、将来のリターンが著しく低いことが、米国内外の市場で実証されています [2, 5]。
・このアノマリーは、宝くじ銘柄を避ける、あるいは空売りすることで収益機会となり得ますが、空売り制約という物理的な摩擦や、「希望」という抗いがたい認知的な摩擦によって、市場から完全には消滅せずに存続し続けています。
用語集
宝くじ効果 (Lottery Effect) 投資家が、低い確率で非常に大きなリターンをもたらす可能性のある、宝くじのような性質を持つ株式を過度に選好する傾向のこと。
MAXアノマリー (MAX Anomaly) 過去一ヶ月間の日次リターンの最大値(MAX)が高い株式ほど、その後の将来リターンが低くなるという経験則。
プロスペクト理論 (Prospect Theory) 不確実性のある状況下での人間の意思決定を説明する理論。人々が利益と損失をどのように評価し、確率をどのように認識するかの歪みをモデル化したもの。
確率加重関数 (Probability Weighting Function) プロスペクト理論の中核的な概念の一つ。人間が客観的な確率を、主観的に歪めて認識する傾向を示し、特に低い確率を過大評価することを説明する。
歪度 (Skewness) 確率分布が、その平均値に対してどれだけ非対称であるかを示す統計的な指標。「正の歪度」が大きいとは、分布の裾が右側に長く伸びている(稀に大きなプラスの値を取る)ことを意味する。
ボラティリティ (Volatility) 資産価格の変動の激しさを示す指標。標準偏差で測定されることが多い。
ロング・ショート戦略 割安と判断した資産を買い持ち(ロング)し、同時に割高と判断した資産を空売り(ショート)する投資戦略。
空売り (Short Selling) 所有していない株式を証券会社などから借りて市場で売却し、将来価格が下落した時点で買い戻して返済し、その差額を利益とする取引。
裁定取引 (Arbitrage) 同一の価値を持つ資産間で価格差が生じた際に、割安な方を買い、割高な方を売ることで、リスクなく利益を得ようとする取引。
期待値 (Expected Value) ある試行を行った際に、結果として得られる数値の平均値。確率とその結果の積をすべて足し合わせることで計算される。
参考文献一覧
[1] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
https://doi.org/10.2307/1914185
[2] Bali, T. G., Cakici, N., & Whitelaw, R. F. (2011). Maxing out: Stocks as lotteries and the cross-section of expected returns. Journal of Financial Economics, 99(2), 427-446.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.08.014
[3] Barberis, N., & Huang, M. (2008). Stocks as lotteries: The implications of probability weighting for security prices. American Economic Review, 98(5), 2066-2100.
https://doi.org/10.1257/aer.98.5.2066
[4] Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The cross‐section of volatility and expected returns. The Journal of Finance, 61(1), 259-299.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00836.x
[5] Walkshäusl, C. (2014). The MAX-effect: European evidence. Journal of Banking & Finance, 40, 12-23.
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.11.005
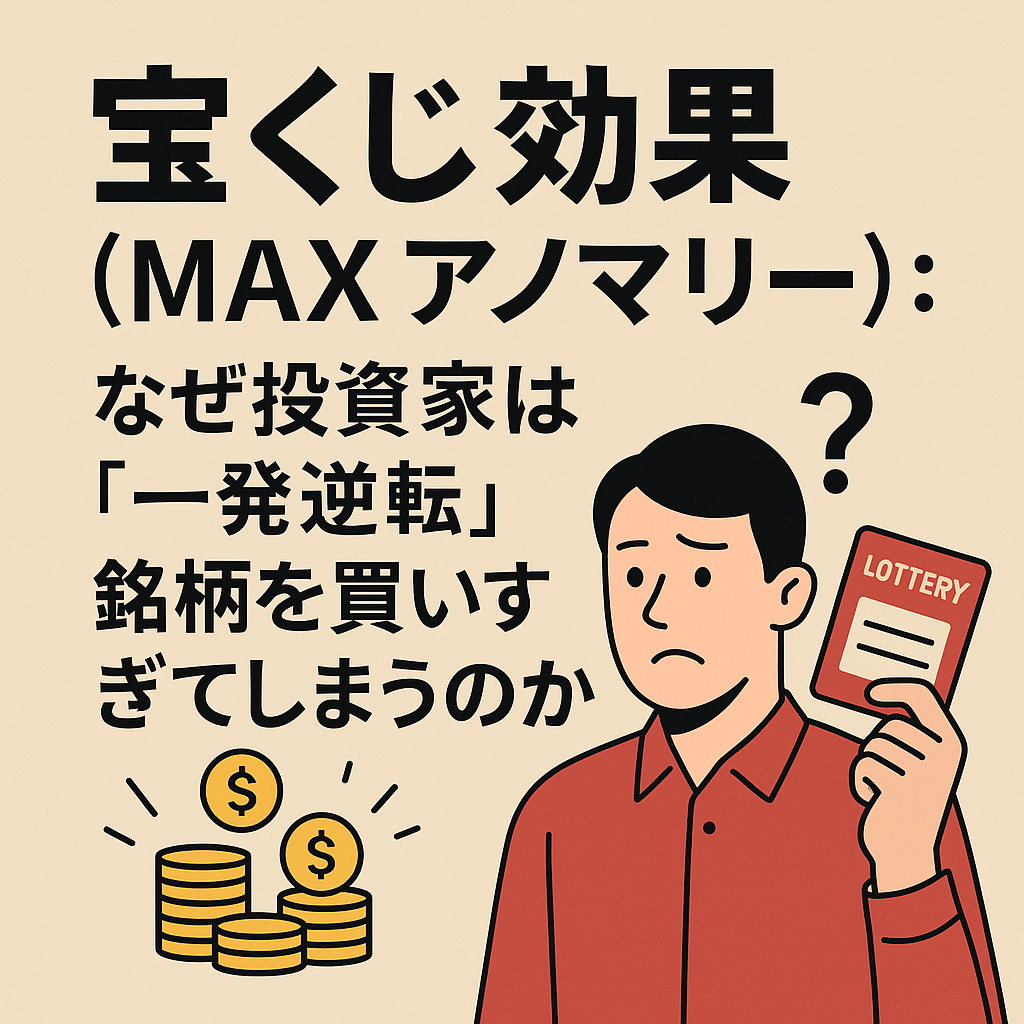
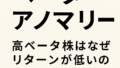

コメント