概論:リスク・リターンの大原則を覆す謎
「ハイリスク・ハイリターン、ローリスク・ローリターン」。これは、投資の世界における最も基本的で、直感的な大原則です。この思想を理論的に体系化したのが、ノーベル経済学賞の受賞対象ともなった資本資産評価モデル(CAPM)です [1]。CAPMによれば、投資家がより大きなリスク(高いベータやボラティリティ)を取るならば、その対価として、より高い期待リターンを得られるはずでした。
しかし、その後の数十年にわたる学術的な実証研究は、この金融理論の根幹をなす大原則が、現実の株式市場では成り立っていないという、衝撃的な事実を明らかにしてきました。
すなわち、「リスクの低い(低ボラティリティの)株式ポートフォリオが、リスクの高い(高ボラティリティの)株式ポートフォリオと比べて、同等か、あるいはそれ以上のリターンを上げてきた」という逆説的な現象です。これが低ボラティリティ・アノマリーとして知られる、市場に存在する最も頑健で、不可解なアノマリー(経験則)の一つです。
この現象に関する初期の指摘は古く、ロバート・ハウゲンとジェームズ・ハインズによる1975年の研究などが挙げられます [2]。彼らは、1926年から1971年までの長期データを用いて、リスク(リターンの分散)とリターンの間に、理論が予測するような明確な正の関係が見られないことを示しました。
そして21世紀に入り、より高度な分析手法によって、このアノマリーは単なる統計上の偶然ではなく、市場に恒常的に存在する構造的な歪みであることが示されていきます。この記事では、なぜ「安全」が「危険」に勝るのか、その謎を学術研究を基に深掘りしていきます。
長短の解説と損益の事例紹介
低ボラティリティ・アノマリーは、伝統的なリスクの概念に疑問を投げかけると同時に、新たな投資機会の可能性を示唆します。ここでは、このアノマリーがもたらす影響を、具体的な研究成果と共に解説します。
長所、強み、有用な点について:安全な株の優れた実績
低ボラティリティ・アノマリーの発見は、「高リスク資産を避ける」という一見すると退屈な戦略が、実は優れたリスク調整後リターンを生み出す可能性を示しました。
収益事例:高ボラティリティ株の長期的な低迷
このアノマリーの存在を現代において決定づけたのが、アンドリュー・アン、ロバート・ホドリック、イェーユン・シン、シャオヤン・チャンによる2006年の影響力の大きい研究です [3]。彼らは、米国市場および国際市場において、株式のボラティリティ(特に、市場全体では説明できない個別銘柄固有のボラティリティ)と将来のリターンの関係を調査しました。
その結果は衝撃的で、1963年から2000年までの米国市場において、ボラティリティが最も高い株式で構成されるポートフォリオは、ボラティリティが最も低いポートフォリオを、月次で1%以上もアンダーパフォームしていたのです。これは、「ハイリスク・ローリターン」という、CAPMの予測とは真逆の現実を明確に示しています。この現象は、G7諸国の株式市場でも同様に観測され、その普遍性が確認されました。
短所、弱み、リスクについて:なぜ危険な株は報われないのか(損失事例)
なぜ、リスクが高いはずの高ボラティリティ株は、期待されるリターンを生み出さないのでしょうか。その背景には、市場参加者の構造的な制約や、非合理的な行動があると考えられています。高ボラティリティ株に投資することは、これらの歪みに起因する体系的な損失を被るリスクを負うことを意味します。
1.制度的な制約:ベンチマークとレバレッジ
低ボラティリティ・アノマリーを説明する有力な仮説の一つが、機関投資家が直面する制度的な制約です。
ベイカー、ブラッドリー、ワーグラーによる2011年の研究は、多くのファンドマネージャーが、そのパフォーマンスをS&P500のようなベンチマークと比較して評価されるという「代理人問題」を指摘しました [4]。彼らの目的が、顧客の資産を最大化することではなく、「ベンチマークに少しだけ勝つこと」である場合、低リスク株だけでポートフォリオを組むと、強気相場でベンチマークに大きく劣後するリスクを負います。そのため、彼らはリターンを上乗せするために、高ボラティリティ・高ベータの株式をポートフォリオに組み入れざるを得ないのです。
フラッツィーニとペデルセンによる2014年の研究は、この議論を「レバレッジ制約」の観点から補強しました [5]。多くの投資家は、規約や心理的な抵抗からレバレッジ(借入)の利用を制限されています。レバレッジを使わずに高いリターンを目指す最も簡単な方法は、本質的にリスクの高い高ボラティリティ株を買うことです。これらの制度的・構造的な理由から、高ボラティリティ株には常に歪んだ需要が発生し、価格が過大評価され、将来のリターンが押し下げられてしまうのです。
2.行動ファイナンス的な選好:宝くじ効果
高ボラティリティ株が報われないもう一つの理由は、投資家の非合理的な選好にあります。
バーバリスとホアンによる2008年の研究が示すように、多くの投資家は、プロスペクト理論で説明される「宝くじ効果」、すなわち、低い確率で非常に大きなリターンをもたらす可能性のある資産を、その期待値以上に好むという行動バイアスを持っています [6]。高ボラティリティ株は、まさにこの「一発逆転」の夢を抱かせる性質を持っています。この非合理的な需要が、高ボラティリティ株を恒常的に過大評価させ、その平均的なリターンを押し下げる一因となっているのです。
非対称性と摩擦の視点
なぜ、CAPMという合理的で美しい理論が、現実の市場では機能しないのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
非対称性と摩擦の視点
当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から今回のテーマを解き明かします。
Asymmetry:リターンの非対称性と代理人の目標
低ボラティリティ・アノマリーの根源には、リスクとリターンの関係における複数の「非対称性」が存在します。
1.ペイオフ(リターン分布)の非対称性
高ボラティリティ株は、しばしば宝くじのように、そのリターン分布が極めて非対称な形(正の歪度)をしています。つまり、「ほとんどの場合は小さなリターンか損失で終わるが、ごく稀に、驚異的なリターンをもたらす」という性質です。プロスペクト理論が示すように、人間の脳はこのような非対称なペイオフを合理的に評価できず、稀に起こる大当たりの可能性を過大評価する傾向があります [6]。このペイオフの非対称性と、それを評価する人間の認知の非対称性が、高ボラティリティ株を過大評価させる一因となります。
2.目標設定の非対称性(代理人問題)
投資の世界では、資産の所有者(顧客)と運用者(ファンドマネージャー)の目標は必ずしも一致しません。顧客の目標が「リスクを抑えつつ、着実にリターンを最大化する」ことであるのに対し、ファンドマネージャーの目標は、より複雑で、「ベンチマークに負けない」という非対称なインセンティブに強く影響されます [4]。ベンチマークに大きく負けることのペナルティ(職を失うリスク)は、ベンチマークに大きく勝つことの報酬よりも遥かに大きいのです。この目標設定の非対称性が、マネージャーを合理的なポートフォリオ構築から遠ざけ、アノマリーを生み出す温床となります。
Friction:ベンチマークという「見えざる鎖」の摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、低ボラティリティ・アノマリーの存続を許している、より強力で根深い摩擦が存在します。
1.ベンチマークという制度的摩擦
多くの機関投資家(ファンドマネージャー)は、その運用成績をTOPIXやS&P500といったベンチマークと比較して評価されます。この「ベンチマーク」という制度そのものが、アノマリーの是正を妨げる巨大な摩擦として機能します。
低ボラティリティ戦略は、長期的には高いリスク調整後リターンをもたらすかもしれませんが、市場全体が強気相場にある局面では、必然的にベンチマークに劣後します。ベンチマークに負け続けるファンドマネージャーは、たとえその戦略が合理的であったとしても、顧客から資金を引き揚げられ、キャリアを失うリスクに直面します [4]。このため、多くのマネージャーは、たとえ高ボラティリティ株が割高だと分かっていても、ベンチマークから大きく乖離することを恐れ、それをポートフォリオに組み入れざるを得ないのです。この「見えざる鎖」が、アノマリーの存続を許しています。
2.レバレッジへの嫌悪という認知的摩擦
多くの投資家にとって、レバレッジは「危険」「破産」といったネガティブなイメージと強く結びついています。この「レバレッジへの嫌悪」という認知的な摩擦は、投資家が低ボラティリティ戦略のポテンシャルを最大限に引き出すことを妨げます。低ボラティリティ資産から高いリターンを得るためには、レバレッジの活用が不可欠ですが、多くの投資家はこの選択肢を自ら封じてしまいます [5]。その結果、彼らは再び「より高いリターンを得るためには、より高いボラティリティの資産を買うしかない」という、歪んだ市場へと押し戻されてしまうのです。
総括
・低ボラティリティ・アノマリーとは、CAPMの予測に反し、低リスク(低ボラティリティ)株が、高リスク(高ボラティリティ)株と同等か、それ以上のリスク調整後リターンを上げてきたという逆説的な現象です [2, 3]。
・このアノマリーの主な原因は、制度的な「レバレッジ制約」や「ベンチマーク運用」によって、多くの投資家が高ボラティリティ株を過大評価(オーバープライス)してしまうためと考えられています [4, 5]。
・また、投資家が「一発逆転」を夢見て、投機的な高ボラティリティ株を好むという「宝くじ効果」のような行動バイアスも、この現象の存続に寄与しています [6]。
・このアノマリーは、安全な資産に投資することの長期的な優位性を示唆しますが、強気相場では市場平均に劣後する可能性があるというリスクも内包しています。
用語集
低ボラティリティ・アノマリー リスクの低い(低ボラティリティの)株式のリターンが、リスクの高い(高ボラティリティの)株式のリターンを長期的に下回らない、あるいは上回ることさえあるという市場の経験則。
ボラティリティ 資産価格の変動の激しさを示す指標。リターンの標準偏差で測定されることが多い。
CAPM (資本資産評価モデル) 資産のリターンが、その資産が持つ市場全体に対するリスク(ベータ)の大きさに比例して決まるという、伝統的な金融理論の根幹。
ベータ 個別の株式が、市場全体の動きに対してどれくらい敏感に反応するかを示す指標。ボラティリティと相関が高いことが多い。
idiosyncratic volatility ( idiosyncratic risk) 市場全体の値動きでは説明できない、その個別銘柄固有の要因によって生じる価格変動(リスク)のこと。
リスク調整後リターン リターンの絶対額だけでなく、そのリターンを得るためにどれだけのリスクを取ったかを考慮に入れたリターンのこと。シャープレシオが代表的。
シャープレシオ リターンを、そのリターンを得るために取ったリスクの大きさで割った値。数値が高いほど、効率的にリターンを上げたことを示す。
レバレッジ 借入を利用して、自己資金だけの場合よりも大きな投資を行うこと。「てこ」の原理に由来する。
ベンチマーク ファンドなどの運用成績を評価するために比較対象となる、TOPIXやS&P500といった市場の平均を示す指数のこと。
代理人問題 (Agency Problem) 企業の経営者やファンドマネージャー(代理人)が、株主や顧客(本人)の利益ではなく、自己の利益を優先して行動してしまう問題。
参考文献一覧
[1] Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425-442.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x
[2] Haugen, R. A., & Heins, A. J. (1975). Risk and the rate of return on financial assets: Some old wine in new bottles. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 10(5), 775-784.
https://doi.org/10.2307/2330270
[3] Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The cross‐section of volatility and expected returns. The Journal of Finance, 61(1), 259-299.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00836.x
[4] Baker, M., Bradley, B., & Wurgler, J. (2011). Benchmarks as limits to arbitrage: Understanding the low-volatility anomaly. Financial Analysts Journal, 67(1), 40-54.
https://doi.org/10.2469/faj.v67.n1.4
[5] Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2014). Betting against beta. Journal of Financial Economics, 111(1), 1-25.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.10.005
[6] Barberis, N., & Huang, M. (2008). Stocks as lotteries: The implications of probability weighting for security prices. American Economic Review, 98(5), 2066-2100.
https://doi.org/10.1257/aer.98.5.2066

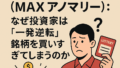
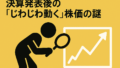
コメント